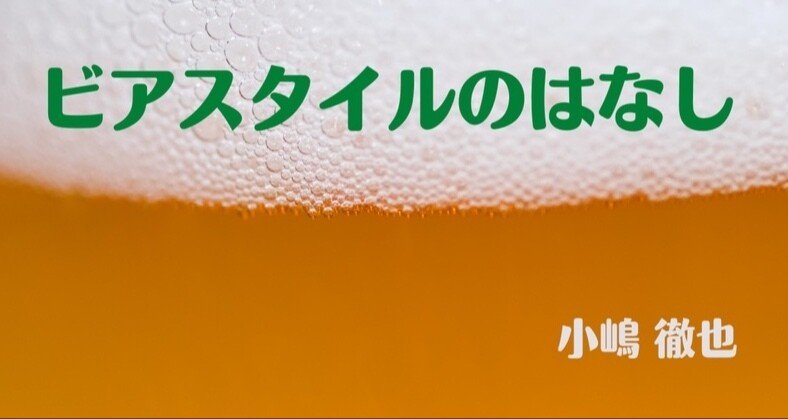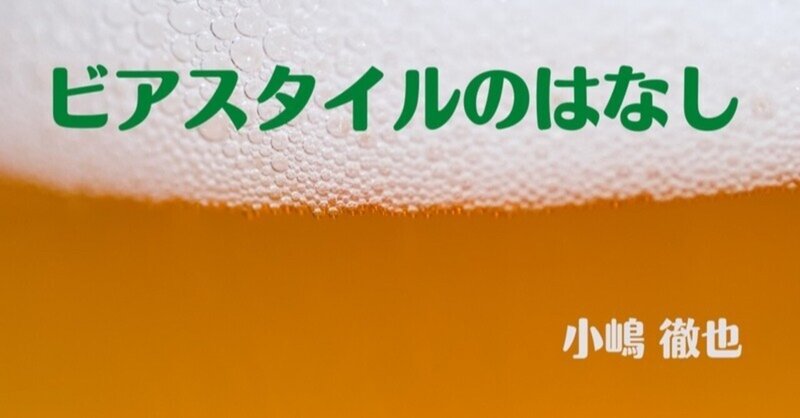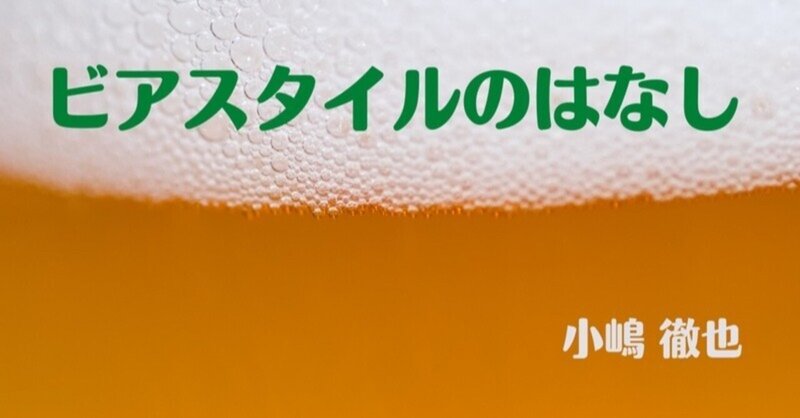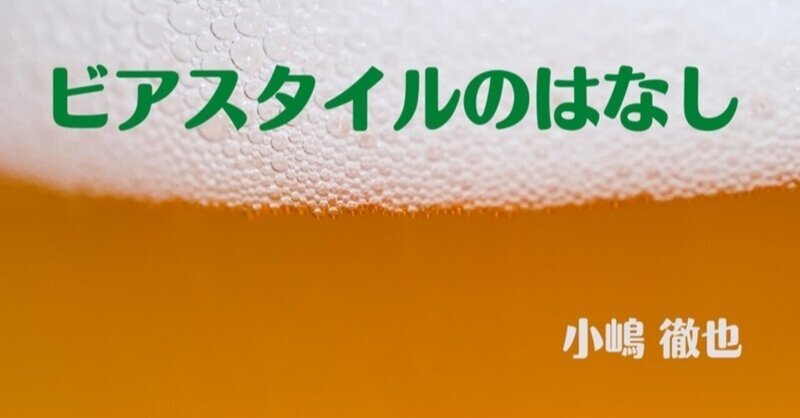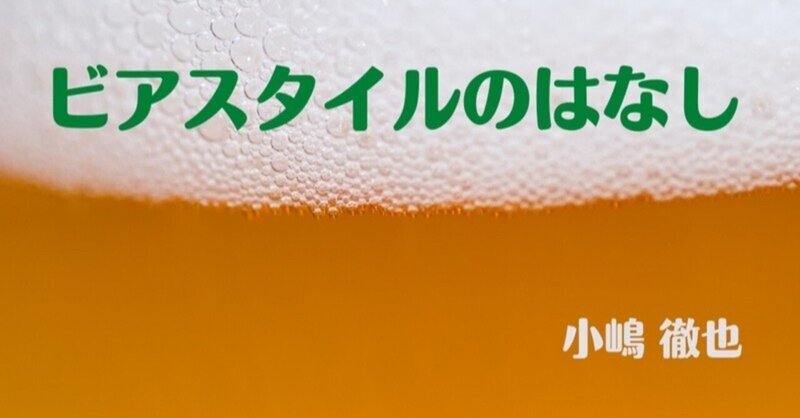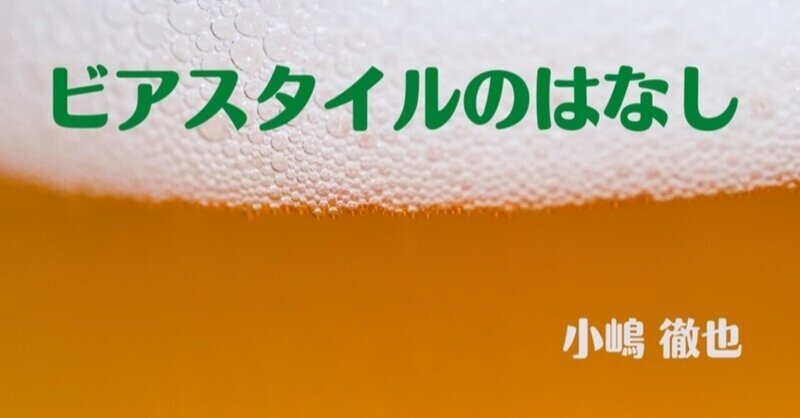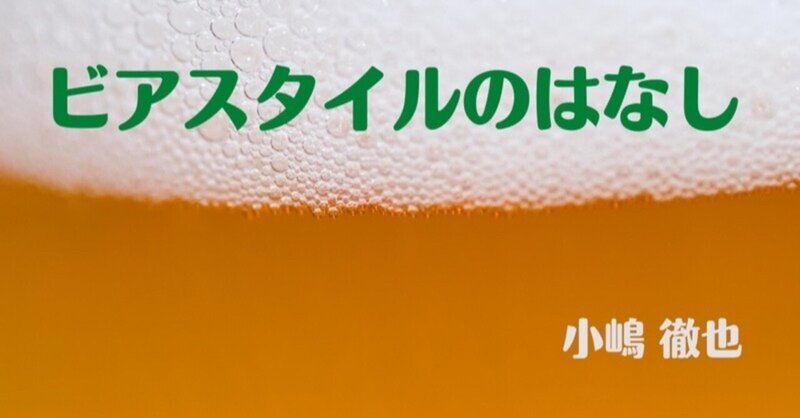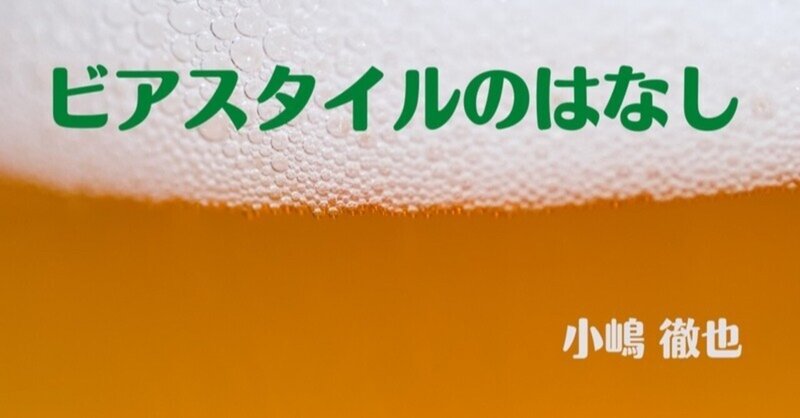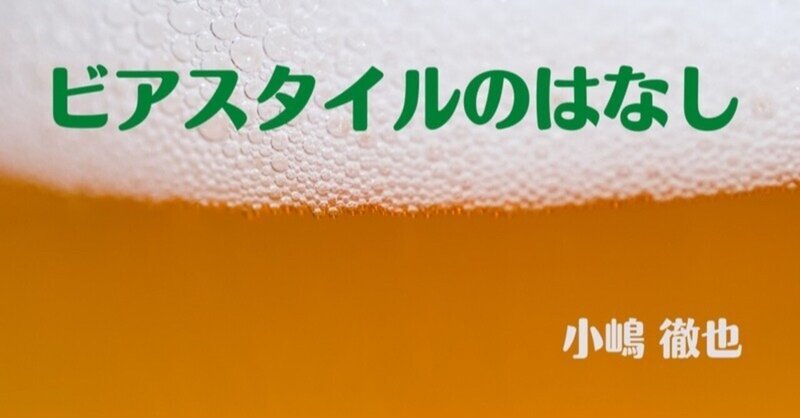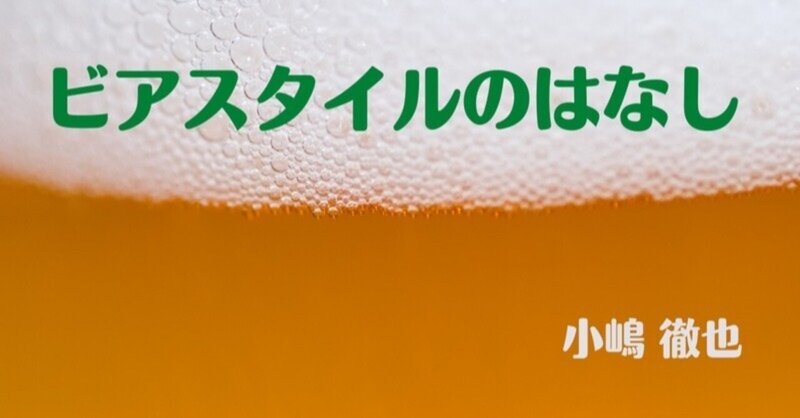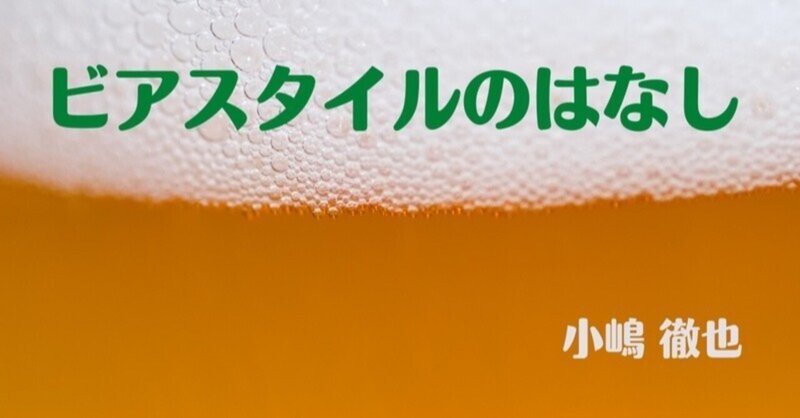2021年12月の記事一覧
Episode 14: フルーツ&スパイスビール〜素晴らしき多様性〜
この連載では、これまでいわゆる伝統的なビアスタイルを扱ってきた。今回ははじめて、伝統的なビアスタイルに新しい副原料や製法を導入した、いわゆるハイブリッドなスタイルを扱うことにしよう。
フルーツやスパイス、ハーブなどを副原料として用いたビールである。以前も書いたとおり、ビール純粋令が施行されているドイツでは、このような副原料を用いることはご法度である。
一方、ベルギーでは、古来よりフルーツやスパ
Episode 13: スコッチエール〜モルトの国からの回答〜
数回にわたったハイアルコールビール・シリーズも今回で最後。最後はスコッチエール(Scotch Ale)を紹介しよう。別名をウィーヘビー(Wee Heavy)ともいう。
スコットランドはモルト(麦芽)用の大麦の一大生産国である。ご存じのように、スコットランドは世界最大級のウイスキーの生産地であり、当然、モルトはウイスキーの蒸留にも使用される。
実は、スコットランドでは長い間、北部のハイランド(H
Episode 12: ボック〜世界最強は誰だ?〜
ここ2回ほどハイアルコールビールを扱っているが、今回は真打ちの登場である。ドイツのハイアルコールビール、ボックである。基本的にはボックはアルコール度数の高いラガーであるが、エールも存在する。
ドイツ語でボック(Bock)はオスヤギを意味する。事実、ボックの中にはラベルにオスヤギを用いたものも見られる。オスヤギの強いキック力とビールの力強さを結びつけ、それがビールの名称となったという説があるが、こ
Episode 11: トラピストビール〜聖杯を掲げよ〜
この連載を始めることになったときから、この日はこのネタで行こうと決めていた。今回はトラピストビール。修道院で醸造されたビールの話である。
私が幼い頃通っていた幼稚園は仏教系で、浄土真宗のお寺の敷地に建っていた。しかし、だからといって私は熱心な仏教徒ではなく、特定の宗教への信仰心は持っていない。
この時期になると、街はクリスマスで騒がしくなる。最近ではイースター(復活祭)を祝う人も増えているのか
Episode 10: バーレイワイン〜特別な日には特別な一杯を〜
12月に入って、私の住む東京も寒さがしみわたってくるようになってきた。こんな日は燗酒やホットワインなど、体を温めてくれるお酒を楽しみたくもなるものである。
ビールは暑いときにジョッキでガブガブ飲むもの、というイメージは、クラフトビールの普及とともに払拭されつつあるのではないかと思う。じっくりとビールの香りや味を楽しみながらグラスを傾ける、そんな楽しみ方をしている方も増えてきたのではないだろうか。
Episode 09: IPA〜進化は止まらない〜
今回のテーマはIPA。前回、ペールエールの回にも、現代のペールエールの直接の祖先として紹介したビアスタイルだ。正式にはインディア・ペールエール(India Pale Ale)である。直訳すれば、「インドの淡色のエール」とでもなるのだろうが、残念ながら、インド生まれでも淡色でもない。前回書いたとおり、正真正銘の英国発祥のスタイルだし、色も赤銅色のようなものが多い。
IPAはホップを大量に投入して、
Episode 08: ペールエール〜ホップの誘惑〜
ピルスナーは淡色のラガーとして19世紀に誕生して以降、急激に世界中へと広がっていった。今ではどこの国に行っても飲むことができるということは、既に触れたとおりだ。同じように、おそらく世界中どこに言っても飲めるであろう「エール」がある。
ペールエールだ。ペール(Pale)は言語的な意味からすると、「淡い」とか「青白い」という意味があるが、実はペールエールの色合いは決して淡くない。ピルスナーと比べると
Episode 07: ベルジャン・ヴィット〜存亡の歴史〜
前回扱ったヴァイツェンは、ドイツで伝統的に作られてきた小麦ビールであった。これに対し、ベルジャン・ヴィットビールは、ベルギーで伝統的に作られてきた小麦ビール、すなわち、ヴァイツェンのベルギー版である。
ベルギーには公用語が二つあり、北部のフランデレン地域ではオランダ語の一種であるフラマン語が、南部のワロン地域ではフランス語が主に使用されている。
ドイツのヴァイツェンはヴァイスビア(Weissb
Episode 06: ヴァイツェン〜小麦色は何色?〜
「小麦色」という言葉がある。辞書を引くと、「小麦の種子を思わせる、つやのある薄茶色。」などという記述がある。小麦色の肌とかいうもんね。
今回取り上げるのは、「ヴァイツェン」(Weizen)というビアスタイル。ヴァイツェンは、少なくとも50%以上の小麦麦芽を原料として使用したビールである。"Weizen" という言葉はドイツ語で「小麦」。ということで、またしてもドイツならではのド直球なネーミングで
Episode 05: オクトーバーフェスト〜時代はまわる〜
オクトーバーフェストという言葉を聞いたことがあるだろうか?英語がわかる方は、あぁ、10月のお祭り(October Fest)かぁ、と思われるかもしれない。ビールの世界でオクトーバーフェストと言えば、1年に一度、ミュンヘン市内にあるテレージエンヴィーゼ(Theresienwiese)と呼ばれる会場で開催される世界最大級のビールの祭典のことを指す。だからアルファベット表記はドイツ語にならって “Okt
もっとみるEpisode 04: ケルシュ〜街の名を誇りに〜
ドイツ発祥のビアスタイルには地名のついたものが多い。すでに紹介したものの中にもデュッセルドルフスタイル・アルトビアやミュンヒナー・デュンケル、ミュンヒナー・ヘレスなどがある。ただし、これらは街の名前だけではなく、ビールの特徴を表す言葉、すなわち、「アルト」だったり「デュンケル」だったりというワードを伴っている。
そこで、今回取り上げる「ケルシュ」だ。ケルシュはベルギーとの国境に近い街、ケルンで作
Episode 03: ピルスナー〜ゴールドラッシュの到来〜
金。これを「キン」と読もうが、「カネ」と読もうが、人は「金」には心奪われる傾向がある。オリンピックの勝者は黄金色のメダルで讃えられるし、米国では黄金を求めて多くの者が西部を目指した。日本でも徳川の埋蔵金などというものに人々が群がったことをみなさんもご存知だろう。さらには、世界のどこであれ、「金」の魅力に取りつかれ、人生を狂わされてきた人の数と言ったら…
1842年は、ビールの歴史の中で奇蹟的な年
Episode 02: アルトとブラウンエール〜褐色のエールたち〜
前回、昔のビールは色の濃いものばかりだった、という話を書いた。今日もそんなダークなビールの話。主人公はドイツ発祥のアルトと英国発祥のブラウンエールである。両者とも茶褐色のエールであるわけだが、これらを並べて論じる、ということはあまり聞いたことがない。でも、並べてみると何か面白いことがわかるんじゃないの?ということで、取り上げてみることにした。
アルト一つはドイツ発祥の「アルト」。正式には「デュッ
Episode 01: ミュンヒナー・デュンケル〜古き時代の遺伝子〜
ビールの絵を描いてみよう。
と言われたとき、みなさんはどんな絵を描くだろうか?よく見るのは
こんな感じ。黄金色に輝くビール。居酒屋さんのビアホールで飲む生ビールも多くはこんな色合いだろう。ところが、こんな色のビールが生まれたのは最近の話。最近、と言っても2、3年というわけではなく(そんなわけあるか!?)、せいぜい200年足らずというところ。19世紀中頃までのビールの多くは
こんな感じの茶色い色