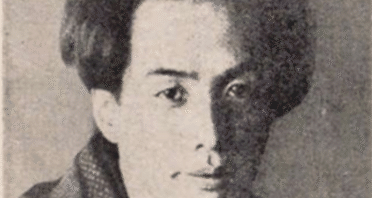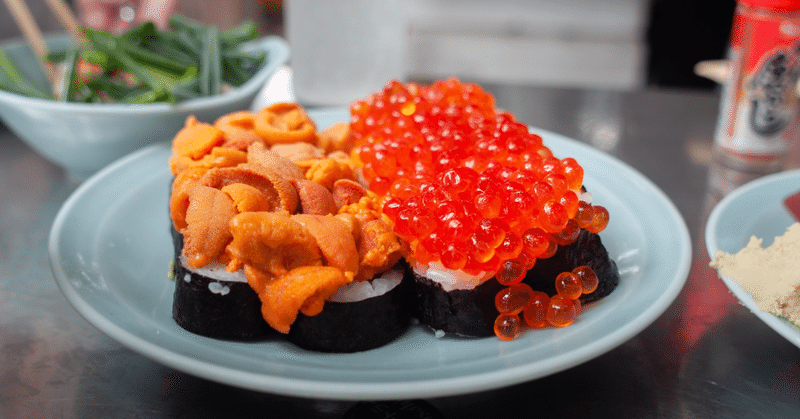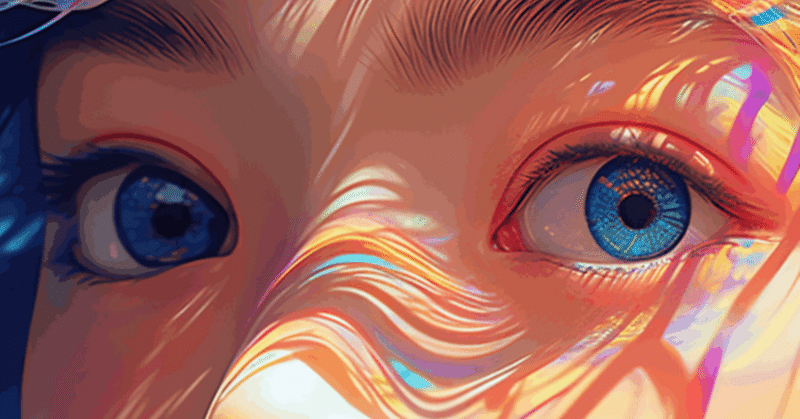2023年7月の記事一覧
芥川龍之介の『手紙』をどう読むか③ そんなしかけがあったとは
結局何が言いたいんだろう?
この『手紙』をそのまま手紙として受け取ったとしたら、やはりこれはわけのわからないものでしかなく、その意味は掴みかねるものなのではなかろうか。
たまたま偶然にその手紙の受取手がS君かK君かM子さんの知り合いでもない限り、M子さんが二股からお坊ちゃんのS君を選び、K君は失恋するという隠れたドラマがあったとしても、そのこと自体は殆ど意味を持たない。あるいはクロ
芥川龍之介の『手紙』をどう読むか② クロポトキンの『相互扶助論』とは?
何かできごとがあったとして、それを誰かに話すか話さないかと判断しない人は頭がおかしい。例えば夕ご飯のための買い物をしている夫婦がGの話をしていたら頭がおかしい。手紙も同じだ。手紙で近況報告をするとして、何でも書いていいわけではない。「赤あかと額の禿げ上った」という文言を禿に送ってはならない。身内にピストル自殺をしたものがあるものにピストル自殺した人の話を書き送ってはならない。そこに取捨選択
芥川龍之介の『三つの窓』をどう読むか④ 晩年
『彼 第三』
例えば川上弘美の『ぼくの死体をよろしくたのむ』に収められた『鍵』という小説を読んでみる。そうすると三十二歳なのか三十五歳なのかよく分からない鈴音という女性が六十五歳の七生というガタイの良いフリーの校閲のホームレスに初めての恋をすることに驚く。これが彼女の常套手段なのか、語り口が妙に幼いし、なにしろ三十五歳の女性が初めての恋をする話という設定に驚いてしまう。
そうしてだいたいそ
芥川龍之介の『三つの窓』をどう読むか③ 近代文学を愛する人への冒涜は断じて容認できない
だからってどうするのだろう。断じて容認できなかったらどうするのだろうと思う。これほど軽く使われている言葉は他にあるまい。それはもうほとんど容認しているということだ。
二万噸の××
この『三つの窓』の各章が「一等戦闘艦××」で始められていることに言及しないことは断じて容認できない。これは「一等戦闘艦××」の話なのだ。
昭和二年の一等戦闘艦といえば富士、朝日、敷島……いや、それにしても「二
芥川龍之介の『三つの窓』をどう読むか② 三つの窓はあった
文学が言葉を駆使しながらも曰く言い難いものとの格闘であるなどと今更お前のようなものから言われたくはないという拒絶が何処から生じてくるのかと云えば、それは男子便所につるされた金木犀の香りの消臭剤こそが饐えた小便の匂いを思い出させるからではなく、図書館一つ分の本を読み、身の丈ほどの高さに積み上がる原稿を書いてきた者の意地と云うものがあるからなのだろうか。
あるいは実際どうでもいいようなことをああ
芥川龍之介の『三つの窓』をどう読むか① 窓は一つしか出てこない
昭和二年六月十日の日付のある芥川龍之介の遺作の一つ『三つの窓』には窓は一つしか出てこない。
出てくる窓はこれ一つだ。書かれていない窓はない。例えば、
この「横須賀の町」が窓越しの景色ならば書かれていない窓があることになるが、SとA中尉は甲板に立っている。つまりそこに窓はない。
仮に川上未映子の『ウィステリアと三人の女たち』は三人の女たちが誰と誰と誰なのかが解らないと読んだことにならな
芥川龍之介の『古千屋』をどう読むか③ そろそろ読もう
古千屋は第二章から登場する。題名からすれば彼女が主人公だ。しかし話は第一章で一旦落ちている感じがないでもない。
古千屋は(記録上)実在した女である。ネタ元の台詞はこのようなものであっただろう。
つまり「塙団右衛門ほどの侍の首も大御所の実検には具えおらぬか? 某も一手の大将だったものを。こういう辱めを受けた上は必ず祟りをせずにはおかぬぞ。……」とは、
なんでわしの首実検せえへんねん。あ
芥川龍之介の『古千屋』をどう読むか② 矢の根を伏せて
さて、こんなことがもう解らない。
この「蓋の上に卍を書き、さらにまた矢の根を伏せた後」というところ、ここには芥川の創意はなく、ネタ元そのままの表現である。だから意味が解らなくても仕方がない、ということにはなるまい。意味が解らなければ読んだことにはならない。
しかしこれもまた「ハイポーが抜ける」同様調べられた気配がない。
まず「蓋の上に卍を書き」に関してはこの「寶冠」という風習にちなん
芥川龍之介の『古千屋』をどう読むか① 改元なんて怖くない
昭和二年五月七日に書かれたとされる『古千屋』はまたおかしなことをやってくる。あと何日かで死んでしまうのに。
どうも芥川龍之介には「改元」というものが引っかかっているようで、大正が昭和に変わったことに納得がいかないのか、元和元年四月二十九日などと書いてしまう。これは森鴎外が『堺事件』で、
「明治元年戊辰(ぼしん)の歳(とし)正月」と書いたひそみに倣ったものであろうか。言わずもがなこれは明治元
芥川龍之介の『長崎』をどう読むか① サント・モンタニ?
芥川龍之介の『長崎』は短い詩のような作品だ。
大正十一年の長崎旅行の後に書かれたこの『長崎』の中に二度現れる「サント・モンタニ」という言葉は、「さんた・もんたに」として『じゅりあの・吉助』において既に使われていた。
この「さんた・もんたに」は聖なる山と言う程度の意味であろうと考えてきた。が、もし長崎という場所で限定して「サント・モンタニ」とは具体的何を指すのかと考えてみると、
ここに
「ふーん」の近代文学25 汁粉はぜんざいか
三島由紀夫が最後の最後におしるこ万歳と言い出したことはよく知られていよう。それは自分が太宰と同じだと認める発言である。ところで夏目漱石と芥川の間、芥川と谷崎の間、芥川と太宰の間、織田作と太宰の間ではぜんざいと汁粉が奇妙に捻じれて見える。
この汁粉のネタからして漱石は汁粉が好きそうである。
ここを見てもそうだ。
この「汁粉、お雑煮」が鳥取では同じものになる。松山の雑煮は澄まし汁だが、