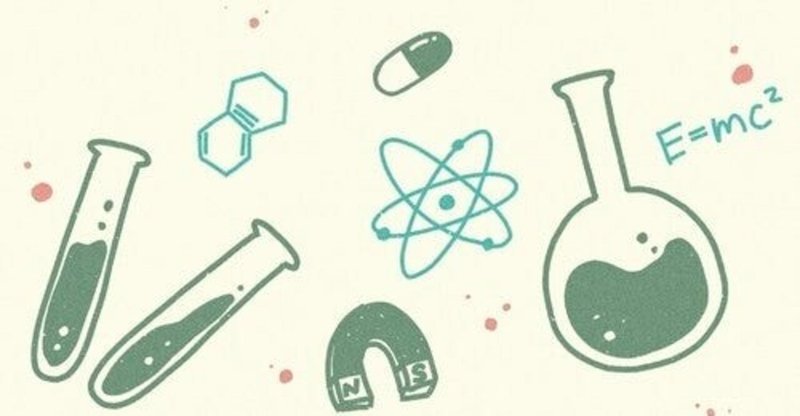2021年5月の記事一覧
分子の形
直線形、折れ線形、三角錐形、正四面体形などがあります。
分子内にある電子対どうしは、電気的な反発によって互いにできるだけ離れようとします。これを電子対反発則といいます。
(音声解説はこちらへ
https://stand.fm/episodes/60baa0c73612c6c2a2678674)
二重結合や三重結合のそれぞれの電子対は、まとめて1組の電子対とみなして考えてよいです。
例)メタ
電子式
電子式・・・電子配置のモデルを表したもの。
元素記号の周りに、最外殻電子を黒い点を並べます。
(音声の解説はこちら!
https://stand.fm/episodes/60b6a6a3a9cdfb7993722da3)
詳しく言うと、元素記号の上下左右に最外殻電子を分けてかきます。最外殻電子が5コ以上の時、電子対ができます。
対を作っていない電子を「不対電子」といいます。例えば、水素分子
イオンからなる物質の性質
電離・・・イオンに分かれること。
電解質・・・電離する物質。
非電解質・・・電離しない物質。
(音声解説はこちらへ!
https://stand.fm/episodes/60b558d8a9cdfb328e721455)
塩化ナトリウムはNaClは水に溶けやすく、その水溶液は電気を通します。これは、塩化ナトリウムが水溶液中でNa+ と塩化物イオンCl −に分かれます。このナトリウムイオンと塩化
イオン結合
(音声の解説はコチラへ!
https://stand.fm/episodes/60b4091055ceb513d5a47e28)
イオン結合
クーロン力、陽イオンとイオンの陰イオンの静電気的な引力による結びつきをイオン結合と呼んでいます。
静電気的な引力はクーロン力とも呼ばれます。
イオン結合でできた物質には、塩化ナトリウムNaCl、酸化カルシウムCaO、水酸化カリウムKOHなどがあります。
状態変化
音声解説はコチラへ!
https://stand.fm/episodes/60b1673c55ceb5e1d1a4501c
https://stand.fm/episodes/60b2c2cc55ceb51288a46768
固体、液体、気体の3つの状態を物質の三態といいます。
氷が水に変わり、水が水蒸気に変わる。このように、同じ物質でも、温度を変えていくことで状態も変わっていきます。これ
物質の分離法
■分離とは混合物を純物質に分ける操作を『分離』といいます。
(音声の解説はコチラへ!
https://stand.fm/episodes/60a97e96ff44a47933f94050
https://stand.fm/episodes/60aacfd3ff44a4fdfff9589c)
混合物は純物質が混じり合ったものです。代表例に、空気、海水、石油などがあります。空気は主に窒素と酸素など
主な原子の酸化数の変化
原子の酸化数は1つに決まっているのではなく、いくつかの値をとります。
(音声の解説はコチラへ!
https://stand.fm/episodes/60a82b5b2a1ed9793c092e31)
これを「酸化数のモノサシ」や「酸化数のはしご」等ということがあります。窒素N、硫黄S、塩素Cl、マンガンMnなどが有名です。
それぞれのSの酸化数について、( )内が酸化数を示します。
H2