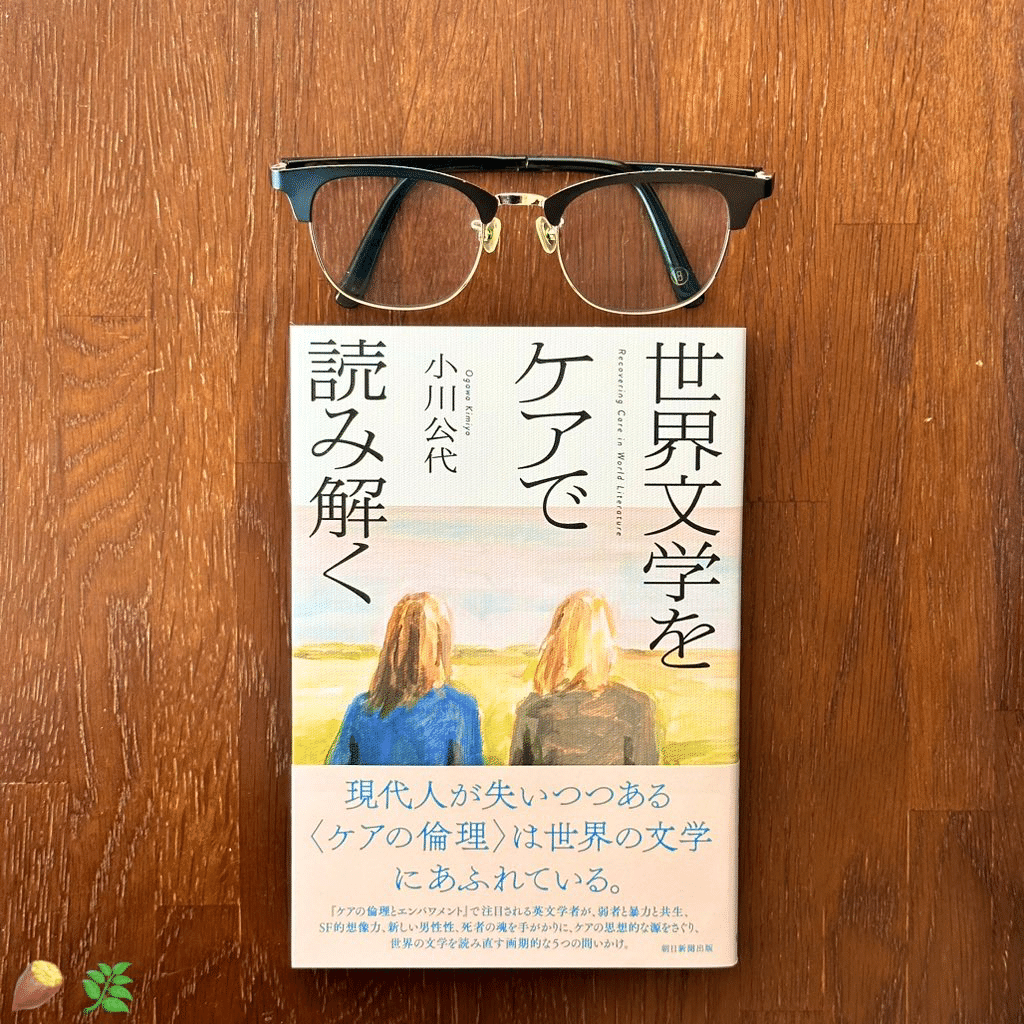#ふと考える
https://note.com/imogine_note/n/n1b1a2dd30731
↑先日つぷやいたことは日頃考えていることなのだけれど、自分のやってきたsmileへの姿勢はこの本の言わんとしている《ケアの倫理》だったのだな…と涙してしまった…(小川公代さん『世界文学をケアで読み解く』。特に「あとがきにかえて」の所)
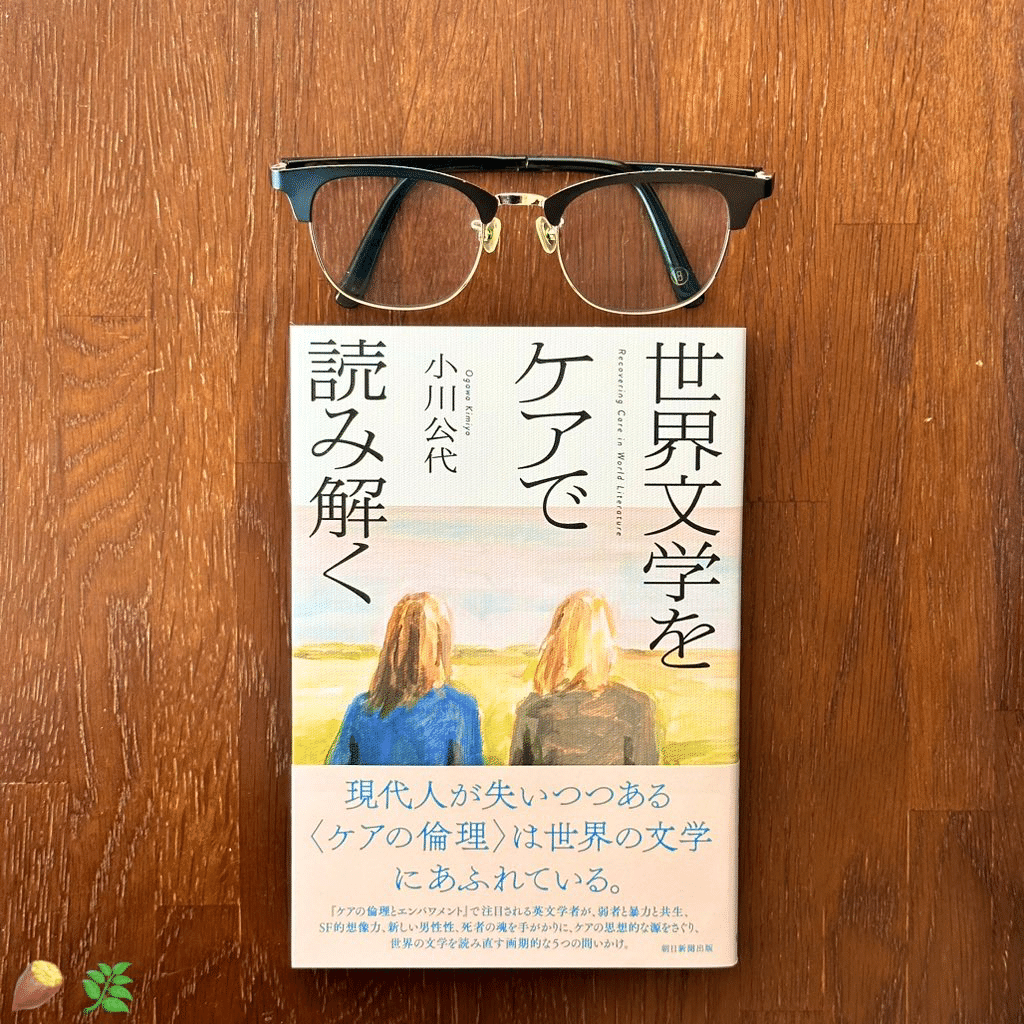
https://note.com/imogine_note/n/n1b1a2dd30731
↑先日つぷやいたことは日頃考えていることなのだけれど、自分のやってきたsmileへの姿勢はこの本の言わんとしている《ケアの倫理》だったのだな…と涙してしまった…(小川公代さん『世界文学をケアで読み解く』。特に「あとがきにかえて」の所)