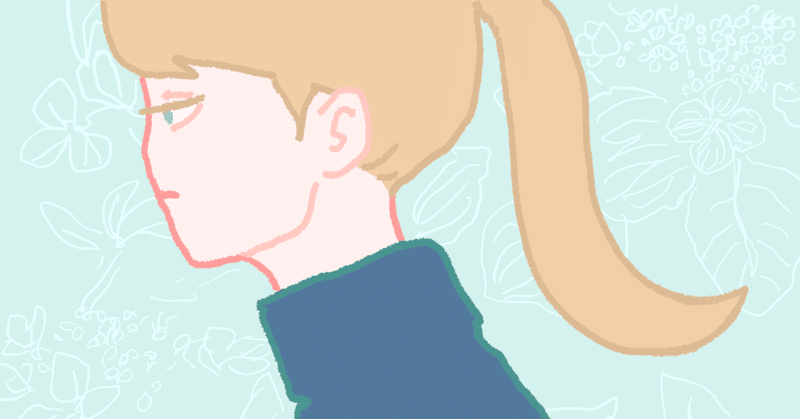
とうぜん、すきなことを仕事にするだけが正解ではない
「これあげる」
朝起きて、手には何も持っていない。
家族の癖。108円の果汁グミが大好物で、いまもずっと食べ続けている。やりたいことがあったのか、それとも焦って、やりたいことを創ったのか。恐らく後者で、背徳感を抱けるだけ自分をやさしい人間だと思い込んでいる。涙がないと、人の頬を撫でられない。
自分が納得できるように、先回りしている。
「保険」と呼ぶかもしれないし、「怠慢」と呼ぶかもしれない。感動的な映画を見て、勇気をもらう。水道水は独特な味がするし、アスファルトを舐めると、天気の味がする。
「ごめん、遅くなりそう」
姉は、好きなことを仕事にしているわけではないらしい。目指そうと思っていたのか、とてもじゃないが、わたしの口からは聞けない。絵を描くのが上手な人に向かって、「絵で食べていけば?」と簡単には言えなかった。
◇
「今日ですよね」
心配そうな声を漏らしていたのは、恋人の彼。一つ屋根の下、わたしは彼とふたりで生活をしている。何かあればわたしは彼にまず相談をするし、何かあれば彼はわたしに話をしてくれる。
食べ物だって、言葉だって、洋服だって、下着だって、ベランダにあるサンダルだって、恋人とは分けあえる。お腹いっぱいなら、わたしが代わりに食べるし、お腹が空いているのであれば、その分わたしが働けばいい。
ふたりして、仕事帰りにシャンプーを買ってきてしまった。「あと何日一緒にいられるかな」と、いつだって考えてしまう。お互いが生活用品を切らさないようにしている、それにたまらなく愛を感じてしまうのはわたしだけだろうか。電気はきちんと消して、便座のふたは閉める。ふたりとも、立ったまま小便はしない。そんなところもわたしが愛しているとは、彼も思っていないかもしれない。「好き」を言い合うだけが、恋愛の正解ではないのである。
「いつも通りでいいですよ」
逆の立場だったとしたら、そんな台詞を聞いても入ってこない。それでもわたしは彼に言っていた。その日はわたしの姉が、わたしたちの家に来る日だった。「結婚」が決まったわけでもない。家族には彼のことを見てほしかったという、大きな大きなエゴから話は始まっていた。
「がんばります」
彼はそう呟きながら仕事でいつも使っているカメラを撫でていた。同棲してから知ったが、彼はカメラを抱えていると落ち着くらしい。わたしが日記を書いて体を休める瞬間があるように、彼にとっても、そうなのだろうか。
彼は写真家として生きている。一方わたしはと言うと、チェーンの飲食店で働いている。パッと見、好きなことを仕事にしているのはどちらだと思うか。とりあえず言えることは、わたしには、自信がない。
「もしもし」
夕方、姉から電話が来たので出ると、少し焦っているようだった。会社で急な会議が入り、定時には上がれそうにないとのこと。「ゆっくりでいいからね」とわたしが言うと、「でも爆速で向かうから!」とそういう言葉遣いなのが、姉だった。
電話を終え、彼の方へ目をやると、今度はカメラをコロコロに持ち替え、部屋の掃除をしていた。正式名称は粘着カーペットクリーナーというらしい。それも彼に教わったし、沁みるように緊張してくれる彼にわたしはやはり、惚れているようだった。
◇
「駅もうすぐ着くよ」
そう姉から連絡をもらった頃、わたしたちは駅前のカフェでアイスコーヒーを飲んでいた。落ち着いたいつもの店内。普段ゆっくりと飲むのに、その時の彼はスポーツドリンクかのように飲み干す。氷は当然、溶けきっていない。「早いですね」と茶化すと、彼は「ばっちりです!」と言葉を零す。愛しい。ずっと、愛しかった。
会計を済ませ、歩幅を合わせて駅へと向かう。単に強がっていただけのようで、何万回と会っている姉の到着を前に、わたしもそこで震えだす。恋とは違う"ひりつき"だった。もしかすると、大事な日が始まろうとしているのではないかと思う。
「たぶん、次の電車から降りてきます」
改札口を前にしてふたり、並んでいる。夏でもないのに、蒸し焼きにされているみたいに暑かった。きっと、天気のせいだけではない。
緊張が伝わり、笑い声が伝わり、涙、愛、それよりももっと曖昧で深いものをこれからも伝えあうのだろう。考え込む、その瞬間。どこからともなく、"わたしたち"を呼ぶ声がした。
「しをりちゃん!」
黒と灰色ばかりの景色に埋もれない、姉はルビーレッドのトップス。すーっと、わたしの脇から水が流れる。家族と会うだけなのに、緊張をした。当然、人生で初めての体験だった。そんな姉に向かって食い気味に、脆い硝子のような声で彼は言う。
「はじめまして。しをりさんとお付き合い、を、させ、ていただいてます。〇〇です…!!!」
甘噛みをしながら、言ってくれた。そこはさほど関係はなく、そこそこに人がいた駅で声を張ってくれたことが、わたしはたまらなく嬉しかった。繰り返しになるが、そういうところが、好きなのだ。
震える小動物のような彼、そしてわたしを見て姉は、「最高じゃん」と笑う。彼とお付き合いをしていることは話していたが、直接顔を合わせたのはその日が初めてだった。
三人で歩くだけで、いつもの景色は全く違う世界。実際は見る余裕もなかった。もう、何も考えられなかった。喋り続ける姉は何も気にしていなそうで、開けっ放しのカバンの中には108円の果汁グミが入っている。
◇
「ただいま!」
玄関を開けて、まず第一声。それを零したのは、姉だった。
「姉ちゃんはただいまじゃないでしょ」と思わず本音とは違う言葉が漏れる。そんなわたしに向かって姉は「家族が住んでる場所に入ったら、ただいまなんだよ!」と、言う。愛を前に緊張し、失言をしてしまった。その横で、いつの間にか ほぐれた表情をしている彼がそっと、見えないところで手を握ってくる。何が幸せかは、前から知らされていた
姉には、わたしと彼の手料理を振る舞った。それを「美味しい、美味しい」と言いながら過ごす姉は、よくある「お互い、どこが好きなの?」といった質問をしてくることはなかった。ただただ、いい意味でわたしと彼のそばで笑ってくれた。
食べ終わった頃、姉はおもむろに一枚の白い紙を取り出す。何をするかと思えば、そこに絵を描き始めたのである。
見慣れた姿。絵を描くことが好きな姉はいま、印刷会社で事務の仕事をしている。仕事で絵を描くことは一切ないらしい。そんな姉が描きながら、わたしに問いかける。
「しをりちゃん、最近エッセイ書くのどう?楽しい?」
姉は知っている。
わたしがこうして毎日エッセイを書いていることを。飲食店で働くわたしは、エッセイを書くのが好きで、それでほんの少しお金もいただいている。好きな気持ち、それはきっと姉の絵と同じように。けれど、違うところもたくさんある。
「楽しいけど、たまに苦しいかな」
正直に、心になるべく近い形で返事をする。
彼は写真家で、好きなことを仕事にしているらしい。わたしも、そうなりたい。本音は、エッセイを仕事にしたいのだ。それも姉は全て、知っている。
少しの沈黙の後、あっという間に姉は描きあげる。そこには、わたしと彼の似顔絵が描かれていた。贔屓ではない、姉はとんでもないほど絵が上手かった。
「これ、ふたりにあげる」
わたしが覚えている、一番昔の記憶をひっぱりだしたとして、その横で姉は必ず絵を描いていた。何十年とそれを見てきた。そんな姉は美大に行って、それでも「絵では食べていかない」と、何かを堪えながらわたしに言ってくれたのはつい最近の話。本当はそれも疑っている。その疑いが意味をなさないこともわかっていながら——。
何をして生きていくか、日々わたしは必死に探している。彼を愛し、そこから先の未来で、自分が何をしているか想像する。「仕事」として成果を中々出せない、ただひたすらエッセイを書くことしかできないわたしのことも、知っていたのか。その日、一番やさしい声色で姉は言う。
「仕事をしてお給料をいただいて、そのお金でごはんを食べて、寝るおうちがあって、家族にプレゼントを渡せたりして、それで姉ちゃんは幸せ者なんですよ。弟よ、どうだい?」
どこかから聞いたり、本で読んだりした。
"好きなことを仕事にしている"と話す人が、「やりたくもない仕事をしてるの、地獄じゃない?」という台詞を使っている。姉は昔もいまも、仕事は「やりたくない」と言う。そんな姉は、屈託のない笑顔で自分のことを「幸せ者」だと言う。
当然、正解はひとつではないし、人によって正解は違う。それが合ったとしても、世の中には大まかな「正解」があるのだろう。そして自分にとっての正解を、誰かに「正解だね」とも言ってもらいたい。わがままはこのまま、最期まで続いていく。
何がしたい?
何をしていたい?
何を愛していたい?
誰を、愛していたい?
人は、わたしは、何を基準にして生きているのだろう。
「しをりちゃん、たのしいね」
少女のようだと思う。ただそれ以上に、痛みを堪えながら笑っているようにも見える。
「なにをして生活したい?仕事じゃないよ、生活の話」
いつだってやさしく聞いてくれるから。改めて彼の隣でわたしは考える。自分との対話を、空に描いた。
エッセイを書きたい。だったら書き続ければいい。
彼を愛したい。だったら愛し続ければいい。
結婚を認めてほしい。だったら自分たちを認めたらいい。
わたしが描き終わるタイミングを見計らっていたのか、少しの間を置いて、姉は彼に話しかける。
「ねえ。"なにをしてる"しをりちゃんのことが好き?」
姉は"そういう質問"はしてこないと、油断していた。
思わずわたしは、気圧されたように息を吸い込む。なんと答えるのか純粋に気になってしまった。エッセイを書いているわたしか、仕事をしているわたしか、それとも、愛か。特に考え込む様子も見せず、彼は言う。
「"しをりさんが"好きなので、あまり考えたことないです」
.
.
「だってさ」
姉は得意げに笑う。
恵まれすぎている自分を抱きしめながら、これからの世界に求めるものを忘れていた。ほとんどの悩みは、贅沢からきている。わたしはいま、なにがしたいのだろう。そうだ、わたしは生きたかった。
「愛」を愛している。
"どんな彼"が好き?と訊かれれば、やっぱりわたしも"彼"が好きなのだ。そこから始まって、そこで終わる。
絵を描く姉と、姉を比べない。
写真を撮る彼と、彼を比べない。
エッセイを書くわたしと、わたしを比べない。
「生きている」
それだけで愛される、社会になってよ。
書き続ける勇気になっています。
