
あの時、ボスからの言葉とウイスキーは苦かった。
生きていると 様々な場面で重要な選択を迫られることがある。
どの選択をとるべきか迷っている時に
声をかけてくれる人は、大抵 こちらの気持ちに寄り添って考えてくれるだろう。
一方で 時には、厳しい(と思える)言葉をかける人も存在する。
なぜこの人は、この局面でこんなことを言うのだろう?
その時は、やはり そう思ってしまうものだ。
しかし、実は 一見 厳しくも見える言葉をかけた人こそ、結果的に正しいことを言ってくれていたり
本当の意味で、温かい人だということがある。
これまでの人生、何度かそうした場面を経験した。
一番忘れられないのは、大学時代、就職活動中に 私のボス こと 指導教官との会話だ。
厳しくとも温かい、私にとって忘れられない 最高の恩師。
きっとこの先も忘れることのない宝物だ。

入学式に学生を怖がらせる挨拶をしたボス
大学の入学式。私は意識せずとも、式の前には既に同じ学科の数人の学生と親しくなっていた。
「帰りにケーキ食べて帰ろう」
「うん、その前にお昼ご飯も食べようよ」
そんな感じでワイワイしていた。
式が始まると一転、緊張感が漂う。
私たちは英語学科で 各クラス毎にひとりひとり名前が呼ばれた。
名前を読んだのは、厳しそうなおじさん教授風味が漂うボス。
全クラス全員の名前が呼ばれたあと学部長挨拶で ボスが壇上に上がった。
「なんか怖そう...」
私たちは静かに話す。
咳払いをしたあと、おじさん教授は一言こう言った。
「入学おめでとう。
私は英語学科担当だが。
君たちの中に、
”この大学の英語学科なんだから
客室乗務員になりたい” とか、
”英語をペラペラ話したい”
なんてバカな夢抱いてる者がいたとしたら、甘いぞ。
大学生活でしっかり現実的と向き合え。」
講堂は静まり返った。
しばらくするとえー、なんでよ?とか 怖いとか口々に言い出す学生もいた。
「面白いじゃん あの先生」
「やっぱほしまるもそう思う?」
私を含めて数人以外は、入学式初日にボスのことを大嫌いになった。
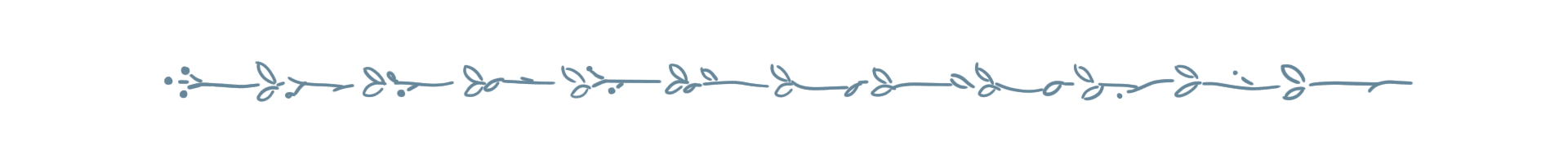
ボスと学生生活
「なんでそんな訳になるんだ?
理解できない」
「おい、君はこの前も間違えたな?
もう一回高校からやり直すか?」
必修の英文読解は毎週、ボスが担当だった。
毎週、2~3人が担当して英文を音読し、和訳を発表するのだが。
必ず誰もがボスから小言を言われる。
けれど、ずっと小言ばかり言ってる偏屈なおじさんではなかった。
学生の良いところは素直に褒める。
そんなボスに「頑固でイヤなおじさん」という印象を持つ学生は徐々に減っていた。
ボス、実は寂しがりやなのかも?
ボスは講義中などでもよく話していたことがあった。
「大学において、
教授と学生の心温まる交流など
幻想に過ぎない」
教授と学生は 飲み会に行ったりすることもあり得ない、とボスは言っていた。
けれどボスは、学生を避けていたわけではない。
私も含め、私と親しい仲間たちと学内で会えば、ベンチで会話を楽しんでいたし。
廊下ですれ違うと、
「ほしまる、
コーヒーを買ってきてくれないか?」
と小銭を渡す。
「はい。砂糖なし、ミルクなしですね」
「そのとおり」
そのときも、コーヒーを研究室に運んだときもとても嬉しそうなのだ。
だから私は、この時とばかりにチャンスを狙って研究室にあるボス所有の洋書や参考文献を沢山借りた。
「ほしまるは、
本当に 本や学問が好きなんだなぁ。
これも持っていきなさい」
「ありがとうございますー」
いつもどっさり本を借りて研究室を出た。でもいつも言われていたことがあった。
「勉強熱心なのは認める。
でも俺のゼミには来るなよ」
そう言って苦笑いしていたボスに私は見抜かれていたんだろうか。
もともと、私は ボスがどんな人なのか知る前から学内一厳しいと言われている ボスのゼミに入るつもりでいた。
「おい、ほしまる。
お前ほんとに来たのか?」
ゼミの希望提出の時に、私の在籍クラス(つまりボスが担任のクラス)からボスのゼミに希望をだしたのは私1人だけだった。
「物好きだなぁ、ほんと」
そう言いながらボスはまた美味しそうにタバコを吸う。
「徹底的にしごくぞ。
ついて来れなくてもしらないぞ」
はいはい、わかってます、そう言って会釈してから私は研究室を出た。

ゼミ生とボスとの熱い日々
ゼミは忙しくも本当に充実していた。
ゼミ生みんな、知的好奇心が強く、また総じてレベルも高いので発表も議論もとても熱かった。
「果たして君の解釈で
正しいと思うかな?」
「この時の時代背景を考えているかな?」
ボスの指摘はとても鋭い。
でも、私も含め 誰1人ボスの質問にたじろいで黙ってしまう学生はいなかった。
就職活動と葛藤
就職活動が始まり、慌ただしい日々になった。
周りの仲間や友人たちが 説明会やセミナーにあしげく通う中、私自身 迷いがあった。
大学在学中に留学していた時にも考えたことだった。
日本を出て、初めて外から多角的に日本、そして日本におけるちっぽけな自分というものを考えた機会を得た。
なぜ働くのだろう、とか、皆と同じように就職活動をすることは正しいのか、とか。
もしも内定先が決まったからといって
そこで就職していいのか、などということをぐるぐると考えていた。
本音を言えば、私は 研究の道に進みたかったのだ。
研究したいことも、テーマもかなり早い段階で明確に決まっていた。
遠回りでも別の大学の、希望の学部に編入して大学院に行きたい。そう思っていた。
けれど、親元から通う私としては大学入学の時に 両親と約束したことがあった。
「編入か留学、どちらかに行きたい。
もちろんバイトも沢山する」
大学に入学してからは 結果として、留学を選んだために、必然的に編入の道はあきらめた。
長女だから、これから妹も大学など通うことを考えるとこれ以上親にお願いするわけにもいかなかった。
とはいえ、どんな職種 どんな会社を希望するのかすらわからないまま説明会やセミナーへ通っていた。
☆
少しずつ、希望する職種も固まってきて資料を取り寄せたり、就職課にも通っていた。
就職活動と講義とゼミ、卒論。
毎日くたくたになっていた。
そんなある日のことだった。ゼミの用事で ボスの研究室を訪ねるとボスがふと尋ねた。
「ほしまる、今日これから時間あるか?
冬さんと、これから飲みに行くんだが」
冬さん、というのは ボスと長い深交のある、学部内の おじさん教授だった。
私は 当時、冬先生の ある古典言語の講義を履修していた。
私が通っていた大学はキリスト教系の大学だった。
聖書やキリスト教、比較宗教学などの講義も多数あった。
私自身は無神論者だが、純粋に様々な宗教のことを学べたことは意義があった。
冬先生の講義も、古典言語 しかも 日常生活で使わない言葉なんて不要にも思える。
けれど、毎週 アルファベットを覚えることだけでも楽しかった。
「ほしまるくん、たまには息抜きしようよ」
冬先生にも言われたら断るのも申し訳なく思った。家に電話を入れて、私はボスと冬先生についていった。
二人の教授に連れられてジャズバーへ
ボスと冬先生に連れていかれたのは、アンティークなジャズバーだった。
大人なお客さんたちが ゆったりとお酒を飲み、音を楽しむ。
こんな素敵な空間に 大学生の小娘が来て良いものか 迷っていた。
背伸びをして 先生たちの キープしている ウイスキーをいただいた。
「ほしまる」
「はい?」
「あのな、お前 就職するな。
どこも取ってくれる企業なんてないよ」
ウイスキーを吹き出しそうになる私。いきなりボスにそんなことを言われるなんて思わなかった。
「就職なんてやめた方がいい」
「...なんでそんなことを言うんですか?」「ほしまるは
企業勤めに向いてないからだよ」
顔が熱くなる。
飲みなれないウイスキーで火照ったのか?違う。
ボスの決めつけに、多少腹が立っていた。
「ほしまるくん、
僕も、君は研究者になるべきだと思うんだ。
君ほど熱意ある学生はいないよ。
いつも フミ(ボスのこと)とも話してるんだ」
冬先生は優しくそう話す。
でも私の顔の火照りも熱さも消えない。
「...私は内定もらえないと思ってるんですか?だからそんな風に言うんですか?」
気づけばそんな言葉が口から出た。
「帰ります。お先に失礼します」
足早にジャズバーを出た。
なんで涙が出るんだろう。
そのまま電車に乗る。ドアが閉まった瞬間、私は座り込んで泣いてしまった。
「就職に向いてない」この言葉は当時の私にはつらかった。
私たちの年代は就職氷河期が始まったばかり。
かなり苦戦したもののそれから間も無く、私は2社から内定をいただいた。

大学卒業までの日々
卒業を控えた年は全て本当にあっという間に過ぎていく。
ゼミも佳境になってきて恒例の文集作りも始まっていた。
「内定もらって、決めました」
「そうか、ご苦労さん」
その会話以外、ゼミでも ボスと私が雑談をすることはほとんどなかった。
ちょうどボスに借りていた卒論の参考資料を返しに行った時のことだ。
「もうじき、
お前たちも本当に卒業しちゃうんだなぁ」
その時のボスの背中がとても寂しそうで。私から呼び掛けて、ボスとゼミ生で ゼミ打ち上げを企画した。
「俺は行かないぞ」
そんな風に言っていたボスも当日はとても楽しそうにしていてその様子がとても嬉しかった。
謝恩会でも、振袖姿の私を見るや否や
「本当に馬子にも衣装だな」
とボスは苦笑いする。
そんな憎まれ口を叩きながらもその時撮ったゼミ生との写真では思いきり最高の笑顔でボスは笑っていた。
最後に:ボスは私を見抜いていた
ゼミの文集には末尾にボスが手書きで1人1人に手紙のようなメッセージをくれる。
手にして読んだときに私はボスの本心がわかった。
ボスは 私が 本当は研究者を目指していたことを見抜いてくれていた。
そして私の可能性や素質を、とても評価してくれていた。
それだけでなく、ボスは宿題を与えてくれていた。
「この解釈、いつか君には解けるかな?」
「いつか君から答えを聞けると信じている」
ボスが笑みを浮かべながら書いている姿まで私は想像できた。
☆
卒業から10年ほど経った時のことだ。
私は結婚してから 再び大学生になった。
ボスの下で学んでいた時に 関連領域として興味を持った学部の社会人学生として編入した。
「君はやはりそうすると思っていたよ。」
社会人を経て、また大学に編入しますと連絡した私にボスはそう言って笑っていた。
「若いやつらになんか気後れせず、
がんばれ。
思った道を信じて行け」
ボス。あなたの言うとおりでした。
私は【ふつう】じゃないから。
社会不適合者だから。
だから、企業勤めは人一倍向いてなかったんですね。
ボスは、そんな私の弱点とも言える特性を見抜いてくれていた。
そのことに気づくまで本当に時間がかかりました。
ボス。
もしも今の時代だったら、ボスはあの言葉の本当の意味を
メールやLINEで教えてくれたかな。
きっとボスは、
「私は、スマホもパソコンも持たない!」
なんて意地張ってるんだろうな、と思います。
ボス。
私は残念ながら、病気をしたことで研究は志半ばであきらめたけれど。
私、まだ諦めていませんよ。
ボス。ずっと見守っていてくださいね。


この記事が参加している募集
この記事を気に入っていただけたら、サポートしていただけると、とても嬉しく思います。 サポートしていただいたお金は、書くことへの勉強や、書籍代金に充てたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
