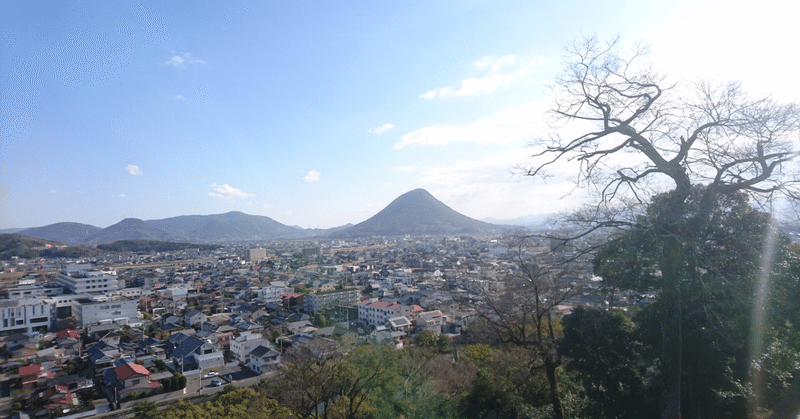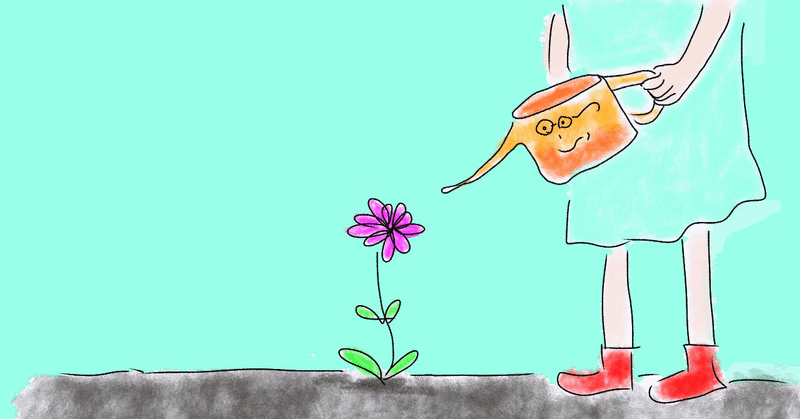2021年5月の記事一覧
性、相近し、習い、相遠し (論語 陽貨篇)
(意味) 人は産まれもった特質に大きな差異はない。だが、習慣や努力によって大きな差がつくものだ。
非常に簡潔な言葉の中に二つのメッセージを込めています。
性 孔子はまず、人間のスタートラインはさして変わらないものだ、と述べています。とはいえ、産まれた直後から自らの意志で生きてきたわけでもなく、環境に左右されながら、考え方や行動、習慣が形成されてきたことになります。
皆さんもこれまで生きてこられ
不憤不啓 不悱不発(憤せずんば啓せず、悱せずんば発せず) 「論語」(述而篇)
「啓発」の語源となる言葉。
「やる気」の無い人には何を無理矢理施しても仕方ない、という意味。やる気を出して勉強しなさい、と門下生に発破をかけている言葉である。
仕事において、何を施さなくとも主体的に動く人と、やる気のかけらも見せない人がいる。それぞれの人たちには、そのような状態になる必然的な背景があるはずだと思う。生まれもった資質、これまで生きてきた経緯から、その人の傾きがちな方向はあるだろう
訥言敏行(君子は言に訥して、行いに敏ならんことを欲す) 「論語」(里仁篇)
「論語」や「韓非子」で学んだことを自分の行動原理として定着させること、仕事に活用すること、これはnote始めてみようと思ったきっかけの一つです。
これらの書物には現代を生きる私たちの生きる指針になる、いわゆる名言格言が並び、これを超訳されている解説書を読むわけです。私はよく守屋洋さんの解説書を拝読しています。数多く執筆されており、自然と守屋さんの書に触れることになりました。
さて、タイトルの