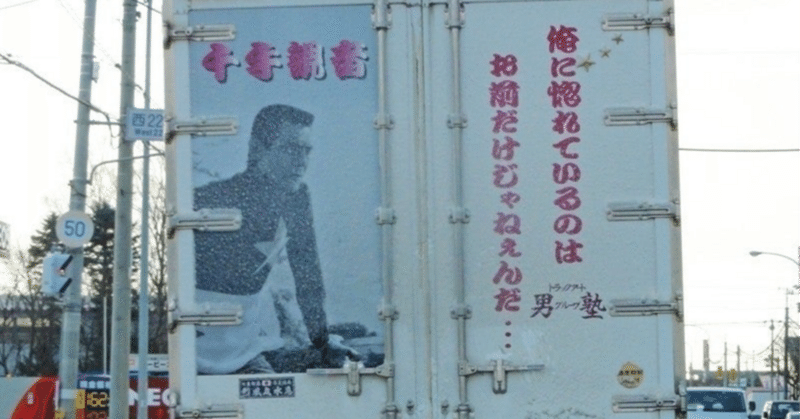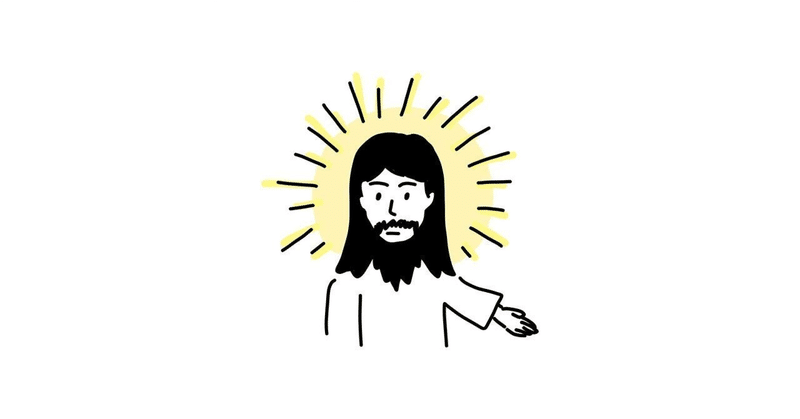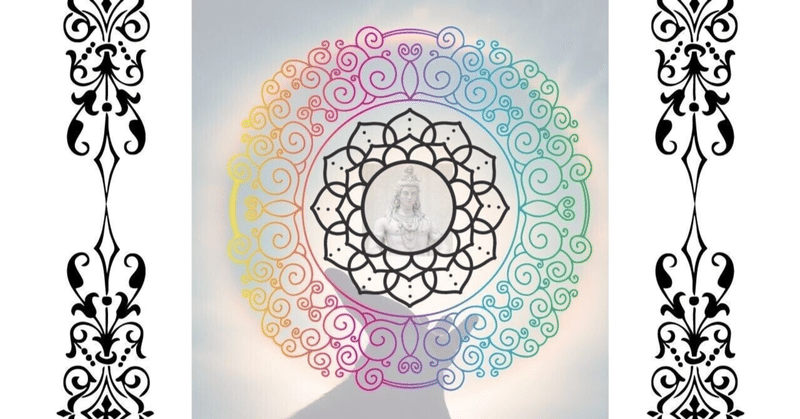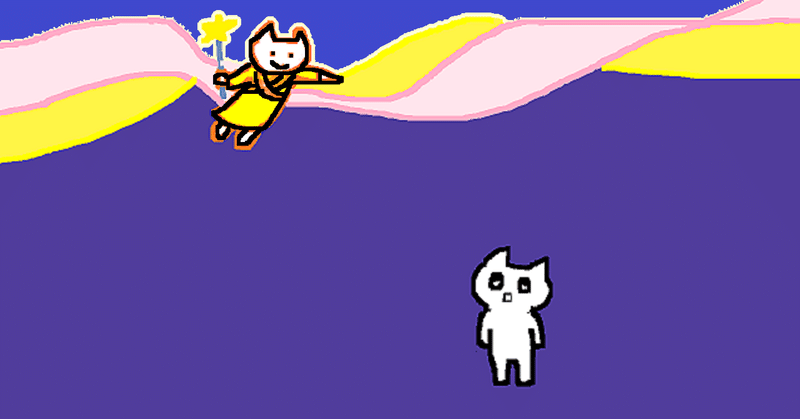#反省
生き方の原典 3章 意念の統制 104【何事も人のせいにする身の程知らず】
いけない霊にやられている人ほど、自分の考えが良いと思って反省しない。
良い事があれば自分の手柄、悪い事があれば人のせい、霊魂のせいと考える。
地上のことは全て霊的なものだが、今の自分にちょうど良い霊が働くのだから、結局、霊が悪いのではなく、人が悪いのではなく、自分が悪いのである。
生き方の原典 1章 人間と霊魂の働き18-20【勝負の背後に霊魂あり・霊魂を動かすのは心】
オリンピック競技にも、すべて霊との関係あり、まず選手となる者は、先天的な備わっているのが原則である。場合によっては後天的な才もあるが、このときも先天性が隠されていたのが、後に発揮されたというのがしばしばある。
第二に、本人がこの才を自覚して努力練習すること。
第三は、本人の心掛け、統制された調和の心を持つことである。
先天性とは本人の使命ということである。しかしこれがあっても、訓練無くして才は発