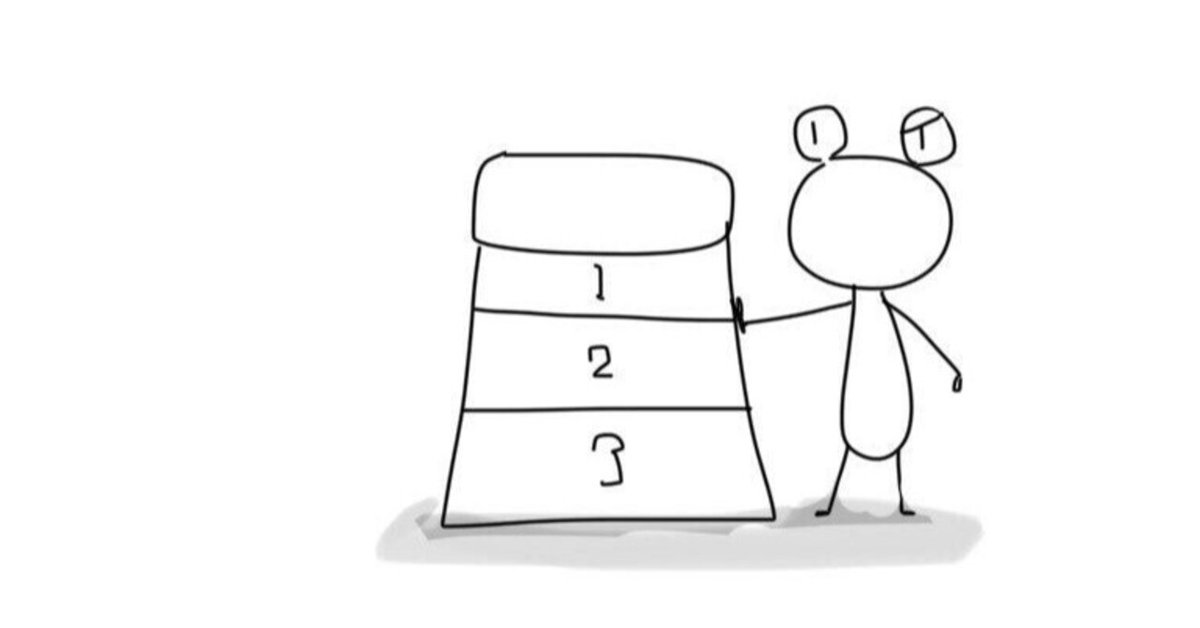
書くという行為の踏切板〜「書く習慣」
「何か書きたいのに書けない」「どうしても発信することをためらってしまう」…。
そんな悩みを抱えた人にとって、跳び箱の踏切板のように心強い本が出版されました。
フリーライターで、noteでも多数の記事を投稿しているいしかわゆき(ゆぴ)さんの「書く習慣」です。
SNSやブログ、そしてnoteなど、個人が発信する敷居が下がった一方で、「何を書けばいいのか分からない」「発信することに抵抗がある」声が多いのも事実。
そういったジレンマを抱える人たちを主に対象とした、「書く」「発信する」ことへのハードルを下げ、楽しめるようになるヒントを著者ならではの飾らない文章で綴った本です。
私は本書をフォローしている方のnote記事で知りました。著書に関するご本人の記事やレビュー、note記事を読んでみて、半年間のブランクからnoteを書きあぐねいていた自分にもこの本が必要かもしれない、と確信めいた予感がしました。
気になった本はまず、kindle版があれば無料サンプルを読むのが私の習慣。
「書く習慣」はサンプルページが多めに用意されていて、読者の敷居を下げる親切心を感じられました。
また、元になったゆぴさん(多分こういう呼び方のほうがご本人に似合う)のnoteマガジンも併せて読み、結果「全文読みたい」と電子書籍版を購入して読みました。
マガジンはこちら。
ここからは、本書で特に「そう!それなんだよ‼︎」、もしくは無言でしみじみとうなずいた章を挙げていきます。
なお、引用ページは全て電子書籍版のものです(2021.10.28追記)。
①「落ち着いたらやろう」は絶対にやらない…まずは行動あるのみ
なにかをはじめようと思ってもなかなか着手できない人は、「とりあえずはじめてしまう」のが一番オススメだったりします。
(中略)「準備」は大切なものです。でも、準備をしているあいだにやる気がなくなってしまったり、時間だけが過ぎてしまったりするのは、すごくもったいないこと。
(P154、157より)
私はnoteを再開するにあたり、新たな方向性を打ち出してから記事を書いていこうとずっと足踏みしていました。
書きたいことはいくつか思いついてはいましたが、結局方向性は不透明のまま、ただ頭の中で答えの出ないひとり会議を繰り返すだけでした。
そこにある一文がガツンとクリティカルヒットしました。
「明日やろう」は馬鹿野郎なのです。
(P155より)
「机上の空論」とはよく言いますが、頭の中にうっすら書きたいことの下地があっても、傍から見ると私のnoteは止まったままです。
方向性なんかくそくらえだ。まずは書きたいことを記事にして投稿してしまおう。
これで私はある日の出来事を投稿し、少なくとも馬鹿野郎からは卒業しました。昔好きだったSURFACEも「動き出さなけりゃ何も始まらない」って歌っていたのを思い出します。
あとは息切れしない程度に継続あるのみです。
②「うわぁ~」と思ったら「うわぁ~」と書いてしまえ…建前という自意識を捨てて本音を書く
いざ文章を書くとなると、急にかしこまる人がいます。
「いや、普段そんな変な話しかたしてないじゃん!」と突っ込みたくなるほどカッチカチな、まるで論文のような文章です。
どんなに話し上手でも、不思議なことに「文章にしなくちゃ」と思うと、急に言葉遣いが変わってしまうことがあるのです。
(P65~66より)
「~だ」「~である」口調の記事が多かった私は身につまされました。趣味で書いている小説も、書き始めた10代の頃から「文体は硬めだね」と評されていたからでしょう。
自分でも「この文体だと本来読んでほしい層の方に届きづらいだろうな…」と投稿後思うこともしばしばでした。
また、別の章『「あのクソ野郎」に共感が集まる!?』からも一部引用します。
飾らない本音だから、面白いんです。本音だから、読まれるんです。
(P284より)
綺麗事ばかりを書いてきたつもりはありませんが、建前を気にしてソフトな言い回しに変えていた文章が今までに結構ありました。
私は人一倍、自分が他人にどう思われるか気にしてしまう人間です。自意識過剰です。
頭の中では「誰も何も思っていない」のを知っていますが、過去のトラウマのせいか、悪く思われないよう必要以上に気を遣って気疲れしてしまうのです。
自覚していた分、「私の言いたいことはもっと違う」というジレンマをずっと感じていました。
ムシャクシャしたことなど、特定の誰かへの文句はネットでは避け、適当な紙に書いてビリビリに破って捨ててしまえばいいとして…
「あれ、今建前でいい感じに書こうとしているな」とセンサーが働いたら、一旦削除してもっと生々しい、心の底からの声を綴ってみることにします。
③反応がなくても、みんな「ひっそり読んでいる」よ…「いいね」「スキ」より別のことに重きを置く
「いいね」にこだわるとモチベーションが下がる。「読んでいる人は確実にいる」と信じてみよう。
(P299より)
「いいね」「スキ」の数はどうしても心が振り回されます。
1つでも増えると嬉しいし、思ったより少ないと私の場合「何がいけなかったのだろう…」とあら探しをしてしまう悪い癖があります。
これについては非常にためになるnote記事を読んだので、紹介させていただきます。
「スキ」をモチベーションにして走っていける方はよし、振り回されて投稿にまで影響が出てしまう私と似た方は、「スキ」でなく別のことに重きを置いたほうが精神的衛生を保てるはずです。
私は「記事を書くことそのもの」「好きなことを書く」「記事を増やす」ことを楽しみながら頑張ることにしました。「スキ」への感謝の気持ちだけは忘れずに。
④誰でもなく、「自分のため」に書いていい…自分語りが悪いなんて誰が決めたのだろう
世にあるもののなかに、いかに「自分語り」が多いかわかると思います。
だから、「自分語りになっちゃう……」なんて悩むことは杞憂です。
むしろ、自分語りをするために書いていい。
「誰かのために書こう」「誰かにとってタメになる話をしよう」なんて考えるのは、もうちょっと先の話。
(P46~47より)
これは本書の最初のほうに載っている内容ですが、私が一番「ああ、それでいいんだ…」と安心できた内容だったので、最後に引用させていただきました。
著者のゆぴさんは自分語りに否定的な風潮を「やさしくないインターネット」だと苦言を呈しています。
私もある本のレビューで、「自分語りが多い」とさもマイナスポイントのように書かれているのを読んだことがあります。
自分語り=悪いことなんて、誰が決めたのでしょうか。
私はnoteの記事でも個人的な日記やエッセイを興味深く読みますし、世の中に出回っている本でも著者の体験や思いを読むのが好きです。
ただ自分で書くとなると、「果たしてこれは他の人が読んで面白いのだろうか」とためらってしまうことはありました。こういった悩みにも本書はきちんと言及してくれています。
以前、このような記事を投稿しました。
それとはまた別の話で、人は自分が抱えている不確かな考えを他の人に「それでいいんだよ」「間違いじゃないんだよ」と言ってほしい生き物なんだなと思います。
本書を読むことで、「私も私の好きなことについて思い切り書こう!」と思えましたし、抱えていたモヤモヤを指摘してもらい、後押ししてもらえました。
おわりに…踏切板を頼りに跳んだ先にあるもの
タイトルで本書を「踏切板」と形容したのは、「書くこと」から「なかなか跳べない跳び箱」を連想したからです。
この記事で挙げた以外にも、本書は多くの人が抱えがちな悩みや疑問を丁寧にすくい上げています。「大丈夫だよ!」と踏切板を置いた隣で友だちが応援してくれるような本です。
巻末に要点をまとめた『「書く習慣」をつくる52のコツまとめ』、お題として『「書く習慣」1ヶ月チャレンジ』も収録されています。
読み終えたあとは踏切板を頼りに跳ぶのみ。まずは好きなことを書いて投稿する。
たとえ3段でも4段でも、跳び終えたあと「よし、もう1回跳ぼう!」と心と筆の運びが楽になっている自分がいるはずです。
※表紙画像はみんなのフォトギャラリーよりお借りしました。ありがとうございます。
※2021.10.11追記
著者のいしかわゆきさんのnote記事「書く習慣」感想記事まとめに掲載していただきました。ありがとうございます!
サポートをいただけましたら、同額を他のユーザーさんへのサポートに充てます。
