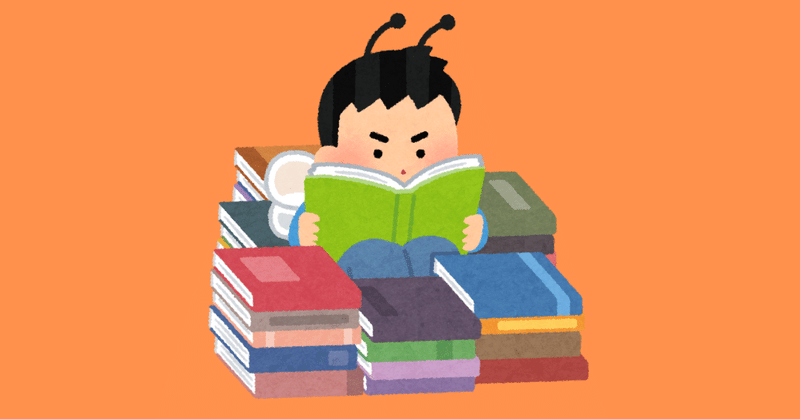
いつまでも消えない本への渇望
思春期の頃からの習慣について触れることになりますので、話すのが恥ずかしいのですが、本の収集癖がついてしまったきっかけというか原点について。
中学2年生の途中から父親の仕事で渡米することとなったのですが、当時住んだのはアメリカ南部のど田舎。
裏庭には鹿が出て、近くのスーパーに行くのにも車で数十分かかるような環境でした。
当時はインターネットも何もないですから、入ってくる日本の情報はというと、日本の友人からの手紙くらい。
アメリカでの学校生活には初めから馴染めずに、現実逃避のために読書に没頭するも、大量に持って行って本棚を埋め尽くしていた本もあらかた読み終えてしまっていました。
同じ本を何度も読み返すものの、気になってしまうのは途中の巻までしか手元に置いていないシリーズものや、未完の話のその続編について。
何度か日本に一時帰国する機会があったのですが、その時のために買いたい本をワープロでリストアップしていました。
当時の文庫やノベルズなどは、本の後ろのページに作家別の新刊情報や出版社が一押ししている作家と著書の名前が宣伝として数ページに渡って掲載されていました。
リストには、そうした数少ない情報源の中からとにかく読みたいと思った本のタイトルと作家名、それから出版社名をあいうえお順にどんどん書き溜めていっていました。
まず、何よりも一番手に入れたかったのはシリーズ物の続編です。
何しろ日本から離れていますから、そのシリーズの続刊が現在何冊世に出ているかさえも分かりません。
また、シリーズによってはナンバリングはなされずにどこから読み始めたらいいのか分からなくなってしまうような紛らわしいタイトルのものなどもあります。
その辺りを間違えないようにリスト化していくのも結構手間がかかりましたが、何しろこれが生命線となりますので、何度も見返してはリストの精度を上げていきました。
そして、日本へ戻ったら、友人に会う時間以外は全て本屋巡りです。
今も昔もそうですが、国会図書館のように全ての本を置いている本屋さんなど存在していないのです。
そして、当時はブックオフのような分かりやすい古本市場もありませんでしたから、お金はない学生だとしても狙いをつけるのは大手の本屋さんになります。
神田神保町のスポーツショップで本を詰め込むためのボストンバッグを購入して、古本屋街の中にある大型店舗を巡回しまくります。
そして、神保町で見つからなければ東京駅にある八重洲ブックセンターへ。
どんどん重くなっていくカバンの紐が肩に食い込もうが、リストにある本を購入してはカバンに詰め込んでいく行為がとてつもなく充実した時間であったのを覚えています。
この頃の体験があるからか、大人になった時には、同じようにエクセルで作った「買いたい本」リストを携帯電話で確認できるようにして、ブックオフや他の古本屋を見つけるたびに立ち寄って、本棚とリストを照らし合わせてはリストの本の消込作業を続けていました。
また、毎月ネットで近日中に発売の文庫本の情報をチェックしては、好きな作家やシリーズものの最新刊をリストに加えていました。
ところがかつてと違ってきたのは、その出版物の量と出版スピードの速さです。
そして、こちらの読む量やジャンルの幅も広がってしまったため、リストに書かれた本の数はちっとも減らないどころか反対に増えるばかり。
と同時に、リストに忠実に購買を続けていった結果、購入したのはいいものの未読本はどんどこ増え続け、家族のもとに1,000冊、単身赴任先の部屋のベッドの下と棚に800冊、電子書籍で100冊という状況に。
当然ながらいつしかリストを作成したり、それをチェックしたりする習慣も途絶えてしまい、振り返ってみるとその理由としては、意識してブックオフに入ることをストップしたというのが大きいのかなと思っています。
古本屋巡りは止めましたが、今の職場が東京駅に近いこともあって、出張などで東京駅に向かう際には、信号待ちしている時間だけという言い訳をしつつその手前にある八重洲ブックセンターには必ずと言っていいほど入店してしまっていました。
35年前にボストンバッグを掲げながら立ち寄った時の面影をほとんど残したままの店内に入ると、ノスタルジーというか、一瞬にしてあの頃の気持ちに戻れるから不思議なものです。
現在は再開発ということで閉鎖されて、信号待ちの際にも入れなくなってしまいましたが、あの建物を見た時にグッと込み上げてくる本への渇望というのは今もまだ私の中に残っています。

そんなことよりも買った本を早く読めって話なのですけどね。
今日も読んでくださいまして、ありがとうございます。
嬉しいです。 サポートしていただきまして、ありがとうございます。 こちらからもサポートをさせていただくことで返礼とさせていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。
