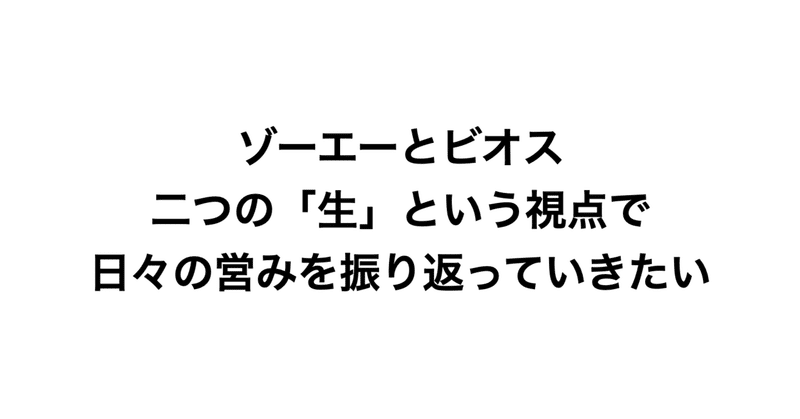
『プシコ ナウティカ』を読んでは独り言・其の三
以前私は
次のような言葉を
よく使っていた
1人の薬剤師として
1人の医療従事者として
1人の地域住民として
そして1人の人間として
以前というか
今でも使うことがあるが…
この言葉を
なぜ使うのかと言えば
それはおそらく
日々の薬局での業務の中で
様々な疑問が浮かんでくるからだと思う
薬剤師の業務の1つに
医師の仕事でいうところのカルテに似た
薬歴というものがある
患者さんの記録とでも言おうか
細かく説明はしないが
薬歴を記載することにも
保険調剤上の点数が割り振られており
その点数を満たすために
書かねばならぬことがあり
どんなことを書く必要があるか
あれやこれやの解釈や見解がある
一方で
患者さんの生きた声を
記録として残し
それをその患者さんのために
使っているという自負がある
つまり私は
保険点数を満たすための薬歴と
患者さんのための薬歴を
分けて考えているわけだ
もちろん
その2つは完全に分けられる訳ではない
グラデーションになっており
どちらの要素が割合として多いか
といった話だと思っている
しかし
薬歴にまつわる議論や
薬歴の書き方といった話になった際には
その2つを明確に意識してしまったりもする
薬歴の例に漏れず
日々の業務を
薬剤師として
医療従事者として
地域住民として
1人の人間として
考えて行動し
それらを分けて
捉えてしまうとでも言おうか
なんだか
いつものように
何を書いているのか
訳がわからなくなっているが
まぁそれはいつものことということで…
そんなわけで
今日もまた
読んだんだか読んでいないんだか
積んだんだか積んでいないんだか
といった本達の中から一冊紹介し
心の琴線に触れた一節を取り上げ
ゆるりと書き記していきたい
今回はこちらの本を読んでは独り言
ちびりちびりと
ゆるりゆるりと
読み進めている本書
いつ読み終わるのだ
というくらいのペースだが
そんなペースであっても
購入して良かった
読むことができて良かった
と感じることができる本でもある
さてさて
いつものように
引用する必要があるんだかないんだか
本来の引用の定義を考えては
自己ツッコミを入れつつ
noteの引用機能を用いて
引用させていただきたい
ところで、イタリアの美学者であり政治哲学者でもあるジョルジュ・アガンベン(Giorgio Agamben)は、まさに彼の思考の中心に「生」を捉えている。ただしそれは、ギリシア人が区別していた二つの「生」のあいだの関係において考察される。一方が、「ゾーエー(zoe)」、すなわち、動物であれ人間であれ、生きている全ての存在に共通する「生きている」という単なる事実としての「生」であり、他方が、「ビオス(bios)」、すなわち、それぞれの個体や集団に特有の生きる形式や生き方としての「生」である[アガンベン 二〇〇三 : 七]。
引用途中の「ゾーエー」だが
長音記号マクロンの入力の仕方がわからず
苦戦した結果そのままのローマ字入力としてしまった
それはさておき
日々の患者さんとの対話の中で
薬剤師とか薬学といった概念に引っ張られると
「ゾーエー」としての「生」という感覚に
なってしまう気がする
一方で
後から振り返って
目の前の患者さんと対応な
1人の人間として対応していると思うときには
「ビオス」としての「生」という感覚に
なっている気がする
もちろん
そんな気がするだけであるし
そう思いたいだけなのかもしれないが
私はそう思っているというのも
また事実認識としてあるのであった
ふたつの「生」という視点で
薬剤師の仕事を捉えていきたい
そんな気持ちでいるのであった
こんなポンコツな私ですが、もしよろしければサポートいただけると至極感激でございます😊 今後、さまざまなコンテンツを発信していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします🥺
