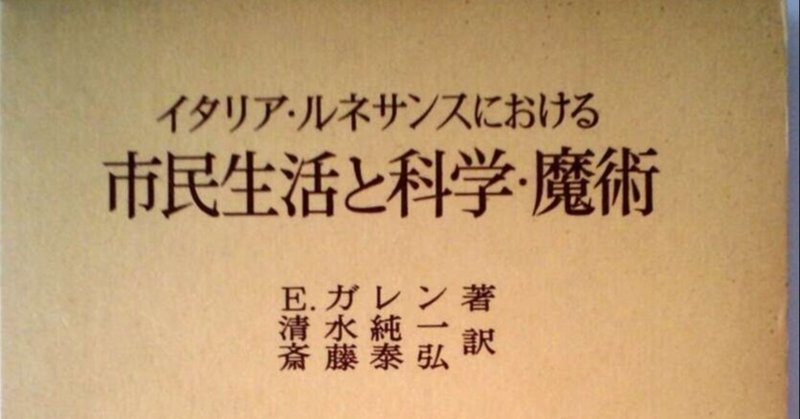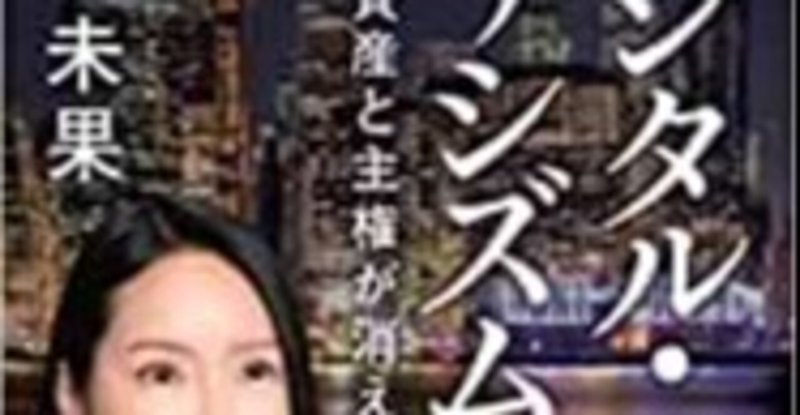最近の記事
「優劣のランキング”が、やがて“人権がない、生まれてこない方がいい”に…SNSや日常に顔を覗かせる「優生思想」」という記事に触発されて。
2月18日の「優劣のランキング”が、やがて“人権がない、生まれてこない方がいい”に…SNSや日常に顔を覗かせる「優生思想」」という記事(https://news.yahoo.co.jp/articles/d17144ce4d66f4edfb444c6d1036068a356c33ab?page=4)に触発されて。 「格付け」という言葉でありとあらゆるものを指標化していく政治体制は、それが全体主義だろうと新自由主義だろうと、結局同じところに収束してしまう。 『新約聖書』に「タ