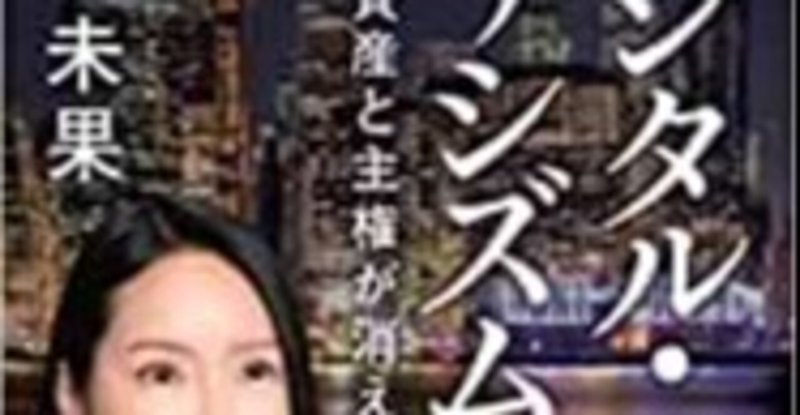
読書百冊 第24冊 堤未果『デジタル・ファシズム』
相変わらずの堤節だが、アメリカの話ではなく日本で現在進行形で起こっていることについての継承ということで、いっそう身につまされるのは確かだ。ありとあらゆることを貨幣に置き換えるのがこれまでの資本主義であったとすれば、貨幣に置き換えられた現実をさらに電子情報に置き換えることにより、より一元的にコントロールしていくことを目指すのが、21世紀の電脳社会というものであろう。
そうした社会がもたらす多様性に期待する支店はもちろんあるだろうが、上に「一元的にコントロール」と書いたように、そうした電脳化により実現される多様性が結局は、根柢のモジュールによりすべて結び付けられてしまうことにより、結局は全体的なものの単なるバリエーションへと回収されてしまうのではないかという疑念から、解き放たれることがない。
こういう社会はどんなものでもすべてを対象にし、組み込み、調律しようとする。こういう21世紀的試みに対していつもブチブチ行っていることだが、「なんでくちばしを挟もうとするんだ」とか「ほっといてくれよ !」 というのは、そういう余白がなければ本当の〈予想可能性〉を裏切る創造性など生まれっこないと信じるからだ。その点ですべてをつなぐユビキタス社会は、その本質からして全体主義的な性格から脱することができない。
それに、電子化で便利になったというが、本当は誰のための便利さなのだろう。IT導入により書類作成が簡単になるどころか、簡単になったことにより以前に増して書類の数が増えたのと同じように、DXでミーテングが簡単にできることで、逆に会議の数が加速度的に増えることになりはしないか。電子マネーは、大半の自己管理能力が乏しい人間に、無意識のうちに〈無駄遣い〉をさせるための方便ではないのか(金を使っている実感がないことで、貧乏人の財布のひもが1割でも緩くなれば、ドン詰まっている資本主義というか資本家とり、福音というしかないだろう。給料を増さずに消費を増させることができるんだから、笑いが止まらんだろうな。豚の貯金箱の小銭貯金とか現金を出して封筒分けにして支出をコントロールするとか言った、貧乏人が貯金できるようになるささやかに戦術さえ奪われようとしている)。
教育に携わるものとして一番さみしいのが、タブレット導入等のデジタル教育の導入だ。それ自体は決して悪いことではない、ただ安きに流れる使い方(こういうところでも悪化は良貨を駆逐する)が先行することにより、つつましい教育しか受けられない階層には、これまで以上に画一的な教育しか与えられなくなる危険がある。賢い使い方をすればそんなことはないというが、そもそも「賢い」使い方ができるほど賢い人は、いつの時代でもほんの一握りだ。たぶんデジタル教材を賢く使える人と、そうでない人の格差は、デジタル教材導入以前よりいっそう先鋭になるだろう。堤
氏はこの本の中で、文科省がタブレットを学校現場に導入するに際して作ったPVを紹介しているが、その中に登場する子供の「タブレットがないと、全部自分の頭で考えないといけない。でもこれがあれば、間違えた時すぐに説明されて、前に進んでいけるんです」という言葉に、暗澹とした思いを抱くのは私だけだろうか。こうした電脳推進者は、おそらく物事を滑らかに進行させることが成功だと思い込んでいるんだろう。だが教育とか成長とかとは、間違えたり、躓いたり、考え込んだり⋯⋯非効率を積み重ねていくことにより、体験を自分の精神に消化していくことそのものなのではないか。
もちろん技術の進歩を一方的にすべて否定するつもりはない。ただ、近代のように国家が企業を頤使するのではなく、反対に企業が国家を道具化する事により、(案外国家は消滅せず)皮肉なことに国家自体も強大化していく21世紀の社会構造の中で、我々そのものと言ってもよい我々の情報が、国家=企業に一方的に吸い上げられる利潤の産出に利用されるという、新しい搾取の様態が始まっている。集積され、連結され、変形される巨大なデータベースの運用を、閉ざされた特権的小集団のためではなく、せめて「最大多数の最大幸福」のために、どのような資質を有する〈代表〉に、どのような〈手続き〉で委託するべきか、その制度の構想は未だまったく手つかずの状態なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
