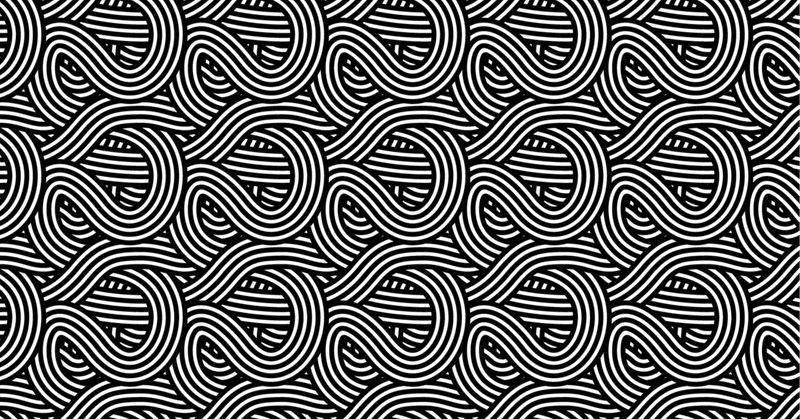
仕方がないから言葉をつかう
2023年8月11日(木)朝の6:00になりました。
大事なことは、そのルールがもっている意味を理解するということなんですよ!
どうも、高倉大希です。
ふたりの人が、おなじものを食べて「おいしい」と言ったとします。
発された言葉はおなじですが、思っていることもおなじだとは限りません。
実家の料理と比べて、「おいしい」と言っているのかもしれません。
一般的なそれと比べて、「おいしい」と言っているのかもしれません。
シェフの顔色をうかがって、「おいしい」と言っているのかもしれません。
その場の雰囲気に酔って、「おいしい」と言っているのかもしれません。
言葉はあくまでも、その場に出されたカードです。
そのカードを選ぶまでの背景は、人によってちがいます。
つまり、コミュニケーションとは、言うならば、自分が頭の中に抱いている〈抽象的〉な広義の思考内容のコピーを相手の頭の中にも創り出す行為であると言える。
コミュニケーションの理想は、テレパシーです。
自分の頭の中にあるものを、相手の頭の中にも生み出します。
しかし、残念ながらいまの人類にはその技術がありません。
だからこそ、仕方なく言葉をつかいます。
思っていることを、いちど言葉に変換します。
そして、相手はその言葉を解読します。
書き手が A → B → C という手順で思考を言葉にしたのなら、読み手は C → B → A という手順で解読する必要があります。
もちろん、完璧におなじ手順を辿れることはありません。
いかに、その精度を上げられるかが勝負です。
書き手とは、大隊を率いて一度に1人しか通れないような狭いすき間を縦列進行させる司令官のようなものだ。一方、読み手は出口で軍隊を受け取り、その隊列を再び整えていかねばならない。題材がどんなに大きかろうが、またどのように扱われていようが、そのコミュニケーションの方法はこれひとつである。
「伝わればそれでいいじゃん」という言葉を、よく耳にします。
残念ながら、そんなに簡単な話ではありません。
おなじ経験をしているからといって、伝わるとは限りません。
おなじ日本語をつかっているからといって、伝わるとは限りません。
僕が「言葉にすることを徹底しよう」「言葉に落とすことに病的なまでにこだわろう」と言うと驚く人が多い。
言葉にすることを徹底しよう。
言葉に落とすことに病的なまでにこだわろう。
言葉マニアになりましょう。
毎朝6時に更新します。読みましょう。 https://t.co/rAu7K1rUO8
— 高倉大希|インク (@firesign_ink) January 1, 2023
サポートしたあなたには幸せが訪れます。
