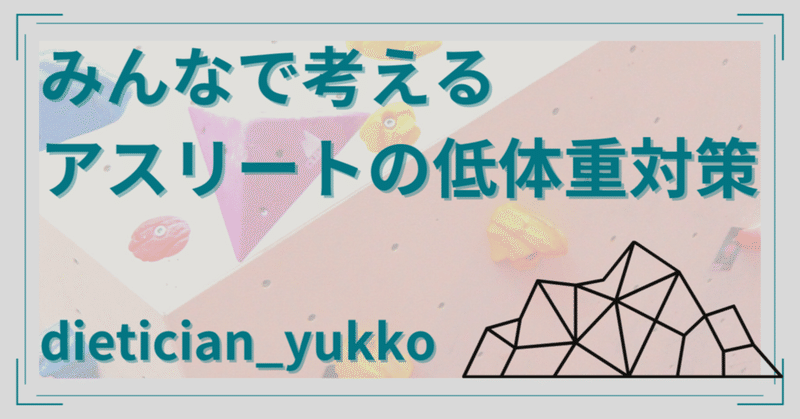
アスリートの低体重対策④
ご覧いただきありがとうございます😊
管理栄養士のゆっこです。
日本山岳・スポーツクライミング協会で設定された低体重対策のトピックス
こちらをテーマに連載にチャレンジしております。
◼️連載目次(各項目を押すと記事ページにジャンプします!)
①
策定の背景を知る
②
・BMIについて
・日本山岳・スポーツクライミング協会が策定する数値についてのまとめ(thestone sessionさんまとめ)を転載
③
・EA(利用可能エネルギー)
・RED-S(利用可能エネルギー不足)
・FAT(女性アスリートの三主徴)
について知ろう
④ ⬅️今ここ
・英国での調査論文より
・日本での調査研究論文より
まとめ
⑤
これまでのまとめを経て、今後本人や周囲、専門職はどうフォローアップしていけばいいのか
◼️英国での調査論文より
▼どんな論文で、どんなことが言いたいのか
論文概要
パフォーマンスレベルの異なる、クライマーの食事やサプリメントの摂取状況、体組成、鉄代謝状況を調査した。
調査対象は、イギリス国内でSNSやクライミングセンターを通じ募集した男女各20名のボランティア。(18歳以上、2年以上の登山経験があり、登山または、登山のトレーニングを週2回以上実施、食事摂取に影響のある疾患のない人)
また、ロッククライミングの国際組織(IRCRA)のスケールでクライミング力を評価(以降、IRCRAスコア)したところ、19名は中上級、21名はエリートレベル、
さらに、分野は27名がボルダリング、13名はスポーツクライミングという内訳だった。
栄養摂取状況は3日間の食事日誌から調査。
※全体の27.5%:ビーガンまたは、ベジタリアン
結論
①男性:IRCRAスコアと身長体重の数値は関連があると考えられる
②女性:たんぱく質摂取量とクライミング力が関連があると考えられる
※ただし、IRCRAスコアのグレードで分けた時、たんぱく質摂取、炭水化物摂取の量に差はなかった
③アルコール摂取者の割合:17.5%
④貧血を認めるものはなかったが、鉄摂取量が不足していることが分かった
⑤全体の45%が何らかのサプリメントを使用していることが分かった
プロテイン、ビタミンD、マルチビタミン、魚油カプセル(DHA、EPA)クレアチン、βアラニン、プロバイオティクス(乳酸菌など)、ビタミンC、BCAA・・・
※エリートレベルより中上級レベルの方が利用率が高かった。
【摂取エネルギー量、鉄摂取量が不足しているリスクが高い。】
→軽体重であることが、結果競技に有利といえるためか、食事量を控えめにしようとする人は一定いる可能性がある。(日本での実態調査の研究論文が見つけられなかったが、同様の思考性が見受けられる可能性が高い)
→クライミングは無酸素運動(爆発的に出力する)・有酸素運動(持久的に出力する)特性をどちらも兼ね備えた種目です。
→筋ダメージからのリカバリー(回復)や、パフォーマンスの維持を目指すためには、エネルギー不足や鉄不足は回避しておきたいところ。🤔
♦管理栄養士ゆっことしては・・・
過体重であると、関節負荷が増大する恐れもあることから、
「低体重」ではなく「低体脂肪率」をめざすのは有効と考えられる、
女性は毎月の月経も考慮して、より、鉄摂取について向き合う必要がある、
→食事を抜くよりも、少量頻回(例1日3食→少量5食)で細やかにカバーすることを検討した方が効率的である可能性が高い。(ユース世代に関しては、3食とったうえで、補食をするという考え方を推奨したい)
◼️日本での調査研究論文より
引用元: 国立登山研修所
スポーツクライミング選手の低体重問題について
▼どんな論文で、どんなことが言いたいのか
論文概要
スポーツクライミングの負の側面、「障害の発生」。中でも、負の側面になりかねない「低体重問題」に焦点を当てた論文。
BMIを用いて、問題の早期発見に繋げることが目的。
具体的な問題である、エネルギー不足や、低体重からリスクが生じやすい「利用可能エネルギー不足」「女性アスリートの三主徴」については連載③をご覧ください。
BMIをスクリーニング(「ふるい分け」をして問題の見つけ出しをすること)に使う対応はヨーロッパの中でもオーストリアがはじめとされている。
→カットオフ値のエビデンスは、オーストリアの基準で、試験的に用いて本決定に至ったようです。
結論・管理栄養士ゆっこの考え
クライミングに限らず、審美系、体重階級性のスポーツも含め、今後もBMIをみて体組成を評価することはスタンダードになっていくものと思います。
(日本人の食事摂取基準も2015年からBMIでエネルギー収支を評価する流れになっています)
→日本では、従来ローレル指数という小児向けの肥満度を示す指数の活用事例も多かったですが、現在は、BMI評価・成長曲線に当てはめた考え方が主流になる可能性が高くなるでしょう。
※BMIを基準にすることの問題点は、体格差、四肢の長さ、若年小児ほど誤差が生じやすいこと。今後も調査研究が進んで、たくさんの比較研究、検討論文が出てくることを祈ります。
ユーススポーツクライマーに対する栄養指導のあり方
▼どんな論文で、どんなことが言いたいのか
論文概要
体重コントロールや減量、食事を意識しているクライマーが多いことはすでに報告例がある反面、実際に食事や栄養について指導を受けたり、専門家によるサポートを受けている事例は少ないという報告例もあることを踏まえて、論文の著者らが取り組んでいる、「ユースクライマーの栄養摂取の必要性」「ユースクライマーに対する栄養指導の実例」を紹介し、まとめています。
なお、栄養不足が懸念される以外に、過剰症についてもトピックスが紹介されています。
結論
①過剰症による障害として、下痢症状、栄養素により異なる過剰症、脂質の蓄積や尿酸の過剰生成(痛風リスク、腎機能低下、骨粗しょう症の一因にも)が懸念されるため、注意が必要
②食事のバランスに配慮する:主食・主菜・副菜・果物・乳製品の5つを揃えることで良好なバランスを目指しやすくなります。
1日の中でバランスを整えられれば理想。
量を確保するのが大変な場合は、補食を活用して、分散して摂取を目指しましょう。
実際のコンペの際も、少量頻回の方が適するため、日頃から慣れておけると良い。(食事摂取も日頃からトレーニングしておくことが大切)
③ユース日本代表に対する栄養教育
1栄養講習の実施
2補食の選び方、栄養の摂取のタイミングを実践的に練習する取り組み
④ユース選手における個別指導の実施
♦︎ 管理栄養士ゆっことしては・・・
なお、社会人などの場合は、複数日、週単位規模で見ていただくのも、状況によりありかと考えます。(生活環境・背景を考慮して)
そして、補食の内容は、消化吸収の良いもの、3食で摂りきれなかった栄養素を補うものを想定して選択できると良いと思います。
スポーツクライミングにおける競技力向上サポート体制のあり方
▼どんな論文か
論文概要
ユース世代からの強化を目的に、選手を中心に各専門分野のスタッフが、コーチや家族、マネージャーなどと密接に連携を図りながら1つのチームとしてサポートすることな常識となりつつある。
2020東京五輪を機に競技化と強化は進む反面、サポートはまだまだ不十分というのが実際である。
さらに、先述の諸問題以外にも骨端症やクラムジー(※)のリスク回避、深刻化回避のためにも、ユース世代からの縦断的なサポートが必要である。
→実例を紹介。
※クラムジーとは、
身長が加速的に伸びることや、筋・骨格系の急激な発達に伴い、身体の支点・作用点に狂いが生じて、これまでに習得した技術が一時的に発揮できなくなったり、上達するのに時間がかかるようになることを指す
パソコントラブルに取り掛かり切りになっていたらこんな時間になってしまいました😇
論文に触れる機会は、あまりないかなと思い、なるべくポイントを押さえてまとめてみました。
もっとこういう事が上手くなれるようになりたいです😇
是非お時間ある時に(笑)読んでみてください。
ご不明な点がございましたら、コメントをお待ちしております。🙇♀️
良かったらスキ・フォローを
よろしくお願いいたします🌱
リンク集はこちらから→https://www.handshakee.com/dietician_yukko
よろしければ、サポートをお願いいたします🙇♀️いただいたサポートは、クリエイターとしての活動費に充てさせていただきます。
