
【読書】シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻)) その1−2
出版情報
タイトル:シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻))
著者:岡田英弘
出版社 : 藤原書店 (2014/5/24)
単行本 : 569ページ
本記事について
本記事は、本書 シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻))の感想についての一連の記事の一つである。
【読書】シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻)) 予告編では、本書の概要と著者 岡田英弘の紹介を行なっている。
【読書】シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻)) その1−1では、漢字についてのうち「漢語の起源から科挙まで」について述べた。
本記事では、本書の漢字についてのうち「漢人の精神世界」と「日本文明圏に入ったシナ」について述べていく…つもりだったのだが、その前に報告者のほんのり考察「日本語の漢字」を述べることにする。
それは、漢人にとっての漢文や漢語や漢字についてどういうものかを理解するために、自分にとって必要なステップだった。比較対象が必要だったのだ。ご了承ください。
前回の概要:漢語の起源から科挙まで
秦の始皇帝までは、漢字の読みは特に定められていなかった。自分たちの都合に合わせて読みたいように読んでいたのだろう。日本語のように複数の読みを持っていた民族もいたかもしれない。だが始皇帝は戦国時代の儒家同士でのコミュニケーションのスムーズさを見て、書き言葉の統一を図ることを思いつく。そして、そのために秦の始皇帝は
漢字の一字につき、一音一音節と決めた
始皇帝がこう決めたことがその後2200年の漢字の運命を定めることになった。こう決めたことで漢字の音は意味ではなく「その漢字の名前」程度の意義しかもたないことになった。さらに漢文には時制もなく品詞も活用もないことになり、つまり文法がないこととなった。文法がない文を読み解くためには用語用例集が必須である。
そこで、用語と文体の模範を古典に求めた。いわゆる四書五経である。その系譜は、現代の毛沢東選集につながるという。用語と文体の模範テキストはいわば漢字という文字を扱い読み書きするための暗号表である。
この暗号表をくまなく暗記したものだけが、自由に読み書きができる。
この人々を「読書人」と呼んだ。彼らは幼い頃からわけもわからず、暗号表である模範テキスト=四書五経を暗記させられる。そして散々苦労して文字を操る技を身につける。こうした努力ができるのは一部の人だけだ。
巨大な帝国は官僚を必要とする。文字を自由に操れるテクノクラート=技術者集団=官僚。その過酷な選抜試験。科挙である。こうしてシナでの漢字文明が育ちゆくことになる。
日本語と漢字
本項目は報告者による「日本語と漢字」についてのまとめ、だ。特に専門家ではないので稚拙な点はご容赦いただければ、と思う。
漢字が生んだ漢人の精神世界について見ていく前に…比較対象について見てみよう。そう、日本語だ。日本語には漢字の読みは複数ある。そして、表意文字である漢字の他にもひらがな、カタカナという表音文字を使っている。比較対象として日本語ほどふさわしいものもない。
シナにおいて漢字には一つしか読みがない、というのは秦の始皇帝の時から始まった2200年以上歴史のあることだが、日本語の漢字にいくつも読みがあるというのも、日本語に漢字が取り入れられて以降、1400〜1500年ほどの歴史がある、と推定されている。なので、漢字の読みがいくつあるのか、ということは、もう根本的な違いと言っていいだろう。
日本語には文法がある
いや、当たり前でしょ、と思うだろうが、岡田によれば漢文には文法がないのである。てにおは、などの助詞、動詞、形容動詞の活用、副詞による微妙な表現の豊かさ(ぐっすり、すやすやなど)、オノマトペの多様さ…。それによって、誰が誰に何をしたか、とか時制とかが明確になり、表現が豊かになり、気持ちを自由にしっくりくるように表現することができる。
表音文字がある
ひらがな、カタカナがあることにより、話し言葉が簡単に書き言葉に変換できる。これも当たり前、と思うだろうが、少なくともシナの漢文の世界では、そうではない。「今しゃべっている音で、しかも同じ意味を持つ漢字を探して」をしゃべっている一音一音に対して行わないとならない。こんな面倒なことは誰もできやしないし、これに方言の問題が重なる。
文法を助けるのが表音文字だ。動詞などの活用も、てにおはなどの助詞も、オノマトペも、表現を彩る副詞も、みんな表音文字のひらがな、カタカナがあってこそ、だ。
表音文字による日本語記述の工夫は万葉仮名に始まる。5世紀にはその片鱗(古墳の副葬品など)が見られるという。やがて和歌や平安文学の源氏物語、さらに日記文学などにつながっていく。女性が自由に文字を操れるのも、その当時、きっと世界でも稀だったことだろう。江戸時代において日本の識字率は世界一であったと推定されている。これも表音文字の恩恵の一つだと思われる。
一つの漢字にいくつもの読みのある日本語
万葉仮名という表音文字への工夫とともに、日本語では古くから一つの漢字に多くの読みをあててきた。それは、どういうことなのか?
東という漢字を例に見てみよう。
とう【東】
[音]トウ(漢) [訓]ひがし あずま
〈トウ〉1 ひがし。「東国・東西・東洋/以東・関東・極東・中東・北東」 2 「東京」の略。「東名」
〈ひがし〉「東風・東側」
[難読]東風 (こち) ・東雲 (しののめ)
goo辞書 漢字辞典 東の解説 - 小学館 デジタル大辞泉 より
『東』という字。これは『ひがし』と読んでもいいし、『とう』と読んでもいい。『あずま』と読むかもしれない。また難読の熟語として『東雲』『東風』なんていうのもある。
この漢字の読みというのは、データベースへのアクセスと関係している。なんのデータベース? 人間の脳に整理されて蓄えられている『経験』と言うデータベースに。
方角としての東という概念に、沿って、音読みのトウの熟語が作られていく。
熟語を比較的簡単に作ることができる、ということも多分日本語の特徴の一つだ。これによって明治維新の時に西欧の概念を「たくさんの熟語を作ることで」「日本語として」取り入れることができた。
それぞれの熟語が日常生活の「どういう場面で」使われるか「なんとなく」場面が想定できる(もちろん、まったく初めて作られた熟語は文脈に依存して意味を推測したり、逆に英和辞典を引くなどして意味を確かめることにはなったかもしれない)(新しい概念を取り入れるとはそういうことだと思う)。
「東国」と言われれば、「なんとなく」昔風の言い方だな、という感触がある。日常生活の中では、テレビドラマや時代小説などで聞いたり見たりする言い方だ。実際辞書を引くと「畿内から見て東の地方。北陸を除いた近畿以東、あるいは箱根・足柄・碓氷以東の諸国。また、関東八か国をさしていう。東。関東。」とあり、古事記だとか宇津保うつほ物語などの用例が載っていて、辞書を見ても昔風の言い回しであることがわかる。東と言う言い方とも重なる。
「東西」とか「北東」と言われれば、それは方向に関する言い回しだし、「東洋」は「西洋」に対する「地球の北半球の東側」と言うイメージで、少し古めかしい印象だし(明治以降でかつ戦前という印象、あるいは高度成長期ぐらいまで。東洋大学と言われればまた、それはそれで別のものを想起させる。都内の大学、だとか、体育会系が盛んそう、とか)、「関東」「極東」「中東」は地理的な場所、だ。極東はさらに米軍が使っていそう、とか、極東裁判を思い起こすかもしれない。そんなふうに簡単に連想が連なっていく。比較的自由に。その時の気分や興味関心によって。
別の例を見てみよう。
「3月1日は日曜日で祝日、晴れの日でした」
日本人なら、難なく読めるこの文章、海外の日本語学校では難問なのだそうだ。「日」の読み方がすべて違う。
「3月1日は日曜日で祝日、晴れの日でした」
これを難なく読めるということから推測できるのは、日本人は「日」という字 単体で、読みを認識している訳ではないらしい、ということだ。熟語や漢字の塊で、「読み」と「意味」を認識している。そして、その塊ごとに、日常生活に結びついている。
例えば、3月1日、日曜日、祝日は、カレンダー的な日付であり、晴れの日は、その日のお天気を表している。
そして、難読の読み以外は、音読み(呉音、漢音など)、訓読みと、2〜3ぐらいの読みに収まっている。
ところが、だ。「生」は、48種類もの読み方がある、という(これには難読も含んでいる)。しかも「生」には普通の訓読みも10通りもある!私たちの先人は「いのちの営み」や「成長あるいは生長」に関係するものに慎重に「生」という漢字を当ててきたのだろうと推測できる。
国字を知っていますか?
この記事を書くことで、初めて国字というものを知った。和字とも和製漢字などともいう。例えば「峠」。この字が日本で作られたことは知っていた。他にも榊(おお神事には欠かせない)、畑(焼畑の影響?)、畠、辻(ええ〜こんなのも!?)など古く作られたものと、西洋文明の影響で近代に作られた膵、腺、腟があるという。さらに驚くのは働(働く)これも国字だというのだ!(ネット情報によると働は、15世紀ごろには日本で使われているらしい。いかにも働き者らしい日本人が作りそうな漢字だ…)
幼いころから読む楽しみを知ることができる日本語
この一連の記事を書くにあたって、検索したところ、「日本語って幼いころから読む楽しみを与えてくれる言語でもあるんだ…」と認識させてくれるブログに出会った。はと@杭州便りの中国の漢字教育である。中国で子育てをしているママさん はとぽっぽさんがブログを書いている。
ユキは中国で育って、話し言葉では中国語の方が日本語より上なのに、ひらがなを覚えたため日本の絵本はもう「読む」ことができる。3歳児でもこの「読む」感覚が味わえるということが、今後の読書や言語の学習にとってどれだけ有難く助けになる事かと思う。中国の子供たちも早い子では3歳からピンインや漢字を習い始めるが、ピンインはひらがなよりずっと覚えにくく、しかも漢字あってのピンインなのでピンインだけ覚えても中国語の絵本を「読む」感覚はなかなか味わえないと思う。
多分こうやって、ひらがなや絵本を通して、文字や文章と、身近な日常生活に現れる物や事柄を結びつけていく。この言葉や文章と事柄や物との結びつきが意味と呼ばれるものの実相だろう。幼くして自然に語彙を増やし文章の作り方を学んでいくことができるのは、本当に幸せなことだと思う。私たちはひらがな、カタカナを作ってくれた先人に、万葉仮名を作った先人に、もっと感謝してもいいのかもしれない。
日本人にとって漢字は経験へのアクセスキー
以上、日本語における漢字について見てきた。また日本人にとって漢字や文字は、日常生活の経験というデータベースへのアクセスキーとなっているのでは、という仮説も提案した。それはごく小さい頃から育まれ、年齢が上がるに従って、文字の量や経験の抽象度が上がっていく。それは日本人にとっては、ごく自然に行われることで、取り立てて困難を感じることではない。江戸時代における日本の識字率の高さも実はこういうところに秘密があるのでは、と感じている。シナ大陸から科挙を輸入しなかったことも、日本語は庶民レベルの人々にも容易に読み書きができるので科挙はそもそも必要なかったのだ。日本語を大人になってから学ぶ外国人にとっては学習上の障壁のように思われる「漢字の読みの多様さ」も、実は幼少時から日本語という言語空間にいる日本人にとっては、かえって文字の意味への理解を深め、自在に読み書きできる基礎になっていると思われる。
今も昔も丸暗記で「漢字の世界」というデータベースを作る
では、漢人の漢字にまつわるデータベースはどのようなものだろう?
私の仮説は、「漢人の漢字にまつわるデータベースは、日常生活へのアクセスキーという意味合いは少なく、漢字そのもののデータベースの構築にエネルギーを使ってるのではないか?それが、岡田のいう漢人の精神世界を作り出しているのではないか」というものだ。
この仮説についての説明は次回以降に譲ることにし、現代中国における漢字教育がどのようなものか、先の人のブログを通してみていこうと思う。
もちろんお一人の意見や経験やある種の感想で、すべてを語るのはナンセンスだ。だが、まったく中国語に触れたことのない私にとっては貴重な意見でもある。多分、私が中国で生活しても、こういうことに興味を持ち、こういう感想を述べるのではないか、と思い、一つの例として挙げさせていただくことにした。では、みてみよう。
現代でも中国の教育が「丸暗記主義」であることには変わりがないようだ。上述したはと@杭州便りのはとぽっぽさんはいう。
日本なら小学校に入学するとまずひらがな、カタカナから勉強を始めて、徐々に漢字も教えるようになるのだが、中国では小学校に入るとすぐ、日本人の感覚ではとにかくハンパでない数の漢字を教え、ひたすら暗記させるらしい。
(中国語にもピンインがあるじゃないかと言われるかもしれないが、残念ながらピンインはあくまで漢字の振り仮名で、ひらがなカタカナのように単独または漢字と混ぜて使うことができない)。
なんと!現代中国でも、暗記ですと!もちろん科挙の時代ほどではないだろうが、それでも暗記に次ぐ暗記とは。
そして、ハンパない量の漢字とはどれほどかというと、
1~2年 読める漢字約1600字、書ける漢字約800字。
3~4年 読める漢字累計約2500字(新出漢字約900字)、書ける漢字累計約1600字(新出漢字約800字)。
5~6年 読める漢字累計約3000字(新出漢字約500字)、書ける漢字累計約2500字(新出漢字約900字)。
…
これを日本と比較するために日本の『小学校学習指導要領』の付録『学年別漢字配当表』から漢字学習量を計算すると、
1~2年 240字
3~4年 400字
5~6年 366字の計1006字 となっている。
日本では中学校を卒業する、つまり義務教育を終えるまで常用漢字2136字が読み書きできるようにカリキュラムが組まれている。つまり中学を卒業しても中国の小学校ほどの漢字しか学ばなくてもよい。
だが、日本で小学校高学年ともなれば、普通に新聞を読む子どもたちもいるだろう。日本では多分1000字程度の漢字の読み書きができれば、それほど不自由なく暮らしていくことができるのでは、と推測できる。もちろん常用漢字すべての読み書きができれば、立派なものだ。
そして、はと@杭州便りのはとぽっぽさんは現代中国の文盲について直接的なことは述べていないが、現代中国も暗記主義であり子どもの健全なエネルギーを暗記以外のことに振り分けられない旨の文章を引用している。
まとめ
本記事では、本書 シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻)) から少し離れて、報告者によるほんのり考察「日本語の漢字」について述べた。
それは、漢人にとっての漢文や漢語や漢字についてどういうものかを理解するために、自分にとって必要なステップだった。比較対象が必要だったのだ。
さて、次回以降、漢字についてのうち「漢人の精神世界」と「日本文明圏に入ったシナ」について述べていく。
引用内、引用外に関わらず、太字、並字の区別は、本稿作者がつけました。
文中数字については、引用内、引用外に関わらず、漢数字、ローマ数字は、その時々で読みやすいと判断した方を本稿作者の判断で使用しています。
おまけ:さらに見識を広げたり知識を深めたい方のために
ちょっと検索して気持ちに引っかかったものを載せてみます。
私もまだ読んでいない本もありますが、もしお役に立つようであればご参考までに。
本書『シナ(チャイナ)とは何か (第4巻) (岡田英弘著作集(全8巻))』
『皇帝たちの中国 始皇帝から習近平まで』
お手頃価格で、お手頃サイズだが、私はあまり面白いと思わなかった。あまりにダイジェストすぎる。本書ですら、読んでみればダイジェストのように感じてしまう。どれだけ深いんだ、岡田史観…。
本書と重なっているところもあるが、弟子であり妻の宮脇淳子らが加筆しているようだ。
弟子で妻の宮脇淳子氏はモンゴル研究の専門家。結構YouTube番組に出演している。検索すれば、他にもたくさんある。面白く視聴できるものばかりである。オススメします。
中国で小学生が読めるようになる漢字の数
https://www.ritsumei.ac.jp/ss/sansharonshu/assets/file/51-4_02-02.pdf
noteからお祝いをいただきました。読んでくださった、スキをしてくださったみなさまのおかげです。ありがとうございます。
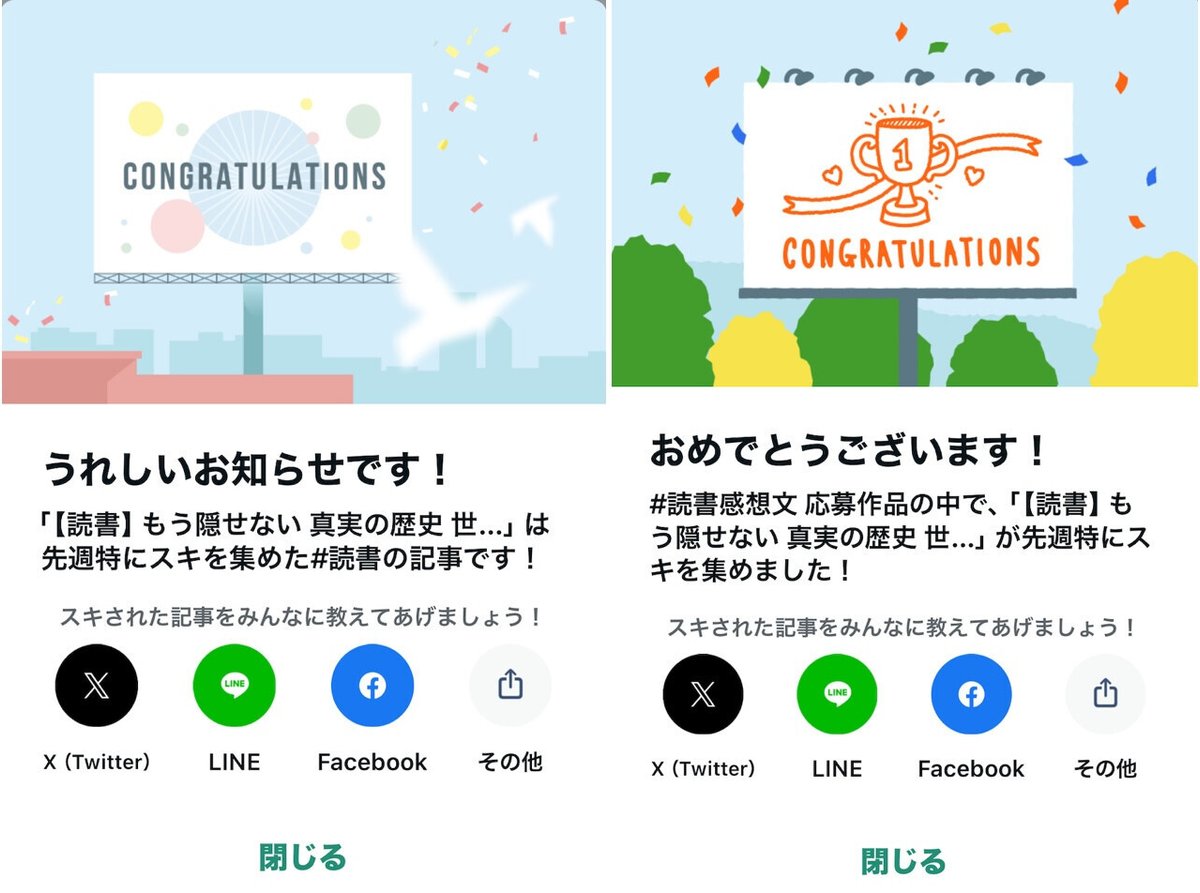
よかったら、読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
