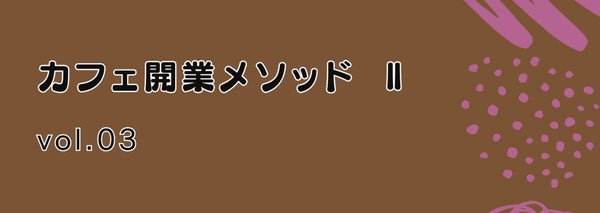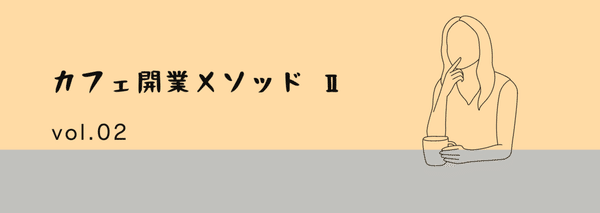記事一覧
オーナーが店に立ち全てのお客様に応対していることの強み
個人店の強みシリーズを続けます。
ワンオペ(もしくはご夫婦2人体制)個人店はオーナーが常に現場にいるということです。
これ実は凄い強みでして、お客様からしてみたら接客した人がそのお店の代表であるということは多大なる安心感に通じるものなのです。
大きな会社ですと、ある平社員が何か大きなヘマをしてしまって問題になるとその後その平社員の上司が応対して鎮静化を図るというように、またクレームにし
「どうなったら店を畳むかを決めておく」
今日はまずひとつ先行告知から。
この情報の詳細一般公開は10月に入ったらすぐに行いますが、ここカフェラボ会員さんには今のうちに先行してお伝えしておきます(※カフェラボ会員でなくともここをこうして読んでいる人、ここにたどり着いた人ももちろん誰でもOKです)。
来月10/29(火)、年に一度のカフェ開業講座を実施します。
切迫した状況にある人や本気で開業を考える人はこの機会を逃さぬよう早めのご応募をお
理想の店舗スケールはズバリ12~15坪です
さて、もう耳にタコが出来るほど聞かされることになるここでの「必ず失敗するメソッド」の中に「大箱ではやるな」「でも小さすぎる箱でもやるな」というのがあります。
特に「大箱」という選択肢はそもそも家賃が高いでしょうし元々あまり考えにはないかもしれませんので、ここの会員さんの店舗は「小さすぎる箱」の心配をしたほうがよくて、さらに最も重要なのは「限られたスペースの中でいかに座席を確保するか」ということで
ヒット商品は狙って生み出せる
前回は「だからぜひ皆さんの店舗でもドリップバッグを導入しましょうということではない」と締めくくりました。
あくまでも「再現性の高いメソッドを活かす」という部分が結論であるため、ドリップバッグは事例の1つとして捉えてみてください。
赤澤メソッドの中でおそらく1,2番を争うほどに重要なポイントとして、「少しだけ上回るべし」という考えがあります。
その「少しだけ上回る」を考える前にまずはその世界で
ここ最近の大成功例を共有しておきます
コロナ禍で叫ばれている飲食店の打ち手として良く言われるのがやはり「テイクアウト」及びそれに準ずるもの(デリバリー等)であると思います。
(この記事は2022年2月に投稿されたものを再投稿しています。)
カフェを例にしたテイクアウトの場合、やはり考えられることは「コーヒー(ドリンク)」あるいは「コーヒー(豆)」などの販売がまずシンプルに思い浮かぶことでしょう。
さらにはウーバーイーツ等の宅配業務
「夢について地に足つけて真剣に考えてみます」
ここカフェラボというのはスピ系や自己啓発系の場ではないので「夢とは?」といったようなフワっとした話をすることはないんですが「夢」というものについては私自身昔からずっと大切にしてきた概念であることは間違いないですし、カフェ経営に対しての夢のようなもの、またそれへの実現に向けての具体的行動というものをガシっと地に足を付けた内容でおおくりしたいと思います。
昨日とあるYouTubeチャンネルのライブ配信
メニューのネーミングについて
商品のネーミングには頭を悩ますところであると思います。 というよりぜひ存分に悩んでください。
ただし悩み過ぎて直感や客観性に欠いてしまうのもよくありません。
他店の素敵だなぁと思えるメニューのネーミングを参考にするのも良いのですが、もしかしたらそれはもはや少し古いものになっているのかもしれません。
例えばモダンな洋食屋さんやカフェやダイナーで出しているメニューの中に「ふわとろオムレツ」
ドラマやCMのロケで使われやすい店舗の特徴
今回のこのテーマで書こうとしたら思い出した話があります。
これまでに珈琲文明が舞台となったドラマやCMの中で、話は来たもののボツになった案件もいくつかありまして、その中でもBIG3を挙げますと・・・
★「今からあなたを脅迫します」←連続ドラマのうちの一回分
★東京喰種(「とうきょうグール」と読みます)←人気漫画の実写版の映画で、原作の中でも「喫茶あんていく」というお店が出てきて重要な舞台とな
取材が来た場合の対応と絶対にやったほうがいいこと
今回は皆さんのお店にめでたく何等かの取材、またはロケがあった場合にどうすべきかということを述べていきます。
まずは取材が1つ来たということはそれだけで物凄い宣伝費に該当する(その効果のほどは前回述べたように近年はあまり高くはなくなってきているものの店側自らが行うただの宣伝広告よりは数百倍の効果はあります)ということをくれぐれも忘れないようにしてください。
珈琲文明の創業時、多くのテレビ局や有名
宣伝広告はどれくらい重要か
2022年2月6日にあの日本放送(私にとってはオールナイトニッポンの局だというだけでテンション上がりました)にて実に10分以上に渡り珈琲文明や私のことを紹介していただきました。
(この記事は2022年2月に投稿されたものを再投稿しています。)
さて、今回の本題はラジオ出たという話ではありません。
これまで様々な雑誌やメディアで取り上げられてきたその後の反響や結果の話をまずいくつかしたいと思い
どうする!?混雑時のオーダーの効率よい提供方法(実践編)
(この記事は2022年2月に投稿されたものを再投稿しています。)
7年ほど前、私はアメブロに1年間に渡って「カフェ開業の仕方」のようなもの書いていたことがあって(カフェラボ発足と同時にこちらは閉鎖)、思えばそれが現在ここカフェラボや一昨年に出版した「人生に行き詰まった僕は喫茶店で答えを見つけた」に繋がったとも言えるものです。
なぜ今こんな話をしているかといいますと、この時のブログの最終回が「オ