
続けて第4弾!サイエンスプレスリリース記事のご紹介👀
弊社は週一でnoteを更新しています。フォローをしていただくと、記事がアップされ次第通知されますので、ぜひこの機会にスキ・フォローいただけると嬉しいです😊🙌
・・・
今回は、サイエンスプレスリリース記事のご紹介第4弾です!!✨
これまでの記事はこちらから↓
月に1度のサイエンスプレスリリース記事をまとめていると、一ヶ月が過ぎるのは早いな~と感じます。
2022年もあっという間に下半期に突如しましたね。
今後もエコラボnoteでは、毎月プレスリリース記事を紹介していく予定です。
毎回、私の好みと独断で選定した記事になりますが是非チェックしてください😊
1.コロナ禍で、都市の人々は海と川に何を求めたのか?
ポイント
生態系がもたらす様々な恩恵 (生態系サービス) のうち、文化的サービスは人々の物理的・精神的ストレスを緩和する上で重要な働きを担っており、昨今のコロナ禍においてもその重要性はますます大きくなっています。しかし、これまでの研究は山地や公園、農地といった緑地に着目することが多く、海や川といった身近な水辺に着目した研究は限られてきました。
そこで私たちは、日本の4つの都市 (東京、横浜、大阪、神戸) でアンケート調査を実施し、第一次緊急事態宣言の期間中 (2020年4-5月) およびその解除後 (2020年6-7月) に、どのような人々がどのような目的・動機で海や川を訪れたのかを調べました。
解析の結果、幼少期の自然経験の豊かな人や周囲に水辺が満足にあると思う人ほど、海や川を訪れる頻度が高いことが分かりました。また、未就学児や小学生と一緒に住んでいる人は、そうでない人に比べて、子どもを外で遊ばせるために水辺を訪れる傾向にあることも分かりました。こうした人々の多くは、ストレス軽減や自然との触れ合いによる健康維持のために、それぞれの水辺を訪れていました。
海と川で結果を比較すると、どちらの水辺でも単にのんびりしていたり散歩したりする人が多かった一方、海では水泳やマリンスポーツといった動的な活動、河川では動植物の採集観察といった静的な活動が比較的多い傾向にありました。また、幼少期の自然経験が豊かな人や宣言期間中に在宅勤務の多かった人は、解除後には海よりも川を訪れる傾向にありました。こうした違いは、都市からのアクセスのしやすさや、それぞれの水辺に対する人々の認識に基づくものであると考えられます。
本研究は、緑地だけでなく水辺もまた、感染症パンデミック下において人々にストレス軽減の場を提供しうることを示唆しています。本発見は、私たち人間の健康と福祉のさらなる向上に向けた都市計画において、緑地と水辺の両方の自然環境を保全する必要性を裏付けています。
詳しくはこちらからご覧ください↓
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_07_01_01.html

2.絶滅したとされていた水生昆虫キイロネクイハムシを琵琶湖で再発見
加藤真 人間・環境学研究科教授と曽田貞滋 理学研究科教授は、日本では絶滅したと考えられていた水生昆虫キイロネクイハムシを、滋賀県琵琶湖で再発見したことを報告しました。
キイロネクイハムシは体長4ミリ程度で、クロモなどの沈水植物を餌とし、卵から成虫まで水中で過ごします。その生息には溶存酸素量が多く、透明度の高い水質が不可欠です。日本では1960年代以降、採集されておらず、環境省のレッドリストでは、絶滅種とされています。琵琶湖では、1950年代に行われた鳥類の食性調査で、ホシハジロの胃内容物から成虫が見つかっており、約70年ぶりの生息確認となります。
今回の再発見は、絶滅種とされるような希少な生物種が私達の身近にも、気づかれることなく生存している可能性を示唆しています。キイロネクイハムシの再発見を機に、人目につきにくい水生生物の保全策にも注意を向けることが望まれます。
研究者のコメント
「キイロネクイハムシはかつて、日本列島の平野部の、水草群落の発達した池沼に生息していたと考えられます。1962年を最後にキイロネクイハムシの記録が日本列島から途絶えたことは、日本の高度成長とともに、豊かな低湿地生態系が日本列島からほとんど失われてしまったことを示唆しています。今回のキイロネクイハムシの再発見は、水草群落の発達した低湿地生態系が、奇跡的にも琵琶湖に残されていたということを意味するだけでなく、日本列島の低湿地生態系の生物多様性を未来に残すための多くの示唆と、そして一縷の望みを与えてくれます。」(加藤真)
詳しくはこちらからご覧ください↓
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2022-07-12-0

3.糖尿病でインスリンが出にくくなる新たな原因を解明
群馬大学生体調節研究所の、井上亮太助教、白川純教授らの研究グループは、横浜市立大学、アルバータ大学(カナダ)、理化学研究所、ジョスリン糖尿病センター(米国)等との共同研究で、糖尿病の膵β細胞からのインスリン分泌が低下する新たな原因を解明しました。
糖尿病は膵臓の膵島に存在するβ細胞から分泌されるインスリンが減少することで発症します。また、糖尿病では、過剰な糖(グルコース)が膵β細胞からのインスリン分泌低下を助長し、さらなる血糖上昇を招きますが、その原因は充分に解明されていません。
今回の共同研究で、糖尿病ドナー由来の膵島で増えているUCP2 (Uncoupling protein 2) というミトコンドリアの蛋白に着目しました。ミトコンドリアでは、細胞が活動するために必要なATPという物質が生成されます。UCPはATPを産生するためのエネルギーを熱へ変換する役割(脱共役)を持ちます。UCPは余計なエネルギーを熱に変換するので、肥満になりにくくなる蛋白であると考えられています。糖尿病でなぜUCP2が増えているのかは不明でした。そこで、膵β細胞でUCP2が過剰に作られる遺伝子組換えマウス(βUCP2Tgマウス)を作成し、UCP2の膵β細胞での役割を解析しました。
βUCP2Tgマウスは、高血糖とインスリンの分泌が減りヒトの糖尿病に似た病態を示しました。βUCP2Tg マウスの膵島では、ミトコンドリアでのインスリン分泌に重要なATP産生と小胞体からのカルシウム放出に異常があり、これらがインスリン分泌減少の原因であると考えられました。βUCP2Tgマウスの膵島における脱共役は糖尿病がないマウスと同等であり、UCP2は脱共役以外の作用でインスリン分泌低下を引き起こす可能性が示唆されました。さらなる解析により、UCP2がアルドラーゼBという酵素を増やすことを見出しました。
膵β細胞でアルドラーゼBが増えると、UCP2が増えたときと同様に、インスリン分泌低下、ミトコンドリア機能異常および小胞体からのカルシウム放出障害が生じることが分かりました。さらに、アルドラーゼBの遺伝子発現を抑制することで、UCP2が増えたことによるインスリン分泌低下が回復しました。
本研究により、糖尿病の膵β細胞で増加するUCP2が、アルドラーゼBを介してミトコンドリア機能異常および小胞体からのカルシウム放出障害を誘導し、膵β細胞からのインスリン分泌低下を引き起こすことで血糖値の更なる上昇を招く新たな機構が明らかとなりました。また、本研究により、UCP2もしくはアルドラーゼB を標的としたインスリン分泌を回復させる糖尿病治療への展開が期待されます。
詳しくはこちらからご覧ください↓
https://www.gunma-u.ac.jp/information/136799
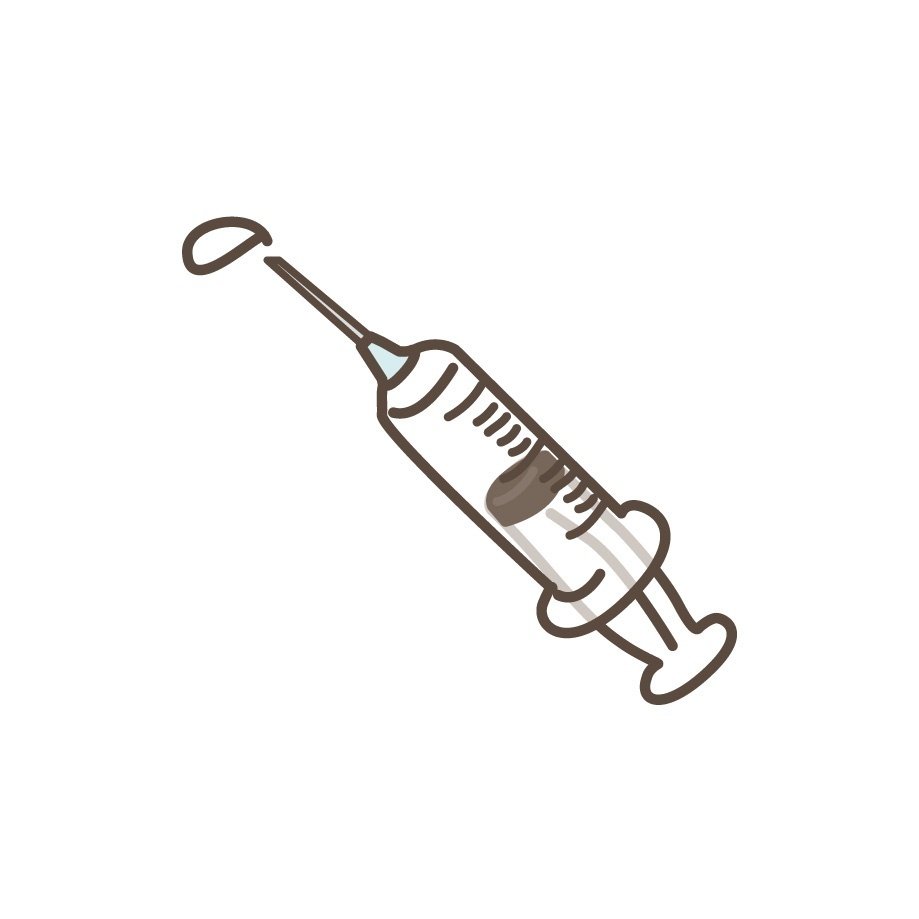
4.理数科目授業時間数の削減と日本の特許出願数の減少
得られた知見
近年、日本の研究開発力が低下しつあることが指摘されている。我々は、2016年、2020年の2度に渡る調査データを活用することで、個人ごとに研究開発アウトプットを調べた結果、2020年時点での47歳以下の世代と、それより上の世代では、特許出願数と特許更新数に大きな違いがあることが分かった。技術者が中学時代に受けた理数科教育の授業時間数との関連を調べたところ、特許出願数と特許更新数は中学時代の理数科の時間数と高く相関していることが分かった。このことは、学習指導要領の改訂とともに、なぜ、技術者の特許出願数と特許更新数が減少してきたかを明らかにするものである。
論文概要
近年の日本において研究開発力が低下していることが、ここ数年の文部科学省の科学技術白書で指摘されてきた。実際に国別の特許出願数の推移をみると、日本の特許出願数は減少し、現在ではアメリカ、中国に後れを取り、韓国との差も無くなっている。また自然科学系論文の発表数も、相対的かつ絶対的に減少し、世界のトップレベルから引き離されおり、日本の研究開発力の低下は一過性のものではない。
我々は、戦後に実施された5つの学習指導要領(古い順に「学習系統性」「教育現代化」「ゆとり」「新学力観」「生きる力」と呼ぶ)を取り上げ、それぞれの指導要領によって定められる中学時代の理数科目の授業時間数が、特許などの研究開発成果に及ぼす影響を分析した。その結果、中学時代の3年間にゆとり教育(「ゆとり」、「新学力観」「生きる力」)の理数教育を受けた2020年時点における51歳以下の世代は、「ゆとり」より前の世代と比べると、特許出願数などの研究開発成果が大きく減少していた。
実際、年齢別の特許出願数を2016年に調査したデータと2020年に調査したデータで比較すると、2016年のデータでは、2016年時点で43歳前半より若い年齢層で出願数が急激に減少し、2020年調査データでは、2020年時点で47歳あたりより若い年齢層で急激に出願数が減少する。2016年のグラフを右に4年ずらして、2020年のグラフとの相関係数を測定したところ0.923と極めて強い相関が示され、二つのグラフがほぼ同じ右上がりの形をしていて、4年のラグをもって重なることが確認できた。グラフは、単なる年齢効果以上の違いを表し、中学時代の3年間ゆとり教育を受けた世代と、それより上の世代での、特許出願数の大きな違いを表すことになる。
より具体的な関係を確認するために、下図のように学習指導要領ごとの一人当たりの特許出願数と理数科目の授業時間数のグラフを描いてみると、「学習系統性」や「教育現代化」の時代に比べ、ゆとり教育における授業時間数、特許出願数はともに低い水準にある。また指導要領の変更とともに生じる二変数の動きが一致し、研究成果と授業時間が強い関係にあることがわかる。
詳しくはこちらからご覧ください↓
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2022_07_01_02.html

5.メタン排出量が多い肉用牛の生理的な特徴が明らかに
【本学研究者情報】
大学院農学研究科 教授 盧尚建
【発表のポイント】
黒毛和種の肥育期間中(前期、中期、後期)に測定されたメタン排出量と、血液・ルーメン液・肝臓の生理的パラメーターを解析し、両者の関係を明らかにしました。
メタン排出量が多い肉用牛は、メタン産生によるエネルギー損失を補うため、体内のアミノ酸を積極的に活用している可能性が示唆されました。
血液中のインスリンとケトン体、およびルーメン液中のプロピオン酸と酪酸の各濃度は、メタン排出量を予測する重要な因子であることが明らかになりました。
【概要】
日本国内から排出される温室効果ガスの量は11億5,000万トン(2020年基準、二酸化炭素換算)で、そのうち農業分野からの排出量は3,220万トンと2.8%を占めています(2022年度日本国温室効果ガスインベントリ報告書)。ウシなどの反芻家畜の消化管内発酵由来のメタンは農業分野の温室効果ガスの約24%(2020年度、二酸化炭素換算)を占めるため、畜産分野ではメタンを低減する飼料の開発や、メタン産生量が高いまたは低い牛の特定などの研究が行われています。これらの研究を遂行するためには、メタン産生量に応じた個体毎の生理的な特徴を明らかにすることも必要です。
東北大学大学院農学研究科の盧尚建教授のグループは、兵庫県立農林水産技術総合センターと共同で、黒毛和種の肥育前期、中期、後期に測定されたメタン排出量、血液中の代謝産物・ホルモン・アミノ酸の濃度、ルーメン液性状*1および肝臓トランスクリプトーム解析*2などの生理的な代謝情報を用いて、メタン産生と生理的特徴との関係を解明しました。本研究でメタン産生との関係が明らかになった生理的パラメーターは、国内で飼育されている黒毛和種のメタン排出量を予測する指標として活用できることが期待されます。
詳しくはこちらからご覧ください↓
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/07/press20220712-01-cow.html

A-Co-Laboについて
弊社は、弊社は研究者が持つ、研究経験・研究知識・研究スキルを活かして企業の課題を解決することを目的としています。
自己紹介記事はこちらからご覧ください↓
興味が湧いた企業の方、研究者の方がいらっしゃいましたらこちらからお問合せ下さい。
ご登録希望の研究者の方もこちらから登録申請して頂けます。
[関連記事]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
