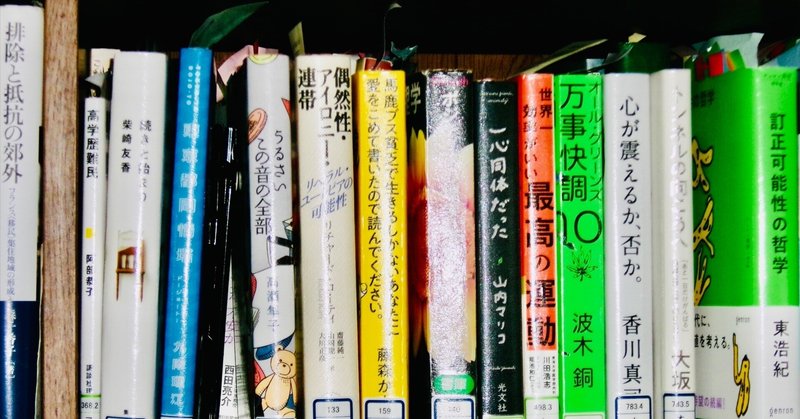
読書感想 『東京都同情塔』 九段理江 「とても強い小説」
どんな本を読むのか。
自分がそれほど早く本を読めるわけでもなく、若い時から古典と言われる作品をたくさん読んできたわけでもない。読書の習慣がついたのは、中年と言われる年齢になってからだった。
本を選ぶこと
だから、どの本を読むのかについて、ただ自分の感覚に従って、例えば昔のレコードの「ジャケ買い」のように、本の表紙や作品名だけで選んで、それが自分にとっての名作であるような鋭い選択をできるような自信は全くない。
ただ、それでも色々な本を読むようになって、ラジオやテレビやインターネットなどで、誰が紹介しているか、どんな声のトーンで本を紹介しているか。そんな条件で、少しずつ、自分にとって必要な本を選べるようになってきた。
芥川賞を受賞したり、その候補になった作品に関しては、本を読む習慣がつき始め、図書館によく通うようになった頃は、難解なのでは----という先入観と警戒心が先に立ってあまり読むこともなかったが、特にここ数年は手に取る機会が増え、しかも興味深く面白い作品が多いので、より気になるようになった。
そして、時々、芥川賞受賞作で、そのざわめきの気配で、今回はちょっと違う作品なのではないかと、読み手としては大したことがないのは自覚しつつも、そんな予感みたいなことを感じることがある。
この『東京都同情塔』のときも、そうだった。
(※ここから先は、小説の内容にも触れていますし、引用もしています。もし、何も情報がないまま、今作品を読みたい方は、これ以降は読むのを中断された方がいいのかもしれません)
『東京都同情塔』 九段理江
読み始めると、その文章の質が気になってくる。
とはいっても、それが嫌な感じというのではなくて、一文節、一文節が、やたらとくっきりしているように感じたからだった。なんというか、異常に滑舌がいい文章、というような印象だった。
それは、この作家のいつも変わらない特徴というのではなく、他の小説、例えば『Schoolgirl』では、こうした印象を受けなかったから、作品に必要だから選ばれた文章ということかもしれないと思った。
『東京都同情塔』の主人公は建築家。これから、いろいろ意味で重要な建築物を建てなければいけない状況にいる。まだ存在しないものを、存在するようにしなくてはいけない。
だから、その思考を文章にすると、一つ一つの強度を上げながら、その上で全体も密度高く隙間なくまとまるようになるのは必然かもしれないと読者は思うようになっていく。
例えば、冒頭のこうした建築家の思考の流れ。少し長いけれど、この引用部分でも、そうした傾向で組み立てられているように感じる。
日本人が日本語を捨てたがっているのは何も今に始まった話ではない。一九五八年、日本電波塔の愛称に「東京タワー」が選ばれたのは、名称審査会の中に日本語を忌避した日本人がいたからだ。一般公募でもっとも多くの支持を集めていたのは「昭和塔」だった。次いで「日本塔」、「平和塔」、「富士塔」、「世紀の塔」、「富士見塔」と続きながら、しかし結果的に応募数第十三位の「東京タワー」に決まったのは、ある審査員の「『東京タワー』を措いて他に無し」の鶴の一声によるものだった。仮に、公平な多数決によって「昭和塔」に決定していたとしたら、きっと今頃あの黄赤と白の塔には、取り残された過去の遺物のような古臭さがついてまわっていただろう。昭和生まれの人間が時代遅れの象徴として扱われ始めているのと同じような現象が起こったはず。結果、今では日本人の大多数が「東京タワー」に納得し、東京タワーに東京タワー以外の名称など考えられないと思っている。強引ともいえる当時の決定は賞賛されるべきだと言うこともできる。民主主義に未来を予測する力はない。未来を見ることができない。
私には未来が見える。
まだ起こっていない未来を、実際に見ているかのように幻視する。何も知らない人たちからは、これを才能だとか超能力だとかアーティスティスティックなインスピレーションだとか言おうとするけれど、もちろんただの職業病の一種に過ぎない。巨大建築の設計を一度でも経験したことのある建築家なら、誰もが同じ病にかかっている。扱う建物の規模が大きくなるほど、都市の風景への影響が大きくなるほど、病は進行する。一度建てたら取り返しのつかないものを構想するのに、「未来は誰にもわからない」などと悠長な寝言を言っているようでは話にならない。
幻視を二次元の線に写したドローイングのうち、九十九・九パーセントは二次元世界に留まる。本当に「世界を起こす」ためには当然、幻視を描き起こすだけでは足りない。建築家の前に出現した美しい幻を現実化するには、実際的な技能も同じくらい必要だ。予算と工期を計算すること。権力にすり寄るのを恥じないこと。その建物がその形状をしていなければならない理由を、素人にもわかる言葉ででっち上げること。これらの技能のうちひとつでも欠けていたら、きっと私は美術館の壁に飾るためのお絵描きでもして暮らしていただろう。でも私にとってそんなのはとても現実の仕事であるとは言えない。
選択できたかもしれない未来
この小説の東京には、ザハ・ハディドが設計した国立競技場が存在する。
実際には、一度はザハ・ハディド案に決定したのだけど、その後撤回されたのが歴史的事実で、その経緯もよくわからなかったし、その建築家が「アンビルドの女王」と言われているのは知識としては知っていたけれど、ザハ・ハディッドという建築家の凄さも、愚かな大衆の一人として分かっていなかった、と思う。
その後、オリンピックに関わる人たちの強引な進め方や、緊急事態宣言なのに開催するという経緯によって、そのことは、さらに記憶の外に行かされてしまったような印象がある。
だけど、少し時間が経って、今は亡くなってしまった建築家の「作品」を写真で見るだけで、俗な表現しかできないけれど、素直に、とても格好が良く魅力的だと思う。
それも実際に建てられた建築物の写真を見ると、もしかしたら撤回された国立競技場も、その図面の案よりも、実現して実際に存在した方がすごかったかもしれないと感じられた。
そんなことに今さら気がつくのは遅いし、やはり愚かなことではあるけれど、この小説に描かれている近未来が、ザハ・ハディドの設計した国立競技場が存在することを前提に組み立てられていて、それが今とは明らかに違う質を持った世界なのは分かった。
実際には存在しないにしても、もしかしたら、選択できたかもしれない未来が描かれていて、それは建築のように緻密に構築されているように組み立てられているから、実在感が濃いようにも思う。
とても強い小説だった。
シンパシータワートーキョー
小説の中で、建築家が設計をしようとしているのは塔だった。
それも、シンプルに今の時代の言葉であれば「刑務所」だった。
あの闇の中に建つ塔は、独立した建築として考えるべきではないのだ。上から見下ろしたときの新宿全体の景色を考慮しなくてはいけない。スタジアムのデザインとの調和を無視して塔を建築することなどできない。いうなれば塔は、南側のザハ・ハディドに対する回答でなければならないのだ。それらが二つ揃って初めて、都市の風景は完成する。つまり、彼女がどのような問いを塔に投げかけているのかを導き出すことができれば、正解はおのずから姿を現す。こう考えればわかりやすい。スタジアムは妊娠中の母体であり、塔の出産を待っている真っ最中なのだ。
その塔は正式名称としては「シンパシータワートーキョー」と名付けられていて、この世界では、ある学者によって「犯罪者」ではなく「ホセ・ミゼラビリス」と呼ばれるようになりつつある。
つまり、犯罪者になるのは、ほとんどの場合、犯罪を犯すように追い込まれる環境で生きてきた「同情すべき」存在だから、罰するのではなく、ケアをするのが適切で、だからそれにふさわしい環境を作るべき、というそれまでにない思想をもとにした建築物だった。(ただ、この思想に対しては、現在でも肯ける部分が少なくない)。
それは、読者にとっては、フィクションとはいえ、ザハ・ハディドの国立競技場が建設される東京だからこそ、そこから積み上がるように実現することなのだろう、という感覚になってくる。
つまり、現実の東京では「シンパシータワートーキョー」は、決してできないのだ、ということも実感させてくれるのだった。
AI
読む前は、気がつかなかったこともあった。
これだけ緻密さのある作品だから、小説の隅々まで、当然、言葉に関しても、うかつな読者にとっては、気がつかないレベルで厳密さが行き届いているだろうけれど、それだけでなく、はっきりと厳密さが表されている箇所もある。
それは、東京同情塔ではなく、東京都同情塔という名称の方がはるかに優れている、という建築家の言葉で分からされるようなところだ。
東京都同情塔だと韻まで踏んでいるという指摘もされているけれど、私自身は最初にこの小説のタイトルを聞いてから実際に読むまで「東京同情塔」だと思っていたから、その違いに注意を払えていなくて、自分のガサツさに、ちょっと恥ずかしくなるような思いにもなった。
さらには、この小説が生成AIを使って書かれている部分があることで、海外までざわざわさせているらしいのも、読んだ後に知った。
それも、全体の5%ということは、400字で200枚らしいので、原稿用紙でいうと10枚程度。小説の中で登場人物がAIに尋ねている場面もあるから、それに答えている部分は、おそらくそのまま生成AIを使ったのではないかとも思えたけれど、そうだとしたら、その方が現時点でのAIの機能を遺すという点から考えても意味があるのではないだろうか。
それに、今後はそうした生成AI使用については、現在の引用に関してのルールのように整備が進むかもしれないが、この「東京都同情塔」では、その使用が小説の質を混乱させているのではなく、AIを使ってより強くなろうとする将棋の藤井聡太のように、九段理恵という小説家にとっては、そうした異なる存在も小説の中に入れることによって、より質を上げているような気がする。
小説家として、とても強い人なのではないかと思った。
未来に対して悲観的な思いしか持てない人に、特におすすめしたいと思います。わかりやすい希望を提示しているわけではないのですが、人の意志が世の中に影響を与えることがあり得るのではないか、といった肯定的な感覚も持てるような気がするからです。
(こちら↓は、電子書籍版です)。
(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。
#推薦図書 #読書感想文 #東京都同情塔 #九段理江 #芥川賞
#生成AI #ザハ・ハディド #建築家 #未来 #小説家 #言葉
#毎日投稿 #シンパシータワートーキョー #刑務所 #ネタバレ
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。

