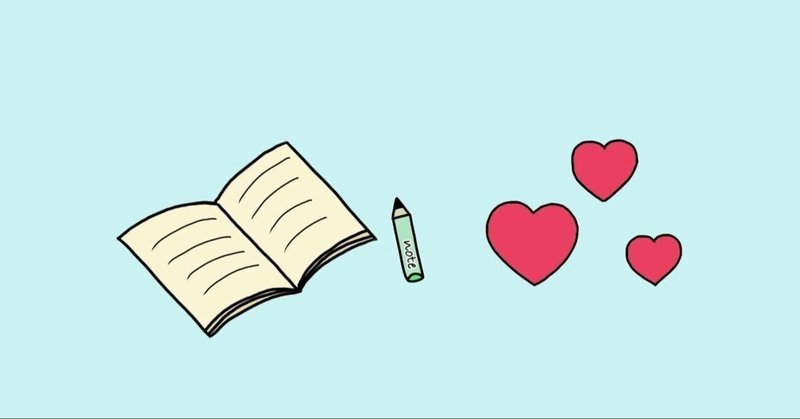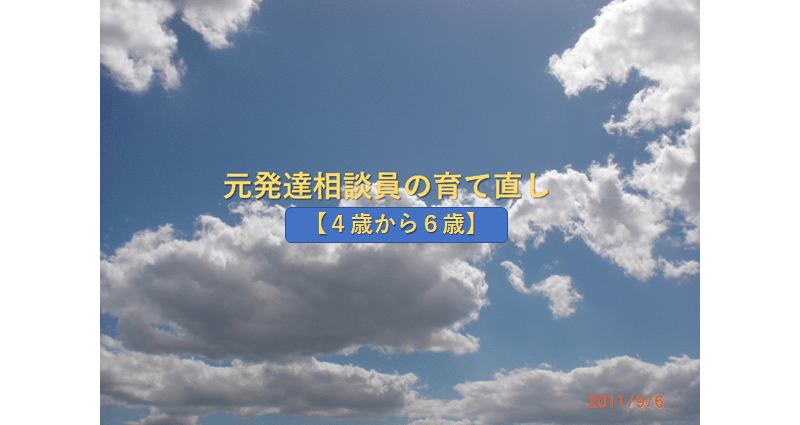
- 運営しているクリエイター
#note_expo2021
4歳から6歳までに『何をどう育てるのか』を、ものすごく具体的に書きます
「これから、何を書こうとしているのか」の説明編です。少し長いですが、読んでください。
1.4歳から6歳までの間に「どんなこと」を教えていけばいいのか 小学校に向けて、4歳から6歳までの間に「どんなこと」を教えていけばいいのでしょう。考えながら、子育てしているでしょうか?
平均タイプなら心配いりません。子どもから出てくる要求に合わせて子育てすれば、普通に小学校に適応するような子どもに育ちまま
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 16 「今、何を聞くべきか」を自動的にできる その3
1️⃣ 先生(発言者)が話し始めたら、してることは全部やめて先生(発言
者)の方を見る。
2️⃣ 身体は先生(発言者)に向け、手をひざに置くかイスの後で手を組む。
3️⃣ 先生(発言者)の話を、理解しようという心づもりで聞く。
4️⃣ 相手の話は最後まで聞き、途中で絶対口をはさまない。
5️⃣ 頷いたり、アイサインを送ったり、感想を考えながら聞く。
6️⃣ 校内放送や集会場面でも同じよ
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 17 「今、どこを見るべきか」を自動的にできる その1
低学年で覚えて欲しい学び方スキルの2つ目は『「今、どこを見るべきかを自動的にできる』です。これには、3つの補助項目が付いているですが、それを紹介する前に『「今、どこを着るべきか」を自動的にできる』について、【解説】しておきます。
「どこを見るべきか」も「何を聞くべきか」と【解説】は、またく同じです。
平均タイプの子どもは、生まれたときから自分のやりたいことを抑制して「周りの大人から学び取ろ
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 17 「今、どこを見るべきか」を自動的にできる その3
1️⃣ 先生(発言者)が黒板に書き出したら、してることは全部やめ先生(発言者)の書いていることを見る。
2️⃣ 先生(発言者)が書き始めたら、何が書いてあるか理解しようとして見る。
3️⃣必要だと思えば、先生(発言者)が言わなくてもノートに写していく。
【育て方】
これら3つを、6歳までに育てるためには、「母親が指差して話しかけたときに、その指先にあるものを見る」ことを育てればいいでしょう
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その1
低学年で覚えて欲しい学び方スキル3つ目は、「ノートのとり方」です。これには、8つの補助項目が付いているですが、それを紹介する前に「ノートを取る」について、解説しておきます。
ノートを写すスキル、つまり「遠くの黒板を見て、ノートに写すスキル」は、かなり特殊なものです。学校でしか使わないスキルです。遠くのものを写すなんてことは、日常生活ではあまりありません。それだけに、訓練が必要です。1番のポイ
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その3
補助項目の【解説】の続きです。
3️⃣ チョークの色とエンピツ色との関係を覚える。 【解説】
これは、小学生には分かりにくいルールです。凸凹タイプの子どもには、なおさらでしょう。
最近、チョークの色は増えています。しかし、有効に使える色というのは余りありません。かつ、板書で目立つように使った色を、子どもたちが同じようにノート使うと、あまり目立たないということも起こります。例えば、黄色で
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その4
5️⃣ 定規でまっすぐ、かつ素早く線が引けるようになる。 【解説】
これは、大事なところを線で囲ませる先生が多くいるから必要です。矢印や筆算の横線やイコールまで定規で引かせる先生もいます。では、なぜそうのような先生が多いのでしょう。それは、効果があるからです。
TOSSの向山洋一さんは「理由はわかりませんが、きれいに書こうという意識が強まり、適当さが減るからではないでしょうか」と言っていま
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その5
補助項目の最後の2つを、解説しまします。
7️⃣ 観察ができ観察ノートが 書けるようになる。(実際に書いた見本を見
せることが大切) 【解説】
1年生になると、すぐさま生活科で「朝顔の観察日記」が始まります。観察日記には、理科的な要素の他に国語の作文や、図工の観察画の要素があります。
保育所や幼稚園から上がってきた子の中には、思い込みで絵を書く子が多くいます。見ないで「花はこう書く」
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その6
1️⃣ 早く視写するときと、丁寧に視写するときの違いと方法を知る
【育て方】
これは、思考の柔軟性が弱い(固執性、こだわりがある)ことと関係しています。凸凹タイプの子どもは、多かれ少なかれこの特徴を持っています。
・一つのことを覚えたら、他のことを覚える気がない
・あることには、一つの方法しかないと思っている
・ある方法を覚えたら、それにこだわる
・いい方法があるのに、なぜ
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その7
3️⃣ チョークの色とエンピツ色との関係を覚える。
4️⃣ 板書以外でも、先生(発言者)の説明等で面白いと思ったことはメモで
きるようになる。
8️⃣ 聴写もできるようになる。(連絡ノートや授業で取り組む)
【育て方】
この3つのことは、文字が自由に書けるようになる小学校になってから覚えればいいでしょう。
3️⃣は1️⃣と同じように「思考の柔軟性の弱さ」と関係しています。18の
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その8
6️⃣ 資料をノリで素早く貼り付けられるようになる。 【育て方】
「紙をのりで貼るスキル」は、遊びやお手伝いで育てておきましょう。【解説】でも書いたように、結構学校で使いますしスピードも求められます。
ノリで遊ぶと言えば、貼り絵でしょう。広告紙や折り紙をちぎって貼って、たくさん遊びましょう。小さいときは、台紙の方にのりをぬたくったりしたあと、貼り絵をしたらいいでしょう。
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 その1
この項目には、6つの補助項目があります。まず、それを紹介する前に「発表」について、少し【解説】します。
最近、指導要領が変わって「主体的で対話的で深い学び」と言うことが言われて、学び方が変わりつつあります。先生の発問に対して「手を上げて発表する」ことが減ってくる傾向にあります。しかし、まだまだ「手を上げて発表する」スタイルの授業は残っています。
「手を上げて発表する」ときのルールが「うま
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 その3
6っ項目の【解説】の続きです。
4️⃣ 成文(文語文)で話す
発表は、できるかぎり成文(文語文)でさせます。それは、私達は、文語で考えるからです。口語で「右、曲がったら、行き止まり。最悪」これでは、解決方法は一生湧いてきません。「もし、右に曲がって行き止まりだった場合は最悪だが、その場合は携帯を使って友達に道を聞くしかないか」と文語で考えるのです。
だから、授業中のコミュニケーション
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 その4
5️⃣ だらだら発表しないために、前以てノートに書いてから発表する
【解説】
ダラダラと表されると、授業はだれていきます。授業には、テンポが必要だからです。だから、ダラダラ発表しないように、低学年では次のように指導していきます。
重要な場面で発表するときに「~について、書いてみましょう」と書く時間を取ります。その書いたもの読んで発表させます。書いていますから、当然成文になっています