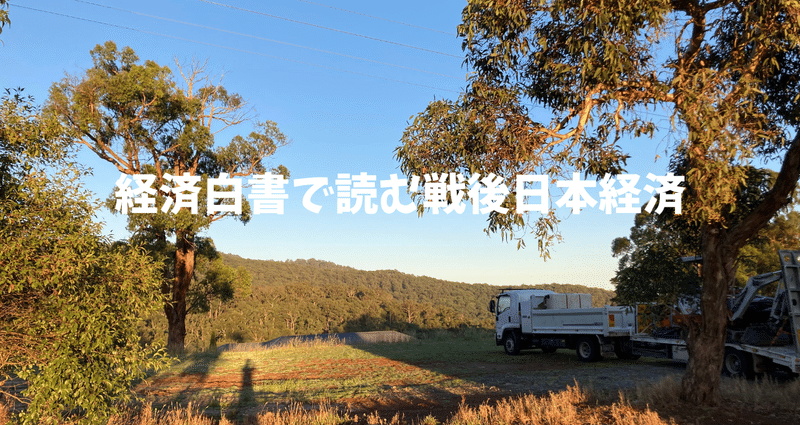
「経済白書で読む戦後日本経済」の書籍をもとに、1945〜1999年までの日本経済を5年ごとに解説しています。
この頃に作られた社会システムは現在に通ずるものも多く、「今の日本は何…
- 運営しているクリエイター
#高度成長
【今でしょ!note#12】 1956-60年 高度成長の開始 (経済白書から現代史を学ぶ その3)
おはようございます。林でございます。
今週から連続で配信中の「経済白書で読む戦後日本経済の歩み」シリーズの続きです。
これまでを簡単に振り返ると、1945~50年では、戦後の経済ボロボロ・財政めちゃくちゃ・国際収支大赤字・国内ハイパーインフレ状態から、新円切替・預金封鎖・ドッジライン・1ドル360円の固定為替、朝鮮特需により一定の回復をしました。
その後の1950年代前半では、高度成長に入って
【今でしょ!note#14】 1966-70年 高度成長の持続と動揺 (経済白書から現代史を学ぶ その5)
おはようございます。林でございます。
「経済白書で読む戦後日本経済の歩み」シリーズその5です。
1955年ごろから開始した高度経済成長では、戦後10年間のアメリカからの支援や特需における回復を基調とした成長ではなく、企業の技術革新・設備投資を基調とした近代化による成長フェーズに入りました。
1960年の「国民所得倍増計画」では、設備投資の増大により供給能力を伸ばす、民間の旺盛な設備投資欲を後
【今でしょ!note#15】 1971-75年 円レート上昇と石油危機の大変動 (経済白書から現代史を学ぶ その6)
おはようございます。林でございます。
「経済白書で読む戦後日本経済の歩み」シリーズその6です。
1955年ごろから開始した高度経済成長では、その後1973年までの20年弱の間、途中「昭和40年不況」などもあり、必ずしも常に上昇気流に乗り続けていたという訳ではありませんが、年平均10%を上回る成長を遂げ、1968年にはGNP世界第二位の国になりました。
この経済成長の背景には、企業の旺盛な設備




