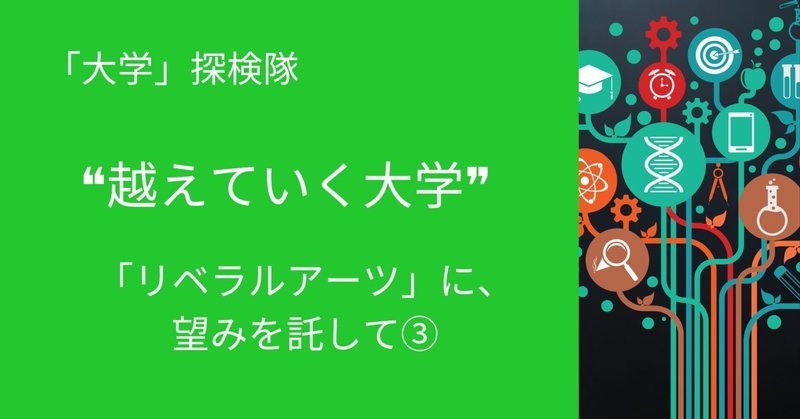
既存の概念を越えた視点で模索し、再構築されていく、これからのリベラルアーツ。
リベラルアーツの火を絶やさぬように
「大学大綱化」以降、すっかり下火になってしまった国内大学の教養教育。
しかし、混迷の世界に突入し、時代が大きな転換期を迎えた現在、改めて教養教育の重要性が認識され始めてはいますが、大綱化以降も、リベラルアーツの火を絶やさぬよう、地道な努力や工夫を重ねてきている大学も少なからずあるのです。
国立大では、東京大学のほか、東京医科歯科大学、東京工業大学、等々。
私立大学では、国際基督教大学、玉川大学、東京女子大学、桜美林大学、関西学院大学、等々。
そのなかには、東京大学のように後期学部教育にも教養教育を導入する試みや、教養自体を専門とする学部や学科を新規に立ち上げる事例も多々見られますが、これからあるべきリベラルアーツそのものを、いままでとは違う視点で、模索し、再構築する動きも出てきました。
上智大学(東京都)のユニークな取り組みも、そうした一つと言えるでしょう。
上智大が提示する新たな全学共通科目
上智大学は、2022年度「基盤教育センター」を立ち上げ、新たな全学共通科目を設定しました。
いわば、現代版「リベラルアーツ教育」というべきものを、上智大独自の視点で構築したと言ってもいいでしょう。
その科目は次の4つのコア科目領域から構成されています。
<人間理解>
◇キリスト教人間学領域
「キリスト教人間学」の科目では、上智大学の教育精神の根幹にある「キリスト教ヒューマニズム」に根ざして、人間として生きる意味や価値を主体的に探求します。
◇身体知領域
「身体知」の科目では、自らの身体への気づきを通して、身体を生きる存在としての人間理解を深めることを目指します。
<思考の基盤>
◇思考と表現領域
「思考と表現」の科目では、クリティカルシンキング(批判的思考)と表現力を身につけることを目的としています。
◇データサイエンス領域
「データサイエンス」の科目では、データを読み解き、活用する力を身につけるとともに、社会におけるデータの影響についても学びます。
そして、基本コンセプトは、次のように謳われています。
新しい上智大学の学びでは、全学共通科目は専門科目を学ぶ前の基礎教養教育ではありません。学部・学科の専門分野とともに、すべての学生が4年間を通して学ぶ科目として重要な役割を担います。課題認識から探究・統合にいたるまでのレベルを表す縦の軸と、専門領域を超えて繋ぐ科目群構成を表す横の軸で展開していきます。これらが、学科科目(各学科の専門科目)や語学科目と有機的に結合し、自ら学び続ける学修者となるための学びを実現します。
「すべての学生」 「専門領域を超えて繋ぐ」
ここでは、この基本コンセプトのなかで、2つの点に着目したいと思います。
まず、「すべての学生が4年間を通じて学ぶ科目」とした点。
所属する学部や専門領域という垣根を越えて、あらゆる学生が学ぶ科目、
ということ。
考えてみれば、学生は例外なく全員が学ぶ、という点は、古来、リベラルアーツにおけるの大事なポイントでもありました。
選択ではなく悉皆で、ということです。
複数の学部やキャンパスを擁する大規模大学には、なかなか実現が難しい面があるのかもしれません。
その点、上智大学は、東京・四ツ谷のキャンパスに全学部が集まっている利点を生かせたと言えるかもしれません。
そして、さらに重要なのは、「専門領域を超えて繋ぐ科目群構成」である点です。
学部後半の3,4年次、つまり専門分野を学ぶ学年になって、専門科目と並行して学ばせる、ということ。つまり、専門領域との壁を超え、その間を行き交いながら繋がる、ということを目指しているのです。
ここには、学部後期の専門領域に進んでからこそ、教養教育が大切である、というメッセージが込められているわけです。
このコンセプトは、前回ご紹介した東京大学の後期教養教育にも通じるところがありますね。
「領域の限界」からの解放
東京大学の元理事・副学長の石井洋二郎氏は、リベラルアーツの意味するところについて、「人を自由にする」、「解放する」という本義に立ち返りながら、次の4つの限界からの解放である、と説いています。
「知識の限界」 「経験の限界」 「思考の限界」 「領域の限界」
そして、最後の「領域の限界」からの解放こそが、後期教養教育につながっている、というわけです。
石井氏は、このように後期教養教育導入の趣旨を説明しています。
「狭い専門性に囚われる前に、まず幅広い知識を」ではなく、
「狭い専門性に囚われかけた段階でこそ、これを相対化する視野を」
「はじめに」より
教養としての、「身体知」
さて、ここで、上智大学が設定した4つの領域のなかにとても興味深いアジェンダがあることをご紹介しましょう。
それは、「身体知領域」です。
従来の教養教育ではあまり目にしないアジェンダといえるかもしれません。
では、「身体知領域」の必修科目である「身体のリベラルアーツ」のコンセプトを覗いてみると、次のように書かれています。
必修科目の「身体のリベラルアーツ」は、“⾝体で感じる・知る”ことを通して、多様な学問や価値観のなかで⾝体(=存在)から思考し、生涯の学びにつながる「教養としての身体」を獲得するために、身体知領域が展開する科目群の入り口として1年次に履修します。授業では、自身のからだに目を向け、生きている身体を感じること、他者や集団との関わり方、現代社会の抱える問題を自らの問題として捉えることについて、講義やさまざまなワークを通じて、実践と学びの機会が提供されます。
基盤教育センター身体知領域の吉田美和子教授は、この科目が“射程”とするところについて、具体的に、
「…心身論からスポーツや武道、ダンスなどのパフォーミング・アーツに至るまで、身体を取り巻く諸現象を広くとらえていきます」
と紹介しています。
パフォーミング・アーツも射程に
端的に申し上げれば、この身体知領域は、「パフォーミング・アーツ」までを射程とする、というわけですね。
さて、このパフォーミング・アーツ。
定義としては、舞台芸術の総称であったり、あるいは音楽や演劇、舞踏など、肉体を使って表現される“芸術”とされています。
つまるところ、芸術もリベラルアーツの対象である、というわけです。
リベラルアーツに芸術も含まれる、と言われると、ちょっと違和感をお持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、日本の大学のお手本になったとも言われる本家・米国大学のリベラルアーツを詳しく見てみると、日本とは「アート」の扱いが大きく異なっていることに気付くのです。
リベラルアーツにはアートが深くかかわっている。
そのあたりについて、次回さらに探索してみたいと思います。

#リベラルアーツ #大学 #上智大学 #東京大学 #教養教育 #基盤教育センター #後期学部 #全額共通科目 #科目領域 #専門領域 #身知体 #データサイエンス #学部 #キャンパス #パフォーミング・アーツ #アート #芸術 #舞台芸術 #音楽 #演劇 #舞踏 #代々木ゼミナール #代ゼミ教育総研
