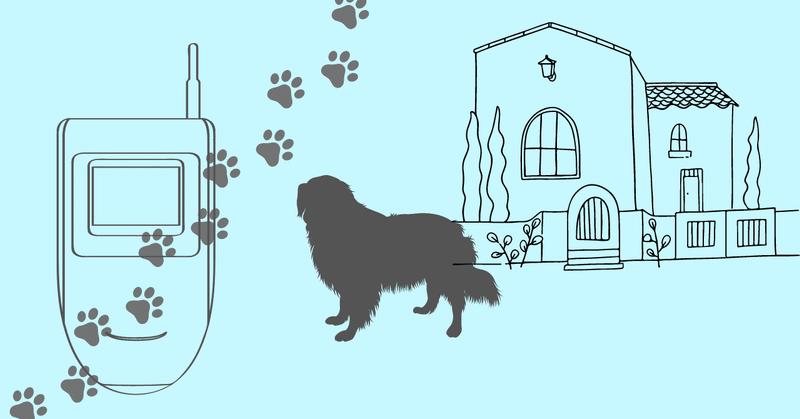
GOLAZO #4
2002年。失恋して仕事も失った30歳の東野紅深と妻に先立たれた65歳の速水草輔は、近所に住む犬の散歩仲間。犬同士が仲良くなったことをきっかけに親しくなり、いつしか互いに大切な存在になっていく。病を得て、一緒に最後の旅をして欲しいと言う速水に戸惑う紅深。旅は実現しないものの、紅深は旅の計画をきっかけに出逢った男性と付き合いはじめる。彼は優しく善良なのだが、紅深は彼との恋愛にいまひとつ踏み出すことができない。
横浜を舞台に、2002年と2022年のサッカーワールドカップとコロナ禍、20年の時を行きつ戻りつする物語。
4. 2002年 鎌倉きのこたけのこ戦争
三千年と一緒に速水の入院先をたずねた日は、ゴールデンウィークの少し後で、暑い日だった。
あれからたびたび会うようになって、紅深の中で「アベくん」は「ミチトシくん」に昇格していた。
速水の病室は、大きな基幹病院の個室だった。到着した時速水はベッドに身体を起こして、ニヤニヤして紅深に言った。
「もうな、絶対きみたちは、上手くいくと思ったんだ」
恥ずかしがったり赤くなったりするほど初心ではないが、やはりばつが悪くて紅深もニヤニヤ笑った。相手の病気が分かっていて病室を訪ねているのに、ニヤニヤするのはどうかと思ったが、ニヤニヤ以外の表情ができなかった。
「いろいろありがとうございます」
三千年が速水に真っ正直にそういうので、ますます変な表情になってしまう。
「東野。こんないい男はそうそういないぞ。俺が保証する。きみたちの仲人を引き受けたかったが、まあさすがに無理かな」
あっけらかんとそういうので、紅深の顔から笑みが消えた。
「だいじょうぶです」
何が大丈夫なのか、三千年が言った。
「いろいろ、急ぎます。すぐに、なんとかします」
顔が真剣だった。
それはつまり、結婚、ということなのだろうか。
紅深は少し、ぼんやりした。
ついこの間付き合い始めたばかりで、キスしかしていないのに、結婚とはこれいかに。
紅深の顔色をどう思ったのか、急に速水が
「おい、東野。ちょっと頼まれてくれないか」
と言った。売店で、きのこの山を買ってこい、という。
「え。何言ってんですか。そんなの病室で食べていいんですか。しかもなんできのこの山ですか。私はたけのこの里派です」
紅深はつい、いつもの調子で軽口をたたいた。
「検査の後は、食べて悪いもんなんてないって言われてんの。なんでもいいんだよ」
「じゃあ、たけのこの里でもいいんですね。きのこの山より断然、たけのこの里のほうがおいしいですって」
「なんだよ。病人がきのこの山食べたいって言ってんだろ」
「だいたい、売店にそんなにお菓子の種類あるんですか」
「この病院のファミマはでっかいんだ。何でもある。絶対、きのこの山だぞ。なかったら、病院でたとこの角にセブンイレブンがあるから、そこ行ってこい。いいな」
いつもの軽口合戦に、三千年は何を思ったか、
「ぼくが買ってきますよ」
と、とりなした。
そもそも、三千年と紅深は大船の「葦」の焼き菓子を持参していた。速水が食べられないかもしれない、と言った紅深に、三千年が速水から指定されている、と言った品物だ。
「いいから。もう、なんでもいい。しょうがねえから、たけのこの里買ってこいよ」
そう言って、ぶつくさ言いながら財布からお金を出そうとした。
「いいですよ。とにかく、行けばいいんですよね」
捨て台詞のようにそう言って、紅深は病室を出た。
「ガリガリ君とジャンプとエロ本も買ってこい」
と、背中に速水の声がしたが振り返らず、紅深は廊下を足早に歩いた。
次第に、感情が盛り上がってきてどうしようもなくなる。エレベーターのボタンを押したのにくるりと踵を返して非常階段の鉄の扉をあけ、階段を下りた。
紅深はコンビニまでたどり着けなかった。
非常階段の踊り場で、紅深は泣いた。
痩せていた。ほんの2ヶ月ばかり合わないだけで、速水はすっかりやせ細っていて、紅深の知らない人みたいになっていた。
枕元には、奥さんとヨーコの写真。
散歩のときにたまたま写真が趣味の近所の岡田さんが撮ってくれた集合写真も飾ってあった。その中にはラルフと紅深もいた。
夕方で、逆光気味でまぶしくて、犬はみんなそっぽを向いているか目が赤目になっている。速水と紅深の間には、風間さんと三匹の犬が写っていた。
嫌だなと思った。
紅深はただの犬の散歩友達のひとりで、集合写真の一部だった。せいぜい、良くて娘のようには思ってくれていたかもしれないが、ただそれだけの存在に過ぎなかった。
でもあんなに、映画を観た。サッカーの話をした。一緒に洒落た店でランチも食べた。絶対に割り勘だったから高い店はいかなかったけれど、速水はジャンクフードもパスタランチも喜んで食べた。本を貸し合って、くだらない冗談を言って笑った。速水はドストエフスキーよりチェーホフが好きだった。ダニエル・プイグの『蜘蛛女のキス』の話をしてくれた。紅深はかわりにミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』の話をした。
耐えられない。
本当に、嫌だと思った。
軽すぎる。自分の存在が。耐えられない。
速水と別れるのが嫌だ。
紅深の気持ちは、違うのだ。
彼を父親のように思ったことなど、一度もない。
父親なんかではない。
ひとりの、男性としてみていた。
まさかの気持ちに、自分でも気づくのが嫌でごまかしていた。
三周りも違う年上の、還暦をとうに過ぎた、奥さんだけを愛している速水に恋をしたところでどうしようもないことだけはわかっていた。
恋?恋かどうかもわからないし、そんなことはどうでもいい。
速水が大切だった。
毎日病院に行ってよければ、毎日通いたい。
でもそれはどう考えてもおかしいから、無理して意識を速水に向けなかった。他人事として考えるように自分をコントロールようとした。
でもこうして見てしまったら、無理だ。気持ちを抑えきれない。
速水がいなくなる――
三千年はとてもいい人だ。速水が気を回してくれたことも分かっている。
スペインは、思いはあっただろうが現実として無理だということはわかっていただろう。でも夢を見た。最初は戸惑ったが、紅深も速水とスペインに行ってみたかった。
病でやせ細っていたこともショックだったが、速水の目の前で、まだプロポーズもされていないのに三千年が結婚の話などしたのも嫌だった。
心の整理がつかない。
きのこの山とたけのこの里のズレも気に入らない。菓子ばかり買いに行かせて、「葦」の焼き菓子はどうするんだよ、とも思う。
頭の中がぐちゃぐちゃで、わけもわからず、紅深はハンカチを顔全体に押し当ててぐぐぐ、と泣いた。嗚咽をこらえているので鼻の奥が痛んだ。
「紅深さん」
三千年がどういうわけか、紅深の位置を正確にキャッチしたように踊り場に表れた。
こんな姿は見られたくなかったが、でももう遅い。
「まだ。まだ、コンビニ行ってないの」
ぐえぐえ言いながら、紅深は言った。こんな姿、せっかくできた彼氏なのに百年の恋も冷めるに違いない。
「たけのこの里も、ガリガリ君も、ジャンプもエロ本も買えてない」
三千年は、紅深をそっと抱きしめた。
「あれは、ぼくと話をするための口実だって、速水さん言ってました」
頭の上で、彼が言った。
「それで、あんなプロポーズはしちゃだめだ、って怒られました」
落ち着いた優しい声。
いい子なんだよ。自分にはもったいない。ほんとに優しい人。
「なんで、ぼくがちゃんとプロポーズしていないって、わかったんでしょうね、速水さん」
それは紅深の顔色を読んだからだ。彼は人のことが本当によくわかる人なのだ。自己申告だが営業成績は常にダントツトップの、すごい人なのだ。
「だって」
紅深は嗚咽の間から言った。
「まだ、付き合って、2か月だよ。三千年くんが、そんな素早い、ステップを踏むとは、思えないじゃない」
ふふ、と、三千年は笑った。
「紅深さんの言い回しって、速水さんとよく似ていますね。面白くて、テンポがよくて、楽しくて」
のんきなやつだなぁ、と、紅深は内心思った。
「結婚は、他人を喜ばせるためにするもんじゃないだろ、って」
「そうだよ、だいいち、まだ私たちまだ」
顔を上げた。きっと史上最悪にブスな顔をしているに違いないのに、三千年は構わず強く紅深を抱きしめた。
「まだ何もしてなければ、結婚したいって思っちゃだめですか」
「三千年くん」
「速水さんを喜ばすためじゃない。ぼくは紅深さんと結婚したいと思ってます。つきあった年月とか、関係ないです。結婚してくれませんか」
「こんなとこで、言う?」
紅深の涙はひっこんでいた。プロポーズの場所が、病院の階段かよ。
でもこんなところが、自分にはふさわしいのかもしれない、とも思った。
「どうでもいいけど、なんで、ここにいるってわかったの」
鼻声できくと、三千年は苦笑した。
「速水さんが、たぶんここだって。ほんとにいたから驚きました」
速水はなんでもお見通しだ。
紅深は、三千年くんの胸を押すようにして彼から離れた。
「ごめん。ありがと。もうだいじょうぶ」
彼の不安そうな表情が、紅深を見下ろしている。
「結婚とか、突然でちょっとびっくりしちゃって。うん。ちょっと、返事はいまじゃなくてもいいかな。ちゃんと、考えたいからさ」
即座に断られるわけではないとわかったからか、ほっとしたように三千年はうなずいた。
「それで、私、帰るよ。ごめん。たぶん、常務、こんな顔見たら心配すると思うから。三千年くん、悪いけど常務に、お菓子買ってあげてくれないかな」
速水さんと言わなければと思いながら、思わず、常務、と呼んでいた。
わかりました、と、部下みたいに三千年が言った。
彼の腕をすり抜けて、紅深は非常階段を下りた。
「紅深さん。ここ7階ですよ」
「うん。わかってる。大丈夫。また連絡するね。常務……速水さんによろしくね」
はい、とまた不安そうにつぶやいた三千年を残して、紅深は階段を下りた。体裁が悪かったからそのまま降りてきたが、7階から降りるのはやっぱり難儀だった。
外は死ぬほど暑くて、病院まで三千年の車で来たので、しまった、と思ったがとりあえず家路につく。
涙はもう出なかったが、気づいてしまった気持ちの渦に巻き込まれて、眩暈がしそうだった。
どうやって家に戻ったか覚えていない。
バスに乗って帰ったと思うのだが、気づいたらマンションに戻っていた。
ラルフが玄関で待っていて、ドアを開けるとハフハフと笑って尻尾を振った。
「ラルフ」
紅深はラルフに抱き着いた。
「もうわかんないよ。私、なんでこんな気持ちになっちゃうのかなぁ」
ラルフの柔らかいような硬いような毛を一生懸命撫でる。この前シャンプーしたばかりのラルフは、シャンプーと犬のにおいが混じった匂いで安心する。
「あんたが口きけたら、なんていうんだろうね」
そう言って、ようやくラルフを解放した。そろそろ夕方だし、散歩に行かなくちゃ、と思った。
リードを出してくると、散歩の気配を察してラルフがまたハフハフ喜んだ。尻尾の振り方が激しい。
「よし。行こうか」
夕方になってもそんなに涼しくはならなかったし、昼間の暑さでまだアスファルトが熱い。ラルフがやけどしないかなと思ったが、すでに散歩モードのラルフを止めるすべはない。
いつもの散歩コースを、ぼんやり歩いた。
いつも速水と会っていた公園のベンチに座ると、心得たようにラルフも座った。
「ここで、ヨーコと会ったんだよね」
誰もいないので、心置きなくラルフに話しかけた。
「ヨーコいなくて、寂しい?」
バッグから水を出して、手のひらに汲み、ラルフに飲ませた。
手を拭いてバッグに水をしまって顔を上げたとき、公園の入り口に、ゆきちゃんのお母さんの姿が見えた。ヨーコとラルフの娘であるゆきちゃんのお母さん。風間さんだ。
「あらあ、ラルフ」
犬友の飼い主同士はまず、犬の名を呼ぶ。
「ゆきちゃん、こんにちは。風間さんお久しぶりです」
「そうねぇ、久しぶりね。今日は暑かったねぇ」
ですね、と頷いて、立ち上がった。
「ラルフ元気になったみたいね」
「あ、はい。おかげさまで」
「良かったわねぇ、春先ってわんこの体調も変わるのよね。夏は夏で、暑いからバテちゃうんだけど」
そう言って風間さんは、ゆきちゃんの身体を撫でた。
「ゆきちゃん、また赤ちゃん生んだって聞きましたけど」
「そうなの。もうね、ゆきちゃんの子って困らないのよ。すぐ貰い手がついちゃう」
そう言って、風間さんはポケットから携帯を出した。
「これこれ。可愛いでしょう。さすがにそろそろ、ゆきちゃんもお母さん卒業かなって思ってるの」
「そういえば、今日はお散歩ゆきちゃんだけですか」
風間さんの家はブリーダーなので、常に多頭で散歩するのだ。
「うん。今日はバイトさん頼んだから。でもゆきちゃんはちょっと元気なかったから、私が連れてきちゃった。東野さんに会えてよかったわぁ。あ、そうそう。そういえば、速水さん。ヨーコちゃんのとこの。入院なさった、って。聞いた?」
「あ、はい。ゆきちゃん生まれたときにメール交換してたんで、時々メールくるんですよ」
紅深は何気ない感じに言った。
本当は、胸がえぐられるような痛みを感じていた。
「最近お見掛けしないなぁ、って思ってたから、どうしたのかなと思ってたの。いつだったかしら、最後に見たときは、なんかお痩せになっててちょっとびっくりしたのよ。なんで入院したとか、おっしゃってた?」
「いえ……病気でって書いてありましたけど、なんでかは」
ごまかした。
今日、見舞ってきたばかりなのに。
「心配ねぇ。お一人で暮らしてるし、お身内の方誰もいらっしゃらないでしょう。お子さんもいないし。どうするのかしらね、家とか」
「え?」
紅深は驚いた。それはもう、速水が死ぬ、という前提なのだろうか、と思った。
「あ。いえいえ、そういうわけじゃないの。まだお若いから、万が一なにか、なんて、そんなことないと思うのよ。でも退院されてもおひとりであの広い家じゃ、困るんじゃないかと思って」
「はあ」
紅深は、曖昧に答えた。風間さんは悪い人ではないが、思ったことを割とすぐに口にしてしまう人だった。
「あ、そろそろ、行かなきゃ」
紅深は公園の時計を確認するふりをして、ラルフのリードをひいた。
「あ。そうね。じゃあまたね、ラルフ」
ラルフはオン、と言った。
「娘のゆきちゃんの飼い主だってわかるのかしら。いい子ね、ラルフ」
風間さんは上機嫌で反対方向に歩いて行った。
紅深はどうも情緒が不安定で、うつむきがちに散歩コースをたどる。気づくとラルフが、隣を歩いていた。
いつもなら、リードをいっぱいにひっぱるくらい先に行くこともあるのだが、今日はそんなこともない。
「どうした、ラルフ」
ついにラルフが立ち止まったので、外だということも忘れて話しかける。
ラルフは室内飼いだが外で便意を催すこともある。ウンチかなと思ったが、そわそわした様子がない。
ラルフはじっと紅深を見ていた。はっとみると、そこは速水の家の前だった。
立派な門構えだ。門に「速水」と刻印がある。
主のいない家は、玄関の扉がぴっちりと閉ざされ、しんと静まり返っていた。
ラルフの尻尾が、丸く足の間に入っている。
「ラルフ、わかるの?」
速水がいないことや、彼が病気であることや、入院していること、紅深が心配していることを、何もかも知っているような眼をしていた。
「心配、だね」
そう言ってみた。ラルフは、返事をするように、静かに軽く、尻尾を振った。
「でもきっと、大丈夫だよ。戻ってくるよ」
紅深自身が信じていないような言葉を、口にしていた。
ラルフは、門の前にそっと座った。
まるで、速水を待つように。
これまでそんなことを、一度たりともしたことがない。
胸がどきどきしてきた。まさか、と思った。まさかあのまま、速水になにかあったら、と思う。もし今日が速水と会う最後なら、きのこたけのこ戦争が最後の会話になってしまう。
紅深は慌てた。
慌てて、携帯を出した。
「今、ラルフの散歩で家の前に来ています。ラルフが家の前で座っちゃって。こんなこと、いままでしたことなかったのに。今日は急に帰ってしまってすみません。また連絡します」
ものすごい勢いで打ち終わると、パチン、と勢いよく携帯を閉じた。
病院だし、メールを見ることもないかもしれない。
もう行こう、とラルフに言おうとしたとき、携帯がブーンと震えた。
「おう。きのこの山は三千年くんが買ってきてくれたぞ」
返事が来た。
たぶん、文章はこれで終わりではない。さすがに打つスピードはゆっくりなのだ。
「早く打てない。あとででんしメーをします」
でんしメー。あ、電子メールか。
納得して、ラルフを促して家に戻った。
まだ薄明るい6時半ごろ、メールが来た。
今日は来てくれてありがとうございます。
三千年くんは間違えて赤マルジャンプ買ってきたし、エロ本の趣味が 悪いです。
医局のインターンの先生にプレゼントしました。
それはそうと、アシの焼き菓子は看護婦さんに人気です。ありがとう。
たけのこの里もまあ、うまいな。三千年くんは、両方買ってきて、けんかしないでください、と言ったよ。あの子は本当にいい子だよ。
ラルフが家の前で座ってたって話ですが、今日、ヨーコの命日だったんだよ。
なんか感じるのかね、犬は。
ヨーコの墓参りに行けないでいて、気になっていたから、ラルフにお礼を言っておいてください。
可能なら、近いうちヨーコの墓参りにいってやってください。
かみさんの墓が戸塚にあるんだが、ヨーコは一緒に入れなかったから、別の寺なんだ。
よろしくお願いします。
携帯電話のフラップを閉じて、少しぼんやりした。
夕食をどうしようかな、と思った。
春など終わったかのような暑いほどの一日だったが、夕方からは少し涼しい。
紅深は少し開けた窓のそばのソファに座ったまま、動けなかった。ラルフも疲れたのか紅深の足の甲に顎を載せたまま眠っている。
なんだか何も食べる気がしない。独り暮らしというのは、自分が何か行動を起こさなければお腹も満たせない。何か簡単に食べるものがあったかなと思ったが、生憎カップラーメンのひとつも買っていなかった。
速水にもこんな日があったに違いない。彼はどうやってひとりの食事を取っていたのだろう。
ヨーコの命日だったのか。
何にも知らなかったな、と思った。
紅深は速水のことなど何一つ知らない。あんなに親しく付き合ったようで、親戚でもご近所でもない年の離れた男女など、ほぼ全くの他人だ。
紅深は病院の階段での出来事を思い出した。
三千年からは、あれから連絡がない。紅深の反応が彼の想像とは違っていたからかもしれない。急速に親しくなったから、紅深も彼と同じくらいこの恋にのめりこんでいると思い込んでいたのかもしれない。
紅深は再び手に握っていた携帯電話を開いた。
三千年の番号は、まだ、紅深の特別ではなかった。
短縮番号に入っているのは、いまだに入っているのは、紅深が人生で出会った中で、最低最悪の人物だ。
YOU。
優、という名前だった。全く優しくないのに。
この文字列にしたことを、今では深く後悔している。なにしろ英語にはものすごい頻度で出てくる単語だ。この世は「YOU」に溢れている。
優の名前を漢字で登録しなかったのは、紅深が最初から、彼の唯一の彼女ではなかったからだ。そう。最初から。
出会ったのは高校生のころだから10年近く、彼に縛られたことになる。
17歳。バイト先の先輩。相手は大学生。よくあるパターンだ。
最初は松木先輩、と呼んでいた。当時は家にしか電話のない時代だ。ポケベルもピッチも何にもなかった。松木先輩にはその時も彼女がいたけど、片思いでもいいと思っていた。
先輩は東京の大学生で、地元は千葉だった。それなのになぜか大船に住み、大船のハンバーガーショップでバイトをしていた。当時の彼女と同棲していたからなのだが、高校生の自分は、まさかそこにそんな理由があるとは想像もしなかった。彼は誰にでも優しくて、愛嬌があり、器用で、誰からも好かれた。身長もそこそこ高くて、学校もそこそこ良くて、顔もそこそこ良かった。だから当然モテた。
紅深は彼を追いかけて東京に行きたかった。東京のトリマーの専門学校に行こうとしたが、親に反対されて家から通うという条件で短大に進学した。当然、彼の学校に近い学校を選んだ。
紅深が短大に進学したころに彼はアルバイトをやめたが、学校が近かったから時々示し合わせて同じ電車で通うようになった。そのころには彼女と住んでいることは知っていたが、方向が一緒だから一緒に行こうと言ったのは彼だ。学校の近くの安くて美味しいカフェを教えてくれたり、ファミレスでご飯を食べたりするようになった。互いの大学の学園祭にも行ったり来たりした。
そして、当たり前のようにそういう関係になった。
年上の、社会人の彼女がいることを知っていながら、と背徳的な気分に浸りながらも、紅深に心が動いたと思い込んだ。どこか勝者のような気持ちでいたのかもしれない。
就職するときに一人暮らしを始め、横浜の会社に決めたのも、彼が横浜で就職していたからだ。
思えば、彼にとって都合がいいように、というそれだけの理由で、人生のあらゆることを決めていた。
ずっと秘密の関係だった。親にも、当然彼女にも知られないよう、こそこそと付き合った。
それでもいいと思っていたし、必ずしも相手のたったひとりにならなくてもいいと、あのときは思っていた。もちろん欺瞞だったが、それにも気づかないほど、紅深はそんな人生が自分に相応しいのだとすら、思っていた。
速水の会社にいた間、だから紅深はずっと、そんなふうにえげつない恋をしていたのだ。
しかし、本当にえげつないことはその後に訪れた。
ある時、彼が引っ越しをすると言った。
もしかしたら、彼女と結婚するのだろうか、彼女もいい年だろうからな、と、冷めた気持ちで思っていた。どちらにしろ、付き合い方が変わるわけではないし、彼の都合の良い時に彼から連絡をもらうだけの交際が長すぎて、もはやマヒしていたともいえる。
でもどこかでは、自分が彼の「彼女」になることや、もしかしたら結婚しようと言ってくれるのではないかと、夢見た。
実際、彼もほのめかすような発言を繰り返していた。駅に近いマンションを通りがかると、もし結婚したらこんな家に住みたいとか、旅行会社のパンフレットを横目に新婚旅行に行くならこんなところがいいとか、臆面もなくいうことも増えた。寝物語には決まって「ずっと一緒にいようね」と言った。
しかし現実は容赦がなかった。
引っ越し先は千葉だが実家ではない、と彼は言った。そしていくら聞いても引っ越し先の住所を教えてくれない。引っ越しの日すら教えてもらえず、引っ越しをした後になってから連絡をもらった。
いくらなんでもおかしいと、気づくべきだった。
会う頻度はほとんど変わらなかったから、引っ越すまで全く気付かなかった。
彼は別の女と千葉に住んだ。
正直そのことを知ったときは、頭がおかしくなるかと思った。就職してからはずっと一人暮らしをしていたから、会うのはいつも紅深の部屋だった。引っ越しの前後の一か月くらい、帰らなくていいんだと言って家に居候したことがあったが、それが単に、住居の引き渡し期間がズレたことと、一緒に住む女の都合で、ホテルの代わりにされただけと分かったときは、怒りと屈辱と後悔で死にたくなった。臍をかむ、というのはこういうときのための表現なんだなと思った。
事実が判明した時のことを思い出そうとしても、あまりのことにうまく思い出せない。
腹いせもあって彼の後をつけた。横須賀線で東京を突き抜けて千葉に向かい、津田沼で降りて、途中コンビニに寄り、そのコンビニに来た女性と一緒にマンションの一室に入っていくまでを、紅深は見届けた。
早春で、決算期の超絶に忙しい時期だったのを覚えている。
うそうそうそうそうそうそうそうそ
頭の中がう、とそで埋まった状態で家に戻った。身体は寒さのせいだけではなく震えていて、どうやって家にたどり着いたのか覚えていない。
あの時はもうラルフがいた。
そう、ラルフの名前だって、彼がつけた。
保護センターにも一緒に行って、家族になるんだねと笑っていた。
あの頃は本当に8キロぐらい痩せた。みるみるうちにやせ細った。ラルフがいたから生きていた。ラルフの温もりともふもふした毛が紅深のすべての傷を覆い隠した。
このままでいれば、このままなのだ、と思った。
今まで通り、いわゆるセカンドとかセフレとか、そういった状態の二番目でいられる。優とは別れずにいられる。その方がいいんじゃないのかとも思った。
でももう、心も身体も悲鳴を上げていて、限界だった。
相当おかしくなっていたのだろう。ラルフの散歩に行っても心ここにあらずで、ぼんやりベンチに座り、携帯をいじっていた。携帯も、ただ触っていただけだ。優と付き合う間に、友達もだいぶ無くしていた。そのころにはゆきちゃんの飼い主の風間さんとも、速水とも挨拶したり立ち話をしたりしていたのだが、当時のことは全く覚えていない。
とても仕事を続けられなくなって会社を辞め、ときどきハローワークに失業保険の手続きに行くほかは用事もなくなって、日がな一日、ベンチに座るようになった。
ある日、見かけない奥様風の女性が公園に表れた。優と長く同棲した年上の彼女だった。ちゃんと会ってはいないが最後のほうはお互いにお互いの存在を知っていた。
「こんにちは」
と、彼女は言った。
「あ、はあ。こんにちは」
と、紅深も間抜けな返事を返した。
「優くんの、でしょう」
と、彼女は曖昧なんだか率直なんだかわからない言い方で紅深の前に立った。勢いで、紅深も立ち上がった。
「ええ、ああ、まあ」
ぼそぼそと返す。彼女と話す話など何もないと思っていた。
「ちょっと、話してもいいですか」
しかし彼女の方には話があったらしい。紅深は愚かにもベンチを指さして、どうぞ、と言っていた。
彼女はどうしてか、紅深の右側を選んで座った。わざわざ紅深の前の横切ったので、右側を「選んだ」としか言いようがない。
「初めて会う気がしない」
と、彼女は言った。にこやかだった。変な感じだった。紅深は黙っていた。
「優くん、今、千葉にいるって知ってる?」
何を今さら、と思ったが、はあ、と曖昧に答えた。
「女と住んでるの。知ってる?」
「別れたので」
紅深は急いで言った。少し落ち着いてくると、何しに来たのか、と今さら疑問に思った。しかしゲス優のせいで、互いに相手のことに知識があった。どこに住んでいて、どんな仕事をしていて、どんな生活をしているのか、何年もの間に知ることになっていた。おめでたいことに自分だけが相手のことを知っていると思っていたが、当然相手にも話していたことをそのとき知った。
「ああ。そうなんだ」
と、興味がなさそうに、彼女は言った。
「あなたは、別れないのかと思ってた」
「あなたは?」
変な言い方だったので、オウム返しにたずねた。
「優くんはさ、私の家にいるときから、あなただけじゃなかったよ。今一緒に住んでる彼女は、優くんの幼馴染。あの人も、きっとずっと自分とだけつきあってると思ってたのかもね」
余裕の風情で、彼女は肩までの髪を左耳にかけた。
左手で。
ああ、ふうん。と、紅深は納得した。
それで右側を「選んだ」のか。
「もう、どうでもいいです」
紅深は投げやりに言った。
「それだけですか?」
そういうと、彼女は振り向くように、紅深をみた。
初めてしっかり、目と目があった。
思わず言葉を失って、彼女の顔を見つめた。すごく美人ではなかったけど、いいにおいのする人だ。何とも言えない表情だった。傷つけようと思って来たくせに、傷ついているような顔つきだった。
「なんで私がここにいる、ってわかったんですか」
間が持たず、そう問いかけると、彼女はまた前を向いた。小さい子供向けの動物の乗り物を、じっと見た。
「あなたが、犬を飼った、って、優くんがね。前に。写真を見たの。公園の名前、憶えてて」
そういうと、ラルフに視線を向けた。
「私、彼と10年以上暮らしたの。あなただってそうでしょ。なんだったんだろうって思うよね。思ってる。私は思ってる。最低な男、なんていうんだっけ、完ぺきな、だめんず。そうじゃない?」
彼女はひとりで話した。
紅深は相槌すら打たなかった。
彼女と同病相憐れむつもりはなかった。
「もう、いいですか。犬が飽きるので」
紅深は立ち上がった。傷つけに来た女に傷つけられて、深く深く、傷ついていた。
「ねえ」
ベンチに座ったまま、彼女は紅深を見つめた。すぐに立ち去りたいと思っていたのに、彼女の顔を見つめてしまった。彼女は目に涙をためていた。
「あなたと住むと思ったんだけどな」
紅深は刺さった言葉を抜くことができなかった。
そのまま、振り向きもせずに、紅深は逃げるように家に戻った。実際、逃げたのだと思う。
自分でもそう思っていた。一緒に住むのだと思っていた。結婚すると思っていた。あの人より紅深を選んだと思っていた。彼女以外にも誰かいたのは知らなかった。そんなに驚く話ではないのかもしれない。でもさすがに彼女と自分以外にも「共有者」がいたとはにわかに信じられなかった。
しかし、彼と別れたことより、他にも女がいたことより、別の女と暮らしたことより、紅深は、彼女の言葉が、なによりも痛手だった。
なぜ、自分ではだめだったのか。
その根源的な問いが紅深を苦しめた。
当時のことをすっかり思い出してしまい、紅深は再び傷ついた。温かいラルフの顎から足を外して、ソファに丸まって横になった。まだ、傷が疼く。まだ、血を流している。あれから何年も経つのに。三千年と出会ったのに。
もう二度とあんな思いはしたくない。
自分の男を見る目に自信がない。
三千年がもし変貌したら?紅深のせいで変わったら?
紅深が男を駄目にする女なのかもしれない。
速水は最初からまったくそういう対象ではなかったから、気が付いたら自分が思う以上に心を許してしまっていたのだと思う。
速水を思い出し、メールを思い出し、ついに紅深は泣いた。
むせび泣いた。
つづく
※「GOLAZO(ゴラッソ)」サッカー用語。
スペイン語で「最高のゴール」。
