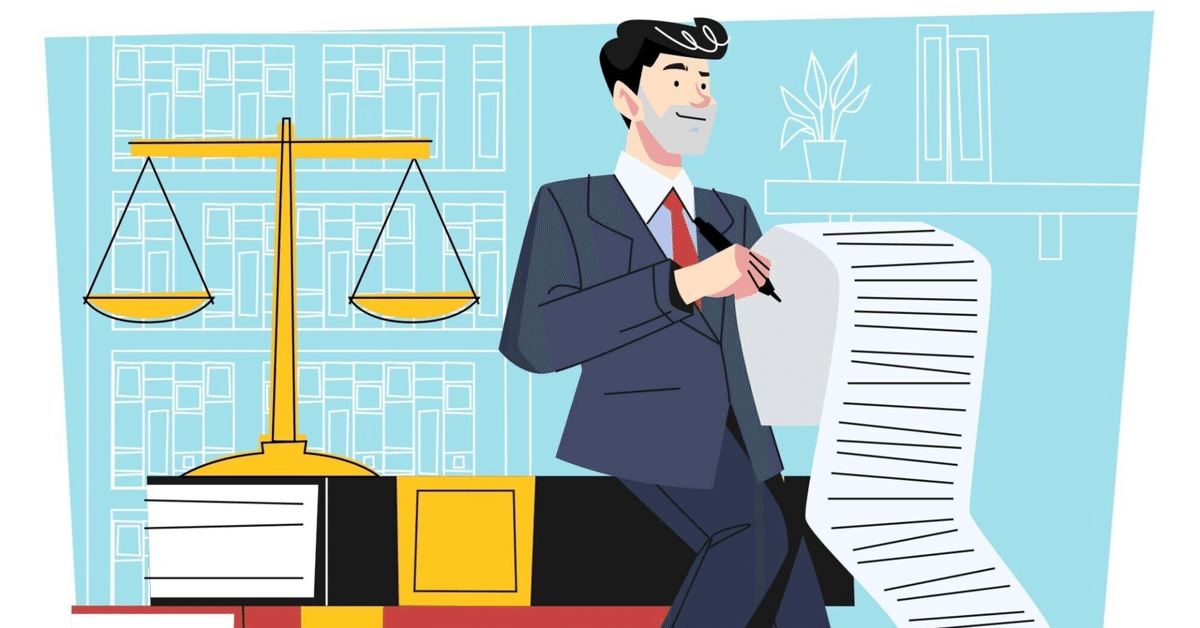
USCPAを取得してはいけない4つの理由
1.筆者の紹介
🌟CURATION ACADEMYとは👇
皆さん、このノートのタイトルを見て、「こいつ何を言っているんだ」と思っているかもしれません。
既にUSCPAを取得してメチャクチャ成功している人、大学生のうちにUSCPAを取得して良い就職先に入ろうと努力している人、会計に全く関係ない仕事をしているけど今後会計方面への転職を見据えて既に予備校を通っている人、いろいろな読者がいるかと思います。
かくいう私も実はUSCPAホルダーで、監査法人にもコンサルにも勤めたことがあり、USCPA取得前と取得後の期待ギャップ、監査法人やコンサル、そして日本の上場企業の経理や日本外からのUSCPAに対する評価等々、様々な場所で色々な評価を聞いてきました。
そこで、USCPAホルダーとして、これからUSCPAを取得しようとしている人や今USCPAを既に取得していて、監査法人、FAS、コンサル、投資銀行などで転職を目指している方々にUSCPAの現実(筆者の戯言?)のご紹介ができればと思います。
本題に入る前に、ポジティブ材料を2点お伝えすることがあるとすれば、1つ目はUSCPAを取得するに越した事はない、そして2つ目は筆者自身USCPAを取得したことについて後悔したことは一度もない、です。
1つ目については、特に深く考えず、USCPAを勉強するのと勉強しないのとでは勉強する方がもちろん良いに決まっています(機会損失は考えない)。
2つ目については、自分の既に持っている能力・スキルとの親和性が高かったため、USCPAを取得することでブースターとして機能したからかもしれません。(他のNoteで今後ご紹介させてください)
上記、ポジティブなお話を踏まえた上で、本題に入りますが、USCPAは過大評価されすぎています(USCPAを全く知らない人から)。そして、USCPA取得後の世界はそんなに甘くありません。
2.USCPAとは
USCPA、USCPAと何度も言っていますが、USCPAとは何なのか。
日本語では、米国公認会計士であり、正式名称はU.S. Certified Public Accountantとなります。
日本で取得しても、独占的な業務ができるわけではないですが、本国であるアメリカで業務を行う場合、個人の会計事務所が開けたり、税務アドバイス等も可能になります。
社会人であれば、仕事をする上で、一度は米国公認会計士(ワシントン州)と記載された名刺を見たことがある方もいるかもしれません。
※日本で取得する場合、ライセンス取得要件が緩いので、基本的には8~9割ワシントン州で登録します。
3.なぜUSCPAが人気なのか
なぜUSCPAがこれほどまでに人気なのか。
少し本題とそれますが、
YouTubeの広告や、どこかのウェブサイトの広告などでも「誰でも1000時間で取れるUSCPA」みたいな謳い文句で塾への入学を誘っているスクールを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
細かいスクールはいくつかあるかもしれませんが、日本における大手スクールは以下の4社になります。それぞれ金額、方針等々違いますが、やはりダントツでアビタスが人気です。
受講料はかなり高いですが、その分丁寧なサポートをしてくれると思います。
アビタス
TAC
CPA会計学院
大原
さて、本題に戻りますが、なぜUSCPAが社会人・学生にとって人気の資格なのか。
一言で言うと、”グローバル人材に必要なスキルを一気に学べるから”ですよね。
会計×英語×IT の文字面のインパクトは大きいです。
ビジネスの真髄である会計という専門分野を、グローバル言語である英語で学び、そして更にはITに関しても勉強できる、といういいとこ取りの資格になっています(正確には、いいとこ取りの資格のように”見える”だけですが)
USCPAを通して、会計と英語が学べるのは当たり前ですが、最近はITの風潮がきていたことから、IT分野からの出題もかなり増やしています。
さらに加えて、名刺にも書けます。
名刺に”米国公認会計士”がつくだけで、会計のプロフェッショナルですということをアピールできます。もちろん履歴書にも書けますね。
ただ、本当に英語で会計を学んで、USCPAを全科目合格する頃には、英語も会計もITもビジネスで使えるレベルになっているのでしょうか。
答えは "否”です。
そんな都合の良い資格ありません。
日本の公認会計士でさえ、監査法人に入って苦労します。
大学で経営学部に入ったからといって、4年学習して、会社に入って、経営のプロとしてパフォームできますでしょうか。
もちろん出来ないですよね。
USCPAについても同じことが言えると多います。
既に厳しいことをたくさん書いていますが、次の章でさらに項目ごとに分解して説明していこうと思います。
4.USCPAを取得してはいけない4つの理由
さて、ここからが本題ですが、USCPAを取得してはいけない4つの理由について、一つずつ解説していきます。
USCPAを取得してはいけない4つの理由と書いてありますが、正確には、USCPAをオススメしない4つの理由になります。
会計専門家からは高く評価されていない
英語なんて伸びない
浅い会計知識しか得られない
投資額が高すぎる
4.1 会計専門家からは高く評価されていない
一つ目は、会計専門家からの評価はそこまで高くない、というか寧ろ何も知らないと思われている、点についてです。
日本における会計専門家の主戦力は日本の公認会計士の先生方です。
日本の会計士は、世界で一番難しい会計士試験であり、私自身も何十年勉強したとして受かる気がしないと思っているほど、もう言葉で表せられないほど難関試験だと思っています。
その先生方が数年、数十年、監査や会計アドバイザリーを通して実務で補強してきた会計知識になんて、当たり前ですけど、USCPAに受かったくらいじゃ及ばないです。
もっというと日本の公認会計士の合格者と比べても、ちょっと足元に届くかなレベルだと思います。会計知識の面から見た場合は、それほど差があるというのを認識する必要があります。
ただ、なぜ、USCPAが重宝される、というかUSCPA取得者を各企業は欲しているのか。
それは、USCPAを取るだけの胆力があるからです(+うっすい会計知識のベース)。
あと、日本の会計士よりリーチしやすいからだと思います。
4.2 英語なんて伸びない
次に英語力です。
USCPAを目指されている方の中には、英語も学べるじゃん、海外の人とも英語で仕事ができるようになって、英語力があるだけで評価される日本では無双できるじゃん、と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
英語なんて伸びないです。
得ることが出来るのは、①会計用語 in Englishと②TOEICのReadingで長文を読むことができる体力の底上げ、くらいじゃないでしょうか。
アメリカの子会社の経理と英語を使って仕事ができるようになるなんて、夢にも思ってはいけません。
USCPAはあくまで会計の資格であり、英語力を向上させる資格ではないからです。もっというと、日本語で会計の勉強をし、英語は英語で個別に勉強したほうが効率良い気も個人的にはしています(時間の効率という面で言うと)。
4.3 浅い会計知識しか得られない
3点目は、あっさい会計知識についてです。
1点目と関連しますが、1点目はどちらかと言うと、USCPAを取得した後の周りからの総合評価について、そして3点目はUSCPAで学ぶことが出来る会計知識という面で記載をしています。
現在USCPAの受験の仕組みが大きく変わり、新試験制度になりますが、旧試験制度では、4つの科目があります。
それぞれ、FAR、AUD、REG、BECであり、以下の試験項目の略称となっています。
FAR=Financial Accounting and Reporting
BEC=Business Environment and Concepts
AUD=Auditing and Attestation
REG=Regulation
財務会計や管理会計、マクロ・ミクロ経済に加えて監査論と税法、これでもかというくらい盛りだくさんな内容を勉強しなくてはなりませんが、USCPA取得後に、実務において、勉強してきた知識がそれぞれどれくらい使えないか説明していきます。
FAR=Financial Accounting and Reporting
FARという科目は4つの中では、一番使える知識が多いかと個人的には思います。
ただそれでもレベルとしては、簿記2級に合格した人と同じレベル。
むしろ、簿記2級の方が、JGAAP(日本における会計基準)を想定していることから”日本における実務”という意味では、USCPAよりキャッチアップしやすいかと思います。
また、USCPAで勉強するFARという科目では、USGAAP(アメリカにおける会計基準)とIFRS(国際会計基準)における会計方針の違いを勉強する必要があります。
それでは、例えばJGAAPに準拠して財務諸表を作っている会社に入った後、IFRSで財務諸表を作っている子会社と連結をしますという時に、どこが論点になるかわかりますでしょうか。主なGAAP調整がどこで行われるのか分かりますでしょうか。
やっぱりわからないんです、実務という文脈においては、何となく用語が分かるレベルで、会計について何も知らない人とスタートラインは大して変わりません(もちろん、成長曲線に若干の差異はあるかとは思いますが)。
BEC=Business Environment and Concepts
続いて、BECですが、4つの科目の中で、一番知的好奇心を掻き立てる科目です。なぜかというと、広くて浅い膨大な経済知識、管理会計知識、そしてIT知識をテキストを通して勉強することが出来るからです。
ただ、やっぱり範囲が広すぎるが故に、暗記ゲームになってしまい、実務で使うことが出来るレベルの理解はできません。
管理会計の指標として有名なEBITDAが何の略で、どうやって計算するかは分かるようになります。ただ、なんでEBITDAが他の指標より優れているのか、なぜマルチプルで多用されるのか、膨大な知識を頭に入れ込まなきゃいけない関係で、本質的な理解をする時間はありません。
また、BECでは原価計算、簿記で言うところの工業簿記、を勉強します。
ただ、ここで勉強するのは、薄っぺらい理論と計算方法。
実務レベルの原価計算は、会計システム、生産システムが大きく関わってくるので、日本の会計士でも手を焼くほどのブラックボックスになりがちな領域です。工場経理を数年やっている方と比べると、知識レベルはやはり雲泥の差になります。
AUD=Auditing and Attestation
AUDは日本語で言うところの監査論です。
監査の手法や、不正リスク、内部統制について勉強します。
この科目は、理論科目であることから、監査法人に絶対入るんだ!と言う人からすると、実務にも直結する科目になるかと思います。
ただ、それ以外の人からすると、全くもっていらない知識になります。
もちろん、内部統制の理解は、一般的に仕事を行う上で、非常に重要です。不正なんて誰もやってはいけないですから。
とは言うものの、ここで学んだ内部統制の理解を持って、実務の内部統制に当たれるかと言うとそうではありません。
個人的には、内部統制は生き物だと思っていて、ある程度型はあるものの、会社の文化、事業形態、事業内容によって千差万別の内部統制の手法があると思っています。そのため、監査法人に入って内部統制監査をしない限りにおいては、結局浅い知識を持ったまま、転職先または就職先で仕事をすることになり、AUDで得た内部統制知識も少しずつフェードアウトしていきます。
REG=Regulation
最後に、米国税法です。アメリカで税務申告する人以外は、全くもって参考にならない知識となり、かつ暗記ゲームの科目です。
筆者自身、監査法人でも就労経験がありますが、USCPAの4つの資格の中で、唯一何の役にも立たなかった科目です。
書くことがなさすぎて、非常にあっさりとしたコメントとなってしまいました。
4.4 投資額が高すぎる
そして、最後に、USCPAを取得する上での投資額が高すぎて、人によっては、費用対効果が合わないということです。
やはり、皆さん、USCPAの響きと、会計・英語への憧れが強すぎて、費用対効果について考えていない人が多い気がします。
もっというと、将来のゴールを考えた上で、必ずしもUSCPAが必要なのか、ということは今一度考える必要があるかと思います。
USCPAのスクールにフルパッケージで通うと30~80万+受験料10万×4科目となり、諸々含めるとやはり少なくとも100万円はトータルでかかってしまう資格です。
筆者自身も100万円以上かけて取得しました。
そんな大金をかけて取得する必要はあるのか、についてはもちろん皆さんの考え方次第ですが、日本の会計士や簿記の資格と比べると、昨今の円安の影響もモロに受け、かなり金額の大きい自己投資の部類には入ってくると思います。
また、費用対効果という話で言うと、USCPAを取得した後に、BIG4の監査法人やFASに入って、給料がめちゃくちゃ上がるから、一年ですぐ回収できると思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、現在転職・就職しようとしている会社に入るためには、必ずしもUSPCAは必要でしょうか。書類要件にUSCPAが必要条件に入っているのでしょうか。
筆者の知る限り、USCPAが必要条件になっているところは、監査法人(監査に限る)とFAS(Financial Due Dilligence)部門のみかと思います。それでも、トレーニー制度などを用いて資格勉強途中の人でも入れます。
逆に言うと、これらの部門以外では、必ずしもUSCPAを取得する必要はないと言えます。(もちろん、持っていた方がプラスに働く”可能性”はありますが、USCPAに投下する時間・お金・労力を使って、他の資格取得や他の経験を積み、アピーリングな履歴書を作ることはできると思います)
5.最後に
これでもかというくらい、USCPAのネガティブキャンペーンを行いました。USCPAスクールも、資格取得者もUSCPAのメリットしか伝えていない人が多すぎるからです。
これはUSCPAに限った話ではないですが、何を行うにしても、期待ギャップというのは必ず存在します。せっかくUSCPAを目指すのであれば、なるべく期待ギャップを小さくした上で、USCPA取得後の将来を考えてほしいというのが筆者からのメッセージになります。
今後も少しずつ、監査法人でのUSCPA裏話やコンサル内でのUSCPA裏話、そしてUSCPAのメリット(今回のネガティブキャンペーンを上回るメリットを頑張って書きます)、USCPAホルダーがキャッチアップしなければいけない領域等々、小出しにNoteにまとめていこうと思います。
※こちらのNoteでは、USCPAの4科目について、高得点で合格した筆者によるまとめノートを掲載しております。
もし、USCPAの勉強が大変で毎日嘆いている方や、NASBAへのお布施が止まらない方がいらっしゃったら是非覗いてみてください!
🌟CURATION ACADEMYとは👇
最後まで読んでいただきありがとうございます。 就活・転職・留学サポート活動を応援していただける方、よろしければサポートをお願いいたします。 いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
