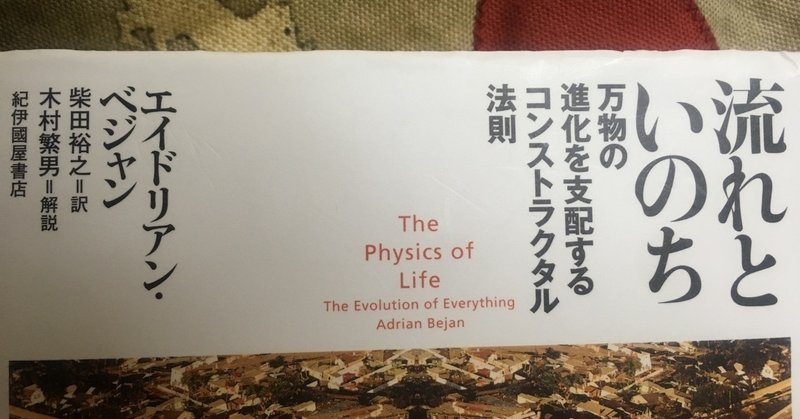
流れといのち 万物の進化を支配するコンストラクタル法則/エイドリアン・ベジャン
とてつもなく示唆に富んだ本だ。
これを読まずして何を読む? そう言ってよい一冊だと思う。
進化とは、単なる生物学的進化よりもはるかに幅の広い概念だ。それは物理の概念なのだ。
と著者で、ルーマニア出身のデューク大学の物理学教授であるエイドリアン・ベジャンは書いている。
この本でベジャンは物理学視点によって生物の進化と、河川などの無機物の変化、さらには人間によるテクノロジーの進歩の流れを、統合的に予測可能なものにしている。
本書は、生命とは何かという問いの根源を探求しようという私の試みであり、そのために、動くもの、動きながら自由に変化するものすべての最も深い衝動や特性を吟味する。
とベジャンがその目的を記した、この『流れといのち 万物の進化を支配するコンストラクタル法則』は、あらゆる変化が時間の経過そのものだということを示している。ベジャンの、生命とは何か? 問うべき対象である生命そのものを従来とは別の領域にまで広げているように思う。
最近の僕の「変化とは?」という問題意識ともびったり合っていたし、おそらく、この見方がいま最も新しい物事の見方の傾向なのだと思う。それは物事をスタティックに見るのではなく、ダイナミックなものとして見ることだ。
そういう観点においても、これから多くのことを考えるにあたって参照できそうな一冊だ。
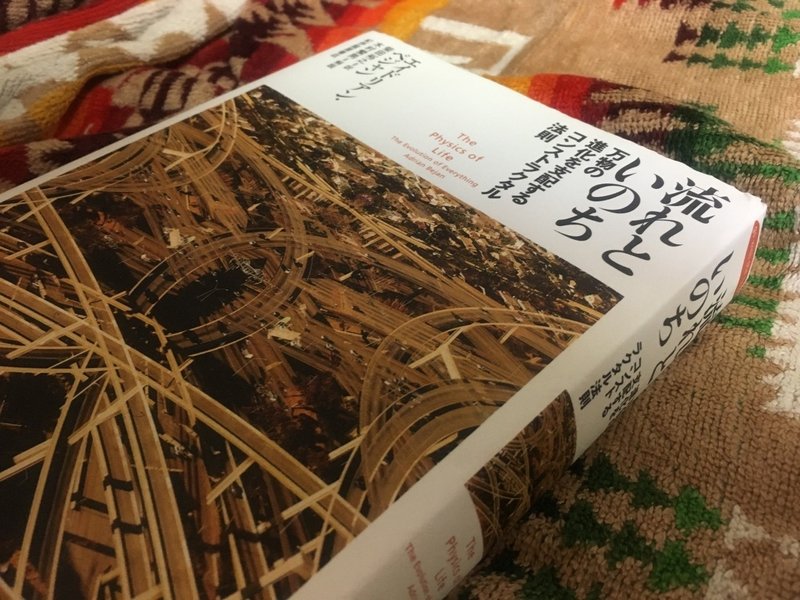
動的なものの科学
「科学の地殻変動が起こりつつある」とベジャンはいう。
「たとえば、社会構成に関する科学的論説が、静的なもの(構造、結びつき、接続ポイント)から動的なもの(動き、交流、流れ、進化)へと変化している」のだという。
動的であることで科学は、従来のような記述的、説明的なものではなくなる。特に、生物進化は、過去の進化を扱うことからも記述的かつ説明的なものであった。
しかし、ベジャンが本書で提示するコンストラクタル法則による生物進化は、記述的なものでなく、予測的なものだ。
それは動きを、変化を予測する。
進化の物理法則は事象を予測するものであり、記述するものではない。これがコンストラクタル法則と、自然界の進化に関する他の見方との大きな違いだ。
本書中、ベジャンは何度も、あらゆるものに関して「それは予測可能である」と述べる。
河川流域の変化、貨物車両や動物の大きさの変化、短距離走者や野球のピッチャーの身体の大きさの変化。それらは物理学的に予測可能だとベジャンはいう。
物理の原理はスポーツの進化と、進化の未来全般を予測する。私を指導したコーチの1人がよく言っていたとおり、「トレーニングにはかなわない」。彼は、常軌を逸するほど練習するべきだと言っていたわけではない。断じて違う。彼は、いったん身につけた技能は(良いものも悪いものも)決して捨て去ることができないと言いたかったのだ。この原理は、音楽から数学まで、あらゆる技能に当てはまる。
トレーニングを通じて身につけた技能、決して捨て去ることのできない、その技能は、ようするに、デザイン変更=流動構成の変化である。
トレーニングを通じて、元の形が変わってしまったのだから、少なくとも、そう簡単には元には戻らない。さらに言えば、その変化はより良い状態にする変化のはずだから、戻す必要もない。
技能の習得というものを、そのような意味で物理学的なデザイン変更と見るのがベジャンのコンストラクタル法則の見方だ。デザイン変更、変化することが生命を含めた、生きるもの、この世に存続し続けるものの特性である。
むしろ、どんなものにでも一定の形のようなものを想定してしまう従来の見方がおかしかったのだ。あらゆるものが変化し続けている。
コンストラクタル法則は生命を、生物界と無生物界の両方の領域で自由に進化する動きと定義している。
コンストラクタル法則
あらゆるものは流れを良くする方向に変化する。
河川の流れ、お金の流れ、情報の流れ、都市の中の車の流れ、それらを最適なものにしようと、デザイン変更が行われる。生物の進化も同じで、動物はみずからの生涯移動距離を増やそうと身体を大きくする方向に変化するし、さまざまな機械の構成もより効率よく仕事量を増やす方向に進化する。
流動系は、時の流れの中で存続する(生きる)ためには、その系の流れへのより良いアクセスを提供するように自由に進化しなくてはならない
ベジャンはコンストラクタル法則について、こう記述する。
「流れを促進し、動きへのより良いアクセスを提供するような、自由に変化する流れの配置とリズムは生きている」のだとベジャンはいう。重要なのは流れ」だ。すべての物事は放っておいたら流れないし、動かない。「動きが止まると生命は終わる」。
動くためには動力となるエンジン、エネルギーがいる。そして、動くもの、流れるものに対しては必ず障害物が存在する。川の流れをはばむ大きな岩、泳ぐもの、走るもの、飛ぶものに流れとは逆の力を課す摩擦抵抗。
動くもの、流れるものはそれらの障害に争い、より自由に流れ、動けるようなデザイン変更を行う。川は流れを変えたり、動物はみずからの形状を進化によって変化させ、より泳ぎやすい、走りやすい、飛びやすい形状を見つける。飛ぶ鳥と飛行機の形状の変化には相関関係がある。
そして「変化し、より良いアクセスを見つける自由を動きが持たないときには、生命は終わる」。
生きるべきか死ぬべきか―― それは問題ですらない。生命は自然界における普遍的傾向だからだ。生命は自由を伴う物理的な動きだ。動くもの、流れるもの、突き進むものはすべて、配置や道筋やリズムを変えることによって、しだいに動きやすくなる傾向と、動き続ける傾向を示す。進化するこの流動構成とその終焉(死)こそが自然であり、生物・無生物の2領域を網羅する。
予測可能であることで
動物のデザインは予測してできる。ベジャンはそう言っている。
動物の器官は2つのデザインの特徴を持っているという。1つは「動く体全体として配置されている流動構造」で、もう1つが「器官の大きさと体全体の大きさとのあいだに予測可能なかたちで存在するスケーリング関係」だ。
これに基づいて、それぞれの部分の相対的な大きさが分かれば、動物の姿は描くことは可能である。それが従来のような単なる経験値からではなく、動きの効率化という側面から理論化されたコンストラクタル法則によって可能になるのだ。
コンストラクタル法則によれば、他の条件が同じであれば、短距離走の選手は背が高いほど有利である。
物理の観点に立つと、走行は前へ転がる人間車輪の2本のスポークによって地面の上方に維持されている重力の前方傾倒運動と言える。前方により速く傾倒する必要があるからこそ、人は自然に(本能的に)両腕を持ち上げて、脚のストライドに同調させて交互にやって前へと降り出す。そうすることで、一歩一歩の動きのあいだに、垂直の(重力による)落下によって生み出される前進よりも遠くまで体の重心が前に進む。
前方に速く倒れることが速く走ることにとって物理的に有利だからこそ、重心がより高い位置にある選手の方が速く走れる。これは紛れもなく物理だ。
そして、この人間の前方への動きが、物理的な前方傾倒によるものだと分かると、都市における被害時の避難経路の設計の際の人間の密集度が非常に重要なファクターであることにも気づくことになる。
というのも「密度の低い群衆の平均速度はおよそ秒速1.3m メートルだが、平均距離が0.5メートル以下になると、群衆は止まってしまう」からだ。「0.5メートルという重要な間隔」が問題になることこそ、「歩行は繰り返し前に倒れる体の動きである」ことを証明するものでもある。
この動きでは倒れかかる体の垂直方向の姿勢を立て直すためには、前に足を踏み出すことが欠かせない。人間にとって、前への一歩は平均するとほぼ0.5メートルになる。この間隔が得られないと、たとえ体どうしが触れていなくても、前へ足を踏み出すことが不可能になり、群衆は止まってしまう。
そう。これは物理法則のなかにあって予測可能な事柄なのだ。
被害時の避難経路の「流れを良くする」ことで「生命が終わる」ことがないようにするには、人の密集が0.5メートル以上を保てるようにすることが要件になる。
予測可能であるからこそ、そうした事前のデザインは可能だ。
ホロビオントをつくる物理法則
とはいえ、世界はもちろん、それほど単純ではない。複雑なファクターが入り混じるかこそ、予測には引き続きむずかしさは残る。
今日地球は、少数の大きな動物と多数の小さな動物が織り成す網で覆われている。新しいものは数が少なく、大きい。古いものは数が多く、小さい。新しいものは、古いものに取って代わりはしない。古いものに加わるのだ。これが、いたるところで歴然としている「複雑性」の織物だ。
ただ、この複雑な織物と化した新旧入り混じった構成も、ただバラバラに存在しているわけでもない。それぞれにとって良い流れになるよう、協力が必要なら多様性をもった新旧さまざまなものが共生の道を選ぶ。
ベジャンが示すカラハリ砂漠での例などはその典型だろう。
そこは乾燥した平たい地表で、およそ50メートルごとにシロアリの塚がある。そして、砂漠で成長する数少ない木(棘のある低木)は、ほぼ確実にそうした塚に3、4本ずつ生えている。これは「養樹システム」として知られる。塚はシロアリとともに生きており、地中に作られたシロアリの巣はあらゆる方向に(木の根のように)塚の裾の外側にまで拡がっている。ツチブタが来て塚を掘り返してシロアリを食べ、シロアリは再び巣を作る。この三者(アリ、木、ツチブタ)が共生しているのは、塚の構造ゆえに繁栄する第4の「動物」、すなわち自然界の水の循環が存在するからだ。この第4の「動物」が最も大きい。
水の流れを中心として、アリ、木、土が見事なエコシステムを成す。それら3者のおかげで水もその乾いた地での最適な流れを得る。3者がいなければ、水も枯れ果ててしまうかもしれない。水を欲するものと水そのものが共生関係をつくる。環境のデザインだ。
地中深くにまで掘られたシロアリの巣には、無数の通路があり、下の地下水の水分が染みこむ。塚は周囲よりも湿っていて、アリと木とツチブタは繁栄し、水の流れも良くなる。ようするにこれは、少なくとも4者共生と呼んでいい。
環境に影響を与えない生命は生命とは言えない
前に、進化生物学者のリン・マーギュリスが唱えたホロビオントという概念を紹介した。複数の生物が1つの複合的に生命体として生きるという考えだ。このホロビオントを、生物ではない水も含めて作り上げているのが、このカラハリ砂漠での4者共生の例だろう。
従来の進化論では生物は環境に適応するよう進化すると考えられていたが、この例をみると生物が環境に適応するだけでなく、環境のほうも生物に適応するようデザインを変えるということが分かる。
物理学の全体像の中では、少数の大きなものと多数の小さなものがいっしょに流れ、協働し、ともに進化する。少数の大きなものは多数の小さなものを排除しないし、排除できない。そのバランスのとれた多様なスケールのデザインは、ますます良くなって、流動系全体が改良される。
流動系全体の流れを良くするという観点は、この持続可能性が問われる現在の社会環境においてはとてつもなく重要なことだろう。
「環境に影響を与えない生命は生命とは言えない」とベジャンは書いているが、であればこそ、この影響をちゃんと予測して活動することが必要だ。
環境に影響を与えるというのは、流動構成や進化と同義だ。流れるというのはすなわち、周辺にあるものを排除することを意味する。自然界のどこを探しても、そこを通過しようとする流れや動きに抵抗しない部分はない。動きとは浸透であり、この現象の名前は、それがどちら側から観察されるかによって異なる。河川流域を観察する側にしてみれば、動きという現象は樹枝状の脈管構造の出現と進化をいう。地表を観察する側にとっては、浸蝕であり、環境への影響であり、地球の表面の形を変えることだ。
影響を与えることは必須だとすれば、あとは、流れる側と流れにとっての環境となる側、双方の影響をちゃんと予測して動けるようになることこそが必要なのだろう。
その際、流れや動きというものに着目する視点をちゃんと身につけておくことは、これからの時代を生きるための必須条件であると思われる。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
