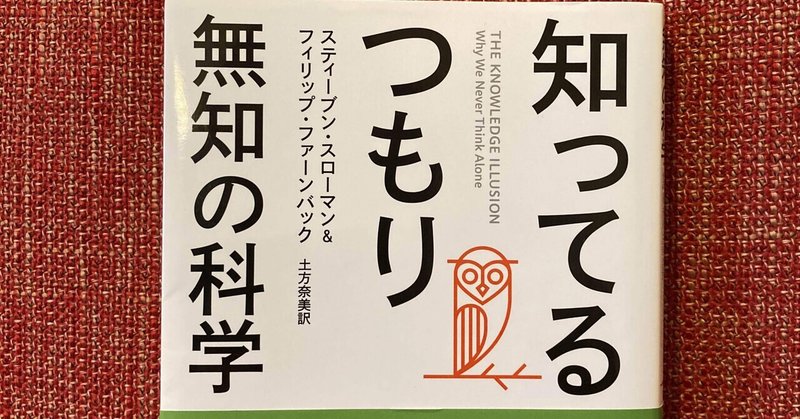
【知ってるつもり 無知の科学】真の知能は集団に宿る
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆☆
〜僕のモヤモヤを言葉にしてくれた〜
面白かった。
なぜなら、本の内容が兼ねてから僕が世の中の人々に対して思っていた事だったからだ。
「自分も含めて、個人が出来ること(知っていること)なんてたかが知れているのに、なんでこんなに自信満々に『何でもわかっている』『何でも出来る』ような態度を取れる人が多いのだろうか?」
僕は極端に自分の知識に自信が無い人間である。
慎重に考えすぎて決断が遅くなる事も多々あるし、考えをまとめないと意見が言えないので瞬時に発言を求められるような議論も苦手だし、周りの人の助けが無ければ一人で何かを成し遂げる事も出来ないと思っている。
しかしながら、世の中にはあまりにも浅薄な知識でもって、行動し状況を悪化させる人や発言して他人を攻撃し傷つける人が多いように思う。
「人は無知である」というのは僕の中では自明の事であり、「錯覚した自信」を持った人々に対して嫌悪感を持っていた。
この本のタイトルを見た時に、そんな僕の思いを代弁してくれそうな本だと感じた。
結論、僕が感じていた世の中の人々に対するモヤモヤとした疑問を見事に言葉にしてくれたと思う。
〜無知、錯覚〜
本書では、まず「人は思っている以上に無知である」という事実を明らかにする。
例えば、身の回りに当たり前にあるトイレやファスナーの仕組みについて多くの人がその仕組みを理解していると思っているが、詳しく説明して欲しいと言われた時に、ほとんどの人はその仕組みを理解していない事に気づくのである。
人は、専門的な学問でなくとも、身近にある単純なものに対してすらその仕組みや知識を理解していないのだ。
そして、「人は自分が無知だという事に気づいていない」と著者は語る。「無知の知」とも言えるだろうか。ほとんどの人は、実際よりも自分は多くの事を知っていて理解していると錯覚しているのだ。
自分は多くの事を知っている、という錯覚は実際の行動や意思決定にも大きく影響を及ぼす。
本書の中で印象的だったのが次の実験だ。
ある政策(例えば、新しい医療保険制度)について、被験者に7段階で評価をしてもらった(強く賛成なら7、強く反対なら1、中立なら4)。そして、評価した後にその政策の内容や仕組みについて説明をしてもらう(なぜ、賛成か反対かという理由ではなく、あくまで政策の内容についての説明)。その説明をした後、再度その政策を同じ7段階で評価をしてもらった。
この実験の評価のポイントは、被験者たちの賛成か反対かの判断ではなく、意思決定の強さにある。強い意思決定か(1または7)、弱い意思決定か(中立の4)を評価する。
結果は、説明前と比べて説明後では被験者たちの意思決定の強さが弱くなった(中立寄りになった)。被験者たちは、自分がその政策についてよく理解していないと気づくことで自分の意思決定に慎重になったのである(自分の判断に自信が持てなくなった、とも言える)。
この結果から見えてくることは、ある事象についての判断や意思決定は、その事象についてよく理解していない時または自分が理解していない事を自覚していない時ほど皮相的な知識を基に強く反応してしまう、という事だ。
これは、僕が普段から嫌悪感を持っていた「考えてる風の人たち」の話に当てはまった。
多くの事には多かれ少なかれメリット・デメリットがあり、単純な是非だけでは解決しない。世の中は0か100ではないのだ。状況に応じて40や60の判断をしなければいけない時は往々にしてある。しかし、ある政策や最新技術などに対しての是非を問われた時に、強く賛成または反対をしている人たちは0か100かしかないと思っている。どちらかの意見を持っていれば、対して考えていなくてもそれについてよく理解していると装う事が出来る。そんな人たちを僕は「考えてる風の人たち」と日常的に揶揄していた。
あまりに極端な意見しか言えない人は、わかっている風を装っている人たちなのだ、というのがこの実験で僕の中では確信に変わったのだった。
〜知能は集団に宿る〜
さて、ここまで読んでいただいて僕個人としてはかなりネガティブな感情で読み進めてきた事は伝わっていると思う。
しかし、著者は「人は無知である」「人は自分が無知である事に気づいていない」という問題提起をした上で、世の中に対して希望となる提言をしている。
まず、知能は個人ではなく集団に備わっている、という事だ。
企業などの組織は決して個々の能力が成功に起因しているわけではない。IQの高い人が組織に投入されたからといって、その組織やチームが上手くいった、というようなデータはあまり無い。本書でしつこく述べられているように個人の能力には限界がある。極端に言えば何でも出来る個人など存在しないのだ。
個人によって得意分野が違う。重要なのは「自分は何を知っていて何を知らないか」を知り、知らない事を他の得意な個人の知識から補い合う事だ。そうして、何でも出来るチームは作ることは出来るかもしれない。
科学者の世界でも、新しい発見や革新的な発明はある天才的な個人の功績では無い。数人の別分野の科学者が知識を寄せ集めて一つの偉大な功績を挙げる、というのが現代では常識となっている。
個人の知能を測るIQのような、チームの知能を測る数字的な指標はまだ存在しないそうだが、社会として考える価値はありそうだ(ここらの話は以前読んだ「『みんなの意見』は案外正しい」にも通じるところがある)。
そして、もう一つ、僕のネガティブな感情を打ち砕いてくれたのは「無知」や「錯覚」は決して悲観的な事ばかりではない、ということ。
むしろ、「無知」であるが故に専門家が思いつかないようなアイデアを思いついたり、「錯覚」するが故に誰もが不可能だと思っている事に挑戦する人が現れるのだ。
人類全体を一つの集団としてみた場合、こういった人々の存在は人類の進歩に大きく寄与するのだ。
僕は「無知の知」を知らない人や「錯覚」している人に対して嫌悪感を抱いていたが、この本を読んでその部分は理解し直せたように思える。
「無知」や「錯覚」を嫌悪するのではなく、理解して上手く活用して付き合っていく事が、無知な僕個人が世の中に対して出来る事なのだろう。
というわけで、この本を理解しているつもりになって書評を書いてみた。
ここまで、読んでいただいてありがとうございます笑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
