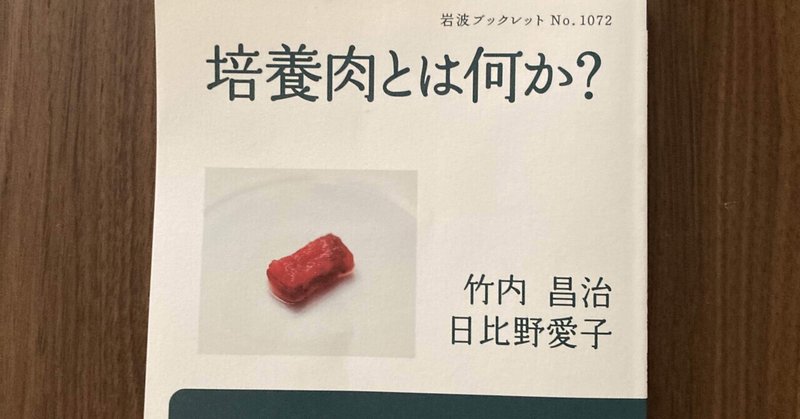
【培養肉とは何か?】最先端技術の課題とは?
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆
〜肉の未来〜
世界の人口がどんどん増えていき、数十年後の食糧不足の危機が叫ばれる一方で、畜産が地球環境に及ぼす影響も指摘されており、板挟みの状態となっている"肉"の存在。
そんな肉に関する諸問題を解決するために、大豆からとれる植物性タンパク質を利用した肉のようなものを生成したり、昆虫を肉のように加工したもの、などの代替肉を作り出す研究は世界各地で実施されている(カップヌードルの「謎肉」も肉と大豆を組み合わせて作ったハイブリッド肉であり、この代替肉のひとつである)。
世界では既に代替肉が市場で売られているという国もあるそうで、代替肉は経済的にも環境的にも社会的にも、最先端かつ期待の大きい研究分野のひとつとなっている。
本書で書かれる「培養肉」は代替肉の一種である(というより、世界的には正式な名称決定や区分分けなどはなされていないそうなのだが…)。
この培養肉が食卓に並ぶようになるための課題を、技術的、社会的、倫理的な面から解説してくれるのが本書である。
〜培養肉とは何か?〜
日本でも、本書の著者である東京大学教授の竹内氏と日清食品HDが連携して、代替肉たの研究を進めており、2022年には日本で初めて試食が行われたそうだ。
竹内氏の研究する培養肉は、植物性タンパク質を混ぜたりして「肉らしいもの」を作るのではなく、「本物の肉」を作ることを目指している。「本物の」とはどう定義するかはさておき、竹内氏が培養肉を作る方法は、生きている牛から少量の肉の細胞を摂取し、体外でも細胞分裂出来る土台を作り、肉を形成する、というものであり、なるほど、いわゆる混ぜ物ではなく、本物の肉から本物の肉を作り上げる試みである。肉のコピーを作り出すイメージだ。
なるほど、これが実現すれば、畜産による環境負荷や屠殺の問題を攻略しつつ、僕らの食卓に肉を並べることも可能になる。
実現すればあらゆる問題を解決する技術であり、そんな夢のような研究が日本で行われていることに僕は感動した。読めば読むほど僕はこの培養肉に期待してしまう。
〜社会的・倫理的課題とは?〜
さて、そんな夢のような技術なのだが、世の中に広まるためには、技術的な問題だけでなく社会的・倫理的な課題も多い。
まず、「培養肉」というものを人々が食べてみたいと思うのか、という点だ。
僕はぜひとも食べてみたいのだが、ある人にとっては「培養肉」というものが「不自然なもの」と感じて受け付けないということがあるだろう。そもそも、まだ日本においては「培養肉」に対する認知度が低く、存在すら知らない人は多い(僕も本書を手にするまで知らなかった)。その存在が多くの人に知られた時に、どれだけの人が「培養肉」を食することを受け入れるのか、それはまだ未知なのである。
もう一つは倫理的な課題である。
生きてる牛から肉のコピーを作るのだから、僕個人としては何の問題もないだろうと感じるのだが、本物の肉を作ることは生命科学の範疇にも食い込んできて、これを応用したクローン技術などに批判が出てくることが考えられる。また、培養肉を大量に生成した場合の環境負荷も今のところ未知数だ。
これらの課題はまだ世の中に表面化していない。培養肉の存在を多くの人が知った時にどのような問題が出てくるかを、先回りして考えておき対策を練らなければいけないのだ。
この培養肉に限らず、新しい科学や技術は、世の中にインパクトを起こし、人々に不安を与えることが常である。そして、それらの声に対して説得を繰り返さなければ、世の中に浸透しない。
技術の進歩だけでなく、こうした世の中の動きにも気を使わなければいけない研究者、科学者の人たちにエールを送りたい。
個人的には、この培養肉の研究を応援したい。
世の中のあらゆる諸問題を解決出来る期待に溢れているからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
