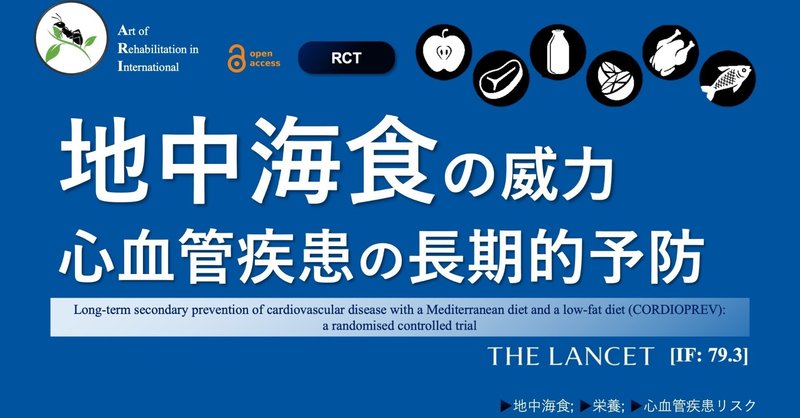
地中海食の威力。心血管疾患の長期的予防
📖 文献情報 と 抄録和訳
地中海食と低脂肪食による心血管疾患の長期的二次予防(CORDIOPREV):無作為化比較試験
📕Delgado-Lista, Javier, et al. "Long-term secondary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet and a low-fat diet (CORDIOPREV): a randomised controlled trial." The Lancet 399.10338 (2022): 1876-1885. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00122-2
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers
※ Connected Papersとは? >>> note.
✅ 地中海食とは何か?
・地中海食とは、イタリア、ギリシャ、スペインなどの地中海沿岸の国々の人が食べている伝統的な料理のことで、以下のような共通の特性がある
・地中海食の特性
①果物や野菜を豊富に使用する
②乳製品や肉よりも魚を多く使う
③オリーブオイル、ナッツ、豆類、全粒粉など未精製の穀物をよく使う
④食事と一緒に適量の赤ワインを飲む

[背景・目的] 地中海食と低脂肪食は、心血管疾患の一次予防に有効である。我々は、心血管疾患の二次予防におけるこれら2つの食事の効果を比較するために、長期無作為化試験を実施した。
[方法] CORDIOPREV試験は、スペインのコルドバにあるReina Sofia大学病院で行われた単施設の無作為臨床試験である。冠動脈疾患が確立している患者(20~75歳)を、アンダルシア公衆衛生学校が1:1の割合で、地中海食または低脂肪食の介入を受けるようにランダムに割り当て、7年間のフォローアップを実施した。治験責任医師(医師、治験担当医師、臨床エンドポイント委員会委員)は治療割り付けをマスクされていたが、参加者はマスクされていなかった。栄養士のチームが食事介入を行った。主要アウトカム(intention to treatで評価)は、心筋梗塞、再灌流、虚血性脳卒中、末梢動脈疾患、心血管死などの主要な心血管イベントの複合であった。本試験はClinicalTrials.gov(NCT00924937)に登録されている。
[結果] 2009年10月1日から2012年2月28日までに、低脂肪食群500人(49.9%)、地中海食群502人(50.1%)の計1002人の患者が登録された。平均年齢は59-5歳(SD 8.7)、1002例中827例(82.5%)が男性であった。
■ 各郡の心血管疾患発症とハザード比
・主要エンドポイントは198名で発生し、地中海食群87名、低脂肪群111名であった(1000人年当たりの粗率:地中海食群28.1[95%CI 27.9-28.3]対低脂肪群37.7[37.5-37.9]、log-rank p=0.039)。
・異なるモデルの多変量調整ハザード比(HR)は、0.719(95%CI 0.541-0.957)から0.753(0.568-0.998)となり、地中海食が有利であった。
・女性175人よりも、地中海食群の男性414人中67人(16.2%)に対して低脂肪食群の男性413人中94人(22.8%)(多重調整HR 0.669 [95% CI 0.489-0.915], log-rank p=0.013 )にみられた。
[結論] 二次予防において、地中海食は低脂肪食よりも主要な心血管イベントの予防に優れていた。我々の結果は臨床に関連し,二次予防における地中海食の使用を支持するものである。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
この論文の注目度がやばい。
Nature Medicine (IF: 53.4)が選ぶ「2023年の医療を形作る11の臨床試験」に選出(📕Arnold, 2022 >>> doi.)。
2023年1月24日現在、出版から1年未満にも関わらず被引用数50程度。
さすが、世界4大医学雑誌『THE LANCET』。
結論としてはシンプルで、「心血管疾患リスク低減のためには、単なる低脂肪ではなく、バランスの取れた食事が大事だよね」ということ。
『ライフ・エッセンシャル8』という心臓血管の健康についてのアメリカ心臓協会の推奨事項の1つにも食事療法が入っている。
それほどに、心血管疾患予防に食事は重要なものなのかもしれない。
『リービッヒの最小律』という考え方と『ドベネックの桶』という比喩がある。
✅ リービッヒの最小律とドベネックの桶
■ リービッヒの最小律
- 植物の生長速度や収量は、必要とされる栄養素のうち、与えられた量のもっとも少ないものにのみ影響されるとする説。
- ドイツの化学者・ユーストゥス・フォン・リービッヒが提唱した。
- 一般に、バランスの悪さや一点豪華主義への皮肉・警告として、リービッヒの最小律を引き合いに出す場合がある。
■ ドベネックの桶
- リービッヒの最小律を分かりやすく説明するものとして、ドベネックの桶が知られている。
- 植物の成長を桶の中に張られる水に見立て、桶を作っている板を養分・要因と見立てる。
- これならば、たとえ一枚の板のみがどれだけ長くとも、一番短い部分から水は溢れ出し、結局水嵩は一番短い板の高さまでとなる。

人間の栄養バランスと健康の考え方は、これに近いのかもしれない。
「ドベネックの桶」よろしく、バランスが取れた状態で良い方向に向かっていく必要がある。
単にカロリーや脂肪を減らすということでは、栄養バランスは保たれない。
過剰にならない量を、バランスの取れた内容で口に運ぶこと。
歳をとっても伸びていくのはバランス感覚だと思う
羽生善治
⬇︎ 関連 note✨
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
