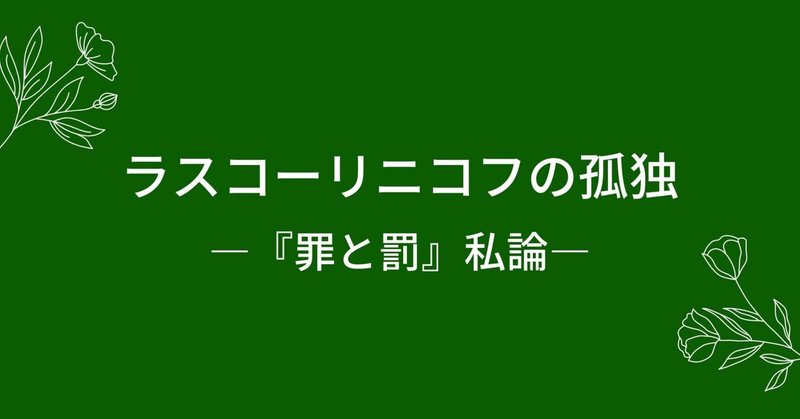
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(10)
目次
問題の所在
様々な解釈
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
前回までの要約
ラスコーリニコフの「無限の孤独と疎外の感覚」の正体は、自ら神との絆を断ち切った結果として、必然的に世界の誰ともつながることができなくなったことを、直観的に、皮膚感覚として突きつけられたものであった。
この「仮説」を裏付ける証拠として、筆者は次の5点を挙げた。
・「ラスコーリニコフ」という姓から読みとれる暗示
・ラスコーリニコフが老婆の死体の上に投げすてた十字架と聖像の暗示
・ラスコーリニコフのファーストネーム「ロジオン」の命名の由来となった可能性があるシラーの詩句
・ラスコーリニコフの孤独を見抜いたソーニャの直観
・ラスコーリニコフと『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャに共通する「大地にひざまずき口づけをする」という行為から読みとれる暗示
さらに、筆者は、ラスコーリニコフと「神」の関係、リザヴェータが殺された意味等について考察した。
エピローグ
『罪と罰』の本編は、ラスコーリニコフの自首の場面で終わり、その後日談として短い「エピローグ」が付いている。
エピローグでは、ラスコーリニコフの裁判の経過と判決(八年の徒刑)、妹ドゥーニャの結婚と母の死、シベリアの監獄での生活、その監獄のある町に移住したソーニャの暮らしぶりなどが淡々と描かれる。
このエピローグは、記述は簡潔ながら、その内容は非常に豊かな充実したものであり、引用を始めるときりがないと思えるほどだ。
まず、注目すべきこととして、ラスコーリニコフは、監獄に入った後も、悔恨もなければ良心の痛みもなく、自分の運命に投げやりで、ソーニャにすら粗暴な態度をとったことが述べられている。彼は、ただひたすらに、自分の誇りがひどく傷つけられたことを恥じたのだ。
……ああ、もしも自分で自分の罪を認めることができるのだったら、彼はどんなにか幸福だったろう! そうなれば彼はすべてを、恥も恥辱も耐え忍んだことだろう。しかし、彼はきびしく自分を裁きはしたが、彼の激した良心は、だれにでもありがちなただの失敗以外、自身の過去にとりたてて恐ろしい罪をひとつとして見出すことができなかった。彼が恥じたのは、ほかでもない、彼、ラスコーリニコフが、何か盲目的な運命の判決によって、こうまで盲目に、希望もなく、むだに、おろかに身を滅ぼし、いくらかでも心の安らぎを得ようとすれば、その何かの判決の『無意味さ』におとなしく従い、屈服しなければならないということであった。(エピローグ)
ラスコーリニコフは、彼を脅かす「孤独と疎外の感覚」に耐えきれずに自首したのだが、依然としてその「感覚」の正体を理解していなかった。
むしろ「監獄にはいって、自由の身になった」ラスコーリニコフには、自分の行動が、かつて感じたほどに「愚劣なものとも、醜悪なものとも思えなかった」ほどだ。
彼が自分の犯罪を認めたのは、それにもちこたえることができず、自首して出たその一点においてだけであった。(同上)
ひとことで言えば、ラスコーリニコフは、服役後もなお、自分がナポレオンではなくしらみであったことに苦しみ続けたのだ。
作者は、また、ラスコーリニコフが、自首する前に川のほとりに立ちながら、なぜ自殺しなかったのかという思いに苦しめられた、とも書いている。
彼は苦しみながら、しきりとこの問いを自分に発したが、しかし、川のほとりに立ったあのときすでに、彼がおそらくは自分の内部に、自分の信念の中に、深刻な虚偽を予感したはずだということは理解できなかった。彼はまた、この予感こそが、彼の生涯における未来の転機、彼の未来の復活、未来の新しい人生観の先ぶれとなりうるものであることを理解していなかった。(同上)
犯行の前後にも、また、自首する前も後も、ラスコーリニコフの信念には、なんらの変化もない。それでいながら、彼の変わることのない信念と、彼の本能が直観的に指し示す真理とは、決定的に相容れないものであった。
消極的な選択であったとしても、彼が「自殺を選ばなかった」という決断そのものの中に、いまだ理解できない真理への直観が、すでに無意識のうちにはたらいていたということなのだろう。
もうひとつ、エピローグで着目したいのは、監獄におけるラスコーリニコフと他の囚人たちと関係、そして、そのあり方とは対照的なソーニャと囚人たちとの関係である。
監獄内で、何よりもラスコーリニコフを驚かせたのは、自身と他の囚人たち(すなわち民衆)との間に横たわる「恐ろしい、越えられることのない深淵」であった。
彼自身はみなに愛されず、避けられていた。しまいには憎まれるようにさえなった。なぜだろうか? 彼はそれを知らなかった。彼はさげすまれ、あざけられ、また、彼よりもはるかに罪重い人たちから、自分の犯罪を嘲笑された。
「あんたは旦那衆だよ!」と彼は言われた。「斧なんか持ち歩くのはあんたの柄じゃねえ。旦那衆のやるこっちゃないさね」
大斎期(復活祭前の精進の期間[訳注])の第二週に、彼は自分の獄舎の人びとといっしょに精進をする番がまわってきた。彼は、教会へ行って、みなといっしょに祈祷した。どういうことからか、自分でもわからなかったが、あるとき喧嘩が起こり、みながいっせいに彼に突っかかってきた。
「この不信心ものめ! おめえは神さまを信じちゃいねえだ!」とみなは叫んだ。「叩き殺してやらにゃ」
彼は一度として彼らと神のことや、信仰のことを話したことはなかったが、彼らは不信心者として彼を殺そうとしたのだ。彼は沈黙を守り、彼らに言い返そうとはしなかった。ひとりの徒刑囚が夢中になって彼に飛びかかろうとした。ラスコーリニコフは冷静に、無言で彼を待った。眉ひとつ動かさず、顔の筋肉ひとつふるわさなかった。折よく看守がふたりを引きわけてくれた。でなければ血を見るところだった。(同上)
ラスコーリニコフにとって、さらに「解決しえない問題」は、なぜ囚人たちがみなソーニャを好きになったのか、ということだった。
囚人たちがソーニャに会うのは、彼女がラスコーリニコフを労役の場所に訪ねるときくらいであったが、彼らはみな、彼女がラスコーリニコフを追って町に来たことも、「どこでどんな暮らしをしているか」も知っていた。
ソーニャと囚人たちとの関係はしだいに親密なものとなり、ソーニャは囚人たちのために手紙の代筆をしてやったり、身内のものが彼らに届ける差入れの品を取り次いでやったりした。彼らの妻や情婦まで、彼女をたずねて来た。
……彼女がラスコーリニコフを訪ねて労役の場に現われたり、労役に向かう囚人の一隊と顔を合わせたりするときには、みなが帽子を取って、お辞儀をした。「ソフィヤ・セミョーノヴナ、あんたはおれたちのおっかさんだ、やさしい、思いやりのあるおふくろだよ!」粗暴な札つきの徒刑囚たちが、この小柄な、やせた女にこう言うのだった。彼女は微笑で答えて、会釈を返す。みなは彼らにほほえみかける彼女が大好きだった。彼らは彼女の歩きつきまで好きになった。振り返って、歩み去る彼女を見送っては、彼女をほめそやす。彼女がそんなに小柄であることまでほめそやし、もうなんと言ってほめればよいのか、知らないほどだった。彼女に病気を診てもらいに行くものまであった。(同上)
ラスコーリニコフとソーニャのそれぞれと囚人たちとの関係は、両極端と言ってよいほどのものである。
これまで述べてきた「仮説」に従えば、ソーニャには、囚人たちとつながる「回路」としての「神との絆」が厳然としてあり、一方で、ラスコーリニコフは「それ」が失われたままである、ということになろう。
それはそうなのだろうが、筆者がここで指摘したいことは、また別のことだ。
それは、唐突なようだが、ラスコーリニコフと囚人たちとの関係は、おそらくドストエフスキー自身が経験したものであって、作家は自分自身の監獄での体験を振り返っているのではないか、ということである。
もちろん、ドストエフスキーは殺人のような凶悪犯罪を犯したわけではない。
彼は、二十代の終わりに、社会主義的なサークル活動に参加したかどで他の仲間とともに逮捕され、死刑宣告を受けたあげく、執行まぎわに減刑され、徒刑囚として四年間シベリアのオムスク監獄に収容された。有名なペトラシェフスキー事件(1849)である。
ドストエフスキーは、その監獄での体験をもとに『死の家の記録』(1861-62)を書いているが、「他者から見た」彼の監獄生活に関する数少ない証言によれば、ドストエフスキーは、ラスコーリニコフと同様に、他の囚人たちとの間で「断絶」があったことがうかがわれる。
例えば、E.H.カーの伝記には、次のような記述がある。
……また聞きではあるが、ドストエフスキーのオムスク時代について書いた他の証人は、彼の友人ドゥロフも貴族の出ではあるが、みなから愛されたといっている。ドゥロフはみなを微笑と暖かい言葉とで迎えたのに反し、ドストエフスキーは、眼を帽子でかくして、「罠にかかった狼のような様子」で、止むをえない場合のほかは口もきかず、仲間との交際を病的なまでに恐れていたようであった。時にはドゥロフと親しく口をきかないときもあった。少くともドストエフスキーの監獄生活の初期については、この証言を否定することはできないであろう。こういう気むずかしい囚人としての彼のうちに、工科学校時代孤独を求めた気むずかしい学生としての、また親友にさえやりきれなく思えた憂鬱症の青年作家としての、周知の彼の特徴が認められる。
筑摩叢書, 1968 pp.62-63.
また、同様に、小林秀雄は、ある作家がオムスク監獄の兵卒から聞き取った次のような記録を引用している。
……マルトヤノフの記録によれば、「彼は見たところ、強壮ながっしりした、充分訓練された労働者であった。言わば残酷な運命の下に化石して了った様で、物憂そうな、無骨な様子で、口もきかなかった。暗褐色の斑点のある、蒼ざめ疲れた灰色の顔には、微笑の影さえ見た事がない。仕事の事で、途切れ勝ちな言葉で切れ切れに返答するだけだった。帽子はいつも眉の隠れるほど額目深にかぶり、その眸は、怒ったように苛々と鋭く、殆ど下ばかり向いていた。囚人等は彼を好かなかった。彼の道徳的な威信は認めていたが、先ず見て見ぬふりで、憎むというのではなかったが、黙って彼を忌避する態度だった。彼にもそれがわかっていたので、みんなの仲間には這入らなかった。非常に稀れだったが、堪えられない気持ちにある時だけ、二三の囚人に話しかけていた様子だった」。
『ドストエフスキイの生活』新潮文庫 pp.78-79.
証言を読む限り、客観的に見れば、ラスコーリニコフのようにあからさまに目の敵にされ、攻撃されたわけではなかったとしても、自身の心情において、作家は、理不尽に疎んじられ、嫌われたと感じたのではないだろうか。少なくとも、ラスコーリニコフが感じた「深淵」が、作家自身の経験の反映だった可能性は大いにありうるように思う。
『罪と罰』のエピローグにおいて、ラスコーリニコフは、上で引用した喧嘩沙汰の直後に病気になって監獄内の病院に入院する。そして、彼は、熱に浮かされて、奇妙な夢を見る。それは、新種の「旋毛虫」が媒介する前代未聞の疫病の拡散によって全世界が滅亡の危機に瀕するというものだ。
この疫病は、ラスコーリニコフが憑りつかれた、歪んだ「選民思想」の比喩であったろうか? ともかく、この悪夢からさめ、病気からも回復すると、それが契機となったかのように、ラスコーリニコフは、ソーニャへの愛を自覚しはじめ、また、囚人たちとの関係もよい方向へと変わりはじめる。
そして、エピローグは、次のように結ばれる。
……ここにはすでに新しい物語がはじまっている。それは、ひとりの人間が徐々に更生していく物語、彼が徐々に生まれかわり、一つの世界から他の世界へと徐々に移っていき、これまでまったく知ることのなかった新しい現実を知るようになる物語である。それは、新しい物語のテーマとなりうるものだろう。しかし、いまのわれわれの物語は、これで終わった。(エピローグ)
ラスコーリニコフが「徐々に更生していく」とすれば、その「更生」が意味するものはなんだろうか?
ヒントは、エピローグの中で、ラスコーリニコフとソーニャの対比が強調されるように描かれた囚人たちとの関係にある。
ラスコーリニコフと囚人たちとの間には「越えがたい深淵」が横たわっていた。この「越えがたい深淵」を「越えようとする」こと、それこそがラスコーリニコフの「更生」が意味するものなのだろう。
ここで、ひとつの推測が浮かび上がる。
もし、作家が、監獄におけるラスコーリニコフの描写に自身の体験を重ね合わせていたのだとしたら、そして、作家自身がラスコーリニコフと同様に他の囚人たちとの間で「恐ろしい深淵」を実感したのだとしたら、ラスコーリニコフの「更生」の過程も、また、作家自身の経験の反映であったのではないだろうか?
つまり、ラスコーリニコフの「更生」がはじまったように、作家自身にも、囚人(民衆)たちとの間に横たわる深淵の超克に向けたなんらかの精神的過程がはじまっていたと、考えられるのではないだろうか?
次回は、この点について考察し、そこから作家が『罪と罰』を書いた意図を照らし出すことで、この「私論」を締めくくることとしたい。
きりよく十回で完結させるつもりだったのだが、元の原稿を大幅に修正し、部分的に逸脱もした結果、当初の予定におさまらなくなってしまった。
一回分よけいになるが、次回でうまくおさめられるとよいなと思っている。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
