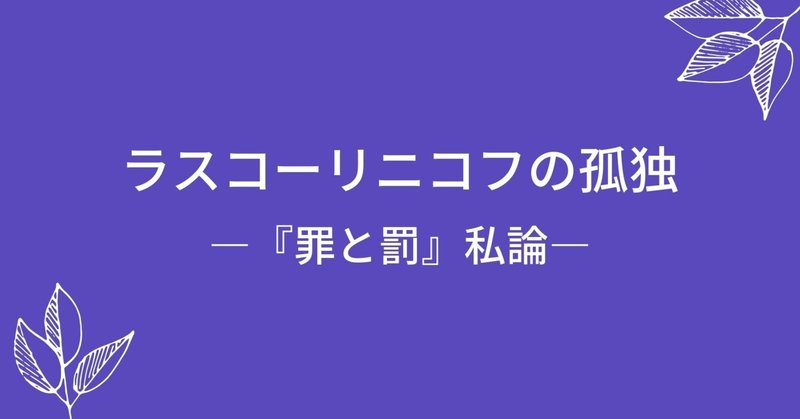
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(3)
目次
問題の所在
様々な解釈
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
前回までの要約
ラスコーリニコフは老婆の殺害の直後から「無限の疎外と孤独の感覚」に苦しめられる。この「感覚」の正体は果たして何か、それが本論の重要な問題提起であった。
小林秀雄は、その感覚の正体を明言することを慎重に避けた。
ベルジャーエフは、「内在的な神的原理」が主人公の良心を打ったものと解釈した。しかし、作者は、ラスコーリニコフが自首に至るまで良心の呵責と無縁であったことを強調する。
シェストフは、ラスコーリニコフの絶望的な孤独感を、『地下室の手記』以来の作家自身の苦悩と同一視するが、この感覚と老婆の殺害との因果関係については、何も説明しない。
江川卓は、ラスコーリニコフの苦悩を、自分自身を殺したことによって「愛の不能」という「地獄」に陥ったものであると解釈した。そうだとすれば、「なぜ老婆の殺害が自己の死に転化したのか」という新たな「問い」が生じてくる。
仮説
ドストエフスキーは、処女作『貧しき人々』を二十三歳で書き、当時の著名な批評家であったベリンスキーに絶賛され、鮮烈な文壇デビューを果たした。
ドストエフスキーは、『作家の日記』において、この時ベリンスキーから受けた賞賛と激励が「自分の生涯における荘重な瞬間、いわば一つの転機」となり、「自分はベリンスキーの賛辞に値する人間になろう」と誓ったと、回想している。
ベリンスキーの賛辞とはどのようなものだったのか、『作家の日記』から引用しよう。
「……君(ドストエフスキー)は物の本質に直接触れたのです、最も重要なことを啓示したのです。われわれ、評論家・批評家たちは、ただそれを考察して、言葉で説明しようと努めるだけだけど、君がた芸術家は一線一画をもって、ただちに形象の中に本質的な真髄を示し、手に触れるがごとく感知させ、どんな思索に縁遠い読者でも、忽然といっさいを悟ることができるようにするのです! これが芸術の秘密であり、芸術に表現されたる真実であるのです! これこそ芸術家の真理に対する奉仕の方法です! あなたは芸術家として真実を啓示され、告知されたのです、天賦として与えられたのです。だから、この天賦を大切にして、どこまでもそれに忠実にやっていけば、やがて偉大な作家になるでしょう!」
「形象の中に本質的な真髄を示し、手に触れるがごとく感知させ、どんな思索に縁遠い読者でも、忽然といっさいを悟ることができるようにする」こと、それが「芸術の秘密」であるとベリンスキーは言った。
このベリンスキーの言葉によって、ドストエフスキーは、自ら『貧しき人々』で無意識に実践した方法論を明確に意識化し、創作原理として規範化したのではないか、と私は考える。その方法論とは、読者が登場人物を「思索によって理解する」のではなく、その人物の想いを「生身の感覚として共有する」ように書く、というものだ。
もしそうであれば、『罪と罰』においても、作家が読者に求めたものは、ラスコーリニコフに対する「理解」ではなく、むしろ「共感」であった、ということになる。
小林秀雄が「恐らく、作者は、読者の思想の裡にも、同じ触覚が現れることを期待しているのである」と見事に看破した(前述)とおりである。
そうしてみると、例えば、前回紹介した江川卓の解釈は、確かに緻密な分析であり、深い洞察であることは疑いようがないが、それを、ドストエフスキーが読者に期待したと考えるのはいささか無理があるように思う。
というのも、江川の解釈に到達するためには、ラスコーリニコフの感覚の描写である「苦しい」という一般的な形容詞から、その語源である「苦悩」という名詞のニュアンスを通じて「地獄」を連想し、さらに『カラマーゾフの兄弟』のゾシマ長老の地獄観(地獄=愛の不能)にまで思い至ることが要求されるからである。
もしドストエフスキーが、理解よりも共感を重視したのであれば、そのような難しい謎解きなど必要としない、もっと単純な、感覚的な、直観的なイメージに訴えようとしたのではないだろうか?
私の「仮説」は、そのような、ある直観的なイメージに関わるものである。
「ラスコーリニコフの感覚の正体は何か」という問いを抱え始めてから数年も経たぬうちに、その「答え」は、ある日突然、思いがけず降ってきた。
最初は、いわば思いつきのようなものであり、決して詳細な検討の結果などではなかった。前回、先行研究として挙げた四人の議論は、いずれも、すでに「答え」に到達した後に、事後的に確認することができたものだ。
それは、私がまだ二十代初めの学生の頃に、他愛もない偶然のように降りてきた。正確な年月は全く思い出せないのだが、その状況は、はっきりと覚えている。
ある日本のロック・バンドが夏の高原で野外コンサートを開催したのだが、当日は生憎の豪雨となってしまった。バンドのメンバーも観客もずぶ濡れで、楽器やアンプなどの機器類も盛大に水をかぶり、まともに音など出せる状況ではなかったのだが、そのような大雨の中でバンドと観客が一体となって最後まで公演を続けたという。
そのバンドのリーダーが、テレビのインタビューか何かで、次のような趣旨のことを言ったのである。
「あのような悪天候の中でバンドのメンバーと観客とが保ちえた絆は、単に人と人とが横につながった結果とは思えない。音楽の神様が仲立ちになってくれたとしか考えられない一体感だった。」
それを聞いたとき、私は咄嗟に「ああそうか」と思った。唐突に、そんな何の変哲もないバンドのリーダーの言葉に弾かれるように、『罪と罰』の「謎」が解けた、と感じたのだ。
あの作品世界においても、人と人のつながりが、直接の水平的な横のつながりではなかったのだとしたら……。あらゆる人間どうしのつながりが、すべて天上の神を仲立ちとした垂直的な縦のつながりであるのだとしたら……。
そうだとしたら、神に背き、自ら神とのつながりを断った者は、必然的に、世界のいっさいの人間から切り離されて、もはや誰とも結びつくことができなくなってしまうのだ。
つまり、犯行直後のラスコーリニコフの、あの絶望的な孤独感、疎外感、「まるで鋏で切り離しでもしたかのように」この世のいっさいのものとの絆が失われたような感覚は、彼が自ら神との絆を断ち切った結果であったのだ。
それを直感的に、身体感覚として「突きつけられた」としたら、その恐ろしさは想像を絶するものではないだろうか!
これを読んでくれている note の読者は、「なんだ、そんな単純なことか」と拍子抜けしたかもしれない。
しかし、この「仮説」は、私にとって、目から鱗が落ちるような、胸のつかえが取れたような発見だった。何故なのか自分でもよく分からないのだが、それに直面した瞬間から紛れもない「直観的」な確信となったのだ。
もちろん、ドストエフスキーは、作品の中で、直接にはそのような種明かしは何もしていない。
しかし、もし私の仮説が当たっているなら、つまり、もし、ドストエフスキーが、ラスコーリニコフの「孤独」に「神との断絶への報い」という意味を込めたのだとすれば、そして、ラスコーリニコフとともにその「恐ろしさ」を体感することを読者に求めているのだとすれば、おそらく、そのような「罰」の意味を、読者が「手に触れるがごとく」感知し、悟ることを促すようなメッセージを作品中に仕掛けているのではないか?
次回以降は、そのような「仕掛け」と思われるものを、いくつか拾い上げることを試みてみたい。
* * *
一つだけ注釈を加えておきたい。
「あらゆる人間どうしのつながりが、天上の神を仲立ちとした垂直的な縦のつながりである。」それが、仮説として想定した作品の世界観である。
この場合、では「神」が存在する「天上」とはどこなのか、という疑問が当然生じてくる。
というのは、地球が球体であり、太陽の周りを回転しているとする地動説が科学的な常識となった近代以降、すでに雲の上は「神」の居場所ではありえなくなったからだ。今この地点における真上は、地球の裏側から見れば、当然真下になる。
文字どおりの「天上」が神の居場所でないとしたら、神はどこに存在するのか?
佐藤優によれば、この問題を解決したのが「近代神学の父」と言われるフリードリッヒ・シュライエルマッハー(1768-1834)である。
そもそも人間にとって、キリスト教の神は「見えない世界」にいます。近代以前の世界観においては、神が天上に存在することに誰も疑念を持たなかった。しかし、地球は球体であることがマゼランの世界一周で実証され、また、コペルニクス以降、地動説が主流の世界観になっている状態で、近代以前の上と下という概念で神を表象することが難しくなったのです。<中略>
この問題を根本的に解決したのがシュライエルマッハーでした。彼は、初期の著作『宗教論』(一七九九年)で「宗教の本質は直観と感情である」と定義し、晩年の著作『キリスト教信仰』(一八二一~二二年、第二版一八三〇年)では「宗教の本質は絶対依存の感情である」と定義したのです。その結果、神は天上ではなく、各人の心の中にいることになりました。神を「見えない世界」にうまく隠すことに成功したと言ってもいいかもしれません。これで、神の居場所の問題は見事に解決したわけです。
NHK出版新書, 2011 pp.12-13.
ドストエフスキーが、「神は各人の心の中にいる」というシュライエルマッハーの説を、どのように考えていたかは分からない。
しかし、彼が、高等教育を受けた一九世紀の近代的知識人として、文字どおりの、物理的な意味での「天上」を神の居場所であると認識していなかったことは間違いない。
従って「天上の神を仲立ちとした垂直的な縦のつながり」という表現は誤解を招くかもしれないが、ここで「天上」と言うのは、あくまで象徴的な、図式的な、直観的なイメージとしての天上界あるいは異界を指すものであり、「垂直的な縦のつながり」という言葉もそのような意味で用いていることをご理解いただきたい。
いずれにせよ、科学的・合理的な知性の持ち主である現代人が、「神」を想うときに思わず天を仰いだとしても、不思議ではないだろう。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
