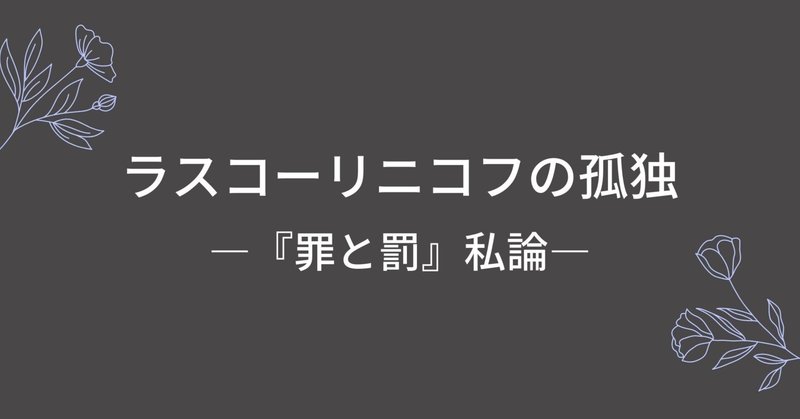
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(8)
目次
問題の所在
様々な解釈
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
前回までの要約
ラスコーリニコフの「無限の孤独と疎外の感覚」の正体は、自ら神との絆を断ち切った結果として、必然的に世界の誰ともつながることができなくなったことを、直観的に、皮膚感覚として突きつけられたものであった。
この「仮説」を裏付ける証拠として、筆者は次の5点を挙げた。
・「ラスコーリニコフ」という姓に読みとれる「神との絆を断ち割る者」という暗示
・ラスコーリニコフが老婆の財布を奪い取ったときに、紐から切り離し、死体の上に投げすてた十字架と聖像、すなわち「神への信仰のしるし」
・ラスコーリニコフのファーストネーム「ロジオン」の命名の由来となった可能性があるシラーの詩「ギリシャの神々」の中の「英雄と神と人間との絆」を意味する詩句
・ラスコーリニコフが「神から離れたことによって、人間を失った」ことを見抜いたソーニャの直観
・「大地にひざまずき口づけをする」という行為におけるラスコーリニコフと『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャとの相似、及びその行為とともに描写されたアリョーシャの心象風景
ラスコーリニコフと神
前回までに置き去りにしてきたいくつかの問題について、気の向くままに考えてみたい。
まず、ラスコーリニコフは神を信じていたか?
このような問題設定は、馬鹿げたものに聞こえるかもしれない。ラスコーリニコフ本人の自覚において、彼が神の存在を信じていなかったことは明白だからだ。
そもそも、彼の恐ろしい犯行は、信仰の不在ゆえに企図され得たのだ、と言うことができる。
とりわけ、ラスコーリニコフが無神論者であることが際立って描かれるのは、彼が初めてソーニャの住む粗末な部屋を訪れ、彼女と奇妙な会話を交わす場面(第四部 四)だ。
義理の母やその幼い子どもたちの生活を支えるために娼婦にまで身を落としたソーニャ、そんな境遇をいぶかってラスコーリニコフは彼女を問い詰める。
「どうしてきみのなかには、それほどの汚辱といやしさが、まるで正反対の、神聖な感情と同居していられるんだ? だって、さっさと頭から水のなかに飛び込んで、一思いにきりをつけてしまうほうがずっと正しいじゃないか、千倍も正しくて賢明じゃないか!」(本文からの引用は、江川卓訳岩波文庫より。以下同じ)
ソーニャは、この言葉の残酷さに驚いた様子も見せず、消え入りそうな声で答える。
「でも、あのひとたちはどうなるんです?」
「あのひとたち」とは、もちろん彼女なしでは暮らしていけない家族たちのことだ。
それでもラスコーリニコフの疑問は解けない。
「なぜ彼女はこんなにも長い間、こうした境遇にとどまりながら、水に飛びこむだけの勇気はなかったとしても、どうして発狂しないでいられたのか?」
むしろ、彼女はすでに発狂しかかっているのではないか、とラスコーリニコフは疑い、ふとある考えに思い至る。
「じゃ、ソーニャ、きみはずいぶん熱心に神さまにお祈りするんだね?」彼(ラスコーリニコフ)がたずねた。
ソーニャは黙っていた。彼はそのそばに立って、返事を待っていた。
「神さまがなかったら、わたしはどうなっていたでしょう?」ふいにきらきらと輝きはじめた目でちらと彼をふり仰いで、彼女は早口に、力をこめてささやき、彼の手をきつくにぎりしめた。
『ははん、やはりそうか!』と彼は思った。
「じゃ、そのかわりに神さまは何をしてくださるんだい?」彼はさらに問い詰めた。
ソーニャは返事に窮したように、長いこと黙っていた。彼女の弱々しい胸は、興奮のためにはげしく波だっていた。
「言わないで! 聞かないでください! あなたは、その資格のない人です!……」きびしい怒りの目で彼を見つめながら、だしぬけに彼女が叫んだ。
『やはりそうだ! やはりそうだ!』彼は心のなかでしつこくくりかえした。
「なんでもしてくださいます!」彼女は、また目を伏せて、早口にささやいた。
『これが結論さ! 結論の説明さ』彼はむさぼるような好奇のまなざしで彼女をながめまわしながら、ひとりこう断定した。(第四部 四)
ラスコーリニコフの「結論」とは、ソーニャが「ユロージヴァヤ(聖痴愚)」である、ということだった。
「ユロージヴァヤ」とは何か?
因みに「ユロージヴァヤ」は名詞の女性形であり、男性をさす場合は「ユロージヴイ」となる。江川はユロージヴイを「聖痴愚」と訳している。ロシア語の辞書には、ほかに「佯狂者」や「瘋癲行者」などの訳語がみられる。いずれにしても日本人には耳慣れない言葉だ。
手っとり早く、江川卓の訳注から説明の一部を引用しよう。
……本来は苦行僧の一種で、信仰のために肉親や世間とのつながりを絶ち、常識や礼儀をさえわきまえぬ狂人、痴愚をよそおって、真実の神の言葉を説いた者をいうが、ロシアでは、ユロージヴイへの信仰が他のどの国にもまして民間に広く普及していた。いくぶん神がかった狂人や白痴をこの名で呼んで、神のお使いとして大切にした風習もあった。……
恥辱と気苦労にまみれた悲惨な日常を生きるソーニャにとって、唯一の救いは神の存在であり、神への信仰であった。そのような彼女を、ラスコーリニコフは「いくぶん神がかった狂人」すなわち「狂信者」とみなしたのである。
いっさいの人間から切り離されたと感じるラスコーリニコフにとって、ソーニャは唯一、ともに生きることを期待しうる人間であった。自分で自分を滅ぼしたと感じるラスコーリニコフは、ソーニャもまた、「むだに自分を殺し」た「罪の女」であると考え、そのことを本人に面と向かって告げている。そして、「いま、ぼくには君ひとりしかいない」「ふたりとも呪われた同士だ。だからいっしょに行こうじゃないか!」とまで訴えている。
つまり、ラスコーリニコフにとってソーニャは、彼の唯一の「同類」なのだ。
ところが同時に、ラスコーリニコフとソーニャとの間には、決定的な「みぞ」がある。それは、神に対する想いの違いである。
神への無条件の信仰は、ソーニャにとっての生きる支えにほかならないが、ラスコーリニコフは、そこに「発狂の徴候」を見てとるほど、ソーニャとは対極的な場所に立つ。このように、この場面では、「信仰」をめぐる二人の対比がくっきりと描き出される。
だが、ラスコーリニコフが、本当に、心の底から「神」を信じていなかったかというと、そうとも言い切れない、あいまいさが存在するのだ。
ラスコーリニコフは、彼に老婆殺しの嫌疑をかけるポルフィーリー予審判事との対話の中で、「神を信じているか」と問われ、「信じている」と答えている。もっとも、これは「偽装」かもしれない。
むしろ、注目すべきは、ラスコーリニコフが犯行に至るまでに、長い間迷い、思い悩み、いったんは断念する場面(第一部 五)である。
彼は、ペテルブルクの街を当てもなく歩き回り、空腹を感じて酒場でウオツカを一杯ひっかけ、たちまち酔いが回って、帰る途中、道をそれて草の上にぶっ倒れ、眠りこみ、悪夢にうなされる。
全身汗まみれで目を覚ましたとき、彼は自身のたくらみに対する嫌悪感で「全身をぶちのめされたよう」になって頭をかかえる。
「だめだ、おれにはもちこたえられない! 耐えられない! たとえ、たとえあの計算に一点の狂いがないとしても、この一カ月に決めたことが全部、真昼のように明らかで、算術のように正確だとしても。ああ! おれはどうせ決行しっこないんだ! だっておれには耐えられない、もちこたえられやしない!……だのに、なんだって、なんだっておれはいまだに……」
彼は立ちあがり、あきれたような顔であたりを見回した。どうしてあんなところに立ちよっていたのか、合点がいかぬふうだった。それからT橋のほうに歩きだした。顔は青ざめ、目は燃えるようだった。手も足もくたくたになっていた。だが、呼吸が急に楽になったようにも感じた。長いこと心にのしかかっていた恐ろしい重荷を、ようやく振り捨てたのだと感ずると、気持ちまでふいに軽々として、おだやかになった。『神さま!』と彼は祈った。『私に道をお示しください。私は断念いたします。あの呪われた……私の空想を!』(第一部 五)
このような描写を読む限り、ラスコーリニコフが正真正銘の無神論者だとは考えにくい。彼は、あたかも神に導かれたかのように、ひとまず邪悪な想念を振りはらったのだ。
ところが、その帰り道に、運命の非情な罠が待ちかまえていた。彼は、通りすがりに、偶然リザヴェータの立ち話を聞くことによって、翌日の晩、老婆が家に独りきりになることを知り、「絶好の機会」を与えられてしまう……。
ラスコーリニコフが、本心では神を信じていたか、信じていなかったのか、たぶん彼自身にも、はっきりとわからなかったのではないだろうか。
ラスコーリニコフの神に対する態度は混乱している。もはや自首するほかに残された道がないと悟ったとき、彼は妹のドゥーニャとの別れに際して、次のように語る。
「ぼくは神を信じちゃいない。それでも母さんには、ぼくのためにお祈りしてくれと頼んできた。何がどうなっているのか、神さまにしかわからないさ、ドゥーネチカ、ぼくには何がなんだかわからない」
ラスコーリニコフは、神に対して懐疑を抱きながらも、その存在を完全に否定し去ることはできなかった。あるいは、神を信じることも否定することもできなかったという心の在りようが、彼の愚行を許す素地となったと同時に、彼の再生への希望を辛うじてつなぐための命綱となったとも考えられる。
そして、主人公のそのような「心の在りよう」は、『罪と罰』という物語を成立させるために必要不可欠な条件でもあったのだ。
『罪と罰』において、ドストエフスキーは主人公を破滅させることを望まなかった。むしろ、作家が構想したのは、致命的な罪を犯した人間にとっての再生の可能性を追求する物語だった。おそらく、そうした再生のための鍵となる存在として造形された人物がソーニャであった……。
次回は、ラスコーリニコフの再生にソーニャが果たした役割について、それと合わせて、リザヴェータが殺された意味について、さらに深入りして考えてみたい。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
