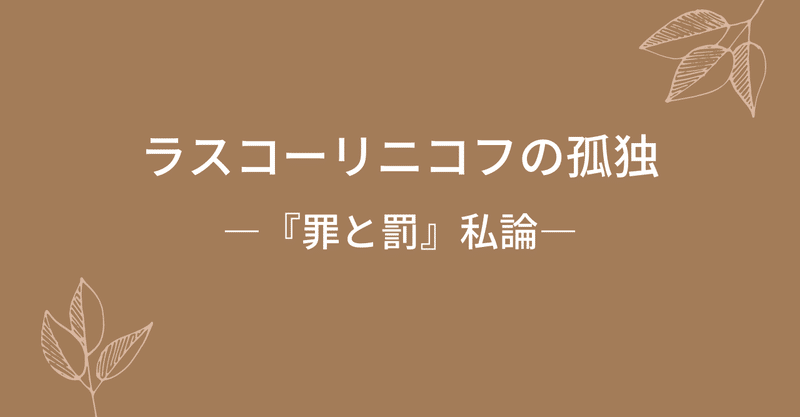
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(1)
目次
問題の所在
様々な解釈
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
今回から計10回程度(予定)にわたり、極「私」的・独善的な『罪と罰』論を投稿しようと思う。
なぜ自ら「独善的」などと自虐めいたことを言うかというと、実は、この『罪と罰』論を、2020年度及び2021年度の2回にわたり、それぞれ異なる評論文学賞に応募したのだが、ともに最終選考に残ることもなく、あえなく落選したからだ。
筆者としては、これこそ『罪と罰』の画期的な解釈であると、秘かにうぬぼれていたのだが、最終選考にすら残らなかったということは、客観的に見れば、この論稿は、面白み、斬新さ、独創性、説得力、文章力等々の各賞の選考基準のいずれかあるいは全てにおいて、評価に足るレベルに達していなかったということなのだろう。
あるいは、『罪と罰』というテーマ自体が、すでに語りつくされ、手垢がついたものであると同時に、それを真正面から取り上げることが、あまりに大それた、仰々しい試みであったために、選者たちに鼻白む思いをさせてしまった、ということはあるかもしれない。
そんな代物をあらためて読まされるなど、note の読者にとってみれば、いい迷惑だろうか?
しかし、私の個人的見解としては、ここで論ずる内容はきわめて重大な意味を持つものである。そう信じる以上、大げさに言えば、これを世に出さずには死ねないという想いがある。
そのような想いを託す場として note という媒体を選択することは、私にとって自然な成り行きであるように思った。
どれだけ受け入れてもらえるかわからないが、文学賞落選という結果も受け止め、あらためて内容を精査し、加筆修正を行いながら、不定期の連載形式で発表したい。
前置きはこれくらいにして、早速、本論に入ることにしよう。
問題の所在
そもそも、なぜ私が『罪と罰』にとらわれてしまったかと言えば、それは、逆説的になるが、『罪と罰』が理解できなかったためであったように思う。
ドストエフスキー(1821~1881)の『罪と罰』(1866)は、世界文学史上あまりにも有名な作品である。舞台は、当時の帝政ロシアの首都ペテルブルグ、主人公は、貧乏な元大学生のラスコーリニコフだ。ラスコーリニコフは、意地が悪く、強欲で、他人の生き血を吸うような金貸しの老婆を殺害し、金品を強奪する。それは衝動的な犯行ではなく、彼が考えに考え抜いた末の計画的な殺人だった。
私が理解できなかったのは、犯行後のラスコーリニコフに生じた突然の精神的な変化である。
ラスコーリニコフの犯行の動機の一部に、彼の極度の貧乏があったことは否定できない。
彼が有為の人材として世に出ていくために、それどころか、日々の暮らしにも事欠くような赤貧から脱け出すためには、金が必要だった。
その上、故郷で母と暮らす最愛の妹ドゥーニャが、好きでもない男の求婚を受け入れたことを母の手紙で知り、どうやらその理由が、将来の夫からの兄に対する援助を当てにしたものであることを悟ってしまった主人公は、何としてでもその結婚を阻止せねばならなかった。母や妹を安心させ、無謀な結婚を思いとどまらせるためにも金銭問題を解決することが急務である。そのためには行動を起こさなければならない。
作者は、主人公の切羽詰まった心理状態を次のように描いている。
明らかにいまは、問題解決の困難さばかりあげつらい、受け身にまわって悩んだり、煩悶したりしているときではなく、是が非でも何かをしなければならないときだった。それも、いまただちに、一刻も早く。どうあっても何かを決行しなければならない。(第一部Ⅳ)
(本文中の引用も含め、『罪と罰』からの引用は、原則として江川卓訳, 岩波文庫による。)
その「何か」が「強盗殺人」であるというのはあまりにも突飛な飛躍のようだが、当の老婆殺しの「計画」はすでに久しく主人公にとりつき、もはや肥大化した強迫観念となっていた。
しかし、なんといっても殺人は「悪」だ。倫理的にも、もちろん法律上も「悪」である行為が、果たしてどのように正当化され得るだろうか。
作品の中盤になってようやく明らかになるのだが、ラスコーリニコフは、以前に執筆し、ある雑誌に掲載された犯罪に関する論文の中で、「ある種の人間にとっては犯罪が許容される」という思想を暗示していた。ラスコーリニコフに対して密かに老婆殺害の嫌疑をかける予審判事のポルフィーリーとの対話の中で、この論文の話題を持ち出された主人公は、その思想の内容について、概ね次のように説明する。
この世の人間は、大多数の凡人と極めて少数の非凡人とに分類される。選ばれた非凡人は、「つねに法の枠をふみ越える」人間であり、「より良き未来のために現在を破壊することを要求」し、その思想のために流血を犯す必要がある場合には、「良心に照らして、流血をふみ越える許可を自分に与えることができる」。
ラスコーリニコフは、自分自身が非凡人であることの可能性に賭けていた、ということである。
彼にとって、自ら犯そうとする殺人の意義及び正当性の問題は、自身の内部において事前に一応の決着がつけられていた。彼は、それが「自分の欲と肉のためにすること」ではなくて、「別の立派な、よき目的のためにすること」であるということを、「まる一月もの間、全能の神様を証人に呼びだして」自分自身に対して説得した、と独白の中で振り返っている。良心に照らしてやましい行為ではない、ということだ。
ところが、犯行が成就した直後から、ラスコーリニコフは、自らの行為の結果として、絶望の奈落に突き落とされてしまう。
犯行の翌日、ラスコーリニコフは、いきなり警察署から呼び出しを受け、戦々恐々として出頭する。しかし、用件は下宿代の未納から生じた金銭取立て請求の件であった。ほっと胸をなでおろしたラスコーリニコフは、署長や副署長の前で、いささか情に訴えるような弁明をひとくさり述べ立てた後で、突如として「無限の孤独と疎外の暗い感覚」に襲われる。
ラスコーリニコフの心の中に生じた変化について、少し長くなるが、作品から引用する。
いま、彼の身に起こりつつあったのは、彼にとって全く未知の、新しい、思いがけぬ、ついぞこれまでに例のないことであった。頭で理解したというのではなかったが、彼は明確に、全感覚をつらぬくほどの力で感じ取ったのだった――。ほかでもない。彼はもう二度と、さっきのような感傷的な打明け話はもちろんのこと、たとえどんな種類の話であっても、警察署のこういう人間どもを相手に話しかけることはできない、いや、たとえ相手が警察署の警部ふぜいではなく、彼と血を分け合った兄弟姉妹であっても、今後、生涯のいかなるときにも、彼らに話しかける理由は全く失われてしまった、ということをである。いま、この瞬間まで、彼は一度としてこんな奇怪な、恐ろしい感覚を経験したことはなかった。そして、何よりもやりきれなかったのは、意識とか、観念とかいうよりも、むしろ感覚であったこと、直接的な感覚、これまでの生涯で彼が体験した感覚のうちでも、もっとも苦しい感覚であったことである。(第二部Ⅰ。強調は引用者による。)
これに続く場面では、ラスコーリニコフは、放心状態でペテルブルグの街なかを彷徨し、ふと立ち止まったネワ川にかかる橋の上で、「いっさいの人間といっさいのものから、自分の存在を鋏で切り離しでもしたように」感じる。これは、どういうことなのだろう?
ラスコーリニコフは、殺人という行為の後に、誰であれ他の人間と正常な人間的な関係を結ぶ能力を失ったかのようだ。しかし、彼は、なぜそのような不能に陥ってしまったのか?
「良心の呵責」に耐えられなくなったのだ、と答えることはもちろん容易である。しかし、犯行後のラスコーリニコフになんら悔恨の情が生じなかったことは、作者が明確に述べている。
物語の終盤、まさにこれから警察署に自首しに行くというときになってさえ、彼は、妹のドゥーニャを前にして次のように怒りをぶつけるのだ。
ぼくが、あのけがらわしい、有害なしらみを、だれにも必要のない金貸しの婆ァを、殺してやれば四十もの罪障がつぐなわれるような、貧乏人の生き血を吸っていた婆ァを殺したことが、それが罪なのかい? ぼくはそんな罪のことは考えない、それを洗い浄めようなんて思わない。(第六部Ⅶ)
ラスコーリニコフを襲ったものは、善悪の観念に基づいた自責や後悔の念などではない。そのように予め想定し、防御を準備しうるものではなく、全く予期していなかった「肉体的な感覚」であったのだ。
果たして、この「感覚」の正体は何者なのだろう?
小林秀雄は、『罪と罰』を論じた評論で、この「感覚」に言及し、次のように書いている。
今、彼(ラスコーリニコフ)の裡に現れたものは観念でも意識でもない、それは嘗て経験したことのない悩ましい触覚であった。恐らく、作者は、読者の思想の裡にも、同じ触覚が現れることを期待しているのである
『ドストエフスキイの生活』新潮文庫 p.440.
私が初めて『罪と罰』を読んだとき、その同じ触覚をどれだけ実感することができたのか、今となっては思い出すことができない。覚えているのは、その感覚の正体が、すなわち、ラスコーリニコフに現れた「悩ましい触覚」がどのような心理的、生理的な由来で生じたものであるのかが、全く理解できなかったということである。
しかし、間違いなく理解できたのは、その「感覚」こそが、『罪と罰』という作品の意味を解く重要な鍵であるということだった。
おそらく、ドストエフスキーは謎をかけているのだ。この「感覚」の正体を捕えてみよと。私には、そのように思われた。そして、この謎が頭から離れなくなってしまったのだ。
本稿は、この「謎」をめぐる一つの仮説を提示し、その検証を試みるものである。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
