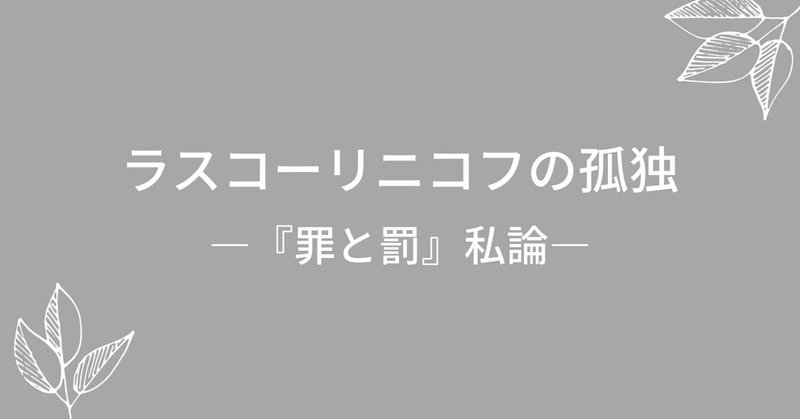
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(2)
目次
問題の所在
様々な解釈
小林秀雄
ニコライ・ベルジャーエフ
レフ・シェストフ
江川卓
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
前回の要約
ラスコーリニコフは金貸しの老婆を殺害した直後から、地上のいっさいの人間やものから切り離されてしまったような「無限の疎外と孤独」の感覚に襲われる。
それまでの彼の生涯で体験したことがないほどの、この苦しい「感覚」は、決して、善悪の観念に呼び覚まされた悔恨や自責の念などではなかった。彼の犯行は、「選ばれた非凡人は法の枠をふみ越え、流血を犯すことが許可される」という思想によって正当化されたものであったのだ。
だとすれば、ラスコーリニコフに耐えがたいほどの苦痛を与えるこの孤独感は、いったいどのような由来で生じたものなのだろうか?
この「謎」を解くことが『罪と罰』を理解するための重要な鍵であるに違いない。
様々な解釈
『罪と罰』で提起されたこの「謎」、この「感覚」について、著名な研究者・批評家はどのような説明をしているだろうか。
以下では、この「感覚」に注目し、あるいはなんらかの解釈を行っている先行研究の事例として、文芸評論家の小林秀雄(1902-83)、ともにロシアの哲学者・思想家であるニコライ・ベルジャーエフ(1874-1948)及びレフ・シェストフ(1866-1938)、ロシア文学者の江川卓(1927-2001)の四人の議論をごく簡単に紹介する。
小林秀雄
小林秀雄は、『罪と罰』を論じた難解な評論において、前回も触れたように、この「感覚」に特別な注意を払っている。
小林は、ポルフィーリー予審判事の追及を受け、いよいよ自分の犯行が露見する寸前までに追い詰められた主人公の心理を描いた次の一節に注目する。
「実に奇怪な話で、誰もそんなことを信じないかもしれないが、彼(ラスコーリニコフ)は現在目前に迫った自分の運命について、ほんのぼんやりとした微かな注意しか払っていなかった。何かそれ以外にずっと重大な、並々ならぬものが彼を悩ませていたのである――それは彼自身のことで、ほかの誰のことでもないけれども、なにか別のことで、何か重大なことなのである。それについて、彼は限りない精神の疲労を感ずるのであった。」(日本語訳は小林の評論による。)
これらの描写を受けて、小林は、次のように述べる。
……いわばそういう不安状態のうちに、主人公を掴んで離さぬ為に、作者はどれほどの努力を必要としているかを想い見るがよい。もはやそれはあれこれの観察だとか分析だとかいうものの力ではない。いわば絶対的批判の前で七転八倒する主人公に、面をそむけず見入る作者の愛の緊張である。読者は、それを想いみて信ずるがよい。若し読者が、主人公の精神が限りない疲労を感ずるという、あの主人公にはわからぬ「並々ならぬ重大な或るもの」を信ずるならば。――それは何であるか。作者が答えなかったことを、ぼくが答えてはならないのである。(強調は筆者による。)
『ドストエフスキイの生活』新潮文庫 p.457.
小林秀雄は、主人公を悩ます「並々ならぬ重大なもの」の正体を、軽々しく言葉にすることを慎重に避けているかのようである。
むしろ、ドストエフスキーは、読者に対して、理解ではなく「共感」を求めているのだ。ラスコーリニコフの「感覚」は言葉で説明することで伝わるものではなく、かえって、言葉による説明は、それを読者が皮膚感覚として共有する機会を損ねてしまう。
小林は、そのように言いたかったのかもしれない。
ニコライ・ベルジャーエフ
ベルジャーエフは、ラスコーリニコフや、その近親者と言える著名な登場人物たち、すなわちスタヴローギン(『悪霊』)やイワン・カラマーゾフ(『カラマーゾフの兄弟』)らの悲劇的運命を、「我意としての自由」が「自分自身を滅ぼし」たものであると説明する。
……外的な罰が人間を待っているのではない。外的な法則が、その重い手を人間の上に置くのではない。そうではなくて、内面から、内在的に展開する神的原理が、人間の良心を打つのである。炎々と燃える神の火を浴びて、人間はみずから選びとったあの暗黒と空虚のうちに焼死する。これが人間の運命であり、人間の自由の運命である。
斎藤栄治訳, 白水社, 1978 p.89.
ベルジャーエフは、また、次のように述べる。
……彼(ラスコーリニコフ)はその我意のゆえに、人間の中の最下等のものをすら、《観念》の名のもとに殺していいかどうかという問題を、自分勝手に決定する。だが、かかる問題の決定は、人間の手にあるのではなくて、それは神のものなのだ。神こそは、唯一のより高い《観念》なのだ。そして、こうした問題の決定に際してかかる《より高き意志》の前に頭を下げない人間は、隣人たちを滅ぼし、自分自身を滅ぼす。ここに『罪と罰』の意味がある。
ベルジャーエフは、犯行後のラスコーリニコフを捕えたあの恐ろしい感覚の正体として「内面から、内在的に展開する神的原理」を示唆している。これは、一般的に受け容れられている解釈に近いものであるように思われる。
しかし、そのような原理が働くためには、それが「内在的に」存在することを前提としなければなるまい。つまり、ベルジャーエフは、ラスコーリニコフやスタヴローギンやイワン・カラマーゾフといった面々が内在的に神的原理を備えていた、と言っていることになる。
果たして、ラスコーリニコフは、神の存在を信じていただろうか?
この難しい問題には、ここでは深入りせずに、後に立ち戻ることとしたい。ただし、少なくとも、スタヴローギンやイワン・カラマーゾフの悲劇の背景には、信仰の不在あるいは否定が色濃く影を落としている。イワン・カラマーゾフは、父フョードルから、「答えてくれ、神はいるのか、いないのか?」と問われて、「神はいません」と断言する(『カラマーゾフの兄弟』第一部第三編)。
また、ベルジャーエフは、内在的な神的原理が「人間の良心を打つ」と断じるが、繰り返し述べているとおり、「良心」の問題は、すでにラスコーリニコフの思想において、入念な検証に耐え、克服されていたはずである。
従って、作者の言葉を信じる限り、我々は、ラスコーリニコフの苦悩の中に「良心の呵責」を読みとることはできないのだ。
レフ・シェストフ
シェストフは、ラスコーリニコフの孤独のうちに、神的原理に限らず、あらゆる既成の価値や真理の否定を見る。そして、シェストフによれば、そのような苦悩を、主人公は作者のドストエフスキー自身と共有している。
ドストエフスキーが最初にこの苦悩を託したのが『地下室の手記』の主人公であった、とシェストフは述べる。
『地下室の手記』、これは――生存の最高の目的は「最も下賤な人間」への奉仕であると自他に説いていながら、全生涯にわたって自分は嘘をつき、偽っていたのだということを突然確信した一人の男から響いた、胸をかきむしられるような恐怖の号泣である。
近田友一訳, 現代思潮社, 1968 p.52.
ここでシェストフがいう「一人の男」とは、まぎれもなくドストエフスキー自身を指している。果たして、その「恐怖」とは何を意味するのだろうか?
その内容を端的に示している一節をもう一か所『悲劇の哲学』から引用しよう。前後の文脈から切り離して抜き出すことで、分かりにくい部分があることはご容赦いただきたい。
……ドストイェフスキーは、とうとう、最後の言葉にまで言い及んだ。『地下室の手記』で多分の釈明と註釈をつけて初めて口にしたことを、彼は今あからさまに表明しているのである――いかなる調和も、いかなる思想も、いかなる愛や赦しも、要するに、古代から現代に至るまで賢人たちが考えついたもののうち、個々の人間の運命の無意味さや愚かしさを弁明できるものは何一つとしてない。彼は子供について語るが、それはただ、それでなくても複雑な問題を「単純化」するためであり、より正確に言えば、議論の中で「罪」という言葉を巧みに弄ぶ相手の武器を奪うためである。実際に、果してこの小さな拳で自分の胸を打つ子供が突然自分を「すべてのもの、すべての人々から鋏で切離したようだ」と感じたドストイェフスキー・ラスコーリニコフより恐しいであろうか?(強調は筆者による。)
若干の注釈が必要だろう。
上の引用で直接に扱われているテーマは『カラマーゾフの兄弟』におけるイワンとアリョーシャの対話である。その中で、イワンは、さまざまな児童虐待の実例を物語る。「小さな拳で自分の胸を打つ子供」とは、実の親に真冬の真っ暗な寒い便所に一晩中閉じ込められて、泣きながら神さまに祈った幼子の描写である。
イワンは、現世のすべての人々の苦しみ、特に子どもたちの苦しみによって贖われねばならない「永遠の調和」に異議を唱える。
現実の人間社会においては、実の親によるものも含め、恐ろしい残忍な幼児虐待が日常茶飯事のように繰り返される。大人の身に降りかかる不幸であれば、それは自身が犯した「罪」のせいであると言えるかもしれない。しかし、幼子になんの罪があるというのか?
このような苦しみに対して、現世において何ら救済がもたらされないのであれば、最後の瞬間に「永遠の調和」が人類に約束されているのだとしても、そんな神の王国への入場券など自分は即刻返上する、とイワンは宣言するのだ。
ここで注目すべきことは、『地下室の手記』の主人公から、ラスコーリニコフ、そしてイワン・カラマーゾフへと脈々と受け継がれる苦悩のうちにシェストフが見出したものである。
「いかなる調和も、いかなる思想も、いかなる愛や赦しも、要するに、古代から現代に至るまで賢人たちが考えついたもののうち、個々の人間の運命の無意味さや愚かしさを弁明できるものは何一つとしてない。」
つまり、いかなる高邁な理想も高遠な思想も、個々の人間の有限な生を「無意味さや愚かしさ」から救うことができない、という感覚こそが、ラスコーリニコフの「絶望的な孤独感」の正体である、とシェストフは指摘しているのだ。それは、無垢な子どもに襲いかかる不条理な苦しみに限ったことではない。
しかし、この「孤独感」は、シェストフによってドストエフスキー自身の文学的苦悩の核心に据えられることにより、抽象化され、『罪と罰』の具体的なプロットから引き離されてしまう。
そのため、シェストフは、この「孤独感」と老婆の殺害との間の因果関係は問題にせず、「なぜ、ラスコーリニコフは、犯行の直後に、突如として、そのような地獄に突き落とされることになったのか」という問いには何も答えていない。
江川卓
江川卓は、優れた評論作品である『謎解き『罪と罰』』(新潮選書, 1986)において、この「問い」に正面から向き合っている。
江川は、ラスコーリニコフが「いっさいの人間といっさいのものから、自分の存在を鋏で切り離しでもしたように」感じたネワ川上の場面を、「「人類との断絶」という抽象的な理念が、これ以上望めぬほど鮮烈にイメージ化されている場面」であるとし、彼が突きつけられたこの「直接的な感触」こそが、「ラスコーリニコフにとっての「罰」の実体であったと考えてよいだろう」と述べている(pp.158-159)。
ところで、この感触は、作者によって「これまでの生涯で彼(ラスコーリニコフ)が体験した感覚のうちでも、もっとも苦しい感覚」と表現されている。
江川は、ここで用いられているロシア語の「苦しい」(мучительный)という形容詞の語源である「苦悩」(мука)という名詞が、通常の「苦痛、苦しみ」の意味のほかに「地獄での責苦を思わせる特殊な語義」を持っていることに着目する。
そこから、ラスコーリニコフの苦悩は、地獄の苦悩、すなわち「「死によってのみ」体験可能な「感触」」、「つまりは神による「罰」の最高形態と考えればよい」と結論づける(p.161)。
さらに、これを、『カラマーゾフの兄弟』に登場する高僧であるゾシマ長老が臨終前の法話で自ら語った「地獄」観、すなわち「地獄とは、もはや愛することができないという苦悩である」という見解と結びつけ、「実は、この地獄観、苦痛観が、ラスコーリニコフの「感触」の根源に置かれていたものなのである」と結論づける。
……(老婆を殺害したことによって) 彼(ラスコーリニコフ)は自分からソーニャに告白するように、「自分自身を殺した」、「ひと思いに自分をパシリとやった」のだった。となれば、現在の彼はすでに死んでいることになり、当然、愛の不能者ということになる。それでいながら、「愛」への渇望がいまだに彼の身内から消えていないとしたら、これは不能者の愛にならざるを得ない。むろん、チャタレイ男爵など連想する必要はさらさらあるまいが、これがこの世の地獄でなくて何であろう。
江川特有の極めて緻密な分析と深い洞察であり、ドストエフスキーの世界観に迫る解釈であると言えるかもしれない。
確かに、江川が引用したように、作者はラスコーリニコフに「自分自身を殺した」と言わしめている。
しかし、ラスコーリニコフが「自分自身を殺した」のだとすれば、また、それが神による「罰」であるのだとすれば、では、なぜ「老婆の殺害」が「自己の死」に転化したのか、「生きながら死ぬ」という罰にどのような意味があるのか、という問いが残されるのである。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
