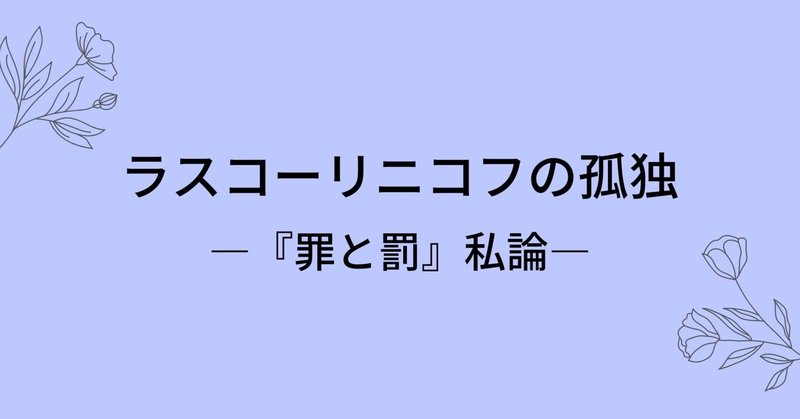
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(6)
目次
問題の所在
様々な解釈
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
前回までの要約
ラスコーリニコフが犯行直後に陥った「無限の孤独と疎外の感覚」。
それは、老婆を殺害することで、神に背き、自ら神との絆を断ち切ったラスコーリニコフが、その結果として、必然的に世界の誰ともつながることができなくなったことを、直観的に、皮膚感覚として突きつけられたものであった。
この仮説を裏付ける証拠となりうるものとして、これまでに次の事柄を挙げた。
・「ラスコーリニコフ」という主人公の姓に「神との絆を断ち割る者」という暗示が読みとれること
・ラスコーリニコフが老婆の首から紐で吊るされていた財布を奪い取ったときに、いっしょにくくりつけられていた十字架と聖像、すなわち「神への信仰のしるし」を死体の上に投げすてたこと
・ラスコーリニコフのファーストネーム・ロジオンの語源はギリシャ語の「英雄」であり、その命名の由来となった可能性があるシラーの詩「ギリシャの神々」の中に、「英雄と神と人間との絆」を意味する詩句があること
ソーニャの直観
神との絆を自ら断ち切ったことによって、あらゆる人間から切り離されてしまったラスコーリニコフの運命を、直観的に把握した登場人物が存在する。それが、ソーニャ・マルメラードワである。
ラスコーリニコフは、まだ取り返しのつかぬ犯罪に手を染める前に、酒場で偶然知り合った酒浸りの元官吏マルメラードフから、彼と前妻との間の娘であるソーニャの不幸な身の上を聞くことになる。
ソーニャは、貧しさのどん底にあえぐマルメラードフの家族たち、すなわち肺病を患う義母やその幼い子どもたちのために、進退窮まって、自分の身を売って生計を立てることを余儀なくさせられたのだ。きゃしゃで小柄な、まだ少女のような身体つきでありながら、娼婦としての生業を営む、悲惨な運命を生きる娘である。
ラスコーリニコフが初めてソーニャと出会うのは犯行の後だ。
自己を脅かす苦悩と絶望的な闘いを続けるラスコーリニコフは、ソーニャもまた、われとわが身を滅ぼした存在であり、自分と同類であると考える。
そして、ついに、ソーニャの前で罪を告白するに至る。
『罪と罰』の「第五部の四」は、ラスコーリニコフの苦しい告白を、そして、その告白をやはり絶望的な思いで受け止めたソーニャとラスコーリニコフとの対話を詳細に描く、息詰まるような場面だ。
この罪の告白の場面は、後でもう一度立ち帰って検討したいと思っている。ここでは、順番が前後するが、告白後の、ラスコーリニコフとソーニャの対話を丁寧に見ていきたい。
彼女(ソーニャ)は、まだ正気にかえれぬ様子で、深い疑惑のなかから口走った。「どうしてあなたに、あなたみたいな方に……そんなことができたんです? どういうことなんです!」(第五部 四)
(本文中の引用も含め、『罪と罰』からの引用は、江川卓訳, 岩波文庫による。)
そう問い詰めるソーニャに対して、ラスコーリニコフは取り乱しながらも、さまざまに説明を試みる。
ぼくはナポレオンになりたかった、母や妹を安心させ立身出世を果たしたかった、有害なしらみを殺しただけだ……。
しかし、ソーニャには理解できない。互いにかみ合わないやりとりの果てに、ついに、ラスコーリニコフは、犯行の真の動機をはっきりと口にする。
「ぼくはそのとき気づいたんだよ、ソーニャ」彼(ラスコーリニコフ)は有頂天になってつづけた。「権力は、あえて身をかがめて、それを拾いあげるものだけに与えられるとね。そこにはひとつ、ただひとつのことしかない、つまり、あえて断行しさえすればそれでいいんだ! そのときぼくにはひとつの考えが生まれた、生涯にはじめて、ぼく以前にはだれひとり考えつかなかったような考えが生まれたんだ! だれひとりだよ! ぼくにはふいに、太陽のようにはっきりと見えた、つまり、どうしていままでただのひとりとして、こうした不合理のそばを通りながら、その尻尾をつかんで、ぽいとほうり捨てるという、実に簡単なことさえ、思い切ってやろうとしなかった、いや、いまもしていないのか! ぼくは……ぼくは思いきってやりたかった、だから殺した……ぼくはね、ソーニャ、ただ思いきってやりたかったのさ、それが原因のすべてだ!」(同上)
長い間ラスコーリニコフの頭の中で渦巻き、膨れ上がり、やがて強迫観念となって、彼を犯行に駆り立てた暗い信念が、あたかも初めて明確な「言葉」としてかたちをとったかのような犯行声明である。
これに対して、ソーニャは、きっぱりと宣告する。
「ああ、黙って、黙ってください!」ソーニャは叫んで、手を打ち鳴らした。「あなたは神さまから離れたのです。それで神さまがあなたをこらしめて、悪魔にお渡しになったのです!……」(同上)
ラスコーリニコフの弁明はさらに続く。
自分がナポレオンのような人間なのか、そうでないのかと悩み抜くことに疲れ果て、「踏みこえることができるのか、それともできないのか! あえて身をかがめて拾うことをやるのか、それともしないのか?」それを「一刻も早く知りたいと思った」。
しかし、事がすんでしまった後になって、自分にその資格がなかったことが分かった。なぜなら、自分は「ほかの連中とそっくり同じしらみ」だからだ。
そして、ラスコーリニコフは、「絶望のために醜くゆがんだ顔で」ソーニャに問いかける。「さあ、これから何をすればいいんだ、教えてくれ!」
ソーニャは、決然と告げる。今すぐ出かけて行って十字路に立ち、あなたが汚した大地に接吻しなさい、そして罪を告白しなさい。しかし、ラスコーリニコフは自首を拒む。
「じゃ、これからどうやって、どうやって生きていくの? 何をたよりに生きていくの?」ソーニャは叫んだ。「いまさら生きていかれるものかしら? お母さまにはなんと話すつもりなの?(ああ、あのひとたちは、あのひとたちはどうなるんです?)まあ、何を言ってるのかしら! あなたはもうお母さまも妹さんも捨ててしまったのね。そう、もう捨ててしまったんだわ、捨てて。ああ、神さま!」彼女は叫んだ。「こんなことは、もうこの人が自分ですっかり承知している。でも、どうして、どうして人間なしで生きていけるの? あなたはこれからどうなってしまうのかしら!」(同上)
上で引用したソーニャの言葉の中で、太字で強調した二つの部分に注目してほしい。
「あなたは神さまから離れたのです。」「でも、どうして人間なしで生きていけるの?」
ソーニャは、本人すら分からなかったラスコーリニコフの苦悩の正体を見抜いていた。つまり、人間が「神から離れる」ことによって「人間を失う」ということを分かっていたのだ。
ドストエフスキーは、ラスコーリニコフに向けて放たれる、無我夢中の、感情のほとばしりのようなソーニャの「言葉」の中に、無造作に、しかし巧妙に「ヒント」を埋め込んでいた。そのヒントが示すものは、ラスコーリニコフには、「神」という「人間との接点」が閉ざされてしまった、ということだ。
だとすれば、ラスコーリニコフがなすべきことは、罪を償って神との絆を回復する以外はない。ソーニャには、そのこともはっきり分かっていた。
しかし、ラスコーリニコフは、まだ分かっていない。だから、自首を促すソーニャの言葉に対して、穏やかに反論する。
「子どもみたいなことを言うんじゃないよ、ソーニャ」、「あの連中にたいしてぼくがどんな悪いことをしたと言うんだ? どうして(自首に)行く必要がある?」
むしろ、ラスコーリニコフは、ソーニャとの対話を通じて、つかの間息を吹き返したようだ。「もしかすると、ぼくは、まだ人間で、しらみではないのかもしれない、自分を責めるのをいそぎすぎたらしい……ぼくはまだたたかうぞ」
自分はすでに嫌疑をかけられているので、収監は免れないだろう。もっとも、証拠不十分でいずれ釈放になるのだ。ラスコーリニコフはそう言って、「ぼくが監獄にはいったら、面会に来てくれるかい?」とソーニャに聞く。ソーニャは、もちろん行くと答える。
その直後のソーニャの言葉を、もう一か所、引用したい。
ソーニャは、ふと思い出したように「あなたは十字架をかけている?」とラスコーリニコフに問う。
「かけていないのね、そうなのね? じゃ、これをあげるわ、糸杉のを。わたしには、もうひとつ銅のが、リザヴェータのがあるから。わたし、リザヴェータと十字架を換えっこしたの。リザヴェータは十字架をくれて、わたしは聖像をあのひとにあげたの。これからわたし、リザヴェータのをかけて、これはあなたにあげるの。さあ、受けとってよ……わたしのなんだから! わたしのなんだから!」彼女はせがんだ「いっしょに苦しみましょうよ、いっしょに十字架を負いましょうよ!……」(同上)
「糸杉と銅の十字架」が再び登場する。
ソーニャは、自分の糸杉の十字架をラスコーリニコフに与え、自分はリザヴェータからもらった銅の十字架をかける、と言う。
前回とりあげたように、ラスコーリニコフは、老婆の死体の首にかかった財布を引っ張り出そうとして、苦労して紐を切り離したときに、財布と一緒にくくりつけられていた糸杉と銅の十字架を死体の上に投げすてている。
上で引用したソーニャの言葉は、この挿話と明らかに対をなしている。
おそらく、この「言葉」には、いったん切り離してしまった「神との絆」を、ラスコーリニコフとともに結びなおすという試練を引き受けようとする、ソーニャの悲痛な覚悟が暗示されているのだろう。
だから、あとでもらうよ、というラスコーリニコフに対して、ソーニャは、はっきりと言うのだ、「苦しみに行くときにいっしょにかけていきましょう」と。
* * *
ソーニャへの罪の告白の後に、ラスコーリニコフは、重荷の幾分かを肩から下ろしたように、生気を取り戻す。
ソーニャとの間に生じた真の人間的なつながりが、いっさいの人間から切り離されたと感じていた彼をよみがえらせたのだ。地獄の責苦にあえぐ主人公にとって、それは何という福音であったことだろう。
だが、自ら神との絆を断ち切ったラスコーリニコフが、どうしてソーニャと結びつくことができたのだろうか? ラスコーリニコフが、ソーニャの大切な友だちであったリザヴェータを殺したにもかかわらず、である。
さらに重大な問題がある。リザヴェータはなぜ殺されなければならなかったのか?
これらの問題を考える前に、いったん『罪と罰』を離れ、ドストエフスキーの最後の長編小説である『カラマーゾフの兄弟』の一場面に、視点を移すこととしたい。
実は、そこに、作者が「神をつうじた人間どうしの絆」というイメージを抱いていた可能性を、さらに強く示唆してくれる情景が描かれているのだ。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
