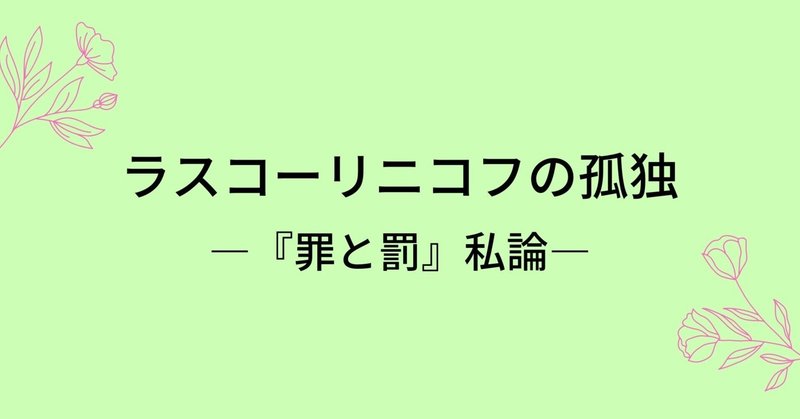
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(9)
目次
問題の所在
様々な解釈
仮説
断ち割る者
糸杉と銅の十字架
ギリシャの神々
ソーニャの直観
アリョーシャの絶望と再生
ラスコーリニコフと神
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
エピローグ
終わらない「問い」
前回までの要約
ラスコーリニコフの「無限の孤独と疎外の感覚」の正体は、自ら神との絆を断ち切った結果として、必然的に世界の誰ともつながることができなくなったことを、直観的に、皮膚感覚として突きつけられたものであった。
この「仮説」を裏付ける証拠として、筆者は次の5点を挙げた。
・「ラスコーリニコフ」という姓から読みとれる暗示
・ラスコーリニコフが老婆の死体の上に投げすてた十字架と聖像の暗示
・ラスコーリニコフのファーストネーム「ロジオン」の命名の由来となった可能性があるシラーの詩「ギリシャの神々」の中の詩句
・ラスコーリニコフの孤独を見抜いたソーニャの直観
・ラスコーリニコフと『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャに共通する「大地にひざまずき口づけをする」という行為から読みとれる暗示
そして、前回は、ラスコーリニコフと「神」との関係を考察し、無神論者でありながら、神の存在を否定しきれなかった彼の「心の在りよう」について述べた。
リザヴェータはなぜ殺されたのか?
第6回で述べたように、ラスコーリニコフはソーニャへの罪の告白によって、束の間、自己を脅かす苦悩から癒され、息を吹き返す。
それは、あらゆる人間から切り離され、もはや誰ともつながることができないと感じていた主人公が、ソーニャとの間で人間的なつながりの回復を実感したためにほかならない。
なぜそのような「奇跡」が生じ得たのだろうか?
実は、そこに「リザヴェータが殺された意味」が絡んでいるのではないか。
今回は、そのことを考えてみたい。
リザヴェータは、ラスコーリニコフの犯行計画の標的であった老婆の腹違いの妹である。
作品の中では「三十五になる未婚の娘で、臆病でおとなしく、少し頭が足りない」ようで、「姉の家にいて、夜昼なく奴隷のようにこき使われ」ていると、描かれている。
彼女は、老婆が殺害された直後に帰宅し、その現場を目撃したために、哀れにも第二の犠牲となってしまう。これは、ラスコーリニコフにとっても、まったく予定外の殺人だった。
このリザヴェータはソーニャと深いつながりがあった。
ラスコーリニコフは、はじめてソーニャの部屋を訪れたときに、たんすの上の新約聖書を手にとり(リザヴェータから贈られたものだ)、なぜか唐突に、ソーニャに向って福音書の「ラザロの復活」の箇所を読んでくれと頼む。
しかし、ラスコーリニコフの信仰心を疑うソーニャは、読むことをためらう。
「お読みになったことがないんですか?」テーブルの向こうから上目使いに彼を見あげて、彼女はたずねた。彼女の声はいちだんとけわしいものになった。
「ずっとまえ……学校にいたころには。さあ、読んで!」
「教会で聞かれたことはないんですか?」
「ぼくは……行ったことがないんだ。きみはたびたび行くのかい?」
「い、いいえ」ソーニャはつぶやいた。
ラスコーリニコフは苦笑した。
「わかったよ……じゃ、明日もお父さんの葬式には行かないわけだな」
「行きます。わたし、先週も行ってきたんです……供養をしに」
「だれの?」
「リザヴェータのです。あのひと、斧で殺されたんです」
彼の神経はますますいらだってきた。頭がくらくらしはじめた。
「きみはリザヴェータとは仲よしだったのかい?」
「ええ、あのひとは心の正しいひとでした……ここへも来てくれました……たまにでしたけれど……そうそうは来られなかったんです。でも、いっしょに読んだり……お話ししたりして。あのひとは神を見んとする方です」
この文語めいた言葉は、彼の耳に異様にひびいた。それに、彼女とリザヴェータとのどこか神秘めいた会合も、ふたりがふたりとも聖痴愚だということも、これまた新しい発見だった。
『こんなところにいたら、こっちまで聖痴愚になってしまう! 伝染するぞ!』と彼は考え、ふいに「読んでくれ!」と押しつけがましい、いらだたしい調子で叫んだ。(第四部 四)
この場面では、ラスコーリニコフから見たソーニャとリザヴェータの同質性が強調されている。
リザヴェータとソーニャは仲の良い友だちどうしだった。
ソーニャが手元に置いていた聖書はリザヴェータから贈られたものであったし、ソーニャはリザヴェータと十字架の交換までしていた。
しかも、ラスコーリニコフは、リザヴェータもソーニャと同様に「ユロージヴァヤ」であったことを「発見」する。
リザヴェータはなぜ殺されなければならなかったのだろうか?
この二人目の殺人が『罪と罰』という作品を成立させるために、必要不可欠な構成要素であったのだとすれば、そこにどのような意味が込められていたのだろうか?
作家は、本来の計画になかった無用な殺人を犯させることで、主人公の苦悩を、より深刻な、悲劇的なものとすることを意図したのだろうか?
ところが、不思議なことであるが、犯行後のラスコーリニコフの苦悩は、リザヴェータの予期せぬ殺害によって、必ずしもより強められてはいないかのようだ。
リザヴェータを思い出す場面で、ラスコーリニコフは次のように独白している。
『……かわいそうなリザヴェータ! どうしてあんなところへはいって来たんだ! それにしても妙だな、どうしておれは彼女のことをほとんど考えないんだろう、まるで殺さなかったみたいに?……』(第三部 六)
きわめて突飛で、馬鹿げた冗談に聞こえるかもしれないが、リザヴェータは、ラスコーリニコフが再生する契機となるために殺されたのではないだろうか? 読者は、実際に、そのような不可解な思いに立ち至る場面に遭遇するのだ。
以下に引用するのは、ラスコーリニコフが、リザヴェータを殺害したのは自分であることを、遠回しにソーニャにほのめかした直後の場面である。
しばらく、ラスコーリニコフと互いに顔を見つめあっていたソーニャは、ようやく事の真相を悟る。
……彼(ラスコーリニコフ)はソーニャを見た。と、その顔にリザヴェータの顔を見たように思った。彼は、自分が斧を持って近づいて行ったあのときのリザヴェータの表情を、まざまざと覚えていた。彼女は片手を前に差しだして、まったく子どものようなおびえた表情を顔に浮かべながら、壁のほうへ後じさって行った。それは、幼い子どもが、ふいに何かにおびえて、その何かをまばたきもせず、不安にそうに見つめながら、じりじりと後じさって行き、小さな手を前に差しのべて、いまにも泣きだしそうにする、その様子にそっくりだった。ところが、ほとんどそれと同じことが、いまのソーニャにも起こった。彼女は、同じように力なく、同じようにおびえきって、しばらく彼を見つめていたが、突然、左の手を前に差しのべ、指の先をかすかに彼の胸に突き立てるようにして、しだいに彼から身を引くようにしながら、ゆっくりと寝台から腰を浮かせた。彼に見すえられたその視線は、見る見る動かなくなっていった。ふいに彼女の恐怖が彼にも伝わった。同じようなおびえた表情が彼の顔にも現われ、彼もまったく同じような目で彼女を見つめはじめ、ほとんど同じように子どもっぽい微笑まで浮かんでいた。
「わかったかい?」とうとう彼がささやいた。(第五部 四)
ラスコーリニコフからリザヴェータの死の真相を知らされたとき、ソーニャが見せた反応、そのたよりない防御のしぐさと恐怖の表情は、死に直面したリザヴェータとそっくりそのまま同じであった。ラスコーリニコフは、そんなソーニャの姿に「リザヴェータの亡霊」を認め、リザヴェータの恐怖を追体験する。そして、まるで、ソーニャの恐怖が伝染したかのように、ソーニャとラスコーリニコフの間に奇妙な共感が生じるのだ。
小林秀雄は、前述の評論において、上の場面を引用し、次のように論じている。
……ラスコオリニコフが全く無意味だと嫌厭の念をもって考えた自白という行為から、彼自身にとって、又読者にとってもと言ってもいいように思われるが、或る思いも掛けぬ意味が生じている様が見られる。リザヴェエタの幽霊が出たのである。<中略> 彼は彼女の恐怖を、まざまざと感ずる。ところで、つづいて第二の意味が生ずるように見える。リザヴェエタの恐怖は、実はソオニャから貰ったものであり、ソオニャの恐怖は、彼自ら与えたものである。どうしても人と心を分ち得ないと考えている人間が、思いも掛けぬ形で人と心を分ち合う有様が見られる。<中略> 恐怖がラスコオリニコフとソオニャを一人にする。真実不思議な事ではあるのだが、恐怖が愛でないと誰に言い得ようか。……(強調は筆者による。)
『ドストエフスキイの生活』新潮文庫 pp.450-451.
あらゆる人間とつながるためのルートが閉ざされていたはずのラスコーリニコフとソーニャとの奇跡的な交感! その絆を媒介したものは、実は、リザヴェータの亡霊だった。
ここで思い起こしてほしいのは、ラスコーリニコフが、リザヴェータの殺害に、あえて斧の刃を用いたことである。
ひとつの仮説が成り立つ。ラスコーリニコフがリザヴェータに刃を向けたのは、彼女が、ユロージヴァヤ、すなわち「神がかりの狂人」あるいは「神のお使い」であったためではないか、という仮説だ。
これは、老婆を斧の峰打ちで殺害したときに、斧の刃が天に向けられたこととも符合する。
そして、この仮説に基づくなら、すなわちリザヴェータが「神のお使い」であったとすれば、ラスコーリニコフとソーニャとの絆を仲立ちしたものは、まさに「神」であったと考えられるのだ。
ここで生じた一瞬の絆は、さらに、ラスコーリニコフにとって意外な展開を導く。
ソーニャの恐怖は、彼女がラスコーリニコフを拒絶し、あるいは彼から逃れ去るという当然の成り行きへ向かわない。
ソーニャは「へたへたと寝台に倒れ、枕に顔を埋めた」。だが、つぎの瞬間、さっと起き上がり、ラスコーリニコフの「両手をつかみ、自分の細い指でひしとばかり握りしめた」。そして、「最後の希望」を見つけ出そうとでもするように、ラスコーリニコフの顔をじっと見つめるが、もはや「疑いの余地がない」ことをはっきりと見てとる。
彼女はわれを忘れたように飛びあがると、手をもみしだきながら、部屋のなかほどまで歩いて行った。しかし、すぐまた戻ってきて、また彼のすぐ横に、肩と肩をふれ合わさんばかりにしてすわった。突然、何かに刺しつらぬかれたように、彼女はぴくりとふるえ、一声高く叫ぶと、それが何のためか自分でもわからぬまま、いきなり彼の足もとにひざまずいた。
「あなたはなんてことを、いったいなんてことをご自分にたいしてなさったんです!」絶望にかられたようにこう口走ると、彼女は突然はね起き、彼の首にとびついて、彼を抱きかかえ、両手でかたく、かたく抱きしめた。
ラスコーリニコフは一歩後ろへさがり、悲しげな微笑を浮かべて、彼女を見やった。
「ソーニャ、きみも奇妙な女だね。ぼくがこんなことを言ったのに、抱きしめて、キスするなんて。自分で自分がわからなくなっているんだろう」
「あなたはこの世界のだれよりも、だれよりも不幸なのね!」彼の言葉も聞こえぬらしく、彼女は夢中で叫んだ。そしてふいに、ヒステリーでも起きたように、おいおいと泣きはじめた。
もうとうの昔に忘れていた感情が、ひたひたと彼の心に押しよせ、たちまちそれをなごめた。彼はその感情に逆らわなかった。二つの涙の玉が彼の目からあふれ、睫毛にとまった。(第五部 四)
ラスコーリニコフの告白を受ける直前まで、不幸な孤立無援の境遇にあるソーニャにとって、彼は、心からの感謝を捧げるべき恩人であった。
ラスコーリニコフは、ソーニャの父マルメラードフが泥酔のあげく路上で馬車にひかれた事故現場に行き合わせ、率先して瀕死の怪我人を家まで運ぶように尽力したり、医者を呼んだりと親身に世話を焼く。そして、その最期を見届けると、残された未亡人に対して、葬儀費用の足しにと、母からの仕送りであるなけなしの二十ルーブリ(かつてのマルメラードフの俸給に匹敵する額だ)を渡すなど、無思慮とも思える手厚い弔意を示す。
また、その葬儀後に行われた会食の場面では、卑劣な策略から窃盗の濡れ衣を着せられたソーニャを窮地から救っている。そのような経緯もあり、ソーニャにとってラスコーリニコフは、すでに特別な存在であったことは疑いない。
それにしても、リザヴェータの死の真相を告げられたソーニャの心からの同情が、リザヴェータよりも、むしろ憎むべき犯人であるラスコーリニコフに向けられたのは驚くべきことだ。このようなソーニャの偽りのない心情が、絶望的な孤独に陥っていたラスコーリニコフの心に橋を架けるのである。
上に続く場面で、前述(第6回)のように、ソーニャはラスコーリニコフに自首するよう促し、ラスコーリニコフはそれを拒む。
ラスコーリニコフは、なおもしばらく決着を引き延ばすが、結局は、ソーニャに指し示されたとおりに、広場のまんなかで地べたにひざまずき、大地に口づけをして、そして自首におもむく。
一瞬の奇跡から生じたソーニャとの一体感が、ラスコーリニコフの再生に向けた第一歩となったとすれば、彼の再生への道すじは、まさにリザヴェータとソーニャによって照らされたものであったと言えるだろう。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
