
士業はシンプルに、ヤナ場をイメージしながら事務所運営してはどうか?というお話(マーケティング編)

これは、Google写真検索で「ヤナ場」と検索した画面です。
わたしは常々、士業の事務所運営において、ヤナ場をイメージすることはプラスに働くと思っています。事務所運営の全体において、頭の片隅に常に置いておくイメージです。
ヤナ場とは、川の一部に流れの通り道を作り、そこに仕掛けを設置して、流れてくる魚を穫る場所、のことをいいます。
こんな ↓ 場所のことですね。

引用:ヤナってなに?
士業とヤナ場?
ジャンルが違いません?
というはてなマークはさて置き、読み進めてみてください。
それから、ヤナ場と書くと、顧客を漁業のように穫る、というか、尊重の念のないようなイメージを持つ方がおられるかもしれませんがそうではありません。顧客には尊敬の念をもって接し、誠実に実務を行う。これは前提です。あくまでも「シンプルに」「いつも頭に描きやすい姿」を考えると、ヤナ場になる、という話でございます。悪しからずご理解ください。
今回は【マーケティング編】です。
士業にはそれぞれストック業務とフロー業務があります。
ストック業務とは毎月(又は一定期間)固定で発生する業務
フロー業務とは、固定ではなく、都度都度、発生する業務
を指します。
ストック業務の代表格は税理士さんの顧問契約。弁護士さんや社会保険労務士さんの顧問契約もありますね。
フロー業務の代表格は(多種多様ではありますが)行政書士さんの業務全般。
厳密に言えば、ストックとフローとの中間的な位置づけとして、銀行・不動産会社と密接に関係しつつ事業を営むタイプの司法書士さんもあります。
※すべての士業で、ストック、フロー業務はあります。あくまでも各々の士業でウェイトが大きい、という話ですのでよろしくお願いいたします。

今回の「ヤナ場」は、マーケティング(営業含む)に大きく関係してきますので、そのお話を書き進めて参ります。
なお、マーケティングとは日本マーケティング協会の定義に沿って話を進めさせていただきます。
↓ ↓
「企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である」
つまり、マーケティングとは市場創造のための総合的活動であって、集客の代表格と言われるウェブサイトやチラシ、営業活動は一部にすぎない、という考え方ですね。
ちなみに、士業の実務もマーケティングの一部と言えると私は考えています。
さて、士業は「集客」を苦手とする職業だといえます。
なぜなら、一般的な商売のように「いいよ!又は安いよ!」とアピールしにくいですし、昔は広告に規制があるほどの職業だったので、一定の法律の縛りもあります。他業種との連携(コラボ)に際しては、相互紹介フィーの仕組みを取れないなどの縛りもあります。
そしてそもそもなんですが、部屋にこもって勉強して合格してからなるのが士業(一部、公務員の特認の方を除く)。
マーケティングの専門部署、営業部署等を経験した人が少ないのも要因かと思います。
集客の問題は、事務所の歴史が浅ければ浅いほど深刻です。
事務所運営を3年以上やっている先生であれば認識している方が多いと思いますが、集客に苦労する事務所は、実は実務にも苦労します。
なぜかと言うと、期待する顧客層からの依頼を得ることができないからです。
期待する顧客層とは、各々の事務所で像があると思いますが、共通点としてはこのような感じではないでしょうか。

・お願いしたことはきちんと約束の日までにしていただける
・値引きをしない
・相見積もりを取って価格で判断しない
・イレギュラーな事態が起こらない
・あなたの事務所だから依頼したいという想いが多少なりともある
その顧客層が来ない。
えてして逆の顧客層で染まってゆきやすい。
依頼者さんが他の依頼者さんを連れてきてくださることの多い職業ですので「染まりやすく」なります。
具体的には、
イレギュラーが多く、自然と生産性が低い案件が多くなり、中には「させてやっている」という思考の顧客もいて顧客満足度も低く、体力と心がすり減る。
代表先生だけならまだしも、職員さんがいる事務所では、事務所全体が疲弊してゆく。組織にマイナス感情が蓄積してゆく。
高い離職率と呼応する新規採用コスト。引き継ぎと育成期間の労務コスト(これジャブみたいに経営に響く…)が発生します。
そして何よりも、代表先生の心と身体を蝕みます。これもキツい。
まだ他にもありますけども、要は、
案件の入り口をしっかり考えないと、途中の実務も、出口の顧客満足度まで悪くなる、そして事務所全体に影響し続ける、という事態になってしまうわけです。
特に相手(顧客)が個人や中小零細及び中小企業であれば、この傾向が強くなってゆきます。
ずさんな入り口からの案件遂行の結果は、ストック業務、フロー業務共通ですが、どちらかといえば、ストック業務のほうが長く、ボディブローのように、事務所運営に悪影響を及ぼします。
ではどうすれば、最適な入り口とすることができるのか?言い換えると、どうずれば期待する顧客層が来てくれるのか?
私は「常にヤナ場を意識する、ヤナ場を構築する努力をする」が、極めて重大な要素の一つだと思うのです。
ヤナ場とは、先述のとおり「川の一部に流れの通り道を作り、そこに仕掛けを設置して、流れてくる魚を穫る場所」です。
写真も再掲いたしますね。

あなたが士業だったとして、あなたが来て欲しい顧客が流れている「川」というのが必ずあります。
士業ごとの立地、人柄、得意分野などに応じて、川の本流がそうかもしれませんし、支流に流れているのかもしれません。
どの川にヤナ場を設置するのか?
川のどの部分にヤナ場を置くのか?
この要素を深掘りして、知恵を絞って、やってみる。
そして、マーケティングの究極的な目的は
「販売(クロージング)を不要にする」ことにあります。
顧客が来てくれた時には、すでに依頼する気持ちが醸成されており、あとは費用、期間等の必要事項を伝えることが背を押す行為になり、その場で実務の内容の打ち合わせに自然に入ってゆける、という状態。
集客においての士業の理想形だと思いませんか?
自分のキャリア、人脈、取り扱いサービス、商圏、出店形態(路面、アクセスのしやすさ、広さ、自宅兼など)によって、それぞれのヤナ場の作り方は違ってきます。
ヤナ場を作っても、顧客が流れてこずに不完全と判断したら、めげずに構造を改造する、ブラッシュアップする。
ヤナ場で期待する顧客層と出会えない場合は、川上を見にゆき、何かを設置して、自分のヤナ場に流れてくるよう、整える。
失敗と判断したら、次のヤナ場を設置する。
一つのヤナ場がうまく機能し始めたら、次のヤナ場の設置場所を探し、設置作業に入る。
誰かが特別に何かの判断をすることなく、自然と、期待する顧客と出会う接点があり、自然と依頼につながってゆく姿が、ヤナ場を作る、ということになります。

ヤナ場がうまく機能し、期待する顧客層が入ってくると、誠実に応対する限り(実務の大変さは変わらずありますが)、事務所全体が良い循環に入っていきやすくなります。
先生と事務所に一定の尊重の念を持ち、信憑資料の用意を、お願いした時期にしっかりと行っていただける依頼者さんと一緒に仕事をする。
依頼者さんが先生はもちろん、職員さんにも誠実に対応してくださるため、みんなにストレスが少なく、やりがいへとつながりながら進んでゆく実務。
支払は速やかになされ、結果、堅調に売上が立ち、適正な利益と、次への投資の原資も確保できる。
これは、質の良いヤナ場を設置するからこその結果だと思います。
良いヤナ場が機能するその先には
「先生だから」の依頼の減少と
「事務所の代表者がそういえば先生」という、事務所全体が仕組み化してゆくことにもつながります。
※名前で名指ししてほしいのか、事務所として名指ししてほしいのか、という代表先生の志向にもよります。
次に、具体的なヤナ場の例について挙げさせていただきます。
・先生が来てほしいと期待する顧客層が通る川、すなわち、目につく場所に、さりげなく先生の事務所の販促物が置いてある状態(場所の管理者に対しての話の持って行き方、協議の仕方、相手方へのメリットの提供)
・先生と価値観が合致する「キーマン」が、いつなんどきでも先生や事務所の案内ができるように、連絡先等の情報周知がなされている状態(先生と事務所を勧めたくなる定期的な動機づけ)
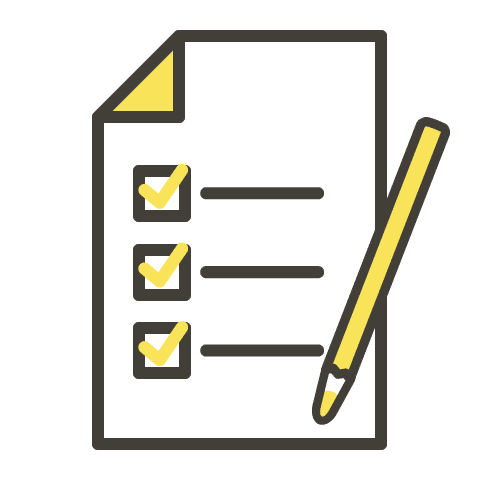
・先生のやりたいサービスを先生や職員さんに代わって勧め、受任の一歩手前まで進めておいてくれる会社や組織(いわゆる、販売チャネル)

・先生の主要取扱いサービスが企業向けであれば、当該企業にとって欲しいサービスの情報が、苦労せず入手できるようになっている状態

・先生や先生の事務所を勧めることが第三者でも可能となるくらいの「旗印」と、第三者が一言で先生や事務所を言い表せるくらいの「ブランディング」

・異士業から「この問題・手続だったらこの地域ではこの先生しかいない」と言わせるくらいの実績と周知。同業からも推薦されるくらいのブランディング

・普通思いつかないような「器を作るため」の企画(結果的に、期待する顧客層が通ってくれる川になる)

・同業、異士業から「先生・事務所を紹介しても不義理はされない」という信頼感の醸成

・先生や先生の事務所を勧めたいと思う人が、第三者に難なく情報提供できるようなウェブサイトの整備、SEOやMEO、販促ツールの用意

・紹介くださった元に対して、感謝の意を伝える(または紹介フィーを支払う)ために、事務所のルーチン業務として遂行可能な体制(そういえばお礼と報告しなきゃと思い出さないと実行されない状態からの脱却)

・業務提携の種類と内容をしっかりと学び、提携候補先にどのように話を出し、どのような契約書面を出し、どう維持してゆくのか、の、研究と経験

・期待する顧客層がテレビ視聴層であれば、CMの放映や、地場テレビ番組への出演(どうすれば出演まで進めるのか、も要研究です)

・マーケティングのうち、販促施策の効果を判断することができるための知識(マーケティング基礎、原価管理等)の研鑽
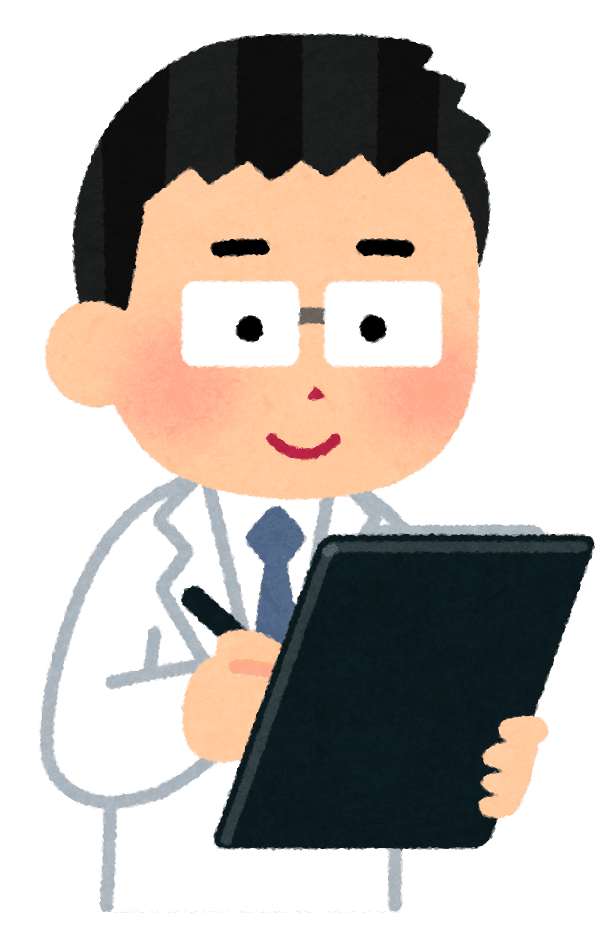
これら以外にも、ヤナ場を設置するためには、様々な施策や要素があります。出店の立地や人脈という側面で考えると、また別の施策が出てきますね。
あれ?そんなこと?
これが具体例?
と思う士業の先生、おられるかもしれません。
いわゆる「成功」している士業の先生や、成功への道を歩んでいる先生にとっては普通のことかと思います。
10年くらい前からでしょうか。
・人づてで紹介いただいて士業の先生からのご相談を承る中で
・私自身も士業法人を経営する中(現在は事業承継)で
・同じフロアで税理士、司法書士、土地家屋調査士さんと日々のやり取りをする中で
・士業のグループを立ち上げ、役員をさせてもらう中で
すごく感じます。
やっぱり、ヤナ場を設置するという意識は大事だよね・・・と。
これができていない先生は苦労し、できている先生は苦労が少ないし「普通じゃん」と思う。できている先生は、ヤナ場作りを継続して作り出し、愚直に、誠実に維持管理しておられます。すごいなと思いますね。
事務所運営がうまくいっていない先生の中でも「普通じゃん」と思う方がいるかもしれません。
ただ、こんな時はありませんか?
・何となくチラシを作る
・〃 名刺を作る
・〃 DMを作る
・〃 ウェブサイトを作る
・〃 ブログを書く
「なんとなく」をずっと繰り返している先生は多いと私は感じます。
一貫性がないんです。
根底に「ヤナ場」を意識しつつの施策とそうでない施策は、その効果に大きな差を生みます。
または他の原因として、期待する顧客層がぼんやりしている、というのも、うまくいっていないもあるかもしれません。(この顧客層をマーケティング用語で「ペルソナ」と呼びます)
今回は、士業はシンプルに、ヤナ場をイメージしながら事務所運営してはどうか?と題して、そのマーケティング編、ということで書かせていただきました。
ただ、述べてきましたヤナ場も有力な手段の一つに過ぎません。
手段の前に思想があり、思想の次にはそれに基づいた志向があり、志向の次には、事務所全体の姿勢(=イズムの沈殿など)があります。
たくさんの要素が積み重なって調子の良い事務所、悪い事務所ができあがっているわけですね。
今回は、マーケティング編、ということでそれ中心に書かせていただきましたが、実は、ヤナ場は、人材採用と育成にもつながります。
このお話も今度、書きたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
