
理想の自分をつくる セルフトーク・マネジメント入門
持てる力を十分に活かしきれない原因の対策として、自分自身との対話(セルフトーク)に着目した本。
「セルフトーク」
意識、無意識に関わらず終始自分の内側で繰り広げている。
➜自分に言葉を投げかけ、答えを作り出そうとしている。
=「コーチ」と「クライアント」の一人二役状態。
良い問いかけ。
➜ポジティブになる。
=パフォーマンス向上。
悪い問いかけ。
➜ネガティブになる。
=パフォーマンス低下。
<PART1 セルフトークとは何か>
🐾セルフトークと行動
「セルフトーク」
人間の感情や行動を左右する「特別な独り言」
内側のセリフがスイッチになる。
例)
部下を大声で叱りつけてしまう上司の場合。
部下の報告から大爆発までのフロー。
①報告に対して「許せない」というささやきが自分の中に生まれる。
②視野が狭くなり、目の前の部下以外見えなくなる。
③胸の辺りが圧迫され、息が詰まる。
④大爆発(「バカヤロー」)
「許せない」という内側のセリフが大爆発のスイッチ。
➜「許せない」=セルフトーク
対策)
=スイッチを変える。
「許せない」➜「何があったんだろう?」
=セルフトークを変える。
「何があったんだろう?」
相手が叱るべき部下から、育てなければいけない子供のように見えてくる。
「セルフトーク」
感情や思考、行動の引き金として自分の中に生まれる「言葉」
刺激の多い環境下では大量のセルフトークが生まれる。
➜努力して意識しなければ捉えられないほど速く流れていく。
=感情、行動に結びつかないセルフトーク。
形にならないセルフトークのパフォーマンスへの影響。
例)
ゴルフの場合。
よいショットが打てたとき。
➜インパクトの瞬間は何も考えていない。
失敗する確率が高くなるとき。
「200ヤードは飛ばさないと・・・」
「ここでOBになったら・・・」
➜ネガティブなセルフトークに捉えられている。
ビギナーズラックの仕組み。
初心者=失敗して当たり前。
➜成功体験もない。
=ネガティブなセルフトークが生まれない。
知識、成功、失敗の経験もないので自然体でいられる。
=緊張なく行動できる。
ネガティブセルフトークが生まれる理由。
➜アイデンティティを守るため。
「アイデンティティ」
・自分はこうあるべきだ。
・他人からこのように見られたい。
=自分にとって非常に重要なセルフイメージ。
➜本能的に持ってしまうもの。
「実際の自分」=「自分が持っているアイデンティティ」
➜快適な思いで過ごせる。
「実際の自分」≠or≒「自分が持っているアイデンティティ」
➜ギャップが有るとき。
=不快感が生じる。
ギャップがあるとき。
「失敗したくない」
「どうしたらいいんだ?」
「なんで自分が・・・」
➜ネガティブなセフルトークが生まれる。
=生存本能に対するアラーム。
アイデンティティ
➜些細な刺激に対して敏感に反応するもの。
アイデンティティが揺らぐ。
➜取り戻そうと焦る。
=セルフトークが生まれる。
セフルトークが雑念になってパフォーマンスの低下につながる。
=アイデンティティが危うくなる。
➜セルフトークが生まれる。
=悪循環
アイデンティティを守りたい。
➜非常に強力な思い。
例)
中小企業経営者が自殺する場合。
事業の失敗で借金が返せなくなった。
「自分が死ねば保険金がおりる」
・自分は借金を踏み倒さない。
・自己破産して迷惑をかけない。
・責任感のある人間だ。
※生きるために持つものであり、命を捨てても守りたいと思うもの。
➜アイデンティティ
コンプレックス(劣等感)
自分の理想像をアイデンティティにしているために生まれるもの。
➜セルフトークも生まれやすくなる。
思春期
アイデンティティも現実の自分も不安定。
➜アイデンティティが常に刺激を受けている。
=セルフトークが多くなる時期。
セルフトークを処理できない子ども。
➜思春期特有のトラブルを起こす。
価値観、世界観への刺激でもセルフトークは発生する。
「ビリーフ(belief)」
・アイデンティティ
・価値観
・世界観
=セルフトークを生み出すもの。
「刺激(stimulus)」
➜ビリーフに影響を与えるあらゆる出来事、環境。
セルフトークが感情、行動に影響を与えるプロセス。
①判断基準のビリーフがある。
②ビリーフが刺激を受け、セルフトークが発生する。
③セルフトークが感情を決定する。
④感情によって行動が決定する。

科学的に証明することはできない。
➜自分自身をコントールすることはできる。
🐾セルフトークマネジメント
「行動」を直接変えることは難しい。
「論理療法」
現在主流の認知行動療法に影響を与えた心理療法の手法。
➜イラショナル・ビリーフによって歪んでしまった非合理的心情を修正し、症例を治療する。
「イラショナル・ビリーフ」
=誤解や先入観。
例)
自分はモテない(先入観)と思っている男性の場合。
130人の女性に声を掛ける。
➜30人はすぐに立ち去り、100と会話。
結果)
・自分は女性に話しかけることはできる。
・自分が話しかけても最悪のことは起こらない。
➜ラショナル(合理的)な事実を認知できた。
=論理療法、認知行動療法の有効性。
行動を変える。
➜ビリーフも変化する。
=自分を変える。
※多くの人は行動できないから困っている。
例は例外。
➜行動力のある人なら可能。
=モテない人が「自分を変えたい」という理由だけでは耐え続けることはできない。
➜行動を自分一人で変えるのは難しい。
「やってみればいい」
➜「やれないから困っている」
=堂々巡り
「感情」を変えるという考え方。
「ポジティブシンキング」
「アファメーション」
➜自分に宣言する肯定的な言葉。
=意欲や感情を直接的に変えようとする手法。
例)
「前向きに考えよう」
「オレはできる!と10回繰り返してみましょう」
など。
一定の効果はある。
「ダウト(doubt)」
語源は「ダブルハート(double heart)」
➜心が2つある時(セルフトークが生まれたとき)
=「疑う(ダウト)」
ポジティブシンキングの後に出てくるセルフトーク。
「ホントにできるわけないだろう」
「こんなこと言って大丈夫なのか?」
➜ネガティブなセルフトークが生まれる。
=ダブルハート状態。
自覚なしのポジティブな言葉。
➜達成できずに力尽きて元の自分に戻る。
ビリーフを変えるという考え方。
行動=ビリーフに刺激を受けることがスイッチ。
ビリーフが変わるとき。
➜経験したことがないほどの衝撃を受けたとき。
=簡単にビリーフは変わらない。
ビリーフ=アイデンティティ=自分自身
ビリーフを変える。
「自分自身がなくなってしまう」
「自分が別のものになってしまう」
➜強い抵抗感をもつ。
=恐怖
ビリーフ➜セルフトーク➜感情➜行動
「ビリーフ」
「感情」
「行動」
➜変えようとしてもうまくいかない。
セルフトークを変える。
セルフトーク=「言葉」
言葉を生み出す脳の部位
=前頭葉。
前頭葉
➜人間らしい感情や意欲も司っている。
セルフトークを変える。
➜前頭葉内で感情も変わる。
=感情の変化で行動も変わる。
感情➜曖昧で掴みどころがない。
セルフトーク
➜明確に認識でき、司ることのできる「言葉」
セルフトーク
=セフルコントロールのためのハンドル。

🐾PART1まとめ
・人の判断基準はビリーフ。
(アイデンティティ、価値観、世界観)
➜ビリーフが刺激を受けるとセルフトークが発生する。
=感情と行動に影響を与える。
・ビリーフ、感情、行動を直接変えることは難しい。
➜セルフトーク=言葉=変えやすい。
セルフトークを変える。
➜感情や行動を変えられる。
=セルフコントロール
<PART2 セルフトーク・マネジメントのための基礎知識>
「感情」のセフルトークA「automatic(自動的)」
➜自分の意志にかかわらず自動的に「生まれる」セルフトーク。
・ポジティブな感情、反応を導くもの
・ネガティブな感情、反応を導くもの
行動やハッキリとした感情に結びつかない場合。
➜「雑念」
「理性」のセルフトークB「bear(生む)」
➜自ら「生み出す」セルフトーク。
=原則、有用な存在。
セルフトークBの活用。
➜セルフトーク・マネジメントのポイント。

🐾「反応」と「対応」
反応➜感情によって引き起こされる行動。
=「感情的反応」
対応➜理性によって引き起こされる行動。
=「理性的対応」
「感情➜反応」と「理性➜対応」の違い。
=「目的」の有無。
➜受け身か積極的かの違いでもある。
例)
目的をもって悲しむ。
➜感情ではなく演技。
目的を持つ。
➜セルフトークBによる理性的、積極的な行動になる。
「怒る」と「叱る」
ビリーフに刺激を受ける。
➜セルフトークAが生まれる。
=「怒る」
➜自分をコントロールできない状態。
セルフトークAが生まれる。
➜セルフトークBで修正。
=理性的な対応の「叱る」事ができる。
➜自分をコントロールできた状態。
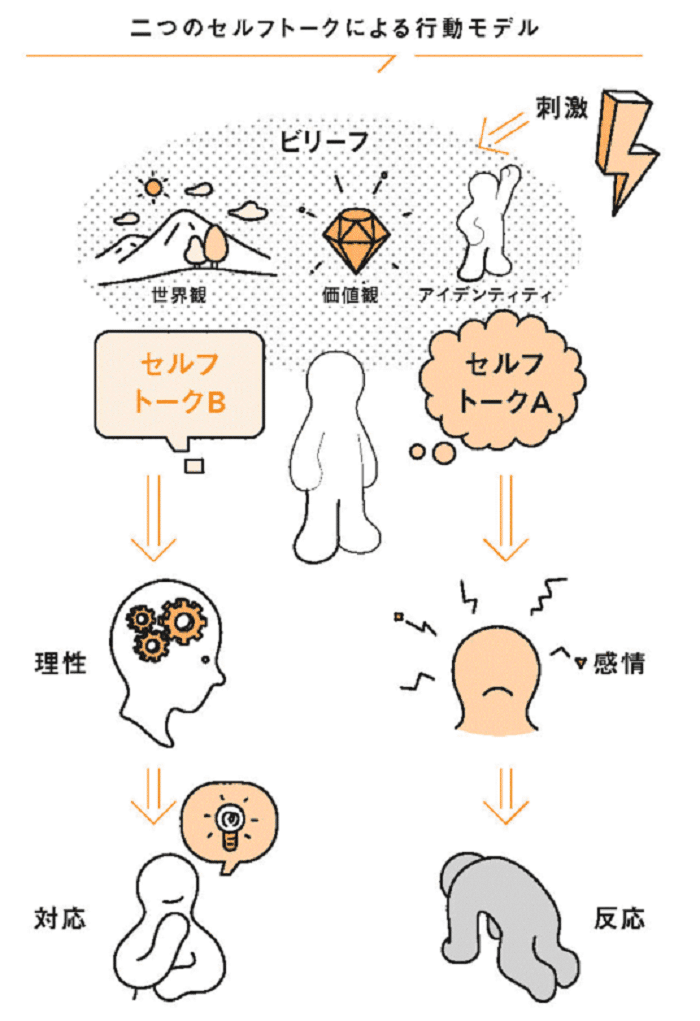
他人に対する行動。
感情にとらわれ、コントロールを失った状態。
➜「反応」による行動。
・自分のために戦う。
・自分のために逃げる。
「対応」による第三の選択肢。
➜「相手のために」何ができるか?
セフルトークマネジメントのイメージ。

🐾PART2まとめ
・セフルトークの種類。
自動的に生まれるセルフトークA
➜反応を生み出す。
自ら生み出すセルフトークB
➜対応を創り出す。
・セルフトークAの反応の種類。
ボジティブな反応
ネガティブな反応(少ないほどよい)
<PART3 セルフトークを「変える」>
ネガティブな感情から脱する方法
セルフトークを「変える」目的。
「緊張」「怒り」「不安」「後悔」「恐怖」
➜ネガティブな状態から回復するため。
🐾「変える」プロセス
①「認識」する。
・自分がネガティブな状態にあること。
・原因であるセルフトークAを認識すること。
②置き換える。
原因であるセルフトークAをセルフトークBに置き換える。
➜理性としての行動に戻す。

※「認識すること」はセルフトーク・マネジメントにおける重要な基本。
セルフトークを認識する訓練。
➜さまざまな場面におけるセルフトークAを書き出してみる。
=常にセルフトークを捉えられるよう意識しておく。
自分への質問でセルフトークを変える。
パワー・オブ・クエスチョン(質問する力)
➜セルフコーントロールの成否が決まる。
質問=セルフトークB
《質問1》
肯定・自責の質問
否定質問から肯定質問へ変える。
肯定質問=未来を創る力。
否定質問=対象、自分の未来を否定する。
例)
忙しい時期の会議の場合
否定質問(セルフトークA)
「この忙しい時期に、なんで会議ばかりなんだ?」
➜自分の仕事を増やすもの。
肯定質問(セルフトークB)
「この会議を建設的なものにするために、何ができるだろう?」
「会議の時間中にストレスを感じないために何ができるだろう?」
➜環境に働きかけられるというスタンスを生みだす。
=さらなる肯定質問も生み出す。
否定質問
➜周囲の状況に「反応」
肯定質問
➜「対応」により環境、相手に対して第三の可能性が広がる。
肯定質問と否定質問の関係。
➜「自責の質問」と「他責の質問」の関係。
肯定=すべてが自分次第。
➜他者や環境に働きかけることができるという考え方。
否定=すべて他人のせいだから。
➜自分には何もできないという考え方。
《質問2》
相手の背景を探る質問
➜対人関係においては非常に有効。
例)
管理職への部下に対する質問の場合。
「その部下にとって、今、一番つらいことは何だと思いますか?」
「彼にとって忘れられない成功体験は何だったでしょうか?」
「二度と思い出したくないような失敗は何でしょうか?」
➜部下の視点で世界を見ることができる。
=部下への認識が変わる。
《質問3》
視点を変える質問
例)
問題の解決。
そのままの状態で解決しようとする。
「どうしたら解決できるんだ」
「絶対に無理だろう・・・」
➜セルフトークAがざわつく。
視点を変える。
➜自分の能力を上げる。
相手とのコミュニケーションの問題。
➜自分のコミュニケーション能力を上げる。
=問題が小さくなる。
問題の視点を変える。
➜新しい出口が見つかる。
セルフトークの質問の視点を変える。
いつも同じ質問をする
➜いつも同じ答えが返ってくる。
質問を変える。
➜これまでにない答えへの検索が起こる。
※よい問いとは新しい検索を起こすような質問。
行動への影響力を上げる方法。
・セルフトークBを言葉として口に出す。
➜口に出して耳から聞く。
・紙に書き出す。
➜書き出して目で見る。
=セルフトークをハッキリ意識できる。
セルフトークを変える例

🐾パターンを整理する
変えるべきセルフトークA(ネガティブ)を整理。
自分を失わせる2つのパターン
1.「もしも~しなかったら・・・?」
(if not?)
例)
「もし面接に失敗したらどうなるのか?」
「スピーチがうけなかったらどうしよう」
➜不確定なこと(未来)に対する否定、自責質問。
2.「どうしてこんなことに?」
(why not?)
例)
プレゼンや面接でつまずいた場合。
「あれ?こんなはずでは・・・」
不本意な状況に巻き込まれた場合。
「なんで私が?」
➜すでに確定した(過去)に対する否定、自責質問
セルフトーク全体の分類。
自他の軸と時間軸の4つに分類。
「セルフトーク」
➜アイデンティティを守るために生まれるもの。
=「自分」しか基準になりえないもの。
「他人」
➜環境を含む自分以外のすべて。
「時間」
➜「未来」(if)と「過去」(why)
=「自分」も「他人」も含む絶対的な軸

セルフトークを「変える」
=図の下2パターンを上の2パターンに変える。
変えなければならないセルフトークは2つ。
有効な質問(セルフトークB)
直接的➜「肯定と自責の質問」
間接的➜「相手の背景を探る質問」
「視点を変える質問」
🐾PART3まとめ
・ネガティブなセルフトークAを認識する。
➜セルフトークBに変える。
=反応を対応に変える。
・ネガティブなセルフトークA
「もし~しなかったら・・・?」
(if not?)
「どうしてこんなことに?」
(why not?)
・置き換えるセルフトークの代表例。
「肯定・自責の質問」
「相手の背景を探る質問」
「視点を変える質問」
<PART4 セルフトークを「使う」>
行動を強化・修正する方法。
🐾使う
セルフトークAの発生に関わらずセルフトークBを使う場面。
例)
プロジェクトを動かす場合。
ゴールから逆算。
「半年の準備期間で何をやる必要があるか?」
「どの部下をメンバーに入れるべきか?」
「どの上司を味方につける必要があるか?」
➜「思考」という形でセルフトークBを使う。
意識して行う行動
➜セルフトークBが関わる。
仕事の要領がよい人。
段取りがよい人。
=頭の中で創り出す質問が優れている人。
「頭のよさ」
➜セルフトークの使い方がうまい。
セルフトークを「使う」目的。
セルフトークBを意識的に生み出す。
➜自らの行動を強化・修正すること。

🐾考える
セルフトークを使う。
=「考える」
悩むこと
私は〇〇ができていない。
「困ったなあ」
「どうしよう」
「どうしたらいいの?」
➜ウダウダすること。
=同じところをぐるぐる回っている状態。
➜セルフトークAの「反応」
考えること
私は〇〇ができていない。
「じゃあ、できる状態とはどんな状態だろう?」
「誰ができていると思うんだろう?」
「あの人はどうだろう?」
➜使った時間だけ発見や吸収があること。
=答えに至る問を自分の中で立てるプロセス。
➜セルフトークBの「対応」
「悩む」「考える」2つの違いを意識する。
➜知的生産の効率は格段にアップする。
得意な領域
➜意識、無意識的に問いを立て考える。
=セルフトークBを使う。
不得意な領域
➜悩むことに終始する。
=セルフトークAに身を任せる。
※問いを立てられる領域で、問いの棚卸しをしてみる。
➜問いをたてられない領域で、問いを検討してみる。
🐾使い続ける
わかったつもりになる。
➜考えなくなる。
=知ることをしなくなる。
どの分野でもうまくいっている人。
「自分はどうするべきか?」
「どうあるべきか?」
➜常に自分への質問をつくり続けている。
※わかったつもりにならないことが大事。
スイッチを用意しておく。
➜場面に応じたルフトークBを用意する。
=事前にセルフトークBを準備しておく。
例)
厳しい態度で当たらなければいけないとき。
「逃げない」
セルフトークを減らして集中したいとき。
「fear into power(恐れを力に)」
いつ、どのような状況で、どのセルフトークBを使うのかを定めているということがポイント。
スイッチをルーティンとしてくり返す。
➜成功体験と結びつく。
=協力なスイッチに成長する。
🐾コントロール
セルフトークAがネガティブを強化する仕組み。
例)
緊張している場合。
「緊張してはいけない」
=ネガティブなセルフトークA
セルフトークA(否定文、否定質問)
➜対象を呼び起こす力がある。
=否定されているものを思い浮かべる。
例)
「緊張してはいけない」
➜「緊張」を思い浮かべてしまう。
=「緊張」が強化されてしまう。
セルフトークBを使った逆説療法。
「逆説療法」
修正する対象を否定せず、とことん推し進めてみようとすること。
例)
緊張に対する場合。
「緊張するな」(セルフトークA)
➜「よーし、もっと緊張しろ!」(セルフトークB)
・「手は震えろ」
・「顔よ、赤くなれ」
・「汗はどんどん吹き出せ」
など。
Aを感じたらBへ変換させる。
➜自分を客観的に見るようになる。
=「可笑しさ」を呼び、緊張のレベルが下る。
BをスイッチとしてAをブロックするのも有効。
逆説療法でクセを直す。
クセをセルフトークBによって強調する。
➜「意識的に」クセをする。
=コントロールできるものにする。
➜クセをやめるという選択肢が選べるようになる。
クセを直そうとする。
➜クセはコントロールできないという気持ちが強くなる。
=直すことを諦めてしまう。
「やめる」ではなく「うまく」する。
➜クセや行動を自分でコントロールできるようになる。
🐾PART4まとめ
・セルフトークBを意図的に生み出して「使う」
➜行動を強化、修正できる。
・得意な領域➜セルフトークB を使う。
=考える。
不得意な領域➜セルフトークAに身を任せる。
=悩む。
・セルフトークBの使い所をあらかじめ決めておく。
➜行動のスイッチとして使う。
<PART5 セフルトークを「減らす」>
集中力を高める方法。
🐾セルフトークを「減らす」意味
「減らす」とは?
・すでに生まれてしまったセルフトークAを減らす。
・セルフトークAが発生しないようにする。
➜ネガティブな感情そのものが起こらないようにする。
生まれてしまったセルフトークAへの対処法。
➜セルフトークBに「変える」こと。
=ポジティブに置き換えて感情、行動を変える。
注意)
あまりにストレスが多い場合。
就寝前など行動する必要がないとき。
➜「減らす」ことに専念してもよい。
セルフトークAを認識して「減らす」
セフルトークAが感情、行動を左右する状況。
=「無意識」であることが必要。
無意識=知らず知らずのうちに影響される。
意識して言語化する。
➜「解決すべき課題の一つ」になる。
例)
座禅、内観、瞑想など。
➜自分の内側と向き合う行動。
=無意識の言葉に気づくこと。
無意識に考えていることが多い状態。
➜多くのメモリが使われている状態。
=気持ちのよくない非効率な状態。
※セルフトークAと向き合う自分なりのやり方を見つける。
セルフトークAが生まれないようにする。
➜心と身体を整える。
=セルフトークマネジメントにおいて重要。
雑念、ネガティブ感情が生まれるとき
➜高ストレス下、体調不良時
=ストレス低減、体調回復が重要。
「自分はまだまだ大丈夫」
「やる気を出せばなんとかなる」
➜一時的な気休めにしかならない。
健康維持と体力向上に努める。
➜セルフトークAへの対応力が高まる。
=セルフトークAが生まれにくくなる。
ストレス状態を認識する。
➜なくそうとするより認識が大事。
主観的な数値でストレスレベルを測る。
➜自動矯正が起こる。
例)
快適な状態を0とする。
「今は80点、かなりたまっている」
「今は30点、まだ気持ちがラク」
「ストレスがたまっている」と確認する。
➜小さなことでも腹が立ちやすい状態だと意識できる。
=意識的に感情の爆発を制御するように気をつけられる。
ストレスに対する有効な捉え方。
➜「その気になればいつでも気分転換できる」
=ストレスは自分で「終わらせる」ことができる。
ストレス➜始まりと終りがあるもの。
=俯瞰した見方。
➜ストレスへの耐性が強くなる。
成功体験のきっかけをルーティンにする。
例)
面接の場合。
椅子に座る前に深呼吸をした。
➜落ち着いて話すことができた。
=深呼吸をルーティンとして毎回行う。
ルーティンの対象。
➜絶対に失敗しないこと。
=簡単なこと。
ルーティンを粛々とこなす。
➜セルフトークAを減らせる。
=集中できる。
※慣れてきてもルーティンは必ず守る。
相手のことを考える。
➜セルフトークAを減らせる。
セルフトークAになりやすい状況。
➜自分を守ろうとしているとき。
例)
「失敗したら『私は』どうなるんだろう」
人が実力を最大限発揮するとき。
=他人のために行動するとき。
例)
母親が強い。
➜子供のため。
宗教の熱心な勧誘
➜世界や相手のため。
スピーチ、プレゼンの場合。
相手に貢献できるかに焦点を変えてみる。
「みんなにいいところを見せたい」
➜「出席者のためには何を伝えるのが役に立つか?」
「できる人間だと思われたい」
➜「相手の仕事をより快適にすることができるか?」
「私」「あなた」を区別しない。
➜「私たち」という全体をイメージする。
「私たちの中で話し合っているんだ」
「私たちが成功するためにはこうしたい・・・」
➜セルフトークを変える。
=緊張することは少なくなる。
自分が言いたいこと(want)にする。
➜セルフトークAを防ぐときの鉄則。
言わなければいけないこと(must)が増える。
➜セルフトークAが生まれやすくなる。
=緊張しやすくなる。
must=決まり文句
➜自分の頭を精一杯使っていない。
=他のことを考えてしまう。
例)
電話口での最初のひと言。
「お世話になっております」
➜頭の中では別のことを考えている。
他のことを考えている。
➜セルフトークが生まれやすい状況。
wantを話しているとき。
➜頭を精一杯使っているとき
=余分なセルフトークが生まれる余地がない。
「レッテル」
人は周りの人を「概念化」して捉える傾向がある。
➜非常に少ないデータで人の傾向自体を判断しようとする。
例)
第一印象
「この部下は自分に挨拶にこない、だから反抗的」
「感情的に怒られた、だから、自分を嫌っている」
➜一つの言葉で相手をくくる。
ネガティブなレッテル
➜セルフトークAを生み出す。
ポジティブなレッテル
➜セルフトークBを生み出す。
レッテルを剥がす質問。
・どこでそう思ったのか?
・その判断をするのにどれだけのデータがあるのか?
・その判断をくつがえすデータはないのか?
➜セルフトークB
「未完了」のないコミュニケーション。
・言いたいことを言い合う関係。
・伝えるべきことが伝わっている関係。
「未完了」
・いえなかったこと
・やらなかったこと。
➜記憶から薄れてもトゲは必ず残る。
=セルフトークAのもとになる。
対話での「未完了」を減らす。
➜先延ばしを減らす。
=セルフトークAも減らせる。
「パーソナルファウンデーション」
(自己基盤)
①健康
②人間関係
③お金・仕事
④身の回りの環境
➜それぞれの課題を明確にする。
=自己の基盤をより確かなものにする。
パーソナルファウンデーションのチェックリスト。
➜未完了を減らすことが可能。

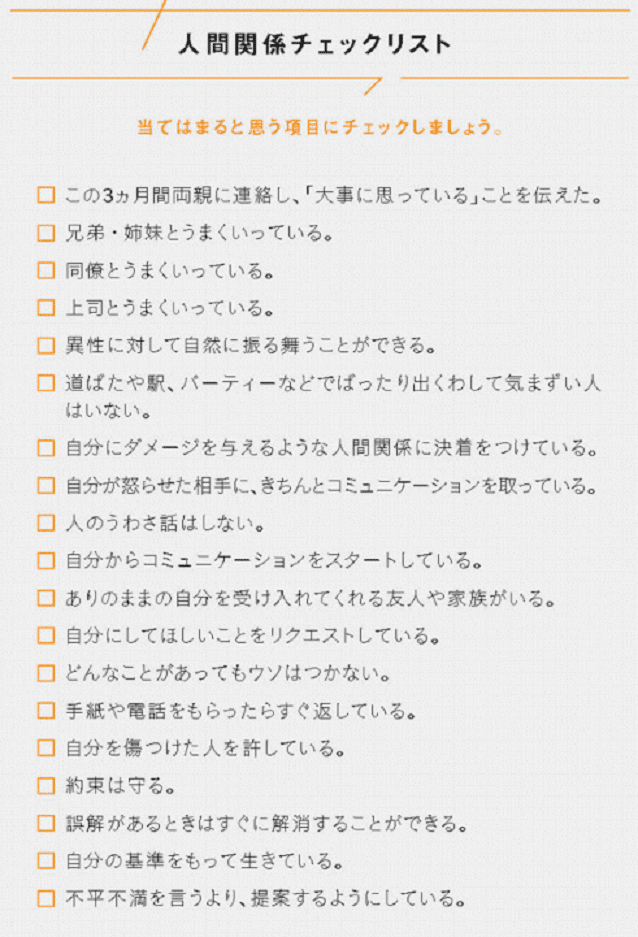


🐾PART5まとめ
・セルフトークを減らす。
1.生まれてしまったセルフトークAをへらす。
2.セルフトークAを発生しないようにする。
・セルフトークを認識することが大事。
・セルフトークAを発生させないために。
/ストレスを認識する。
/ルーティンをつくる。
/アイデンティティとは何かを正しく理解する。
/相手にどんな貢献ができるか考える。
/過剰な期待をしない。
/ネガティブなレッテルを貼らない。
/パーソナルファウンデーションを整える。
<PART6 セルフトークを「なくす」>
最高の実力を発揮する方法。
セルフトークをなくした状態。
➜「ゾーン(zone)」「フロー(flow)」
東洋的な言葉
➜「無心」「無我の境地」
「ゾーン」
集中力が極限まで研ぎ澄まされた状態。
・思考や感情が意識に上っていない。
・身体が自動的に、能力を最大限に発揮している。
➜おもにスポーツの世界で使われる。
身体的な比重が大きい。
➜意識からセルフトークAがなくなり、集中する。
=ゾーンに入る。
例)
「球が止まって見える」
など。
「フロー」
心理学者、ミハイ・チクセントミハイが提唱。
時間の経過も忘れるほど完全に集中している状態。
➜創造的な仕事をする人たちに頻繁に訪れる。
例)
・画家
・小説家
・棋士
など。
日常における行動にもフローは該当する。
例)
・企画書を書いていたら終電になっていた。
・家事に没頭していたら半日たっていた。
など。
頭脳的な比重が大きい。
➜意識がセルフトークBで満たされ、集中する。
=フローに入る。
※ゾーンもフローも雑念となるセルフトークAが完全に消えた状態。

人は心の揺れを常に意識させられている。
➜「揺れ」が存在しない行動に心を惹かれる。
例)
・ゾーンに入っているプロスポーツ選手。
・フロー状態の役者。
・信念を持ち、迷いなく行動する物語の主人公。
など。
➜特別なオーラを感じる。
=心惹かれる。
ゾーン、フロー状態を再現する。
➜「成功体験」が比較対象になる。
=セルフトークAを生み出す。
例)
プロ野球選手の場合
「もし打てなかったら」
「こんなはずでは・・・」
➜感覚を思い出そうとして逆にフォームを崩す。
セフルトークを「なくす」具体的な方法。
減らしておくことが前提。
「結果や目的ではなくプロセスを重視する」
例)
・テニスの場合。
✗試合に勝つこと。
○スイングをすること。
➜さらに強く振り抜くこと。
・スピーチの場合。
✗感動させよう。
○声を低くし、ゆっくり話そう。
・野球の場合。
✗ヒットを打とう。
○強く打つこと。
➜振り抜こうとすること。
「行動そのものを楽しむ」
ポイント)
・行動をセルフトークが発生しないレベルにまで還元する。
・還元した行動は結果や目標として楽しめるものにする。
将来での利益を期待しない。
➜することそれ自体が報酬。
🐾PART6まとめ
・ゾーンに入るから、セルフトークAが消える。
・フローに入るから、セフルトークAが消える。
・セルフトークが発生しにくいレベルまで行動を還元する。
➜還元した行動自体を目的として楽しむ。
<PART7 相手のセフルトーク・マネジメントをコーチする>
🐾相手にセフルトークを気づかせる
敵はステルス。
➜まず見えるようにすることが大切。
=自分の内側のセルフトークに気づいてもらう。
自分のセフルトークに気づいてもらう。
➜「無意識に」言っていることなので気づけない。
=内側の状態を内省してもらう必要がある。
内省してもらう。
➜「その時の身体の状態」に戻ってもらう。
=思い出せるように質問する。
例)
・それはいつだった?
・何時ぐらいだった?
・どこにいたの?
・場所の様子を詳しく教えてくれる?
・何が見えていた?
・どんな風に見えていた?
・何が聞こえていた?
・どんな風に聞こえていた?
・そのときの身体の感じはどうだった?
など。
➜その時に戻れるように質問を重ねる。
客観的な事実
・場所
・日時
・部屋に置かれているもの
など。
主観的な事実
・何が見えたか。
・何が聞こえたか。
・身体の感じ。
など。
過去を再体験しているサイン。
➜表情、呼吸、身体の力みなど。
=「その時、内側で、どんな事を自分に言っていた?」
「もしこうなったらどうしよう?」
「なんでこうなったんだろう?」
➜自分に言っていなかった質問してみる。
🐾相手のセルフトークを変える
「問いの内在化」
良い質問をされる。
➜いざという時に自分の状態を変えてくれる質問になる。
「問いの内在化」を促す質問
《質問1》
肯定・自責の質問
(自分次第で状況は変わりうるという見方をつくる)
例)
・オーディエンスの顔はどんな風に見えるだろうか?
・どこをしっかり見ると落ち着くだろうか?
・何のために君は話すんだろうか?
・誰のために君は話すんだろうか?
・どんな影響を与えたいのだろうか?
・一番伝えたいことはなんだろうか?
「見られる」から「見る」ことを意識する。
➜人は強くなる
例)
影響される➜影響する
結果・評価➜目的・パーパス
質問で自分の状態が変わるという実感。
➜実際の場面でもセルフトークとして活用する。
《質問2》
相手の背景を探る質問
(目の前の人に対する見方を変える)
例)
・一番聞きたかったことはなんだろう?
・その時どんな状態でそこにいたんだろう?
・その日の朝、何を食べてきたんだろうか?
・その日の朝、家族とどんな会話をしただろうか?
・どんな人生を日々送っているだろう?
・長年夢見ていることはなんだろう?
・その人たちのどこが、君は好きだろうか?
・その人達の長所はなんだろうか?
など。
➜特定の誰かを想像してもう。
緊張するとき。
➜相手が自分に危害を加える存在に見える。
質問に対する答えを探索するプロセス。
➜相手が「普通の人間」であることを思い出せる。
=相手の事を考えることができるようになる。
《質問3》
視点を変える質問
(相手の中に違う「人」をつくるための質問)
例)
・スピーチの名手だったら。
➜どんな気を配るだろう?
・会社の社長だとしたら。
➜どんな風にプレゼンに臨むだろう?
・人生を味わいつくした90歳だとしたら。
➜どのようなスタンスで歩くだろうか?
・大統領だとしたら。
➜どう語りかけるだろう?
・もし今日死ぬことがわかっていたら。
➜何を伝えたいだろう?
など。
もしもこうだとしたら、どうしますか?
(what if)
➜相手の状態の変化を見る。
対話で相手のセフルトークを変える。
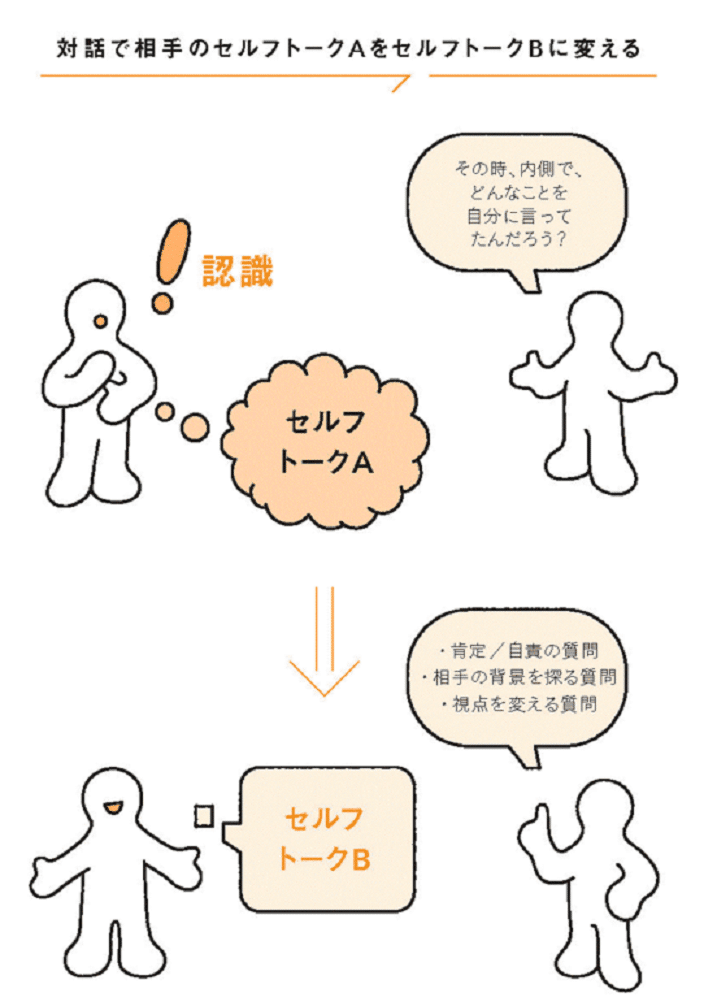
🐾PART7まとめ
・相手をネガティブな状況を再体験してもらう。
➜自分のセルフトークに気づいてもらう。
・肯定・自責/背景を探る/視点を変える質問をする。
➜相手の中に新しい気づきが起こるのを促す。
・気づきを促した問いを内在化してもらう。
➜実際の場面でのセルフトークになる。
=パフォーマンスを上げられる。
<まとめ>
※何をしていても、セルフトークをマネージすることはプラスに働く。
➜セルフトーク・マネジメントは汎用性が高い。
●セルフトークとは。
感情や行動の引き金として、自分の中に生まれる言葉。
➜刺激によって自動的に生まれる。
セルフトークA(automatic)
➜「感情」を呼び起こし「反応」として行動を導く。
セルフトークB (bear)
➜「理性」を呼び起こし「対応」として行動を導く。
●セルフトークが生まれる理由。
セフルトークA
➜刺激からアイデンティなどビリーフを守るため。
=反射的に生まれてしまう。
セルフトークB
➜刺激に対応するために自分の意思で生み出す。
●セルフトークを「変える」
セルフトークAを生まれるままにしておく。
=自分をコントロールできなくなる。
➜セルフトークBで変える。
・肯定、自責の質問。
・相手の背景を探る質問。
・視点を変える質問。
など。
●セルフトークを「使う」
セルフトークBを意図的に使う。
➜スイッチや逆説療法に利用する。
=思考、行動の強化、修正ができる。
●セルフトークを「減らす」
そもそもセルフトークAを発生させない。
➜肯定、自責のスタンスをとる。
注意点)
・心と身体を整える。
・ルーティンをつくる、守る。
・アイデンティティを正しく理解する。
・自分を守るのではなく、相手のことを考える。
・期待しない
・他人にはったレッテルをはがす。
・未完了を減らす。
●セルフトークを「なくす」
「減らす」を突き詰める。
➜「ゾーン」「フロー」状態に入る。
結果ではなくプロセス自体を楽しみ、目的とする。
➜時間の縛りから自由になる。
※セルフトークを認識することを日頃から意識し、練習する。
➜自分の行動が「反応」か「対応」かを意識する。
刺激と反応の間には、幾ばく化の「間」が存在します。
私たちはこの「間」の中で、自分の反応を選択します。
私たちの成長と自由は、私たちが選ぶ反応にかかっているのです。
知ることだけでは十分ではない、それを使わないといけない。やる気だけでは十分ではない、実行しないといけない。
合わせて読むのにおすすめの本
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
