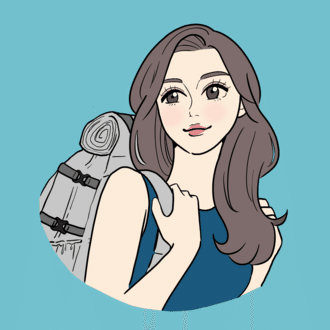生まれ変わってもカンボジアであごを折りたい。#創作大賞2024
わたしのあごは左右にゆがんでいる。
噛み合わせも悪く、1週間に1度は歯が抜け落ちたり、歯が真っ黒になったり、そんな夢をみる。
神経もないので、あごについた焼肉のタレにも気づかない。
このあごは生まれつきではない。
カンボジアになんか行かなければ、あごに焼肉のタレがついたままのアホヅラをしていなかったはずなんだ。
でもね、もう一度人生をやり直せたとしても、
わたしはカンボジアに行く。
たとえまたあごを折ることになったとしても。
月給7万円、社宅付きで、カンボジアで働く
大学生のころに、カンボジアで起業した日本人をインタビューするというツアーに参加した。
カンボジアはベトナムとタイの間にある発展途上国で、国民の豊かさは世界189か国の中でも144位の貧しい国だ。
はじめて訪れたカンボジアは、蒸し暑くて汚かった。
多過ぎる交通量と排気ガスでマスクが黒くなるほどなのに、信号はない。
道が舗装されていないから、砂ぼこりが舞っていた。
人々はみんながTシャツに短パンにピーチサンダルの装いだ。
今までの常識が通じないような、未開の地みたいようなその世界に飛び込みたいと思った。
インタビューした日本人のうち、日本食品の問屋を経営している白井さんに出会った。
白井さんは経営者なのに、気さくな人で、学生のわたしとも対等に話してくれた。
白井さんとはすぐに打ち解けた。
「ここで働きたいな。」
つい口に出してしまった。
無邪気で、無責任で、無計画で、無鉄砲な言葉だった。
カンボジアには人をおかしくさせる、不思議な引力がある。若さゆえか、わたしはカンボジアにすっかり魅了されていた。
「いいね。本気になったら、いつでも連絡してね」
ちゃんとした大人である白井さんは冷静だった。
「一旦頭を冷やせ」ということらしい。
半年ほど経った大学3年生の夏、わたしは行く気満々だった交換留学に行けなかった。
Toefleという英語の資格で、スピーキングの点数が3点足りなかったからだ。
これからどうしようかと途方に暮れたそんなときに、白井さんのことを思い出した。
そうだ、わたしにはカンボジアがあるじゃないか。
改めて白井さんに連絡をすると、「いつでもおいで。」と連絡がきた。
当時カンボジア人の平均月給は4万円だったが、月給7万円もらえることになった。
実際7万円あれば、カンボジアで困ることはなにもなかった。
カンボジアでの初日は会社の説明や借り上げ社宅の案内をしてくれた。
社用iPhoneを貸してくれたが、1時間足らずで盗まれてしまった。
カンボジアらしい初日だと思った。
働く日々、「ブルーパンプキン」で襲われて。
日本食品の問屋の仕事は楽しかった。
特になにをしたらいいとか指示はなくて、やりたいことをやればいいと言われていた。
はじめはカンボジア人の現地スタッフと一緒に配達に行ったり、副社長のまりこさんの打ち合わせに同席させてもらったりしていた。
でも配達も打ち合わせもそんな頻繁にはなかったので、わたしはすぐに暇になった。
日本人の学生を受け入れるのは初めてで、会社もわたしの扱いがよくわかっていなかった。
白井さんに後悔させたくないと、わたしは思いつくことを全部やってみることにした。
日本食品を買ってくれたり、置いてくれそうなお店をかたっぱしから訪問した。やったこともない飛び込み営業、それも英語で。
正解なんてなかった。ググっても出てこなかった。
むしろ正解なんてないほうが自由だと思った。
カタログを置いたり、相手が少しでも気になると言ってくれた商品は、お試し用の少量サイズのサンプルを届けた。
たまに買ってくれる人が現れると、とてつもなく嬉しかった。
届けるときはバイクタクシーを使った。
カンボジアで庶民の足はバイクタクシーだ。
小汚い運ちゃんの後ろに座り、密着しながらの移動が日常だった。
運ちゃんは英語が話せないので、わたしは片言のクメール語で会話した。
会社用の原付で自分で運転もした。国際免許はもっていなかった。
値段も約束もルールも、すべてがカンボジアでは曖昧だった。途上国だから仕方がないという、決まりきらない「余白」があった。
わたしは、その余白の感覚が狂おしいくらい好きだ。
「オッパニャー」
お気楽なカンボジア人がよく口にする言葉だ。
「オッパニャー」とは、クメール語で「no problem」という意味だ。
「おっぱい」と「にゃー」。
カンボジアらしいゆるい響きが気に入った。


ビニール袋に包んでくれる。

オフィスが閉まるとわたしは、家の近くの「ブルーパンプキン」というカフェで作業をした。
「ブルーパンプキン」にはソファ席があって、Wi-Fiが早くて、エアコンが効いていて涼しかった。
いつまでも閉店時間までいる客はわたしだけだった。
わたしの社宅にはエアコンがなくて、蚊と同居していたので、家に帰りたくなかった。
ある日、いつものように閉店間際まで作業をしていた。帰りしなにトイレを利用しようとしたら、その男性店員がトイレに無理矢理入ってこようとしてきた。
わたしが毎晩閉店間際までお店にいるから、その気があると思ったんだとか。
カンボジア、あぶねー。
てかこの国の恋愛事情どうなっちゃってるの。
「こわい、どうしよう」
という感情よりも「まあ、カンボジアだしな」とどこか諦めた気持ちになったのを覚えている。
こんな国で、夜、店内で店員と2人きりになるなんて、わたしが能天気なだけだったなって。
カンボジアになにかを期待するより、自分がなんとかしたほうが、よっぽど確実なんだよな。
良い学びになった。
そんなトンデモ事件の後も、わたしは「ブルーパンプキン」に通った。襲ってきた店員とも仲良くなった。
人生で一番みじめな日
仕事を終えて、家に帰ったらドアがとうとう開かなくなった。
ずっと調子が悪かったけど、副社長のまりこさんが「えいっ」と力を入れると開くドア。
まりこさんはすぐ上の階に住んでいるけど、こんな夜に呼ぶのは気が引ける。
なんでも1人でできるようにならないと。いつも助けがあるなんて限らないんだから。
特にここ、カンボジアでは。
夜でも32度という熱帯夜の中、小一時間ドアと格闘して、やっとドアを開くことができた。
ドアをあけただけなのに、なんだこの達成感は。
ようやく部屋に入れたけど、別に安らげる部屋ではない。むしろ苦痛しかない部屋だった。
エアコンはつけることができない。
エアコンをつけると、下の階の部屋にものすごい水漏れがした。
下の階には、「もう日本では働けない」と自称する日本人男性とカンボジア女性とその息子の一家が暮らしていた。
普段温厚な日本人男性だったが、水漏れが2回連続で起きたときは、犯罪者のような剣幕で怒ってきた。犯罪者かどうか知らないが。
あと蚊がすごい。
窓を閉めても蚊が入ってくる。
煙が濃くて心配になるカンボジア製の蚊取り線香を2個焚きながら、毎晩眠りにつく。
平安時代、日本の貴族は部屋にいい匂いのお香を焚きしめてて、衣服に香りをつけていたという。
わたしはいい匂いのお香ではなく、蚊取り線香の匂いを衣服にまとわせていた。
とまあ、ここまでは毎日のことなのでもう慣れた。暑いのにも、少々けむいのも、前ほどは気にならなくなった。
でもこの日は、さらにシャワーの調子が悪かった。
そもそも水の出はよくないし、ぬるい水しか出ない。でもこの日は水は冷たいままで、ポトポトとしか水が出なかった。
結局この日はシャワーを浴びられなかった。
カンボジアにきてまで、わたしはなにをしているんだろう。
この日、カンボジアに来てからはじめて泣いた。
原付で配達しているときに、3ケツしてるバイクに後ろから衝突されて吹っ飛んだときも、
ベトナム出張のときの不安な夜行バスでも、泣かなかった。
暑くて、けむくて、体がベタつく不快さで眠れなくて、静かにベッドで泣いた。
カンボジア人と日本人
カンボジア人は小柄で、たとえば男性の平均身長は165センチだ。
細くて、肌が荒れている人が多い。慢性的な栄養失調によるものらしい。
たしかに裕福そうなカンボジア人は、みんな体格がしっかりしている。
歯も、虫歯が目立つ人や歯並びが悪い人が多い。歯が欠けると接着剤でくっつけていた。
昼間は仕事をせずにオセロをするおじさんがやたら多く、貧困国ながら平和そのものだった。
カンボジアでは日本人はモテた。
日本人は「アジアの中の白人」なんだと、肌で実感した。
カンボジア人女性は背が低く小柄で、肌の色は浅黒い。
対照的にわたしは背が高く、体も細くはなくて、肌の色も白い方だった。
まさに羨望の的だったのだ。
ちょっと前まで、わたしはカナダのトロントという街で暮らしていた。
アジア人であるわたしは少しだけ肩身が狭く、同じアジア人であるベトナム人のコミュニティに属し、身を寄せ合っていた。
ところが、このカンボジアのわたしといったら。
わたし自身はなにも変わっていないのに、カンボジアでは民族カーストの頂点にいた。
てっぺんからの眺めは確かによかった。なにをするにもイージーモードだ。
ただ得体の知れない不安がつきまとっていた。
なにも偉くないのに、人々が作り上げたバブルのような、虚構のような、「日本人のわたし」がもてはやされる。
もし「日本」という国がカンボジアの中で評価されなくなれば、「日本人のわたし」はチヤホヤされないのだろう。
わたしはわたしなのに。
世界の常識がいつ自分に牙を向くかわからない。そんな不安定さがあった。
母が会いにきてくれたので、1泊1000円の宿を予約してみる。
母がカンボジアに遊びにくるという。
すっかり金銭感覚がバグったわたしは、1泊1000円の宿を奮発して予約した。
平均月給4万円のカンボジアで、1泊1000円の宿は安くなかった。しかも朝食つきだった。
ホテルに宿泊すふと、エアコンは壊れていたし、猫くらいの大きさはあるオオサンショウウオが壁に張り付いていた。
カンボジアでは虫や動物は大きかった。よく道を走っているネズミもイタチくらい大きかった。
朝ごはんは、味の素で味付けをしてある焼きそばだった。味の素はカンボジアのどこのレストランにも置いてあった。
世界遺産である仏教寺院「アンコールワット」を見るためにシェムリアップに滞在していた。
シェムリアップから、「天空の城ラピュタ」のような風景が見られる遺跡に向かった。



トゥクトゥクは暑かった。
屋根はあるものの、熱気は遮られないトゥクトゥクで3時間移動した。
その夜、あまりの暑さに母は熱中症で倒れてしまった。
次の日から、1泊3000円の宿に変えてみた。
エアコンが機能した。朝ごはんは美味しいパイナップルとココナッツのジャムが塗ってあるトーストだった。たった2000円だすだけで、文明を感じる。
やっと涼しい部屋で横になれた母は、半日で回復した。
母が回復したあとは、トンレサップ湖という東南アジア最大の湖のクルーズに行った。
船はにごった泥水のような湖の上を進み、湖の上にボートをつないで生活するボート村のコミュニティを間近で見れる。


クルーズでは、カバンの材料なのか食用なのかわからないワニがいるワニ園や、ボート村の売店やレストランに連れて行ってもらった。
途中で、村の米を買うための寄付を迫られた。カンボジアではよく出会う光景だったので、無視をした。寄付を強制されるのは好きではない。
当時を思い返すと、危機管理がなってなかったなと思う。下手に抵抗して、船を盾にされて脅される可能性もあったから。
大人しく寄付をしていてもよかったのかもしれない。
キリング・フィールドとあご
ある日、キリング・フィールドと呼ばれる「クメールルージュ」の虐殺の跡地に行った。
「クメールルージュ」とは、ポル・ポト政権が政府の実権を握った際に、知識人を大量に虐殺した事件のことだ。
知識人とは先生や士業を生業にしている人はもちろん、それどころか眼鏡をかけている人までもが対象だったという。
跡地では牢獄や処刑場所が見学できた。
「クメールルージュ」で捕まった女性は髪を短く切られる。
クメールルージュを彷彿させないために、カンボジアの女性は髪を伸ばしている髪型の人がほとんだなんだと聞いた。
見学を終えたあと、妙に肩が重くなった気がした。
その次の日、わたしは道を渡っている時に、バイクが右からぶつかってきた。
まさか顎が折れていると思わなかったので、ぶつかってきたバイクとはそのまま別れた。
次の日になっても血が止まらない。
近くのイオンの中の歯医者に行った。
カンボジアではじめてのイオンで、綺麗な建物だった。
そこで顎が折れていると言われた。
タイに行かないと治療できる病院はないと言われた。だったら日本に帰って治療したいと思ったので、その次の日には日本への飛行機に乗った。
急展開だった。カンボジアのインターン生活は思ったよりも早く、それも突然、幕を閉じた。
大学病院で顎の手術と入院をした。
ちょうど就活シーズンに入っていたので、顎を腫らしながら就活をした。
行きたい企業に行けないなら、カンボジアに出戻るつもりだった。
結局、わたしは日本の企業に就職した。
もうあの日常に戻ることはない。そんな予感がした。
信号のない道路で、我先にと進みたがる、多すぎる車とバイク。
土地が貧しいせいか、赤茶色の道。
昼間からオセロばかりするたくさんのおじさん。
あの国でなにかを身につけたとか、かけがえのない体験だったとか、そんなんじゃない。
ただ目に焼き付けたものすべてが、
あの熱帯特有の体にまとわりつくような、生ぬるい熱っぽさが忘れられない。
カンボジアには未来はない。
より正確にいうと、だれも未来のことなんて考えて行動しない。
この国はまさに進化の途中で、なにが起こるかわからなくて、わたしたちの想像を超えることばかりが起きる。
だからみんな今、この瞬間を生きる。
今を死にものぐるいで生きろと、生き急がされるような国。
人生をやり直せたとしても、わたしはきっとカンボジアに行く。
あの熱気とカオスを求めて。たとえ、あごがまた折れるとしても。
いいなと思ったら応援しよう!