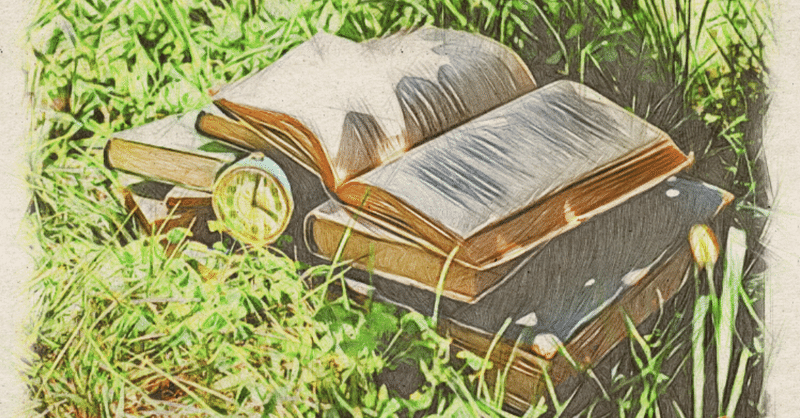
分人主義を知って「母になってから感じている息苦しさ」の正体がわかった話(『私とは何か 「個人」から「分人」へ』感想)
『私とは何か 「個人」から「分人」へ』(平野啓一郎 著/講談社現代新書/2012.8)を読んだ。
「人間は分人の集合体であり、重要なのは、その構成比率だ」(P.140)
というのが本書の要点と思われる。
「分人」というのは、各人との人間関係の中に立ち現れる自分のこと。関係性ごとに「分人」があり、それらはそれぞれ異なっている。
例えば、親の前での自分、友人の前での自分、上司の前での自分、同僚の前での自分などを思い浮かべるとわかりやすい。
すべて微妙に異なっていて、それでいて自分だ。
「分人」はいわば分数のようなもので、私たち個人(=1)は、様々な「分人」の集合体である、という考え方だ。
心当たりもあるし、すっと理解できる。
むしろなぜこれまでこのような言葉がなかったのか、不思議に感じるくらいだ。
■私が「母になってから感じている息苦しさ」の正体
本書を読んで自分が「母になってから感じている息苦しさ」の原因を整理することができ、大変すっきりした。
それは、私がこれまで各人と築いてきた「分人」が、出産したとたん「母親像」なるものに収斂してしまい、私の「分人」の多様性が脅かされたからだ。
例えば職場で私は多くの人と接しているが、ざっくり言えば「はたらく私」の分人を仕事関係者と築いていた。
しかしながら、育休から復帰した途端、これまで築いてきた分人を「母親」としてしか返してくれない人が出てきた。
「これからは仕事よりも子育て優先だね」
「お母さんだから仕事はほどほどにだね」
「お母さんだから、出世とか昇給とか、どうでもいいよね」
などと言われ、「母親」としてしか見てもらえない。
私は働きに来ているのに。
母親になったことは事実であり、「母」としての分人を子と必死に築いている最中なのであるが、職場での私は「はたらく私」であり、「母」の私ではない。
私はそういうつもりでいたのだが、周りはそのようには見てくれなかった。
そのため、職場は私にとってやや居心地の悪い場所になってしまった。
■重要なのは「分人の構成比率」
先ほどの引用で「人間は分人の集合体であり、重要なのは、その構成比率だ」(P.140)とあった。
「重要なのは、その構成比率」とはどういうことか。
分人には、他人との相性もあり、どうにも上手く関係を深められなかったり、不快な分人が発生してしまうこともある。
そういうときは、不快な分人の割合を減らして、自分が愉快で心地よく居られる分人の割合を増やすことで、比較的たのしく生きることができる。
だから分人の割合、構成比率が大事なのだ。
学校に行きたくなかったり、いじめられている子供に、「学校以外の居場所を持とう」というのも、学校以外の分人をもって、そちらに救いを見出そうということなのだろう。
確かに複数の分人を持っていることで、救われる部分はある。息抜きや気分転換、リスクヘッジになるからだ。
私は出産を経てから「母親」という分人に私自身を収斂させられるような感覚を味わった。
実際に「母」としての分人を築く過程は、楽しい面もあるが、何しろ相手の変化が激しいので(赤子の成長と変化はすさまじい)なかなかに過酷でエネルギーがいる。
だからこそ別の分人を持ちたかったし、別の分人を出すことで息抜きをしたかった。
それを潰されてしまったので息苦しかった。
そういう経緯だったのだと、本書を読んで理解することができた。
■見えてきた対応策
現状が把握できたので、対策も見えてきた。
おそらく手っ取り早いのは環境を変えることだろう。
「母」以外の私を見てくれる人・環境を探し、息苦しい分人を手放して、新しい分人を築くのだ。
また、息苦しい分人を心地よい方向へ築きなおすという手もある。ただ、相手あっての分人なので、なかなか変えるのは難しい面もあるだろう。とはいえ可能性はゼロじゃない。
私も、周りの人が悪意があって私を職場でも母親扱いしたわけじゃないことは承知している。実際働き続けることで、周りの様子も変わってきている。
いきなり環境を変えるのが難しい場合は、辛くない範囲で努力してみるのもありだ。
■気が付けた大事にしたい「分人」
自分の息苦しさの原因がわかったと同時に、産前と変わらぬ「分人」を築けた人々のおかげで何とか生きれ来られたのだとも気づいた。
夫や、両親や、友人たち。
私が母になってからも、変わらずにいてくれた。
0歳児育児中にライブに行くのを快く見送ってくれたり、オタクトークに付き合ってくれたり、何かにハマって萌え悶えているのをあたたかく見守ってくれたり。
母親以外の自分も認めてくれた。
本当にありがたい。
改めてこの人たちを大切にしようと思う。
■推しに不祥事があったときにも役立つかも
「分人」という考え方は、自分が好んでいた人が不祥事を起こしたときなどにも使えるかもしれない。
そういったとき、「私は相手の何を見ていたのだろう」「私が愛したものは一体何だったのか」と悩んでしまうことがある。
「本当のその人」なるものが存在し、それはどっち(どれ)だったのだろうと考えてしまうからだ。
しかし分人の考え方では、「本当の自分」なんてものはなく「人間は分人の集合体」である。
自分は相手の「表現者」としての分人を好ましく感じていたが、ほかの分人はそうでなかった、そうじゃない側面があった、ととらえると理解しやすい。
「どっちが本当のあの人なのか」という悩みを「分人」という概念を取り入れることで脱することができる。そのうえで、今後その人の応援を続けるか否かを判断すればよい。
読みながらそんなことも考えた。
なんども「分人」なる言葉を耳にしてようやく手に取った本書。聞き慣れない言葉に、難しい内容なのかなと思っていたが、案外読みやすく分かりやすい内容だった。自分の日頃のもやもやを整理する助けとなったので、おすすめである。
ここから先は
¥ 150
サポートいただけるととても嬉しいです!よろしくお願いいたします。
