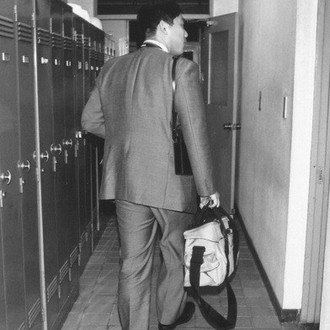- 運営しているクリエイター
2020年10月の記事一覧
老夫婦の日用品が壊れるのは一大事
大事に使っていても、道具や機械はいつか壊れる。壊れたのを契機に使うのをやめるという選択もあるけれど、生活で使っているものの場合、それはまず取り得ない。
私自身、ある朝冷蔵庫を開けて、中の麦茶容器を持ち上げた時、「……冷えていないなあ」と思ったら、実際寿命でコンプレッサーがイカレていて、冷凍食品も「自然解凍」されていて困ったという経験がある。もちろん、買い換えた。
お年寄りにとって、新しいテレビ
母の様子を見た姉の宣言
老人ホームに入居している母。私よりは近所に住む姉が、月1ペースで様子を見に行く。
たまに私と一緒になることもあり、その帰り道に姉がポツッと一言。
「○○(姉の娘)には、『私が年を取って施設のお世話になることになったら、無理に構わなくても良いからね』と言ってあるんだ」と。
我々の母は、子に対して十分に愛情を注いでくれたと思っているし、だからこそその恩返しをしたいという気持ちもある。それも踏まえ
高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請
タイトルが長い。でも、そういうものの案内が、母宛に送られてきたのである。
厳密には、一度春に送られてきたもの。その時は「何だろう?」と思ったが、当時はコロナ禍で移動が制限されていた。「どうしよう?……」とためらっているうちに記憶が薄れて半年が経ち、再通知が送られてきた次第。
このはがきには、「同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下
AIマッチングの提案
インターネットでいくつかのサイトを見ていると、端っこの広告やtwitterの広告tweetで、出会い系のものが流れていることがある。その宣伝文句を見て、ふと思ったこと。
老人ホームの相部屋パートナーも、AIマッチングで選んだら良いのでは?
思いつきと言われれば全くその通り。でも現状は、申込時のたまたまの部屋の空き具合だけで入居する部屋が決まる。それでも、うまくいく場合はあるだろう。しかし、そう
介護の傍ら次の相続税対策も行うことになる
こちらにお越し頂き、ありがとうございます。
あなたのお役に立てれば、幸いです。
さて……
亡父の死後、わが家では相続税申告を行った。その経験から、母の老人ホーム入居後、家計管理では常に証憑(領収証等)を意識するようになった。
母の預金は、当然ながら母のものである。しかし、老人ホームには現金を持ち込めない。また管理の問題もあるため、預金通帳も持ち込めない。
こうなると、事実上私と姉の共同管理