
渋澤怜の自己紹介
■渋澤怜って?
過去には、ライター、文章添削師、日本語教師、有料note運営などなど。
現在はコロナ後遺症療養中。寝ながらパソコンは打てます。在宅ワークをしながらほそぼそと生きている。
▼仕事まとめ
▼有料note&サークル
文章を書くこと、言語芸術が大好き。今まで、純文学、エッセイ、作詞、ポエトリーライヴ、韻踏み、短歌、大喜利……書くことのあらゆるジャンルを節操なくやってきました。
人からはよく
「みんなが薄々思ってるけど言わないことを、言ってくれる人」
「みんなが言語化できていないグレーゾーンを、言語化してくれる人」
「なるほどと思わせてくれる人」
と言われます。
活動場所は主にnoteとtwitter。
▼Twitter例
ホーチミン郊外に突如現れたフェイクな居酒屋「チルタウン」行ってきました。
— 渋澤怜 (ベトナムにいる🇻🇳) (@RayShibusawa) June 16, 2020
いろんな意味で間違いまくってるど…これ、わざとなのか? 偶然なら奇跡だぞ。
歌舞伎町や渋谷センター街を模してるっぽいけど、本気で模してはいなくて、すっごい雑でテキトー。その面白さは日本人しか味わえないはず… pic.twitter.com/UxbLZ8Seyo
納豆を食べたことがあるというベトナム人に
— 渋澤怜 (ベトナムにいる🇻🇳) (@RayShibusawa) July 19, 2021
「どうだった?」
と聞いたら
「怖い」
と言われたことがある。
▼noteでのエッセイ例
■ざっくり自己紹介
1986年生まれ。東京大学文学部卒。
美術大学の職員として5年間勤めた後、2014年に退職。
その後は、「物書きで身を立てたい」という思いをもちつつ、修業のためにいろんなバイトを経る(チャットレディ、ガールズバー、出会い系のサクラ、ライター、作家のアシスタント業などなど)。
ずっと純文学を書いているが、ネットにエッセイを投稿したことでエッセイ本の出版の話が出たり(頓挫)、ライヴハウスで喋りまくるライヴを始める等、節操無く活動する。
▼ライブの例 (※動画プロトタイプ版。限定公開。冒頭10秒に食べ物を粗末にするシーンと汚ったねえシーンあり。苦手な人は35秒からどうぞ)
2018年8月~突然ベトナム・ホーチミンに旅立ち、日本語教師を始める。
■連絡先
Twitter https://twitter.com/RayShibusawa へのDMか、rayshibusawa1103@gmail.com までお願いします!
■どんな小説を書くの?
純文学です。
小学校の頃から小説を書いており、20代後半から純文学の賞へ投稿をはじめました。
・2012年(25歳)、「音楽の花嫁」で第49回文藝賞2次予選通過
・2013年(26歳)、「ファッション・メンタル・ヘルス」で第50回文藝賞2次予選通過
などの経歴があります。(両作ともURLから無料で読めます)
「ネット時代にも読んでもらえる純文学」をテーマに、ネット時代のスピード感や分かりやすさ、キャッチーさを盛り込んだ純文学を執筆したいと思ってます。
▼短編小説例:文章の半数以上をツイートが占める、Twitterを舞台とした小説「ツイハイ」
■どんなエッセイを書くの?
高校生からブログやmixiで書き始め、現在はnoteを更新しています。
・2014年(27歳)、テキスト投稿サイト「CRUNCH MAGAZINE」(現在はサイト消失)で総合ランキング首位獲得および同サイトが主催する「CRUNCH NOVELS新人賞」最終候補
▼テキスト投稿サイト「CRUNCH MAGAZINE」でバズっていた体験エッセイ「チャット嬢をやってみた」
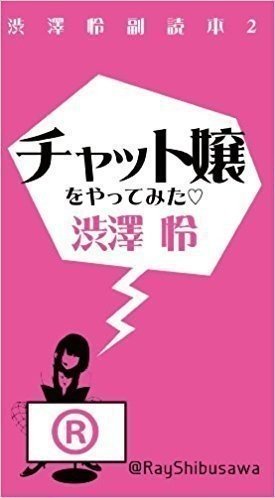
上記がきっかけで、出版社から声がかかりました(仮タイトル「東大卒の女がホワイト企業を辞めてエロバイトを始めた話 −チャットレディ、水商売、出会い系のサクラをやってみて思ったことー」こちらのnote↓↓をぐーーーーんと長くしたような内容でした。)
■なんで急にベトナム行ったの? なんで急に日本語教師始めたの?
それ以前は、東京でアルバイトしつつ、ネットにエッセイや小説を書いて、文章で身を立てることを目標にしてたのですが、2018年8月、突然異業種&異国に飛び立ちました。
日本語を書くことと読むことが大好きな私が、突如日本を離れた理由は、端的にいうと、
「日本語のことは好きだけど、好きすぎて一緒にいすぎると喧嘩しちゃうから、『距離を置いて』るの」
……ってことなんですが、これじゃあ全然分からないと思うので説明します、長くなりますが……。

■日本のネットでの自己発信に虚無感を感じ、日本文化圏の外に出てみた
それ以前は、日本と日本のネット空間で日本語にどっぷり浸り、日本語を読み&書きまくっていました。そして
「好きなことを発信して身を立てられるようになりたい」
「2010年代のネット空間の言語感覚をすくいとった小説を書きたい」
等と考え、ほぼ毎日noteを書いていました。
でも、2018年7月、スペイン巡礼路徒歩旅行に行ったことで、転機に至ります。

道中では一切日本語を喋らず、ネットもほとんどせず、英語で生身の人間と喋りまくっていた、つまり「日本」「ネット」「日本語」という、普段私がどっぷり浸っていたものの一切から離れたのですが、そこで以下のような気付きを得ます。
「あれ、ネットなくても幸せじゃん」
「今の日本(と日本のネット空間)には『好きなことをしよう』『自由に生きよう』っていうメッセージが蔓延しているけど、その外には、素で自由に生きてる(からわざわざそんなこと発しない)人もゴロゴロいるじゃん」
「今の日本(と日本のネット空間)には、差別、偏見、ジェンダー対立が溢れてる。わざわざ日本に住んで、わざわざネットに接続して、それらに触れて、イライラを溜めるのって、変だなあ」
「わざわざ息苦しい日本(と日本のネット空間)に住んで、「自由に生きよう!」「ここはおかしい!」と叫ぶ文章を書くって、もしかして、ひどく、マッチポンプなのでは?」

そして、それ以前にまさに日本(と日本のネット空間)で『自由に生きよう』と謳って身を立てることを目標にしていた私は、帰国後、やることがなくなり、「無」になるんですよね。
(それ以前はマジで毎日noteを書いてばかりいたので、「私の今までネットに書いてきたこと無価値じゃん」と思ったら、やることが一切無くなった)
この辺の葛藤をもうちょっとよく知りたい方はこちら☟☟
ちなみに「無」の時に寺に行ったりもしました。
寺レポ☟☟
「無」を一ヶ月ほどすごしたのち、
「今の日本のネット界隈ではバズることが決まっている。でもそれは私の書きたい事じゃない。だから、書くことを仕事にするのは諦めよう」
「じゃあ全然関係ない仕事しよう」
と結論。
スペイン旅行の際に得たもう一つの気づき、
3週間英語だけで話して分かったが、私は、日本語の言語空間がめちゃめちゃ窮屈だった(謙遜、敬語、慇懃などなど)
を元に、「日本出た方がいいのでは?」と仮説。
日本脱出系の本を読み漁り、「日本語教師が安パイ&適任だろう」と考え、資格無しで応募できる求人に飛びつき、今に至ります。
この辺の決意の過程は、詳しくはここに☟☟
■ベトナム・ホーチミンで私が書いていること
じゃあ2018年8月以降、わたしはどんなものを書いているのか?
2018~2021年はベトナム関連エッセイに注力。
なるべく、日本のトレンドにおもねらず、「認めてくれ」という我も張らず、淡々と、日々発見したことをフラットに書く。
上記が「いいな」と思った方は、このマガジンをフォローしてくださると嬉しいです。
▼「ベトナムの話」マガジン
■興味を持ってくださった方への「おすすめ」
▼おすすめエッセイマガジン
▼おすすめ創作マガジン
▼Twitterもよろしく
■そのた
▼仕事依頼&過去の仕事実績まとめ
▼欲しいものリスト 読みたい本リストと欲しいものリストを兼ねている
読んで頂きありがとうございました! 渋澤怜自己紹介(最新版)は、ここで終わりです!
☟☟以下は、2018年以前に書いた、「ライヴ」についての紹介文なので、興味がある方だけ読んでください~~!☟☟
■どんなライヴをするの?(※2018.8~ホーチミン移住のため休止中)
楽器を使わない、BGMも使わない、歌も歌わない、ただ私一人が喋ってるだけのライヴ。誰の真似もしていないので、まだジャンル名がついてない!
ポエトリーリーディング、ラップ等の要素も含みます。「殴り語り」「演説」「落語的」と言われることも。
カテゴライズされていないのをいいことに、ライヴハウスや画廊、詩の朗読会、クラシックコンサート等に、節操無く出演。
※共演者の加藤千晴さんから嬉しい紹介文をもらったので引用しときます!
ライブもできる小説家。東大文学部卒。初めて会ったのが、一昨年の秋位だったろうか。TASKE企画「歌舞伎町詩人の集い」で現れた謎の美女が渋澤怜である。
彼女のパフォーマンスはとにかく喋る。ただひたすらマシンガンの如く攻撃的に喋る。内容もかなりうちらにとっては痛い内容なので耳にしっかりこびりつく。突如芝居が始まるのかと思えばしっかり笑いもとる。何処までがMCで何処までがリーディングなのか全く検討がつかない。そのうちに彼女の言葉に振り回されていく。
彼女の活動場所はフリースペース、ライブハウス等様々で、特に秋葉原のアートラボで行われたパフォーマンスでは、耳や目の肥えているアーティストや関係者から絶大な絶賛を浴びていた。
※2017年5月より、「既成事実と渋澤怜」という男女2人ユニットもやってます。こちらは、ビート担当・三菱鉄郎(カタカナ)の音楽に乗せて渋澤怜が喋るというスタイルです。
■なんで、物書きなのにライヴ始めたの?
小学生から小説を書き、20代には純文学の文学賞への応募を始めた私ですが、イマイチ行き詰まりを感じていました。
というのも、小説自体は、芸術の中でも私が一番傾倒している、大好きな分野なのですが、小説をとりまく「場」に不満があったのです。
「小説を書いても読んでもらえるまでにタイムラグがあるし、読み手が目の前にいないからどんな感想を持たれたか分からない!」
「賞に応募して、半年待って、落ちて、落選作をネットに上げるっていうサイクルは遅すぎるし、何万字の小説をネットに上げても読んでくれる人何人いるの?」
「純文学って、デビューまでの門が狭すぎる(大体新人賞を受賞できるのは2000人に1人)し、デビューしても、小説好きにしか読んでもらえない! 世界狭い!」
などです。
また、私は22歳くらいからインディーズのライヴハウスに通っていたので、「目の前にお客さんがいて、すぐに肌で反応をもらえるライヴっていいなあ」と思っていました。
しかし当時は、音楽、バンドという媒体、バンドマンという存在に強烈な憧れを抱きつつ、「私は人前に立つのは向いてないから無理」「女がバンドやっても「ギャルバン」とか言われるし、普通に観てもらえない。ああ、男に生まれてバンドマンになりたい人生だった…」と諦め、落ち込む……という謎サイクルを繰り返していました。今思うと、勝手にこじらせてただけなんですけどね。
(この辺の心理が知りたい方は、2012年に書いた小説「バンドマンとは付き合うな」を読んでもらえればと思います)
しかし、色々経て(後述)、自分が女であることへのこじらせを克服した私は、いいかんじにおばさんになった2016年5月より、ライヴ活動を始めました。
そして、今まで小説で書いてきたことを、「目の前のお客さんに」「すぐ言って」「反応を肌で感じる」ことができるライヴという媒体の醍醐味を日々味わっています。
(はじめてライヴハウスに出た時の動画。ある意味伝説的な反響)
また、ライヴ活動をすることによって、普段小説を読まないお客さんにも渋澤怜を知ってもらう手段が増えました。
…というわけなので、私にとっては、小説も、ライヴも、「言いたいことを言う」手段でしかなく、根源は一緒です。
☝☝よかったらこちらも読んでみてください。☝☝
この記事が参加している募集
スキを押すと、短歌を1首詠みます。 サポートされると4首詠みます。
