
【終】憧憬の道、造形の街
その街に行くには、十九年もの間、罪を一度も犯していないという褒賞が必要になる。自由を受け取るために、不自由を選ばなければならない最低年数が十九年だという話である。その街に繋がる道は、この世の何処かに現れるという。しかし、その街での日々を綴った記事は、ネット中どこを漁っても見当たらない。書籍も無い。噂に聞いた街の断片を、繋げてひとつの物語にしてみる。そして自分を、いや世界すらも騙して創り上げる。
「憧憬の道、造形の街」
俺はこの1年間、自分を欺いてきたのだ。空から言葉が、思想が降ってくる。騙し絵のような世界のフック、それが言葉だ。
※ここから、バックナンバーの紹介。当記事で読めるのは【最終話】のみであり、【第一話】から【特別篇】まではリンク集になっています。気になるタイトルがあれば、タップして読んで頂けると幸いです。数日後、作者による各タイトルの評価が追加されます。
【第一話】銃が呼んでいる

【作者オススメ度】★★★☆☆ 3.0
【陰湿度】★☆☆☆☆ 1.0
【恐怖度】☆☆☆☆☆ 0.5
【胸キュン度】★☆☆☆☆ 1.0
【文学性】★★★☆☆ 3.0
【第二話】消えるのが怖いのは

【作者オススメ度】★★★★☆ 4.0
【陰湿度】★★☆☆☆ 2.5
【恐怖度】★☆☆☆☆ 1.0
【胸キュン度】★★★☆☆ 3.0
【文学性】★★★☆☆ 3.0
【第三話】某○○にて

某カラオケにて
某テニススクールにて
某トイレにて
某動物園にて
某温泉にて
【作者オススメ度】★☆☆☆☆ 1.0
【陰湿度】★★★★★ 5.0
【恐怖度】★★★☆☆ 3.0
【胸キュン度】☆☆☆☆☆ 0.0
【文学性】★★☆☆☆ 2.0
【第四話】春が終わる

青の春
霞む下北沢
さよなら、トイレの神様
春の飛鳥山を歩く
【作者オススメ度】★★★★★ 5.0
【陰湿度】☆☆☆☆☆ 0.5
【恐怖度】☆☆☆☆☆ 0.0
【胸キュン度】★★★★☆ 4.0
【文学性】★★★☆☆ 3.0
【第五話】#ウシミツトカゲ

【作者オススメ度】★★★★★ 5.0
【陰湿度】★★★★☆ 4.0
【恐怖度】★★★★★ 5+
【胸キュン度】★☆☆☆☆ 1.0
【文学性】★★★★★ 5.0
【第六話】18歳

十八歳
武道館より
幸せな牛丼屋
桜桃忌に寄せて
「世にも奇妙な物語」に焦がれて
救済、あるいは断罪
月を詠む
【作者オススメ度】★★★★★ 5.0
【陰湿度】★★★★★ 5.0
【諦念度】★★★★☆ 4.0
【胸キュン度】★★★★★ 5.0
【文学性】★★★★☆ 4.0
【第七話】鬼

【作者オススメ度】★☆☆☆☆ 1.5
【陰湿度】★★★★☆ 4.0
【恐怖度】★★★★★ 4.8
【胸キュン度】☆☆☆☆☆ 0.0
【文学性】★☆☆☆☆ 1.0
【第八話】ブルーは欺く
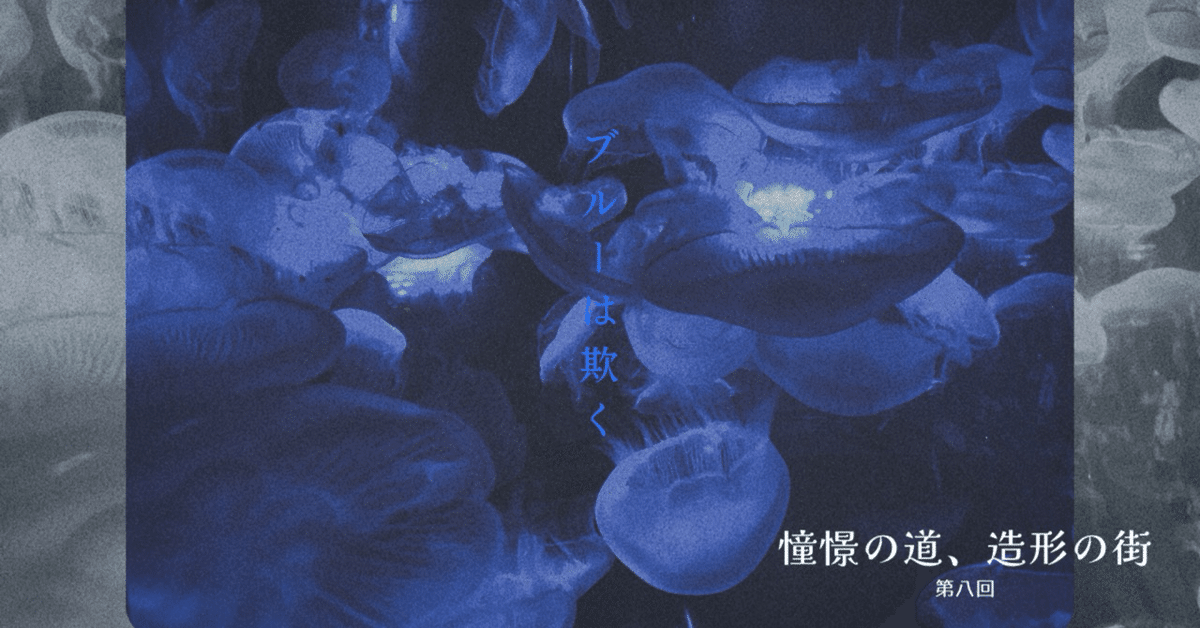
愛欺くブルー
夜惑い
金魚と少女
【作者オススメ度】★★★★☆ 4.0
【陰湿度】★★★★★ 5+
【恐怖度】★★★☆☆ 3.0
【胸キュン度】☆☆☆☆☆ 0.0
【文学性】★★★☆☆ 3.0
【第九話】有るバイト、無いバイト

【作者オススメ度】★★★★☆ 4.5
【陰湿度】★★★★★ 5++
【恐怖度】★★★★★ 5++
【胸キュン度】☆☆☆☆☆ 測定不能
【文学性】★☆☆☆☆ 1.0
【番外編】夏の総復習

恋なんて愚かな気の迷いで、夏のせいにすることでしかこの胸の痛みを言い訳できなくて、けれども実は自分の気持ちに嘘なんてつきたくなくて、俺はただお前が欲しかっただけなのに、あの衝撃的な告白のせいで裏切られた気持ちになったんだ
あの頃は、読書感想文すら書けないただのガキだった
幻想風景~空蝉~
【作者オススメ度】★★★☆☆ 3.5
【陰湿度】★☆☆☆☆ 1.0
【諦念度】★★★☆☆ 3.0
【胸キュン度】★★★☆☆ 3.0
【文学性】★★☆☆☆ 2.5
【第十話】自己紹介ほか

遅すぎる自己紹介
大学と文学と僕のこと
自作を振り返る【エッセイ編】
【作者オススメ度】★★★☆☆ 3.0
【陰湿度】★★★★☆ 4.0
【諦念度】★★★★☆ 3.8
【胸キュン度】☆☆☆☆☆ 0.0
【文学性】★★★☆☆ 3.0
【十一話】秋は短し、滅べよ自意識。

灰桔梗
金木犀
秋と修羅
仮葬暗夜
一限ZOMBIE
【作者オススメ度】★★★★★ 5+
【陰湿度】★★★★★ 5++
【恐怖度】★★★★☆ 4.0
【胸キュン度】★★☆☆☆ 2.0
【文学性】★★★★★ 5+
【十二話】冬の棘

【作者オススメ度】★★★★☆ 4.3
【陰湿度】★★★★★ 4.8
【恐怖度】★★☆☆☆ 2.0
【胸キュン度】☆☆☆☆☆ 0.0
【文学性】★★★★☆ 4.0
【特別篇】箱根一人旅行記

本編
【幻の4日目】箱根湯本奇譚
【作者オススメ度】★★★★☆ 4.5
【陰湿度】★★★★★ 5+
【恐怖度】★★★★☆ 4.0
【胸キュン度】★☆☆☆☆ 1.0
【文学性】★★★★☆ 3.8
【最終話】都落ち
築年数50年のこのアパートには、少し奇妙なコミュニティがある。アパートの1階は喫茶店になっていて、そこには人形のように鼻が高く、彫りが深くて美しい女性がいる。噂だから確証は無いが、その女性の名前は「美夜子」だと聞いた。その喫茶店で半月に一度、美夜子主催のティーパーティーが開催され、住人たちはみな、そこに集うという。しかし、俺は未だ参加できていない。心の準備ができなくて。綺麗な人の横顔を見れるせっかくの機会なのに、窓越しに見る喫茶店の店内に点る間接照明やシワひとつないレースカーテンがミニチュアのオブジェみたいに茶目っぽく映るたび、俺はそこに踏み入れてはいけないのではないかなどと考えてしまう。
美夜子は看板娘で、仕事上沢山の男と話をしているみたいだった。俺は布団の中で、彼女が男に口説かれてついていってしまう恐怖に毎晩震えた。恋というレースは、この世で何よりも難しい。俺は走り方を知らないんだ。走り出す前から躓いて観衆に笑われる妄想がついてまわる。でも、大学生になってそろそろ焦りも出てきた。仲間だと思っていたヤツは、最初こそへっぴり腰で臆病な走り方を笑われていたものの、今では青空の下、美人を連れて街を歩いている。それを目の当たりにした日、「死にてぇ」と言いながら帰ってきたこのアパートの1階にある喫茶店に、なんとしてでも手に入れたい華を目にしたんだ。
俺が住んでいるのは2階の一番端にある、高架に面した部屋だ。ベランダに置いた植木鉢、そこに育てた初恋が、何度も高架を通過する電車の起こす風に揺らされるのを見た。雨にも打たれて、ずぶ濡れになった。けれど、ここで散るわけにはいかないのだ。光の中で堂々と息をしたくて、胸を張って歩きたくて。穢れを全部落とすように、何度も身体を洗った。
新歓の時期が過ぎて、春はいつの間にか夏の様相を帯び始めていた。アパートの斜向かいには公園があって、朝早く起きて散歩をすると気持ちがいいと気付いた。葉桜の下で本を読んでいるお爺さんは、どうやら同じアパートに住んでいるようだ。何を読んでいるのですか、と問うと、今村夏子だ、と答えた。へぇ、結構本格的な文芸作品読まれるんですね、と言ったら、黙れ若造、と言われた。それから、たまに最近読んでる本の交流なんかをするようになるのは、この時の俺には想像できていない。
美夜子はダンスが趣味らしいと小耳に挟んだ俺は、大学のダンスサークルに入ってみた。これが思ったよりガチガチのガチで、俺は週の半ばにある全体練で毎回身体を痛めた。しかも酷いのが、全体練を仕切るサークルの主将はダンスに人生を全振りしている人だったから、木曜日に一限必修があることなどは全く考慮してくれず、全体練が始まるのは夜の9時からだった。そして、フリを少しでも忘れていたり、周囲から目立った動きをしてしまうと、執拗に詰められ、連帯責任だと言って夜明けまでぶっ通しで踊らされるのだ。俺はもうボロボロになって、大学からはどんどん足が遠のいていった。サークルは退部届を出した。でも、半年分の部費や出るはずだった新歓公演の衣装代を含め20,000円近く払わされた。人を好きになっても、ありのままの自分で勝負できない情けなさが気持ちをみるみる沈ませてゆく。俺は春先にあれだけ浴びていたシャワーも全く浴びなくなった。周りが人生を謳歌しているのに、俺はカーテンを閉め切った部屋でストゼロを飲み、レトルトのカレーか安売りのカップ麺を食べ、日が暮れるまで眠るだけだった。実家から送られてくる仕送りの中に同封された手紙に返事をしなくなって、消費者金融からかかってくる電話を無視し続けた。夜、窓の外が赤くなった。俺は取り乱して、酸っぱい匂いのする押し入れに息を潜めた。その時、暗闇の中で着るはずだった新歓の衣装が足の指先に触れた。いざ着てみようとしても、最早袖が通らなかった。無理やり着ようとしたら、飾りのスパンコールが全て剥がれて落ちた。俺ももうすぐ、こうやって社会からポロポロと剥がれ落ちるのかと考えて、震えが収まらなくなった。俺は部屋を飛び出して、暗い夜道を叫びながら走った。途中の道にある祠の前にお供えされたお菓子を頬張る子供が目に入っても、ラブホテルに大人数のまとまった男女が入っていくのを見ても、何も思わなかった。苦しみと恥のグラデーションに目が回り、見えてるもの全てを口にしようとして、途中から言葉ですらない何かを口走っていると気がついた時、俺は知らない街の交番の前にいた。一応、国道沿いを走っていたはずだった。なのに、これまでの人生で一度も踏みしめたことのない土地に俺はいた。どうやら、来てはいけない場所まで来てしまった。冷静にそう思った。
目の前の交番には、警官の一人もいない様子だ。それどころか、見渡すと周囲には人っ子一人歩いちゃいない。交番に入ってみると、警官が白目を剥いて倒れている。カウンターの死角で、さっきまで見えなかったようだ。死んでいるのか? と考えて、カウンターを回り込み、息をしているか確認する。そして、俺は飛び上がった。——それは、蝋人形だ。
蝋人形が警察官の制服を着て、交番の中で倒れていた。となると、これは全てドッキリなのではないか。俺は苦笑しながら、その蝋人形の腰の辺りにある拳銃を手に取った。「おお、重い」と口には出してみたものの、ちゃんと掴めていなかったようで、もう一度銃に手を伸ばす。しかし。
「消えた」
銃の手触りを憶えたのは一瞬で、すぐにそれは消えてしまった。そして、視界の隅にあった交番のカウンターは、いつの間にか台所に変わっている。……そして。
『ふふっ……、驚いた?』
目の前で倒れていた警官の蝋人形すらも消えてしまった。背後から聞こえたその声に振り返ると、美夜子が立っていた。そして、場所は俺の住んでいる部屋の中だった。これは、一体どういうことなんだろう。
『催眠をかけたの』
俺の疑問を見透かしたようなタイミングで、彼女は答えた。そうか。徐々に記憶が戻ってきた。俺はこの数時間前、勇気を出して階下の喫茶店に足を伸ばしたのだ。そして、美夜子の淹れるブレンドコーヒーを飲んだ。それから、色々おかしなことが起きた。窓の外が赤くなって、夜道に飛び出した。そのもっと前から、催眠をかけられていたのか。だけど、なぜ?
「どうしてそんなこと」
『あなた、私のこと好きなんでしょ?』
明け透けにこの気持ちを伝えたいとは思わない。ずっと胸の中に、綺麗なまま仕舞っておくつもりだった。だけど、ここで強がって首を横に振ったとして、彼女はその時何を思うだろう。あらゆる反応も、彼女の術中なのかもしれないと気付き、何とも言えない表情になった。
『好きって気持ちだけで、どこまで行けるか試してみたかったの。私がマゾの性癖をもってたとして、今ここで血が出るまで殴ってって言ったらあなたは殴る? 今でも塞がらない穴のような暴言を、記憶の中から取り去ってって言ったら、あなたにそれが出来る? きっとそのどれも、あなたは出来ないんでしょう。彼女のことを俺なんかが、ってきっとそればかり。変われない、いや、変わらない自分が一番可愛いの。そうやって、あなたは私を利用した。あの日も、今日みたいに蝉が五月蝿かった』
彼女が話してる途中から、部屋に蝉の鳴き声が響いていた。そして、その鳴き声は徐々に大きくなっていき、終いにはサイレンのようなボリュームになった。施錠をしていなかった窓がいきなり外側からこじ開けられ、蝉の死体が大量に投げ込まれた。それを見て俺は、散った桜の花びらはどこへ行くのだろうかと考えた。そして、今自分はどこに居るのだろうかとも。
彼女が口走った、〝私を利用した〟〝あの日も、蝉が五月蝿かった〟の意味を、頭の中で必死に反芻する。突然耳鳴りがして、俺は夏のある日に引き戻された。いやしかし、あれは夢の中の出来事だったはずだ。
7月7日。河川敷を、俺は歩いていた。イヤホンから流れているのは、久石譲の『Summer』である。そして俺は、川の方に視線を向けた。その下流の方で、男女が揉み合いになっていた。男の方は見るからに汚くて、臭そうだった。そいつが、女を死に物狂いで川に引き摺りこもうとしている。ふたりは、紐で身体を括っていた。しかし、女は紐を解こうとしている。男女の身体は激しく縺れ合い、やがて女のTシャツが捲れた。そのあわいから、痣のある斑な肌が覗いた。俺は河川敷の階段に座って、原稿用紙とペンを手に取った。川の流れが激しくなってきて、男は流されそうになっている。女は泣きながら、『ずっと大好きだった』と叫んで、自分のTシャツの裾から、男が掴んでいる手を剥ぎ取った。男は川に流されて、とうとう見えなくなった。俺はその数日後、「金魚と少女」を含む最新エッセイ『ブルーは欺く』を発表した。そして、殺害予告のような奇妙な手紙が届いたのは次の日のこと。
『お前もこっち側に引き摺りこんでやるよ』
その手紙が入っていたのは、アパートの郵便受けである。ただ、恐ろしかったのはそれだけじゃない。郵便受けに、モーターで作られた子供騙しの金魚と、浮き具が詰められていたのだ。俺は怖くなって、部屋を出た。ドアの前には、女が立っていた。
『まさか、書いたわけじゃないですよね?』
え、と声が出た。今すぐに逃げないと、刺されると思った。けれど、否定をしておかないとまた家に彼女は来るかもしれない。
「書いてないです! そんな、あの日のことなんて!」
そう叫んだ途端、〝しまった〟と思った。彼女の顔に嘲笑が浮かび、ナメクジのように口元が動いた。
『そうですか、よく分かりました。洗濯物、次はすぐに回収するようにしますね。ブラとかはほら、男の人だと変な気起こしちゃうかもしれないから』
そう。当時住んでいたアパートは、郊外にある「光が丘」の格安物件で、建物は脆く、地震でも来ればいつ倒壊してもおかしくない建築だった。そこでは、風呂や洗濯機が共用になっていて、彼女の手にあったのは、〝○◆■号室の女!洗い終えた洗濯物はすぐに回収しろ!〟とマジックで刺々しく書かれた紙だった。俺は激しく後悔した。今思い返すと、美夜子と俺はあの瞬間から顔を合わせていた。彼女が、紙切れをヒラヒラさせながら、階段を下っていく。蝉の鳴き声がまばらに響く夏の日の午後、俺は彼女の背中を、過呼吸混じりに眺めていた。
腐臭の如く気分の悪い記憶が蘇り、俺は思わず顔を顰めた。今まで、誰かの吐瀉物を処理させられているような人生だったと思う。いや、それは真夜中に抱くやるせない被害妄想に過ぎず、実際は湿気った煎餅のように無味乾燥な人生だ。誰かを「殺したい」と言いながら、本心では誰かに「愛されたい」と気がついたのが高校2年生で、それから物語を書くようになった。だけど、描いた理想と現実はあまりにギャップがあって、その矛盾が一層物語を鋭利に研ぎ澄ましていくんだった。嫌いな奴も、この世の悲愴な事件も、全て俺は物語に利用した。
部屋の隅にあるワイヤレススピーカーから流れていた蝉の声はもう止んでいて、ラジオに変えられていた。パーソナリティの芸人が、低くてかっこいい声で言う。
「次が最後の曲になります。〝灰桔梗〟」
俺が記憶の混濁に吐き気を催していると、突然上階が騒がしくなった。俺の部屋の真上に住む住人は、この時間帯になると、絶叫しながら沢山のゴミを家の外に放り出す。そして、全てを出し終えるとまた一つずつ、家の中に放り込む。この一連の儀式は、夜明けまで何度も繰り返される。そして、それが今夜もまた、始まったのだ。
『ぎゃああああああああああああああああ』
断末魔のような声が、夜の底を舐める。気が触れそうになる号哭の中、どすん、どすん、と音を立てる怒りが、どうかこの天井を突き破ってここへ侵入してくることがないように、と祈った。同時に俺は、窓の外を電車が走っていることに気がついた。時間は深夜の2時を廻っている。俺は窓を開けてみた、それも何かに誘われるように。
〝牛満都蔭行き〟とだけ表示された、真っ黒の車体が蛇のように右から左へと流れていった。赤い光は、いつしか消えていた。そういえば、美夜子はどこへ行ったのだろう。さっきから声を掛けてこない。部屋を隈無く見渡すと、蒲団の中でモゾモゾと動くものがある。
俺は溜め息をつきながら、蒲団を捲り上げた。蒲団の中では、美夜子の身体を酷く老い耄れた俺が犯していた。しかし、美夜子はピクリとも動かない。マグロかと訝しみ、俺は彼女を近くで仔細に観察した。それはただのラブドールに過ぎなかった。布団の傍を見回すと、ぐしゃぐしゃに丸められた原稿用紙と、ドラッグが散乱していた。季節は分からないが、日めくりカレンダーは「4月20日」と表示していて、だけど、様子がおかしい。テレビをつけてみる。
「は? どういうことだこれ」
ワイドショーが言うには、大谷のマネージャーの水原一平が大谷の金を違法賭博に使って捕まったという話だった。違和感はこれだけに留まらない。扱うニュースのVTRが終わり、映像がスタジオに切り替わる。そこに、見慣れた芸人の姿は無く、代理が座って場を盛り上げようと必死だった。背中を冷たい汗が流れた。俺はいてもたってもいられなくなり、友人に電話を掛けた。
「おい、遠野! どういうことだこれ。水谷一平って最近までWBCに行ってたはずだろ。侍ジャパンがマイアミであったアメリカ戦で3度目の優勝を果たして、大谷が締めてたじゃねぇか。てか、大谷は結婚してるのか? なぁ、○ちゃんはなんでスタジオ出演してないんだよ」
『何言ってんだお前。テレビ捨てたのか? 気でもおかしくなったか。インボイスが始まったのもまさか知らないなんてことないだろうな』
「待てよ。インボイスってなんのことだ?」
『話にならねぇな。宇宙人か何かだろお前』
こうして、電話は切られた。俺の知らないうちに、世界は目まぐるしく変わっていた。枕元には、3月号の『文學界』がある。2024年の『文學界』3月号が。目次に目を通す。安堂ホセ、くどうれいん、九段理江、市川沙央……。知らない作家ばかりだ。検索窓に名前を打ち込んでみる。市川沙央や九段理江は、共に2023年の芥川賞作家だった。両者に共通したのは、文学としての特殊性にあって、それをメディアが注目したのはなんだか理解できた。ただ、そのフックみたいなものが無いと、今では受賞も難しいのだと考えてみると、やや鼻じらむ。
そして、俺は徐々に察し始めていた。俺が今日に至るまで、見てきたもの書いてきたもの。それは全て虚像の世界で創り上げたもので、誰もが消費していく普遍的なフィクションを、つまらない気持ちで全てスルーしていたんだ。そこまでの犠牲を払ってしても、追いつけない距離に文学はあった。幾億光年の旅、それを始めてしまったのが、昨日のちょうど一年前だったんだ。変な自分に当たり前に傷付きながら、それでも酔ってるんだから多分病気だ。そうだ、病気でいい。いつまでも患っていれば、いつまでも煩わしい何かに関わらずに済む。今夜は奇祭だ。俺は奇才だ。数十年後には、遺灰だ。きっと無理なことを全部小説にして乗り越えながら、笑顔で不特定多数を傷付ける。
「文学童貞はとりま死ね」
どうしてこんなに今日は暑いのだろう。煉炭で死のうとしてる時のように息苦しい。ここまで書いた原稿も、どこまでが自分の書いたもので、どこからがAIの書いたものなのか思い出せない。いや、本当は俺が純度100%で書いたものかもしれない。逆も有り得る。俺は名前を貸しただけに過ぎず、100%生成AIの文章かもしれない。けれど。

カメラロールを漁ってみると、カクヨムの運営から俺の書いた小説が警告を受けた時のスクショがあった。こんなミス、AIならばやらない。こんな綺麗じゃない、もっと言葉を選ばずに言えば、ここまでだらしない小説は俺以外に書けない。
俺は部屋を出た。今日の空は、鬱陶しい快晴が広がっている。俺は毒づいた。どうせこんな綺麗な紺碧の空も、ありふれた漆黒の色に染め上げられるのだと。昨日は飲み過ぎたから、家を出て早々、トイレに行きたくなった。トイレに貼られた夥しい量の紙切れには、子供の落書きがある。『トイレの神様』と、律儀に毎回書いている。鏡を覗く。俺はもう人間じゃなく、鬼になっていた。もうそこに、幼少の面影は残っていない。
そうか、俺は最初から喫茶店の中にいたんだ。窓があるとか無いとか、そんなのは妄想に過ぎず、本当は美夜子の隣にいたんだ。俺はふかふかの椅子から立ち上がれず、メニューから目を離せない。あの日の喫茶店から、今日は地続きにあったんだ。すみません。声を出して、美夜子を呼ぶ。


「コーヒー牛乳ひとつ」
『はぁい』と美夜子は答える。猫のような甘い声で。だけど、はて、こんなに髪色は明るかっただろうか。きっと、熱に浮かされたように身体を火照らせた俺と、かつてのバンドメンバーが焦がれた美夜子(仮名)はもうここには居ない。世代交代、と言っては大袈裟かもしれないけれど、〝喫茶深海〟の店員は変わったのだ。衣装もフリフリのレースがついた青いのじゃなくなった。あの甘酸っぱい想い出も今では、青春の亡骸でしかない。目を覚ました頃には、夜の帳が降りていた。


コーヒー牛乳に浮き上がった後悔は、今しか味わえない。酸いも甘いもとぐろを巻いて、海に沈むまで本気になれない。バーカウンターを挟んで浮かび上がる迷いを、咀嚼しようとしたら一杯じゃ足りない。愛されたい。今なら言えるかもしれない。
『お客様、ラストオーダーになりますがいかがされますか?』
胸が苦しくなった。声を掛けようとしても、先に声を掛けられる。手を繋ごうと、女の子に先に言わせてしまう。あと10秒あったら言えた。そればっか思うけど、結局素面じゃ何も言えないのだ。分かってる。
「いえ、何もいらないです」
目の前には、レウィシアの花が置かれている。花言葉は、〝ほのかな思い〟だ。
そう、全てほのかな思いだった。本気で誰かと関わりたいと思ったことなど一度も無くて、正直誰でもよかった。彼女が出来りゃ良かったから、ヤバめの女と付き合った。分かりきっていた綻びが出た時、俺は掌を返して罵った。だって、本気で愛してなかったから。自分の小説に利用したかっただけだから。最後の場面まで役を全うできないなんて、役者なら有り得ないのだから。
俺は店を出た。この先、どこへでも行けると思った。新宿に行けば、夜に惑う俺に会える。未明町に行けば、風俗は腐るほどある。下北沢に行けば、霞の中に姿を隠せる。どこに行っても、独りなんかじゃない。この連載の中で出したエッセイを数えてみると、30本を優に超える作品たちに無料でアクセスすることができる。人生は基本的に楽しくないから、俺が面白いものを作れたらいいなと思って始めた連載だった。呻き声に思わず、背後を振り返ると、一限に出られないゾンビが地面を這っている。ああ、こういう時に使うのね。そう台詞のように口に出し、俺は初めて銃をぶっ放した。夜の静寂を、銃声が切り裂いた。但し、誰も見てる者はいない。現実にそろそろ追いつく頃だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
