
秋は短し、滅べよ自意識。
「おや、こんな所でお会いするとは」
貴方は僕に向けて余所々々しく言った。
「この列車が何処に向かっているのか、あなたは知っていますか?」
僕はよく分からなかったから、首を横に振った。ポケットの中から切符を取り出すと、それは掌の中で落ち葉のように粉々になり、まだ名前のない風に攫われていった。貴方は構わずに続ける。この列車には、終着点が無いのだと。
列車の中では、乗客が事ある毎に深呼吸をしていた。それは、何のためなのか。あと一歩を踏み出さないようにするためである。我々はいつも、あと一歩踏み出せば罪人になれる地平を歩んでいるのだ。

長いトンネルを抜けると、新しい季節が待っていた。秋という季節だ。みな、新たな季節の訪れを歓迎するように立ち上がり、各々車窓を眺めた。その光景は、まるであと一歩を踏みとどまることの出来た人間だけが辿り着いたエデンの園のようだった。ただ僕は、線路の脇に咲き乱れる、季節を代表する花々の鮮やかさに動揺を隠せない。それは、あの時手を伸ばしていれば救えたかもしれない生命だったから。花が綺麗であればあるほど、途方もない不安を募らせた。
🍂
僕はまだ、あのトンネルの暗闇の中にいる。
救えなかったあの子の記憶に
囚われたままでいる。
■灰桔梗
ほんのりと空が赤く染まった明け方、男は話をこう締めくくった。『それに……俺がやらなきゃ誰がやるんだよ』と。
昇りたての太陽を背に語る彼は、まるで世界の安寧を託されたヒーローのようだった。しかし、冷静になってよく見ると、ボロボロの汚らしい洋服を身に纏っていて、その身体からは生理的にきつい臭いが放たれていた。それに……彼の話はとてつもなく長かった。深夜2時過ぎにインタビューを始めて、少なくとも3時間は経過している。彼は日本語をまともに勉強してこなかったのか、私の投げ掛ける質問にはほとんど答えず、自分の人生における武勇伝ってヤツを鼻にかけて自慢した。その内容の殆どは、学生運動に参加して警察に捕まったことや、クラスのマドンナにセクハラをしていた教師に暴行して謹慎処分を受けたことなど、自分の逞しさを見せつけようとして空回りした割に“俺はそれを後悔していない。あの経験があったから、今の俺がいる”と典型的な勘違いを拗らせている話なのだからサムかった。私は途中から耐えられなくなって、カーディガンを一枚羽織ったほどだった。
さて、本題に入る。彼が『俺がやらなかったら誰もやらないだろう』と自負してやっている事が、自販機の横の屑入れから溢れたペットボトルを夜な夜な忍び足で掻き集め、家に持ち帰るという事だ。これは一体、かっこいい事なのだろうか。私には分からない。だって別にその男がそんなことをしなくても、薄々回収業者は気が付いているだろうし、そのうち回収頻度を増やしたりもするだろう。むしろ、彼がこっそり夜明け前にゴミを見えない場所に持っていってしまうせいで、回収業者は事態把握が遅れてしまうだろうし、全ては無意味でしかないのだ。私は帰りに銭湯に寄り、長尺のインタビューに疲れた身体を癒した。湯上りにコーヒー牛乳を飲み、それじゃあ帰って一寝入り……といきたいところだったが、まだ消化しきれていない仕事が山積みであるため、本社に戻ることにした。
『秋月さん』
後ろから声を掛けられ、ハッとして振り向くと、本社に戻って早々デスクで眠り込んでいたことに気が付いた。編集長が立っていた。
「はっ、はいっ! 何でしょう」
『何でしょうじゃないでしょう。特ダネ拾ってきたのか?』
数日前の、企画会議が全ての始まりだった。
同期との出世レースでボロ負けの私は、いつしか会議室に珈琲を運ばされるようになっていた。しかも不運なことにその日は偏頭痛に見舞われ、私はフラフラしながら珈琲を配っていた。窓の外、なんの前触れもなく大きな黒い鳥が突進してきて、私は思わず目を瞑る。頭が割れるような痛みと、鴉のうるさい鳴き声。ぐらっと視界が揺れて、私はとうとうバランスを崩してしまう。数人分の珈琲がこぼれ、横に等間隔で並べられた資料を一直線に茶色く染め上げるまで一瞬だった。数秒後、私は編集長に詰め寄られ、会議室の隅で暴言を浴びせられていた。そして、編集長の先には私を嘲笑う他の部署のお偉いさん方がいて、私は思わず泣きそうになる。そこに割って入ってきたのが、同期の遠野。パーマをあてた前髪をセンター分けしている男で、少し独特なネクタイをつけている。そんじょそこらの男じゃ様にならないコーディネートをさらりと着こなしているのだからズルい。彼は言った。
「まぁまぁやめてあげましょうよ。彼女も彼女なりに頑張ってるんだから。それに、足使って経験値積んでる秋月さんと、使えねぇ安楽椅子探偵よろしくその座面に胡座かいてるアンタらと、俺はどっちの方がこの先長く会社に残り続けるんだろうって考えちゃいますけどね。俺は彼女の頑張り、いつも見てますから」
彼の言葉で、会議室がしんと静まり返った。
流石は少なく見積っても30人以上の女と寝たとウワサの遠野だった。上司に向かってこんな物言いが出来るのは、後にも先にも彼しかいないだろう。
『お前、上司に向かってどの口聞いてんだ』
そう言って詰め寄る編集長の襟首をやすやすと彼は掴み、「編集長ほら、持病持ちでしょ?? そんなに興奮したらまた倒れちゃいますよ。あなたの代わりはいないんですから、お身体大事になさってください」と椅子に座らせた。それから彼は好きな安楽椅子探偵の話で凍りついた場を温め、弟子のような部下に資料を刷り直して持ってこさせた。会議は無事に始まり、私は特ダネを取ってくれば編集長に許されることになった。期限は一週間。来週からの新連載、『巷のマイノリティ』がテーマだった。
そんな数日前の記憶を振り払い、私は編集長と真摯に向き合った。
「来週の連載、“積もった灰を拾う者”というタイトルでいこうと思います」
編集長は変な漬物を食った時みたいな顔をして、『なんだ? 追い詰められすぎて、喫煙所で小人の幻覚でも見たか?』
「違います。良い感じの奇人がいたんです」
『あそ。まぁ、出来りゃあ良いけど。お前には荷が重いだろうなぁ?』
そう言って、むやみに肩を叩いてデスクに戻っていった。最後まで私はそれを目で追い、ちゃんと嫌な気持ちになった。実際、あのゴミ拾いヒーロー気取りジジイのインタビューを全文載せる訳にはいかない。事実確認も取れていないし、近隣住民の声も欲しいところだし、自動販売機のメーカーから委託を受けたゴミ収集業者にも問い合わせをしてみなければならない。と……、そんな山積したタスクを頭の中で整理していたら、後ろから遠野が現れた。
『やっぱウゼェな、あいつ。言動全てが時代遅れだから、きっと半年後には淘汰されるんだろうな。そんなことより、ネタ掴んできたんだね。凄いじゃん、秋月』
そう言って、彼は私のデスクにさりげなくスタバのギフトカードを置いてくれた。裏側のメッセージ欄には、下手くそな猫のイラストが描かれていた。
『色々大変だと思うけど、お互い頑張ろうな。連載終わったら、二人で飲み行こうよ。もちろん俺奢るからさ』
薄らと下心を感じはしたが、不思議と嫌な気持ちはしなかった。
その夜、私はインタビューの録音を全て聴き直した。インタビュー当初はただ頭のおかしいジジイとしか思わなかったが、再び聞いてみると、彼はどこか不自然な間を取っていることに気が付いた。記者の勘、と言って良い程のものなのかは分からないが、私は確信した。このお爺さんは、何かを隠している。
近隣住民Aから聞いた話。
『彼は絶対に病気よ。自分で持ち寄った黒いゴミ袋いっぱいに溢れたペットボトルやら空き缶詰めて、満足そうに、笑い声なのか鳴き声なのか分からない、とにかく奇声を発しながら夜明け前に家に帰っていくの。彼の家の排気口からはコウモリが飛び出してくるって噂もあるんだから。本っ当に気持ち悪い。それでこんな話もあって、彼はテロリストなんじゃないかって。爆弾を秘密裏に開発していて、その実験の痕跡が……』
この人はちょっと他人の噂を真に受けすぎるところがあるな、とは思った。しかし、この中に真実が少しでも包含されている可能性がある以上、単なるゴシップ好きババアの戯言に過ぎないと切り捨てるわけにもいかない。
そして、近隣住民Bの話はいささか衝撃的だった。Aの偏見に塗れた話とは180度くらい角度の違う、人間味溢れるお爺さんのエピソードが語られたのだった。
『あぁ、はいはいマモルくんね。あの人はね、結構複雑なのよ。父親が確か、転勤で異国の紛争が絶えない地域に飛ばされて、爆撃で亡くなったらしいの。瓦礫の中に埋もれた父親は、もう最後の表情すら分からなくなってたって。黒焦げの遺体の一部が数ヵ月後に家に運ばれてきて、彼はボロボロ泣いたそうよ。だってそりゃそうよ。彼が最後に父親に書いた手紙、最愛の人と婚約を結ぶことができましたって報告よ。父親のリアクションを見ることはもうできないし、そもそも生前にその手紙が開封されたのか、届いていたのか、それすらも分からないそうじゃない。そんなことって無いわよ。苦しすぎるわよ。その約一ヵ月後、一家には莫大な保険金が振り込まれて……って話。勘のいいあなたなら分かるわよね? そういうことよ。母親はいずれそうなるって分かっていたのよ。途端に家は裕福になったらしいけど、彼はそれと裏腹に病んじゃったの。洋梨を剥くように指図してきた母親を果物ナイフで■して、こっちに引っ越してきたの。人知れず、ヒーローになるために。彼はずっと何かに囚われながら生きているの』
私はつい、疑問に思って訊ねてしまった。
「その父親っていうのは、何の仕事をされていたのですか?」
Bさんは少し考えるように宙を仰いで、
『それはあたしにも分からないわ。でも、国防とか或いは家族すらも詳しく知らせちゃいけないような“死”と隣り合わせの仕事だったんじゃないかしら』と言った。
後日、いつものように自販機横の屑入れから溢れたペットボトルやら空き缶やらを集めるマモルの後をつけ、家を特定した。すると、彼は家の敷地に沢山ゴミを溜め込んでいることが分かった。それどころか、ゴミの幾つかは道に散乱している。彼の家の周囲だけ、空の色が紫であるような気がした。風が吹くたびに彼の家はミシミシと音を立て、電線に止まっていた鴉も飛び去った。コウモリの存在は、確認できない。あれは流石に作り話に過ぎなかったのだろうか。と、上空から轟音。
途端にジグソーパズルのピースのように、空の一部がバラけ、いくつか戦闘機のような形の穴が空いた。私は恐怖のあまり声が出せなくなり、身をすくめる。直後、地面が波打った。激しい衝撃に咄嗟に頭を守ると、大きな爆撃の音がした。私ももうここまでか、と思ったが、私は誰かに抱きかかえられ、叢の中に飛び込んだ。煙で見えなくなった視界がクリアになるのを待って、命の恩人の顔を見た。それは、恐らく遠野だった。
恐らく、と言うのはここで目が覚めたからだった。私はまた夢を見ていた。時針は既に22時を回っている。デスクを濡らした涎を拭い、窓の外に視線を移そうとする。そこで、隣に遠野がいるのに気が付いた。彼は私の顔を覗き込み、『やっと起きたね』と笑った。
『カップヌードル作っといたから食べなよ』
彼は私の肩から慣れた手つきでブランケットを剥がし、丁寧に折り畳んだ。ありがとうと言った後、少し疑問に思って、
「遠野くん、私と寝たいの?」
冗談半分、本気半分で聞いてみた。彼はちょっと考えるような顔をして、『秋月と寝たら涎まみれにされそう』と茶化してきた。私はムッとして頬を膨らませた。彼はそんなこと気にも留めない様子で、『3分経ったよ』と言った。私は仕方なく、割り箸でそれを啜り始める。
『さっき秋月の寝顔見てたんだけどさ、すっごい不安そうな顔してて。俺も初めて連載任された時はずっと緊張状態だったし、カノジョとも別れたばっかだったからさ、なんか気が狂いそうだったんだよ。だから、お前の気持ちめっちゃ分かんの』
彼は窓の外に見える東京タワーを眺めながら、話していた。
『俺が隣にいるだけでも、違うんじゃないかなって思うんだよ。だからさ、今夜はうち来て寝なよ』
私は皮肉たっぷりの顔でこたえた。
「今夜だけだからね、ヤリチンくん」
彼は『心外だなぁ』と言って笑った。
翌朝、お爺さんの家が崩壊したと本社から電話が来た。私と遠野は、素早く服を着て家を飛び出した。現場に到着すると、そこには黒いビニール袋から飛び出したゴミと瓦礫の山があるだけだった。私は力の限り、叫ぶ。
「おいマモル! 戻ってこいよ!!
お前がいないと、誰かが困るんだよ! それにお前はまだヒーローになってないだろう!?」
しかし、どれだけ声を張っても返事が返ってくるはずも無い。ただ、私たちは瓦礫の山を避けるようにしてほんのわずかな隙間で咲き誇る、一輪の桔梗を見た。その桔梗はピンク色で、まるで父親がまだ生きていることを信じているような色であった。私は嗚咽を漏らしながら、本社までの道をタクシーで戻った。
後日瓦礫の山から発見された遺体は、母親らしき一体のみであった。マモル(本名かは不明)の行方は知れず、戸籍謄本に照らし合わせた限りでは、彼の出生届は役所に存在しなかった。私は桔梗の記憶と夢の中で聞いた爆撃の音が脳裏にこびりついて離れず、気が付けば毎晩夜明けが訪れる前に、ひっそりとゴミを掻き集めるようになった。それは、抜け出せない泥濘だったのだ。新聞は理由はわからないが廃刊になり、組織は解体された。季節の変わり目を読んで本社の前の道を通ると、まるで落葉が戦の後の血溜まりだった。
■金木犀

金木犀の香りが充満した部屋の中で、インディーズ映画を観るのが秋のささやかな楽しみだ。面倒な衣替えを終えた午後、僕は束の間の自由を手に入れた。夏の間は溶けるからあまり食べられなかったキットカットも、今となっては常温で保存できる。テレビの電源を付けた僕は、ホットココアを片手にどんな映画を観ようかと考える。ここは順当に片山慎三監督の『岬の兄弟』か……。あるいは、僕が『マイマザーズ・アイズ』で衝撃を受けた串田壮史監督の『写真の女』か……。いや待てよ、最近足を運んだばかりの下北沢映画祭で上映された作品がU-NEXTで配信されてるじゃないか……!! これをもう一度見るのも良いではないか。よしよし、興が乗ってきたぞ。
思い返せば、イスラエル出身の映画監督オーレン・ペリのデビュー作であり、今もホラー映画史にその名を残す『パラノーマル・アクティビティ』も自主制作映画だった。あの映画の恐怖は凄まじかった。あれを思い出すと今でも鳥肌が立つ。いけないいけない、ただでさえ肌寒い季節になったのにホラー映画のことを考えるなんて。
ブランケットに身を包んだ僕は、キットカットを食べながらふと考えてみる。もし、僕が映画監督をやるとしたら。
僕はディレクターズチェアに深く腰掛けて、黒いサングラスを掛けている。役者の演技にごちゃごちゃ文句をつけながらも、実は映画がいつまでも完成しないと良いななどと、頭の片隅で考えている。作品は完成させた瞬間から、手元を離れていってしまうからだ。そして、映画を共に作っていく仲間たちとも再び全く同じメンバーで作品を撮ることはできないだろうから。僕は人類が滅亡する瞬間の映画を撮ろうとしている。しかし、美しいラストシーンが思いつかず、次第に声を荒らげる回数が増える。役者との衝突は日常茶飯事。「こんな監督には付いていけない」と役者たちはひとり、またひとりと映画の完成を見捨て、現実的な働き口を探し始める。内定をもらった者は就職し、余命の限られた両親から顔が見たいと言われた者たちは地元へと帰っていく。
そして、やがて僕は独りになる。
季節がどれほど巡ったのか分からない。もう誰も戻ってくることはないのに、その頃になって僕はようやくラストシーンを思いつく。静かな秋の湖畔で僕は涙を流し、金木犀の香りを胸いっぱいに吸い込みながら、一人で台本を音読するのだ。そして、最後に
「もう取り返しのつかないとこまで来ちまったな。みんな、僕が間違っていたよ。きっとこの可憐な金木犀のようにあるべきだった」と悔しげに笑って、そこでエンドロールが流れる。
僕は多分、そんな映画が撮りたい。
■秋と修羅
特にやることも無かったから部屋を掃除していたら、机上のゴミ山からクラフト製の紙袋が出てきた。俺は掘り出した瞬間、その痛恨の中身に思い当たって、苦虫を噛み潰したような顔をせざるを得ない。
その中身というのは、元恋人から貰った誕生日プレゼントだった。思ってもない言葉を並べただけのラノベみたいな文体の手紙はとりあえずビリビリに破って捨てるとして、コイツはどうしたものか——。今ではコーヒーマシンの中の黒くて不快な残滓みたいに思えるそれは、ガラスペンとインクのセットだった。

俺はこんな事になるなら貰わない方が良かったとは思ったが、まるで一滴の黒インクがバケツに張られた水に飛び込んだ直後のような考えを巡らせた。そうだ、金に変えてしまえばいい。
思いついた後は、すぐに行動に移した。途中まで進んでいた掃除を投げ出して、それを突っ込んだ鞄を持って俺は家を出た。外に出ると、枯葉が何か気まずいものを覆い隠すかのように一箇所に集められていた。思えば、机上のゴミ山はこういう目的だったのかもしれない。知らず知らずのうちに俺は、気まずいものに蓋をしていた。
長らく乗っていなかった自転車は空気が抜けていて、漕ぐのにも一苦労だった。漕いで数分で身体の至る所から汗が出てきて、全く困った。母校の部活の後輩たちは、今日も元気に外周をさせられていた。
母親がかつて働いていたリサイクルショップに、俺は到着した。とりあえず査定をお願いして、俺は懐かしい気分で店内を散策した。腹筋を鍛えたりする道具があって、『絶対にそんな物買ってくるな』と母親からマジ顔で購入を反対されたことを思い出した。今思い出すと、ちょっと面白かった。
査定の結果、700円の値がついた。あまり期待せずに売った関係ない日用品は100円の値だったが、インクとガラスペンが合わせて700円になるとは思いもしなかった。母親の査定では、ガラスペンとインクを合わせて300円くらいの買い取りだろうということだったから、なかなか良い値がついたのではないか。俺は迷わずにそれらを売り払った。これで当面の生活は食いつなげるだろうと思った。
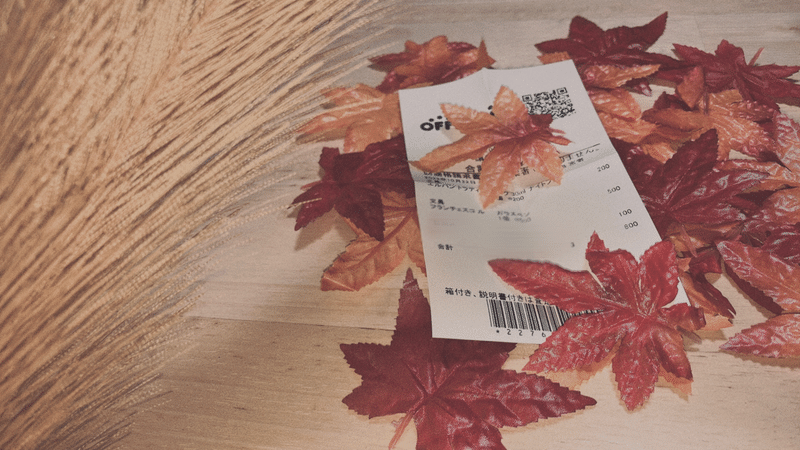

しかし俺は金を受領した後、レシートに印字されたそれらのブランドを検索窓に打ち込んで、雷に打たれたような衝撃を受けた。インクはエルバンのトラディショナルインク、定価1870円。色の名前はナイトブラ、おっと間違えたナイトブルーとかいう呪いみたいな名前であるにせよ、俺は結構上等なものを貰っていたようだった。そして、お次はガラスペン。フランチェスコ・ルビナート社の剣を模したもので、お値段なんと7884円。およそ8000円ということになる。この2点を合算すると、9754円。ラッピングや便箋の値段も合わせたら、10000円前後になるのではないか。買い値と売り値の間に利益があるにせよ、流石に二束三文でそれらを買い取らせてしまった数分前の自分を少し恨んだ。

とはいえ、俺は晴れやかな気持ちでもあった。二束三文で思い出を売ったことによって、あの短命だった恋愛の真似事がそこまで価値のあるものではなかったのだと思うことができた。俺は幸い、嫌な記憶を作品へと昇華させることによって快感を得ることができる人間だったので、生身の異性と身体を重ねられなくても、そいつがたとえ死んだとしても、等身大のキャラクターを浮かべることでいくらでも性処理に用いることができた。
そんなクズみたいなことを考えながら歩いた帰り道、あまりに眩しい斜陽を見た。
それは、最後の最後まで「愛」を知ろうとした俺への皮肉のようでもあったし、この先俺が命を燃やすような恋に落ちる暗示であるような気もした。幼い頃、父親と妹と3人で遊んだ公園には、あの頃と何ら変わらない時間が流れていた。俺だけが焦って、自爆したのだ。地平線を赤く焦がす斜陽から少し視線を逸らせば、薄明の空に血色感のない月が浮かんでいる。目を瞑ったら、それは空から姿を消した。この瞬間、俺は誰かを愛するように自分を愛せる気がした。同時に俺は、大学で週に一回しか会えない女の子の横顔を思い出した。そんなドラマチックな夕暮れに名前をつけていいのか、今の俺にはまだ分からない。
■仮葬暗夜
『トオノさんって、いつの間にか後ろにいますよね』
こんなことを、最近友人に言われた。
存在感が無いということだろうか。
また、カラオケ屋のバイトで受付をしている時、目の前にいるのに「店員呼び出しベル」を客に鳴らされることもあった。これは一体、どうしたことなのだろう。
最近、ハロウィンの気配を街中で感じ取ってもワクワクしなくなった。怪しげなパンプキンやゴーストの描かれたパッケージのお菓子を見ても、おどろおどろしい雰囲気を纏った100円ショップの店頭を見ても、何も思わなくなった。子供の頃は使う宛もないのにコスプレ用の血糊を購入したり、ハロウィン仕様のお菓子を沢山買い込んでいたのに、そういう類のものに徹底的にドライになってしまったのだ。安っぽくて荒い作りのマントを着てはしゃいでいた少年の面影は、今となっては何処にも無い。
俺はきっと今年も、渋谷スクランブル交差点ではしゃぐ話の通じない馬鹿どもの問題行動を翌朝にテレビのニュースで見て思うのだろう。
こいつら早く消えればいいのに。
そう考えた矢先に俺は、渋谷の雑踏の中に立っていた。自分がどの電車に乗ってここへ来たのかも分からないし、来た動機もよく思い出せなかった。雑踏の中に留まることはできず、仕方なく歩き出したら東急ハンズが見えてきた。東急ハンズの入り口は、まるで俺を喰らおうとするかのように大きかった。
俺は東急ハンズに入り、真っ先に2階にある人体模型のコーナーへと足を向けていた。俺は一体、何がしたいのだろう。ハロウィンという外国の文化をその意味もロクに理解しないまま馬鹿みたいな顔で仮装をするニッポンという国にウンザリしてはいるものの、頭を空っぽにしてそのムードに浸って、友人を驚かせたり、誰かに注目されたいなんて幼気な心を持っているのかもしれなかった。
俺は、気付けば1体で数万円する人体模型を購入していた。その傍らでは、女の形をしたマネキンに股間を擦りつけている浮浪者がいた。仮装などしなくても、この世の人間は大抵変態だと思った。
その後、俺は人体模型を抱きながら渋谷の街を歩いた。けれど、そんなことをしても通行人が振り向いてくれることはなく、俺は混乱した。どうして、俺みたいに変わってる人間が注目されないのだろう。ハロウィン前の渋谷では、至って普通のサラリーマンしか歩いていなかった。そして俺は、人混みの中で胸騒ぎを覚えた。俺は、透明人間になってしまったのではないか、と。
ハロウィンの夜が訪れた。
DJポリスが出勤した渋谷の交差点は、数日前とは表情をガラッと変えた。そして俺は、ハロウィンの文化に対抗するような気持ちを込めて、人形浄瑠璃の仮装をした。もちろん、人体模型の人形浄瑠璃である。しかし、そんな奇怪なコスプレをしても、誰も振り向いてはくれない。そして、交差点の中心で叫んでみても、とうとうDJポリスすら俺の行動を咎めなかった。というよりも、俺の存在を認識していなさそうだった。
俺は、やるせなくて渋谷のビルの屋上にのぼった。そして、人体模型を投げ捨ててみた。
けれど、それは夜の闇に吸い込まれてしまったかのように、落下途中で透明になって消えた。その時、俺はなんとなく悟ったのだった。
俺は生きれば生きるほど、透明になっていくのだと。周りが鮮やかになればなるほど、空気に溶けていく存在なのだと。そう気づいた途端に楽になって、俺は脱力したように笑った。そして、まるでプールにでも入るみたいに身を投げた。その瞬間、俺は見た。眼下に透明な彼岸花が咲いている様を。
◇◆
最近、ハロウィンの気配を街中で感じ取ってもワクワクしなくなった。怪しげなパンプキンやゴーストの描かれたパッケージのお菓子を見ても、おどろおどろしい雰囲気を纏った100円ショップの店頭を見ても、何も思わなくなった。子供の頃は使う宛もないのにコスプレ用の血糊を購入したり、ハロウィン仕様のお菓子を沢山買い込んでいたのに、そういう類のものに徹底的にドライになってしまったのだ。安っぽくて荒い作りのマントを着てはしゃいでいた少年の面影は、今となっては何処にも無い。
俺はきっと今年も、渋谷スクランブル交差点ではしゃぐ話の通じない馬鹿どもの問題行動を翌朝にテレビのニュースで見て思うのだろう。
こいつら早く消えればいいのに。
そう考えた矢先に俺は、渋谷の雑踏の中に立っていた。自分がどの電車に乗ってここへ来たのかも分からないし、来た動機もよく思い出せなかった。雑踏の中に留まることはできず、仕方なく歩き出したら東急ハンズが見えてきた。東急ハンズの入り口は、まるで俺を喰らおうとするかのように大きかった。
■一限ZOMBIE
午後11時までバイトに入ると、わたしを組織する身体の細胞が覚醒し過ぎることがしばしばある。自分の想定を上回る仕事量をこなした日は、風呂場のクリーム色の壁が緑のような色に見えてしまうことも非常に多い。
大学生活が今年の春から始まった、わたしと同期の学生たちの中からも、何人かそれは産まれた。
それ、というのはゾンビのことだ。
彼らの多くは、大抵2つのタイプに分類することができる。
ひとつは、そもそも出生時から人間には向いていなかったタイプだ。これは非常に可哀想な話で、そもそも人間用に作られていない“タマシイ”が何かの手違いによって人間の器に移されてしまっただけの話なのだ。神様が人間やゾンビの必要数のリストを無視して、気まぐれに発注を上下させる点については考慮する必要があるし、タマシイを器に移す工場との引き継ぎがしっかりとなされていない現状については、国会でも度々問題提起がされている。まぁ、そんなことは良いとして。彼らはそもそも人間の器に向いていないので、一人暮らしなどを始めれば、当然の如く堕落する。大学で会わなくなった友人がゾンビになってしまったかどうか確認する方法については、政府のホームページに記載されている番号に電話をかけ、友人の携帯番号を教えればすぐに確認が取れる。そして、彼らは目玉が白濁するのが特徴なので、街中などで見分けるのもそう難しくはない。
もうひとつは、何か別の道に目覚めてしまったタイプである。こっちは希少な例であり、国内での確認事例は少ない。ただ、彼らが前者と圧倒的に違う点は、情熱がある点である。彼らは鮮烈なオーラを外部に対して放ち、自らの目的達成のために人を喰う。例えば、ミュージシャンとしての成功を掴むために産まれたゾンビは、人間の彼女に寄生してあるゆる財を喰い尽くす。そして音楽が成功した場合には、あっさりと彼女の前から姿を消すのだ。ただ、彼らはゾンビである時間が前者に比べて圧倒的に短く、夢を掴んだ場合には『虹色人間』へと変化する例も少なくない。
一体僕は、何を言っているのだろう。
ここ最近疲れ過ぎて、変なことばかり言ってしまう。ゾンビはまだいいとして、虹色人間とかウシミツトカゲとか、とにかく気持ち悪い名前を考えるのが特異になってしまったようだ。
10月13日の金曜日。
昨日も23:00までみっちり働いて、終電2本手前くらいの時間に電車に乗り、家に着く頃には日付が変わっていた。ただ、僕は仕事が長かったことよりも自分を遥かに苦しませる要因にぶち当たった。明日、というか今日は一限から授業があるのだ。Am1:00、僕は夕飯を食べ終え、少し計算してみた。今から僕は風呂に入り、丁寧にスキンケアをして、明日のコーディネートをじっくり考える。ファッションにおいて足し算しかできないのは致命的で、まさに足し算しかできなかった知り合いはニートかつゾンビになったから、僕はアイツみたいにはならないように気をつける必要がある。そして、軽く授業準備もする必要があり、揃っていない授業資料があればプリンターで印刷しなければならない。となると、眠りにつけるのは軽く見積っても2:00頃、いや3:00を過ぎる可能性も大いにある。そう考えると僕は、ひどく億劫になった。正直、何もしたくない。
僕は仕方なく風呂に入った。
壁は期待を裏切らない緑色だった。
僕は全身に付着したゾンビウイルスを落とすために熱いシャワーを浴び、ついでに眠気も醒ました。土砂降りのようなシャワーの音を聞きながら、僕はふと一限を諦める言い訳を考えた。しかし、思い浮かぶことは全て、自分が一生世界にとっての悪者になるようなものだった。俺は諦めることを諦めようとして、ため息をついた。その時だった。
窓の外で、物騒なチェーンソーの音が聞こえたのである。そして、風呂場の電気が暗転した。俺は背中に冷や水を浴びせられたような気分で、窓の外を恐る恐る覗いた。僕の瞳が確かであれば、それは仮面の男だった。その男がチェーンソーを鳴らしながら、夜の静寂を破っていたのだ。しかし、よく見るとそれは限りなくジェイソンに近い造形の雨穴だった。
僕は息を潜めて、全身を洗い流した。
そして、風呂場を出て冷蔵庫を開け、水か何かを飲もうとした。しかし、最初にその手に触れたのは、生々しい爪痕が残った缶の飲み物だった。俺はダラダラ汗を流しながら考えた。
『これは多分、回復ドリンクだ……。これを飲めばライフが回復するはず……』
しかし、僕は判断を間違えた。それは、マッドサイエンティストが仕組んだ『ゾンビ覚醒ドリンク』だったのだ。僕はそれを飲んだ瞬間、突然変異に襲われた。人間の言葉が、分からなくなってしまったのだ。急に視野が狭くなり、見る物のすべてが緑がかった。僕は酷く混乱して、とうとう発狂した。すると、その叫び声によってあらゆるものが震えた。部屋の本棚も、壁に飾ったエレキギターも、コンポも、間接照明も。そして、やがて部屋の壁が崩れ落ちた。壁が無くなった部分から覗いた外の世界は、途方もなく荒廃としていた。どこかから立ち上る煙の奥からは、確実にさっきのチェーンソーを持った男が近づいてきている。道端には花束がお供えされていて、剥き出しになった我が家の骨組みは、人間如きの骨から出来ていた。僕は口を開いて、ゾンビ語で迫り来るジェイソン寄りの雨穴を挑発した。
『かかって来いよ』
ここで、ハッと目が覚めた。
回復ドリンク(エナドリ)を冷蔵庫から取り出して飲んだところまでの記憶は鮮明にあった。ただ、そこから先はどうしても思い出せない。まぁいい、ひとまず一限に向かうとしよう。
しかし、どうしてだろう。
いつも通り電車に乗ってただ大学に向かうだけなのに、僕は乗客たちの中でやけに視線を感じるのだ。全員が僕を社会不適合者と看做して監視している……そう思った。そもそも、朝ごはんを食べて家を出るというような日々の営みすらしっかりと出来ない人間が暮らしていけるような社会は、もうこの世の何処にも存在しないのだ。僕は自分がその電車に乗っていることによって、社会の歯車を狂わせてしまうのではないかと思い、逃げるように電車を降りた。そして、その足でコンビニへ。
コンビニで肉まんとカフェラテを購入し、朝陽に僕は目を細めた。肉まんとカフェラテは相性が良くて、こんな朝が毎日訪れたら良いのになと思った。ただ、黒いバンが突如としてコンビニの駐車場に停り、中から刺股を持った男たちが降りてきた。
『あいつだ! あいつが自分を甘やかしてばかりの化け物だ! 絶対に捕縛しろ!』
僕は、何も言い返せなかった。正直捕まっても仕方ないと思ったし、口を開いてもそこから出てくるのはせいぜいゾンビ語なのだろう。
だけど結局、そんな妄想をいくら並べてみても、なんの眠気覚ましにもならなかった。僕は電車の中で眠り込んでしまい、降車駅を乗り過ごしていた。一限には既に遅刻だったが、今から電車を乗り継いで大学を目指すとなると、軽く授業開始から1時間ほどの遅刻になりそうだった。僕は一限を潔く諦めることにした。教授に体調不良の連絡を入れて、車内を見渡した。誰も俺をゾンビのような目で見てはいなかった。ただ、ジェイソン寄りの雨穴に見つかってしまったら何をされるか分からないなと思い、念の為、息は潜めたままでいた。
■自作を振り返る|小説『毒芋』編
まずは、上のURLから作品を読んで頂きたい。このエッセイはネタバレを含み、そして、自作に評価を付けて今後の創作に活かしていくためのものである。是非最後までお付き合い頂きたい。
以下、ネタバレ
↓
↓
↓
まずこの作品を書いた当初のテーマや狙いにスポットを当てていきたいと思う。
本作は肌寒い季節に食べたくなりがちな『焼き芋』をテーマにしたヒューマンドラマである。街中である時期、『蜜芋』という言葉の入ったスイーツやお菓子をやけに耳にしたため、そのアントニムは何だろうと考えて筆を執った次第だ。私のキャリアの中で、食べ物をテーマにした作品は前にも後にもこの一作だけだと思う。
読者の方は小説の冒頭から察しがついたと思うが、本作はとにかく歪で肌にまとわりつく様なジメジメした雰囲気が特徴だ。切れ味の良い作品ではないものの、最後まで展開が読めないのではないだろうか。この時期、俺は家族というもののあるべき姿について考えていた。そして、俺はそんな不明瞭な名前の箱に生まれた瞬間から押し込まれてしまうこの世界の残酷さに絶望したものだった。結論、苦しいくらいなら解体してしまえばいいと思ったのだ。仮にバラバラに暮らしている家族がいるとして、それをとやかく言う者がいたら、そいつに『多様性』という言葉を使うのを未来永劫禁じた方がいい。
しかし、にしてもこの歳にしては背伸びした表現を使いすぎている印象はちょっぴり受けたりもするものだ。どこかで機会があれば、リライトしてみたい。そして、もしこの世界観が気に入ったという人があれば、ひとまず著者の僕からは宇佐美りん『くるまの娘』を推薦しておくことにしよう。
~次の季節へ~
貴方は冷めた表情で言った。
『ずっと何言ってるか分からない』と。
僕はてっきり貴方が、秋月のことも遠野のことも、認知しているものだと思っていた。しかし、僕の話は体育館の裏に散らばった硝子片のようなものばかりで、中途半端に入り組んでいたり、急に現実との境目を破ろうとしたりするのだった。
僕はたまに、ふと我に返ることがあった。友人と楽しく雑談をしていても、俺は一体どうしてこんな話をし始めたんだろうと考え始めてしまい、何も言葉を継げなくなることがあった。そんな時、自分はちゃんと地に足をつけて立っているのかすらも不安になって、幽体離脱した意識が旅をするのだった。
僕の意識は、公園の落ち葉の上を駆け回ってゆく。その絨毯は、僕が生きているのだということを証明するかのように、カラカラと鳴った。そして僕はたまらず、そんな優しい季節にそっと口付けをするのだ。
アパートに干された洗濯物たちはそれぞれ好きな歌を口ずさんでいて、僕は幸せな気分になる。ピアノの白鍵を踏んで進む子供たちには、僕みたいに暗い人間にならないでほしいと願う。クロワッサンのような形の街路樹を目にして、僕はバターの香りを嗅ぐ。
みんながみんな幸せに見える朝、ほんとはみんな鬱屈とした思いを抱えているのだろう。だから、人々は前に進んでいくのだ。貴方の頬を濡らす雨は、いつまでも降り続けるわけではない。だから、僕らはきっと大丈夫だ。
列車はまた、長いトンネルに入る。
手を伸ばせば救えたかもしれないあの子の記憶が、僕の頬を濡らす長雨になる。しかし、きっとそうやって着実に、次の季節へと向かっていく。そう、旅はまだ続いていくのだ。

【完】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
