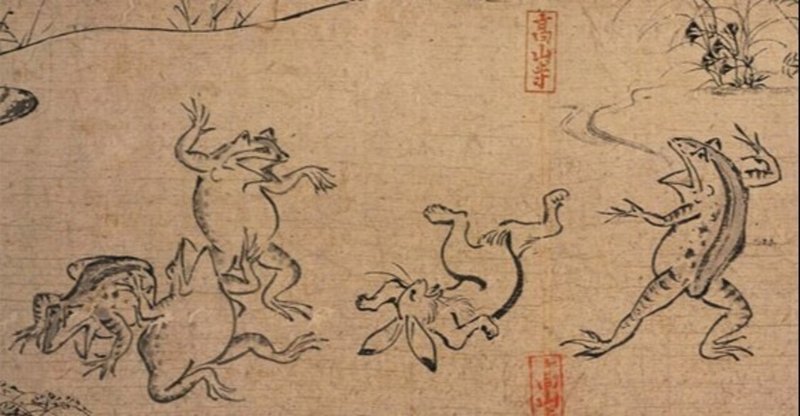
日本に《なじまない》って何? リーダーには論理的に語ってほしい (エッセイ)
選挙が終わるまでこのテーマでの投稿を控えていました。
岸田文雄首相の所信表明演説に対する各党代表質問の中で、新型コロナ対策を強化する法整備について、以下のように回答があった(2021/10/11)。
岸田総理大臣:欧米諸国で行っているような高額の罰金を科す厳しいロックダウンについては我が国には、なじまないと考えますが、これまでの新型コロナ対応を徹底的に分析し、危機管理を抜本的に強化して参ります。
この、「ロックダウンは日本になじまない」というフレーズは、岸田首相だけでなく、遡ること2か月半、7/30のニュースが、菅首相の言葉を伝えています。
菅首相は、コロナ感染拡大対策としてロックダウン(都市封鎖)を求める声があることについて、海外では都市封鎖をしても感染拡大が抑えられなかったとして「日本においてはロックダウンの手法はなじまない」と否定的な見解を示した。
この「日本に《なじまない》」って何だろう?
ここでは、「ロックダウンに関する法整備の必要可否」ではなく、このような表現を一国のリーダーが公的発言で用いることについて考えてみたいと思います。
「なじまない」という言葉は、「違和感がなくならない」「しっくりこない」という意味なんだそうです。
どうして「違和感がなくならない」のか、「違和感がなくならない」ことがその政策とどう関係するのか、そうした説明はありません。
そもそも、「違和感」とは通常、個人的な「感覚」「印象」「感想」だと思うのですが、この二人の首相が「個人的な感覚」を「一国の政策」の是非の判断にからめて語るのは適当なのでしょうか。
行政のトップが、こんな言葉を公的な場所で使うのは驚きですが、首相所信表明演説自体、あいまいな表現が目立ちます。
所信表明はもちろんですが、最初に引用した答弁も、自民党の幹事長の質問に対するものですから、あらかじめ周到に準備されたものでしょう。
この《周到に準備された意味不明》に対しては、「番記者」も含め、政界の「オトナの世界」では、突っ込まない《お約束》になっているのかもしれません。
企業のリーダーならば、このような表現は許されないでしょう。
取締役会で、ある成長分野への投資案件の提案に対し、社長が、
「その案件への投資は、我が社には《なじまない》」
と言い、なぜ《なじまない》のか、会社に対するメリット・ディメリットを論理的に、できうる限り定量的に説明しなかったら、会議出席メンバーはこの社長の資質に疑問を持つでしょう。
主に生産技術の現場で、発生した問題の真の原因を追究して再発防止策を立てるための手法として、《なぜなぜ分析》というやり方があります。
この《なぜなぜ》を繰り返していくと、もちろん、真摯な対応をする仮定のもとでですが、《なじまない》理由や《コトの本質》が明らかになっていくかもしれません。
おそらく首相は、ちゃんとした理由があって「日本」では「厳しいロックダウンの法制化」を避けたいのだと思われます。でも明言したくない。
では、なぜそれを論理的に明言しないのか? 明言すると、その論理に賛同しない人たち、反発する人たちが騒ぎ出すからかもしれません。
中でも野党が、その《論理》はもちろん、その中で使用する《言葉》の上げ足を取ろうとするかもしれません。
そして、それが選挙で論点となり、不利に作用するかもしれません。ひょっとしたら、3-4回の「ナゼナゼ」で《真因?》の「選挙に負けたくないから」が出てくるかもしれません。
論理の筋道を言わなければ反発もない。明言しなければ上げ足の取りようがない。
いや、そもそも最初の「ナゼナゼ」の答えがいきなり、「厳しいロックダウンを行えば、国民に不満が高まり、選挙に勝てなくなるから」かもしれません。
一方、野党が「上げ足」を取る理由も、「ナゼナゼ」していくと、「選挙に勝つため」かもしれません。
では、もうひとつ、なぜ選挙に勝たなければならないのか?
それは……
「オトナの事情」はわからないでもないですが、やはり、
リーダーには、論理的に語って欲しい。
全ての《判断》はトレードオフであり、両面があることはわかっています。
その両面を、国民にとってのメリット、ディメリットとして説明し、長期的視点も含めた《判断》として、示して欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
