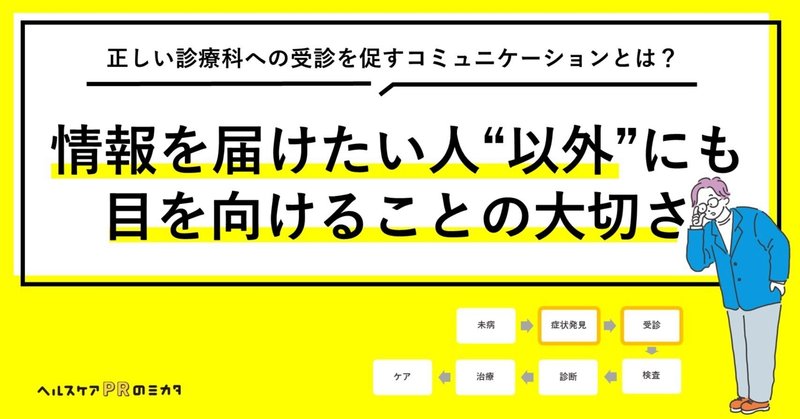
正しい診療科への受診を促すコミュニケーションとは?~情報を届けたい人“以外”にも目を向けることの大切さ~
近年、製薬企業が難病や希少疾患(※)の医薬品の開発を目指す中、疾患啓発活動においてもそういった領域のご相談や依頼が増えてきています。それは例えば、症状に気づいてもらい検査行動を促進する活動や、患者さんが周囲から受ける誤解の解消を目指す活動など、ペーシェントジャーニー下における様々な課題に焦点を当てたものです。
対象者が非常に少ないうえに認知も低い疾患領域に対して、“正しい診療科への受診行動の促進を目的としたPRコミュニケーション”を実施するためには——・・・
今回、ヘルスケア本部のメンバー3名の鼎談を通じて、難病や希少疾患の啓発活動に必要な情報設計の視点についてひもときます。
※希少疾患:日本国内では患者数が5万人未満との疾患と定義

藤原:ヘルスケア本部 コミュニケーションプロデューサー(左)
製薬会社、医療機器、日用品メーカー等、幅広い分野でのPR活動に従事。領域にとらわれないユニークな企画立案と着実な企画実行力を有し、患者さんやそのご家族との共創プロジェクトなど、コミュニティからマスメディアへの情報流通を狙った企画を得意とする。
中村:ヘルスケア本部 コミュニケーションプロデューサー(真ん中)
外資系製薬企業、医療機器メーカー、地方自治体等の医療・企業プロモーションを幅広く手掛ける。メディア発信、ステークホルダー共創、SNS、AD等を複合的に用いるクロスメディア戦略や、ヘルスケア課題を可視化するクリエイティブ開発を得意とする。
西山:ヘルスケア本部 コミュニケーションプロデューサー(右)
医薬専門代理店にて、医療用医薬品のマーケティングサポート業務に従事。新薬上市や疾患啓発プロモーションを数多く担当。その後、ヘルスケアITベンチャーのスタートアップに参画し、医療系学会向けスマホアプリサービスを経験。OZMA PR入社後は、長年の医療業界での知見を活かし、ヘルスケア領域の企業広報やオンコロジー、希少疾患領域での啓発PRプロジェクトを数多く担当。
■患者さんの想いを直接ヒアリングし、受診行動の障壁となっているインサイトを分析

藤原:希少疾患の患者さんは、症状があっても疾患に気づかない、あるいは異変に気づいたとしても正しい診療科を受診できていないことがよくあります。クライアントからの依頼の多くは、こういった潜在患者さんやそのご家族に疾患について知ってもらい、適切な診療科の受診行動を促す啓発活動です。
そういった依頼に対して、私たちがまず行うのは、患者さん像の徹底した把握と理解です。そのために行う方法の一つとして、患者さん自身へのヒアリングもおこないます。「当事者の声や想いに耳を傾ける」というのは私たちがすごく大事にしているところで、受診行動をおこすきっかけは何だったのか、どんな瞬間にどんな体の異変に気づいたのか、そのときの感情など、想いを深掘りしていきます。
数をいえば数名と少ないかもしれませんが、課題解決の重要なヒントになるんです。
中村: 患者さんのお話を伺うことは生活習慣や行動様式の特徴を浮かび上がらせ、まだ症状に気づいていない方(以下、潜在患者さん)にアプローチするための視点を定めるプロセスとして、とても大切なステップですよね。患者さんの行動や習慣のもとになる心理/背景や、「言いづらいけど」「言うほどでもないと思っていたけど」そういった前置きから始まる日々の些細な違和感について、そういった調査やアンケート結果などでは拾い切れない部分にヒントを得ることも多いです。
西山:疾患啓発活動において私たちがもたなければならない視点は、患者さんは、その疾患の患者である前に一人の生活者だということです。医療課題をより生活者視点で見たときに、どんな情報をどう発信すれば届くのかというポイントを見極めることが必要になります。そのためにも患者さんの声・想いに耳を傾けることは不可欠だと考えています。
■潜在患者さんとのハブになる“情報を届けてくれる方”を洗い出し、気づきを与える
西山:数少ない患者さんに情報を届けるためには、最適な発信手法、ルートを見極めた情報設計が肝となります。疾患によっては、患者さん本人“情報を届けたい方”だけでなく、その親御さんやご家族など、患者さんの周りにいて疾患の症状に気づき、受診を促すことができる人たちへの情報伝達が効果的な場合もあります。このように情報のハブとなる“情報を届けてくれる方”の設定も重要なコミュニケーション戦略の一つです。
藤原:たとえば小児の希少疾患では、患者である小さなお子さんは自分が病気だとは気づきません。子どもの様子に気づき、受診を促す人…これが誰なのかを、患者さん像の把握・理解を通して、また患者さんのインサイトから分析していくと、親御さんだけでなく保育士や幼稚園の先生、小中学校の先生、地域の保健師などもいると探り出すことができます。

ここからは事例を一つ紹介しながらお話していきましょう。神経筋疾患(neuromuscular disorder:以下、NMD)の疾患啓発活動「もしかしてNMD?」です。
神経筋疾患(neuromuscular disorder:以下、NMD)とは脳や脊髄、末梢神経、または筋肉などの異常によって、運動機能に影響をおよぼす病気の総称。代表的な疾患には、筋ジストロフィー、先天性ミオパチー、ポンペ病、脊髄性筋萎縮症(SMA)などがあり、どの疾患にもよく似た症状が現れ、進行性の疾患であるため早期受診と早期診断が重要となる。
歩きづらそうにしている、ジャンプができないといった症状は、子どもの運動能力には個人差が大きいことからもなかなか気づかれにくいものです。また異変に気づいたとしても、小児神経内科や脳神経内科といった専門機関の受診には及ばないといった課題があることから、NMDの正しい理解と受診促進を目指したプロジェクトがスタートしました。
患者さんとそのご家族のご協力をいただきながら、難しい疾患をどう伝えていくかを検討していった末、「楽しく踊っているうちに症状のチェックができるダンス」を通じたクリエイティブ開発を行いました。潜在患者の子もそうでない子も一緒になって楽しめるダンスですが、中身はきちんとNMDの運動症状のチェックができるように医療の専門家と共同で設計されています。
中村:NMDに共通した症状は体の状態やしぐさにあらわれるものが多くあるため、開発したダンスを保育園や幼稚園などのお遊戯として取り入れてもらうことを推進しました。集団で実施することでしぐさの違和感や症状の特徴が見えやすく、親御さんだけでなく保育士や教諭など複数の目でチェックすることができるためです。そして、このダンスがお子さんの養育にかかわるコミュニティに広く普及すれば、疾患の認知向上と早期発見に繋がるのではという狙いもありました。
■数少ない対象者に情報を届けるために、広く知らせるところから情報流通を設計していく
藤原:「情報を届けたい人に効果的に届ける」というのと矛盾しているようでもありますが、多くの人が目を向ける情報発信を設計したうえで、その中身が最終的に届けたい人に届いているという構造である必要があるのではないかと私は思っています。
中村:コミュニケーションをすべき方々が、能動的に情報を取りに行く集団であれば、そこにしっかり焦点を当て訴求するのが最も効果的で、幅を広げることにあまり意味はありません。
一方で希少疾患の領域では、そもそも患者さんや周囲の方々が疾患を認知していないところからコミュニケーションが始まるので、まずは疾患の存在に気づいてもらうことが必要です。情報が耳に入る、情報に目を止めてもらう、そのためには、ある程度幅広いコミュニティでの話題化というのも重要になってきます。
西山:その意味では、小さなお子さんが楽しく踊れるダンスは「保育園、幼稚園の子どもとその周りの大人たち」という広いコミュニティが入り口となって、対象となる患者さんに至るまで、情報を流通させるための装置だったわけですよね。
藤原:情報を流通させる装置という点では、ダンスというクリエイティブそのものだけでなく、どんな人と一緒につくるかも非常に大切です。今回のダンスでは、幼児の教育番組で活躍しているタレントさんや制作チームと共創しました。単に人気のある振付師などにお願いするのではなく、情報を届けたい方々=ファミリー層に支持を得ているタレントさんやクリエイターに参画いただき、企画に巻き込むことが、情報が自走的に波及していくポイントになります。

西山:コミュニケーションの仕掛けとして「ダンス」という一石を投じる中で、ただ石を投げ入れて終わり、ではなく、さまざまな考慮があるんですよね。「どこに投じるか」は社会へのメッセージの投げかけ方、「どんな石にするか」はコンテンツクリエイティブ、「投じる石の大きさ」はPRテーマそのもの。PRテーマには、いかに情報を届けたい方や社会に対して、発見や共感を得られるか、また「なるほど」「ふむふむ」と思わせるかも重要です。そこに、最適なインフルエンサーなどを巻き込むことで、投じた石の「波紋の大きさ」を拡張させていくという感じです。つまり、波紋の大きさは“人が人に伝えたくなる価値”なんです。
中村:波紋の大きさと言っても、必ずしも人気タレント、フォロワーの多いインフルエンサーという基準ではなく、大切なのは企画にその方自身が興味をもって、参加意識をもって関わってくださるということ。また、その方と繋がっているフォロワーやファン層と狙うコミュニティとの親和性の高さ、そして能動的情報発信層との繋がりの多さなどを重視しています。インフルエンサー自身が活動に意義と参加意識を感じてくださることで情報の発信の質や頻度も上がり、それが本来情報を届けたい方と親和性の高い方々に届くことで、より広く、ポジティブに拡散されます。
今回のダンスもそうですが、私たちのような、パブリックリレーションズのためのクリエイティブ開発は、開発過程が啓発活動に関わるひとたちのハブになることが重要と捉えています。良質なコンテンツを完成させることはもちろんですが、その開発過程に多くのステークホルダーが参加することによって啓発に関わる発信に皆を巻き込み活動を広げていく、のりしろならぬ“関わりしろ”として機能していく。そんなクリエイティブ設計を意識しています。
■情報を広げていくアクションと対象となる方々へのダイレクト訴求のサンドイッチ戦略で、課題への気づきから解決まで情報をセットで届ける

西山:「コンテンツをどう広げていくか」という広告的な視点ではなく、「どうメッセージを届けて、自走させていくか」という構造の設計をしているイメージですね。特に製薬業界においてさまざまな広告規制がある中、私たちPR会社は単なる企業広報のサポートだけではなく、疾患啓発のクリエイティブ開発において力を発揮できるのはそういった視点をもっているからだと自負しています。
藤原:情報に触れて子どもの症状に気づいた人には、リスティング広告などを併用して、しっかりダイレクトアプローチを実施していくことも重要です。症状でネット検索している、つまりすでになんから子の異変を感じているけれどどうすればいいかわからない親御さんにはきちんと広告で情報を伝えていく。このサンドイッチ戦略が有効ではないかと考えています。
さらに、先ほどお話ししたダンスの例で言えば、ダンスというコンテンツの先にはウェブサイトがあり、医師の監修を入れた疾患解説や病院検索といった情報に接触できます。ダンスを通じて1人か2人、いるかいないかだったとしても、その人により正確な情報を届けて、受診という行動にも移れるように緻密に動線を組み立てています。

中村:また、発信する情報の質にも配慮が求められますね。正確性は当然のことながら、むやみに人を不安にさせないという点を意識しています。希少疾患の啓発では、情報を受け取る多くの方は疾患と無関係な一般の方々になりますが、“疾患”という情報は受け取った人の不安を喚起させるリスクは常にあります。ダンスの良さは、疾患に当てはまらない方々の不安をあおりづらく、多くの人が純粋に楽しめるコンテンツである点にもありました。
西山:そして情報が届いた“疾患に当てはまる人”には、「解決策がある」ということまできちんと伝えるのは、疾患啓発活動に携わるからには絶対に必要なことだと考えています。とくに希少疾患、難病に関しては、治療法はあっても完治することが難しいという病気も少なくないんです。「あなたは病気かもしれません」と正しく伝えられたとしても、本人にとっては知らないほうが幸せだったかもしれない。だからこそ、その先に専門機関を受診して診断を受ければ治療もできるという情報までをセットで届けることが重要です。単なるビジネスでは終われないという絶対的な使命感がそこにはあります。
医療・ヘルスケア分野の中でも、とくに製薬市場では細かな広告制限があり、PRコミュニケーションにおける繊細さが求められる希少疾患の啓発活動においては、必要な人に必要な情報をいかに、どうやって届けていくかという点で非常に多角的な視点が必要になってきます。これまで積み上げてきた知見もフルに活かしながら、今後も患者さんの行動変容や、患者さんが抱える課題の解決までを踏まえたコミュニケーションに取り組んでいきたいと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
