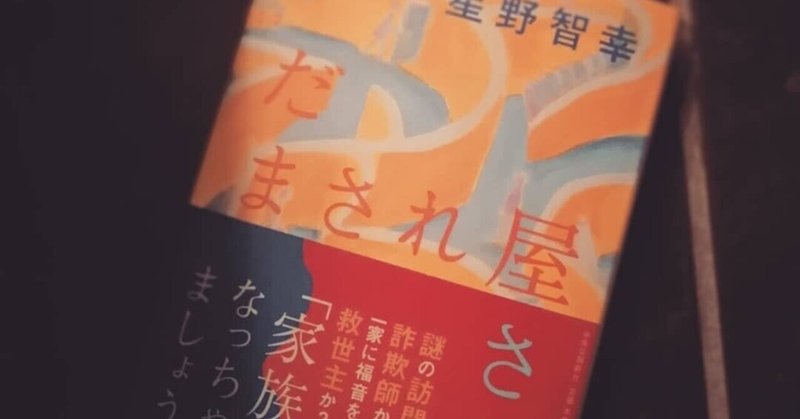
星野智幸さんの『だまされ屋さん』を読んで、家族の中で「あるべき姿」を演じるということについて考えた。
妻の話を聞くのが苦手だ。
あるいは、妻の話を聞くのが「上手じゃない」と言った方がいいのかもしれない。
相手は話を聞いてほしいだけだと分かっているのに、つい口を出してしまう。
かと思えば「なんで、何も言ってくれないの」と詰られる。
あるいは、表情を読み取られ「どうせバカにしてるんでしょ」と非難される(バカにしてるのではなくて、毎度繰り返される同じ話にうんざりしているだけなのに)。
あげくのはてに「いや、俺もあなたに『分かってもらえた』って思ったことないから」と口走ってしまう。
「恋人」だったときの妻からは、「話を聞くのが上手だよね」と言われていたはずなのに、これはいったいどういうことなのだろう、と自分でもイヤになる。
「そうなのだ、私は優志を正しさの鞭で叩き、優志は正しさの鎧で私を傷つけてきた。私たちは理解し合いたいと熱望していたのに、いつの間にか正しさを武器や防具に加工して、戦わせ合ってきたのだ」
星野智幸さんの『だまされ屋さん』を読んだ。
星野さんの熱心な読者ではないけれど、あれ?こんな「熱い」小説を書く人だっけ?と思った。
簡単に要約すると、「家族の中の『あるべき自分』という幻想に縛られ続けた一家の解体と再生の物語」だ。
あるべき母親の姿。
あるべき父親の姿。
あるべき子供の姿。
あるべき兄の姿。
あるべき妹の姿。
あるべき弟の姿。
あるべき妻の姿。
あるべき夫の姿。
そして、あるべき家族の姿。
そういうものに、無意識に縛られ、それによって自分も家族も苦しめてきた人たちが、はたして、その閉鎖的な苦しみや憎しみから脱却できるかどうかを追ったドキュメンタリーでもある。
物語でありながら、答えも結論も結末もない「途中経過」を綴った作品だなと思った。
だから、この作品で描かれているものが「正解」かどうかなんて分からないし、おそらく作者だって分からないだろう。
そもそも、本書を読み終えた僕には、何が正解かなんて、どうでもいい。
でも、ひとつだけ分かったのは、僕はもう「妻の話を上手に聞く物わかりの良い夫」を演じようとしなくていいんだな、ということだ。
恋人相手なら、「演じる」ことは容易いし、ひょっとしたら「演じ続ける」ことだって可能かもしれない。
だけど、家族の中で「あるべき姿」を演じ続けることは無理なんだってことを、僕はそろそろ認めなくちゃいけないな、と思った。
「どうして分かってくれないんだ」という叫びは、時に相手に対する過剰な刃となり、あるいは時に自分を過剰に防御するための鎧になるのだということを本書は描いている。
武器や鎧を捨てて、もう一度わかり合いたいと歩み寄る大人たちの姿は感動的ではあるが、しかし、同時にそれだけで「わかり合える」ほど人間は単純ではないし、他者と自分の壁は薄くないことも本書は描いている。
後半で描かれていく「再生」への道のりは、前半で描かれていた、まるで荒野のような景色(もう本当に心をズタボロにされます)とはまったくの別物であることは事実だけれど、「本音でぶつかり合えば家族の絆はよみがえる」というおとぎ話ではないことも確かだ。
だけど、本書を読み終えて、これまで、どんな家族小説を読んでも「目の前の断絶」に途方に暮れてしまっていた僕が、今回だけはまっすぐに前を向いて歩き出そうとしていることに、ちょっとした感動をおぼえている。
私を分かって。
それは、誰しもが抱えている切実な叫びかもしれないけれど、それが叶わなかったとき、それが届かなかったときのことを恐れて僕は自分の殻に閉じ籠ってしまう。
あるいは、誰かのその叫びを「分かってあげないといけない」と頑なに思い込んでしまう。
でも、本書は、簡単に分かってなんてもらえないし、簡単に分かってあげることもできないけど、それでも私たちは、心の叫びを声に出し、相手の心の叫びを聞くべきだということを描く。
分からなくていい。
分かってもらえなくていい。
それでも「洗いざらいのことを話そう」「洗いざらいのこと聞こう」、そういう夜が家族には必要なのかもしれない。
それは、新たな「寂しさ」を生むことかもしれないけれど、そうであったとしても、僕はそれを受け入れた上で、「どうして妻は僕がうんざりするほどその話を繰り返すのか」を聞いてみたい、そんなことを思った。
あなたの話にはうんざりだし、僕は相変わらず上手に話を聞けないけど、それでも今日は話を聞かせてよ。
そんな風に妻に伝えたら、彼女はどんな顔をするだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
