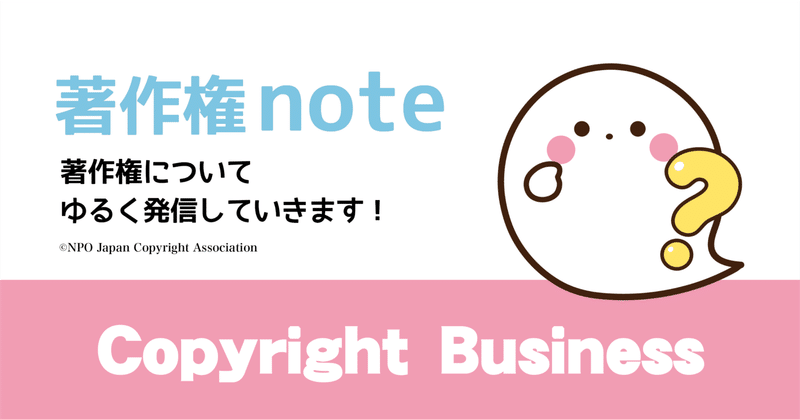
56.「まなぶ」ことは「まねる」こと。
1.人のモノを利用する場合の注意
ホームページや会報を制作する人、パワーポイントを使ったプレゼンテーション、スマホや印刷媒体を使って、ビジネスで行ない企画制作する人にとっては、この著作権の問題は避けては通れないものです。
実際にこれらにたずさわるすべての人は、他人の作品、権利を使用するようになります。そして知的財産権問題で最も深刻な問題が、他人の作品、権利の使用についての知識がないために著作権侵害になる恐れが高いことです。
そのため、他人の作品を使用する場合のマナーや事前にその作品にどのような権利があるのか、ないのか、あとで困らないためにも、他人の著作物を使用する場合のポイントがあります。そのためには、次のことを注意しなければなりません。
2.次の諸点を検討する必要がある
まず、著作物の種類があります。
イラストなのか、漫画なのか、アートなのか、それとも音楽や写真、映像の場合があります。
映像の場合は元の原作者、脚本、コメントや翻訳、撮影者、肖像者、編集やデータ作成者、音楽というように様々な著作物の塊です。
そのため要注意ですね。
YouTubeのものでも公式な映像であれば利用できますが、それが違法ダウンロードのものを使用すれば、違法を行った者と同罪となります。
このように著作物の形態は様々なものですから「引用の定義」にあてはまるものもあれば、あてはまらないものあります。
アイデアというものは不思議なもので、ある日突然に、アタマの中に自然と湧くものではありません。
あのトーマス・エジソンだって、神様からの啓示をもらったのではなく、身近な友人の言葉からヒントを得たり、膨大な書物や資料の中からヒントを発見したり、他のアイデアをマネし、独自のアイデアに練り上げ、オリジナルへと改良していくのです。
しかし、そのままパクれば権利にならず、侵害行為となってしまいますが、法律内容を理解し、合法的に利用すれば、パクリではなく、オリジナルをもつ新しい著作物が生まれる場合もあります。
3.「まなぶ」ことは「まねる」こと
広辞苑では「学ぶ」ことを、「まねてする。ならって行なう」「教えを受ける。業を受ける。習う」「学問する」。
または、「まなぶこと。まねをすること」。
さらに、「真似る」、という意味がある。
それでは「模倣」は、「自分で創り出すのではなく、すでにあるものをまねらうこと」と書かれています。
とかく人はマネをすればすぐに「マネした」「マネはいけない」「モノマネは許されない」という風潮がはびこり、よく見るとあまり似てはいないが、全体の雰囲気が多少似ているだけで目クジラをたてて怒り出す人もいます。最近ではこれらを知的財産権侵害行為といい、模倣に関してとてもきびしい時代になったという人も多くいます。
真似ることができなくなれば文化の発展はあり得ない。
真似することにより、日本の伝統や文化の発展がある。
日本では昔から「和魂漢才」「和魂洋才」という言葉があります。まさに日本の文化、様々なものから情報や表現、知識を取り入れて独自のモノをつくっています。

さて、「無料・無断で使える著作権」シリーズ。引用完全理解のための再復習。次頁からは内容はさらに深くは入ります。
「他人のレイアウトをマネる場合」
「他人のアイデアをマネる場合」
「他人の著作物を自由に利用する場合」
「他人の作品を加工、変更して使用する場合」
「もとの原作をもとに新しく作品を創作する場合」
「他人のキャラクターをマネして利用する場合」
「映像や音楽を利用する場合」という著作権を活用する応用編に入りる予定です。
おつきあい、よろしくお願いします。
※特非)著作権協会の電子書籍のご案内「~無料・無断で使用できる著作権活用法「無断OK著作権!③」全4巻好評発売中!下記にて検索してください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
