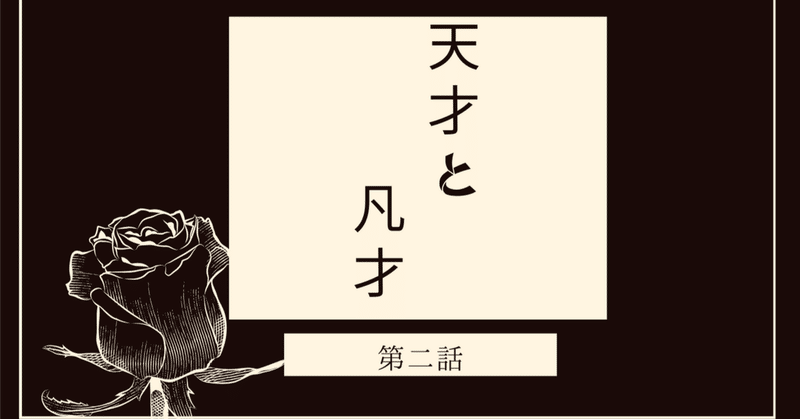
天才と凡才【第二話】
【第一話までのストーリー】
不思議な力が宿った「ミラーペンタント」を手にした沙莉は、不思議な力のお陰で、夢の作家デビューを果たす。
授賞式では、憧れの作家である濱崎ユカから選評を頂き、天にも昇るような気持ちに。
ところが、濱崎ユカと授賞式で会った翌日、彼女が自宅で亡くなっていることを知り、呆然とする。
【第一、三~四話のリンク先】
第一話はこちら
第三話はこちら
第四話はこちら
第二話

濱崎ユカが死んだ
作家の濱崎ユカさん(30)が15日、死亡したことが分かった。
捜査関係者によると、文学賞の選考委員として活動したのち、連絡が取れなかった様子。東京都港区の自宅に、濱崎さんの様子を見に伺ったところ、自宅で倒れているのを発見。
濱崎さんは病院に搬送されたが、死亡が確認されたという。濱崎さんの腕と手は、一部捻じれた状態だったため、警視庁では事件性も含めて確認している。
「えっ」
濱崎ユカのニュースを見るなり、沙莉はすっとんきょうな声をあげた。どうして、なぜ……。昨日まで、あんなに笑顔で、元気そうだったのに。
沙莉はふと、肌身離さず身につけているミラーペンダントに目を向ける。ペンダントはいつもと変わらず、鈍い光を怪しく放っていた。
(まさか。私が無理目なお願いをしたから、ペナルティとして濱崎さんをあの世に連れて行ってしまったのだろうか……。)
沙莉は恐怖で、わなわなと震えた。
ペンダントをつけるのが気持ち悪くなった沙莉は、思わず「いやぁぁぁ」と叫びながら、思いきり放り投げる。ペンダントは、床にゴトリと鈍い音を立てて落ちた。
それからしばらくの間、沙莉は濱崎ユカを失ったショックのあまり、部屋に引き篭もることとなる。
沙莉にとって、憧れていた人の突然の死は、そう簡単に受け入れられるものではなかった。ご飯も喉に通らないし、無理やり押し込もうとすれば、気持ち悪くて吐いてしまう。
沙莉が泣いて暮らしていると、再び体が勝手に動き出しはじめたのである。沙莉の体がスーッと廊下を伝って動き、再び唄子のパソコンに向かっていく。
「もうやめて……。私、文章なんてもう書きたくないし、賞もいらない……」
沙莉が心で強く願っても、ペンダントは聞く耳をもってくれない。腕が勝手に、カタカタと音を立てる。あっという間に、新たな小説が完成した。
「どんな願いも叶えてくれるペンダントなのに、これは私の願いなんかじゃない。どうして……。どうして勝手に、また作品ができてしまうのよ……」
自分の意に反して作品ができてしまうことに、沙莉は恐怖を感じた。
ミラーペンダントが沙莉の体を通して、新たに制作した作品のタイトルは、「愛する人よ、永遠に私の中で眠れ」。
ストーリーは、有名作家に憧れて作家になるも、その人が急に非業の死を遂げてしまう。主人公は悲しみを乗り越えながら、その死の理由と謎を解明していくというものだった。
小説のページをめくるたび、沙莉は怒りでわなわなと震えた。このペンダントは、私の悲しみや感情すらも、すべて糧として作品を作ろうとするのか……。
このペンダントは、自分の感情をすべてネタにして、勝手に作品を生み出してしまう。こんなことなら、喜びも、悲しみも。何もかも感じたくない。何かを感じようものなら、このペンダントはそれを察知して、小説のネタにしてしまうのだから……。沙莉は絶望し、へなへなと座り込む。
皮肉なことに、その作品はたちまち売れ、ベストセラーとなる。沙莉は売れっ子作家として、忙しい日々を送る羽目となった。
ただ、沙莉は濱崎ユカを失った悲しさから、まだ立ち直っていない。売れっ子になってもなお、心にはぽっかりと穴が空いたままだ。
さらに、沙莉が虚しさを感じたのは、濱崎ユカの死だけではなかった。沙莉は受賞してからしばらくの間、努力して文学賞を目指す方々への罪悪感で胸がいっぱいだった。
(世の中には、作家を目指して一生懸命努力している人だって少なくない。
こんな才能もなければ、努力すらしなかった私が、ズルをしていいのだろうか……。そもそも私は、作家になるために、なんの努力すらしていないというのに。
それに、自分が作家になったことで、濱崎さんが死んだのかもしれないのに。)
沙莉は受賞したあの日から、毎日のように酷い悪夢に魘されるようになった。
夢の中では、無数の人々の腕や手が、沙莉の喉にするすると伸び、ぎゅっと力を入れる。彼らの目はすべて白目で、黒目はない。全員、血の涙をぽたぽたと流している。
沙莉は苦しさと恐怖のあまり、息も声も出なかった。夢の中の彼らは、口々にこう言った。
「いつか、お前がズルをした正体を暴いてやる」
「ズルをしたら、いつかツケが回ってくるぞ」
「お前は、ズルをして入賞しただけだ。調子に乗るな!」
時には、その中の1人が、沙莉の髪をぎゅっと掴み、ぐぃっと引っ張ることもある。あまりの強い力に、沙莉の髪がごっそり抜け落ちる。
ぱらぱらと沙莉の髪が落ち、思わず「ぎゃぁぁぁ」と声を上げた。1人が沙莉の髪を抜くと、他の者たちも1人、1人と沙莉の髪を掴んで引っこ抜こうとする。
「ごめんなさい……。もうしませんから。誰か助けて……」
沙莉が助けを求めると、遠くには、死んだはずの濱崎ユカが、ぼんやりと佇んでいる。濱崎ユカの目は白目で、血の涙を流していた。
彼女はいつも、沙莉が夢の中で人々から罵声を浴びせられる姿を、悲しい表情で見守っている。目が覚めるのは、いつも濱崎ユカの姿を見てからだ。
もしかしたら、濱崎ユカがあの世から自分を助けに来てくれているのかもしれないと、沙莉は感じていた。
沙莉が悪夢を見た後は、全身がぐっしょりと汗で濡れた。沙莉が目覚めた直後は、体全体がぐったりしていて、すぐ起きれないこともしばしば。
「きっと私は、心のどこかでズルをして受賞したことに、強い罪悪感を覚えているのだろう」と、沙莉は思った。
夢にでてきた人たちは皆知らない人だが、もしかしたら同じ賞に応募した人たちの魂なのかもしれない。
悪夢を見るのは「ペンダントの力に頼ったことからの、罪悪感」が理由だと感じた沙莉は、少しでも罪悪感が芽生えたら、こう思い直すことにした。
「大切なのは、結果。結果がすべて。所詮、結果さえあれば、どんな過程があれど、人間は評価してくれるから」
罪悪感を感じないよう努めることで、沙莉は次第に眠れるようになった。
悪夢さえ見なければ、もう濱崎さんも悲しい表情をして、夢に出てこなくなるだろう。沙莉は思った。
沙莉の作品は、やがて数多くのメディアで紹介された。作品は「素晴らしい」と絶賛され、やがて雑誌に沙莉のインタビューが掲載されるようになる。
メディアに取り上げられた自分は、鏡で見る姿とはうってかわって、あまりにも美しい。鏡を見るなり、自分の姿に惚れ惚れする。
プロのメイクさんがついて、カメラマンに撮影された沙莉の表情は、とても自信に満ち溢れていた。
最初のうちこそ、沙莉は周囲からチヤホヤされることを喜んでいた。
しかし、時間が経つにつれ、今度はその席を失うのが、怖くてたまらなくなる。今の席を失う恐怖に苛まれる度に、「新しい作家は、もう出てこないで」と、沙莉は願った。
そんな時、沙莉はミラーペンダントの説明文にあった「ネガティブな想いを伝えると、しっぺ返しが訪れる」という一文を思い出す。
「ここで、誰かの不幸を願ったり、ネガティブな感情を抱くと、自分に不幸が訪れるかもしれない……」
ミラーペンダントのしっぺ返しを恐れた沙莉は、身につけている間は、なるべくネガティブな感情を持たないよう、次第に注意するようになった。
これまで自分に自信がなく、ネガティブな感情を抱きがちだった沙莉。ミラーペンダントのお陰で、気持ちも次第に前向きになった。
今まで鏡を見るのも億劫だった沙莉が、少しすつ鏡を見て歯磨きや、スキンケアができるようになれたのは、嬉しい変化だった。
沙莉がデビューすると、各メディアは「美人作家の木村唄子は、双子だった!」「双子でダブル受賞」と騒ぎ立て始めた。
取材はいつも唄子と一緒で、あの女はいつも膨れっ面。無理もない。だって、唄子は文学賞を受賞して鮮烈なデビューをしたにも関わらず、書籍がさっぱり売れなかった。その一方で、沙莉の小説は飛ぶように売れた。
沙莉自身も、自分の本が売れた理由は理解していない。もしかしたら、ミラーペンダントに向かって「売れっ子作家になりたい」と強く願ったからではないかと、沙莉は思った。
「沙莉、よかったじゃない。本が売れて」
皮肉たっぷりの表情で、唄子は吐き捨てるように嫌味を被せてきた。唄子は、眉間に皺を寄せ、わなわなと震えている。
唄子が自分に嫉妬したのは、これが初めてではないだろうか。嫉妬心をあらわにする唄子の姿を見て、沙莉はニヤニヤと笑いが止まらない。
(今まで、私はあなたにずっと嫉妬して生きてきたのよ。これで、わかったでしょう?誰かを羨んで、隣で過ごし続けてきた私の苦悩を……。)
ふとミラーペンダントを覗くと、鏡が少し曇っているようにも感じた。もしかしたら、唄子へのネガティブな気持ちを、ミラーが汲み取ってしまったのかもしれない。
沙莉は慌てて、ミラーに向かって「ごめんなさい」と呟く。ミラーの輝きが蘇るのをみて、沙莉はほっと胸を撫で下ろす。
ミラーペンダントの説明文には、人へのネガティブな想いを持つと、しっぺ返しが来ると書かれていた。
沙莉はしっぺ返しが怖いあまり、少しでも人への不幸を願いそうになると、途端にやめるよう心がけた。
こうしてネガティブな感情を持たなくなったのも、全てはミラーペンダントのお陰かもしれない。
ミラーペンダントをギュッと握る沙莉を見て、唄子が「それ、何?」と尋ねてきた。沙莉は、どきりとする。唄子は、本当に勘がいい。
「これ、お守りなの」と沙莉が言うと、唄子は不服そうな目つきで「へぇ」と答える。
唄子は、その後もジロジロした目つきで、ペンダントに目をやろうとした。沙莉は、唄子に見られないよう、ペンダントを取り外してポケットに仕舞い込んだ。
ミラーペンダントのことは、唄子には絶対にバレてはいけない。唄子にバレたら、きっと彼女から「そうよね。あなたの力で、作家になれる訳ないよね」と、罵られることだろう。
または真似をして自分もミラーペンダントを購入し、今度は成功した自分を陥れようと企むかもしれない。沙莉は唄子のこれまでを振り返り、苛立ちを募らせた。
いつも飄々と暮らしていた唄子が、作家を目指そうとした理由。それは、今から10年前の「あの出来事」がキッカケのはずだ。
【10年前】
「沙莉、読書感想文で賞をとったんだって。凄いじゃない」
そう話す唄子は、とても嬉しそうな顔をしていた。その理由は、読書感想文で賞を取ったのは、唄子も一緒だったから。
「唄子も、読書感想文で賞に選ばれたんでしょ。良かったじゃない」
唄子は、ニヤニヤと嬉しそうな顔をする。いつだって、そうだ。この女は、自分が褒めてもらいたい時、わざとカマをかけてくる。沙莉は彼女のそういうところが、とても浅ましくて嫌だった。
「沙莉の感想文、まるで作家のあとがきみたいだよね。
著者が全てを書き終えてから、その感想を書いたような書き方をしていて、本当に凄いと思った。きっと、作者の魂が読んでいくうちに憑依したんだろうね」
唄子からそう言われて、沙莉は背筋がピクっとした。
その理由は、沙莉が巻末に紹介されているあとがきだけを読んで、感想を書いたからである。つまり、唄子の指摘はビンゴだったのだ。
沙莉は読解力に乏しく、興味がない作家の文章に関しては、どれだけ読んでも頭にスッと入ってこない。中学校の課題である「読書感想文」は、あらかじめ書籍が定められていた。
そのため、どんなにその本に興味がなくても、最後まで読んで、感想文を書き終えなければならない。
興味のない文章を読むのが苦痛と感じた沙莉は、ズルをして「あとがき」のみ読んで、感想を書いたのだ。こともあろうか、その感想文がたまたま素晴らしいと評価され、文集に選ばれてしまったのである。
恐る恐る、唄子の顔を覗き込む。彼女は、ニタッとした顔で沙莉をジロジロと覗き込んできた。
沙莉は、生まれてこの方、文才にはさっぱり恵まれていない。そもそも大して文章を読むのも、書くのも好きではない。
文章を書くのも、読むのも大して好きではない癖に、沙莉には作家になるという壮大な夢があった。その理由は、沙莉が有名作家の濱崎ユカさんに憧れていたからだ。
沙莉は、学校で友達と上手く馴染めず、1人で悶々と過ごしていた。そんな時、沙莉は濱崎さんが書いた小説「孤高の女神」に出会った。
孤高の女神では、社会に馴染めない女性が、ある日突然魔女に出会って、不思議な力を手にすることで人生を一変させていくストーリー。
何をやっても上手くいかなかった沙莉に、彼女の作品は一筋の光となった。
彼女の作品に感動してから、いつか濱崎ユカのように素晴らしい作品を書いてみたいと、沙莉は次第に思うようになった。
しかし、いざ沙莉が筆を持ってみても、良い文章がさっぱり浮かんでこない。無理もない。沙莉の国語の成績は、ずっと1~2を行ったり来たりしていたのだから。
沙莉は文章どころか、漢字の読み書きすら、あやふやな状態だった。
筆を片手に「うーん」と沙莉が頭を抱えていると、唄子が「どうしたの?」と声をかけてきた。沙莉は慌てて、筆と紙を両手でササっと隠そうとした。
「もしかして、沙莉。作家になろうと思ってない?」
沙莉は、ぎくりとした。洞察力の高い唄子は、人の行動を観察するだけで、相手の心理を読み取るのが抜群に上手い。その性格ゆえに、誰とでも彼女は仲良くなれた。
そもそも唄子は、昔から何をやっても卒なくこなすタイプだった。唄子は勉強、運動、作文も、なんでもできた。
どうして、同じ細胞から生まれてきた筈なのに、こんなに違うのだろう。沙莉は、自分の環境と才能を呪った。
母は、いつも才能に溢れた唄子ばかりを贔屓する。唄子がピアノをやりたいといえば、母は迷わず習わせた。
沙莉もピアノを習いたかったが、その言葉がどうしたものか、喉から出てこないのである。
沙莉は声を出すために、両手で喉をぎゅっと絞める。ところが、声が出ることはなく、苦しくて息ができないままだった。
「あ……あ……」と、沙莉がしどろもどろになっていると、母は「沙莉はもう少し、大きくなってからね……」といって、そっと諦めさせた。
母は唄子には何でもさせるのに、沙莉の「やりたい」を叶えることはなかった。
唄子には、ピアノの才能もあった。3歳の頃から神童と呼ばれた唄子は、一度曲を聞けば完コピできるほど、記憶力に優れていた。
唄子は想像力にも恵まれていて、5歳の頃になると作曲を始めた。
テレビ局からも唄子の取材がひっきりなしに訪れ、各局からは「ピアノの天才少女現る」「作曲家の美少女」として、散々持て囃されるようになる。
沙莉はずっと、部屋の隅っこでそんな彼女を恨めしい目つきで眺めていた。
沙莉と唄子はその後成長し、同じ中学校へと進学した。沙莉が中学生になったある日、唄子は突然、沙莉に対して「私、沙莉のために作家になると決めたわ」と、言い放つ。
沙莉が怪訝な顔をすると、唄子は自信たっぷりな表情で答えた。
一瞬、唄子が何のことを言っているのかわからなかった。
「どうして、唄子が作家になろうとする訳?作家になりたいのは、私なのに……」
すると、唄子は自信満々な表情で、こう答えたのである。
「そう。私は有名作家となり、デビューするの。あんた、作家になりたいって言ってたけどさ。
沙莉は、繊細な性格でしょ。だから、売れっ子作家になって、有名になるのは大変よ。有名になると、色んな人から野次が飛んでくるんだから。
だから、私が矢面に立つの。私が有名になれば、読者の文句は私に届くから」
唄子の話を聞いて、沙莉は頭が真っ白になった。
(私は自分の名前で、作家としてデビューしたいし、自分の力で頑張って、憧れの作家である濱崎さんに会いたいというのに……。どうして、あなたがその夢を横取りするのよ……。)
唄子の一件から、沙莉はあまりに腹が立ったので、家の中で彼女を無視するようになった。
唄子はそんな自分のことなどお構いなしで、いつもの通りふんふんと鼻歌を歌っている。呑気な彼女の姿が、より沙莉の苛立ちを募らせた。
唄子はこの頃から、急に「作家を目指す」と言いはじめるようになった。
作家になりたいという割には、たいして本を読んでる素振りもなく、努力の様子は見受けられない。
作家になりたいだなんて、嘘だ。人の気持ちを翻弄するために、あの女は適当なことを言って、いつも私を惑わせる。
中学を卒業し、高校に進学した唄子は、家の近くのファーストフード店で、アルバイトを始めた。明るく朗らかで、いつもニコニコと接客していた唄子の前には、いつも鼻息を荒げる男たちで溢れていた。
やがて唄子が大学に進学すると、バイト時代のお金を使い、世界各国を飛び回るようになった。
彼女は、世界各地の人々と、楽しそうにお酒を飲んでいた。そして、その日々をマメにSNSへアップする唄子。
唄子のSNSを振り返ると、一緒に移っている男性が毎回違うことに、ふぅとため息をする。本当にいい加減でだらしない女だなと、沙莉はつくづく思った。
唄子の話
あれは、唄子がまだ3歳の頃だった。唄子は3才の頃、道端で楕円状のミラーがついた、ペンダントを拾った。
ペンダントは、道端の花壇の上に、乱雑に投げ捨てられた状態で放置されていた。
まるで、誰かが急に思い立って投げ捨てたかのように……。ペンダントは、太陽の光がミラーに当たり、キラキラとした輝きを放っていた。
本来なら、唄子は決して怪しいものを拾うタイプではない。ただ、そのペンダントのことは、見た瞬間から気になって仕方がなく、気づけばそっと拾って、こっそりポケットに入れたのである。
家に戻り、恐る恐るペンダントを首からかけてみる。すると、あたり一面が急に暗くなり、唄子は狼狽える。
暗闇の中、ペンダントのミラー部分がキラリと怪しく光り、唄子の姿を映す。唄子の表情は、いつもより美しく映っていた。
唄子は、怪しい魅力をもつペンダントに魅せられ、毎日のように持ち歩くようになった。
そして、このペンダントをつけてからというもの、唄子の願いは恐ろしいほど、何でも叶うようになったのである……。
【第三話へ続く】
【第一話~第四話リンク】※公開後、こちらにリンクを貼る予定です。
第一話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

