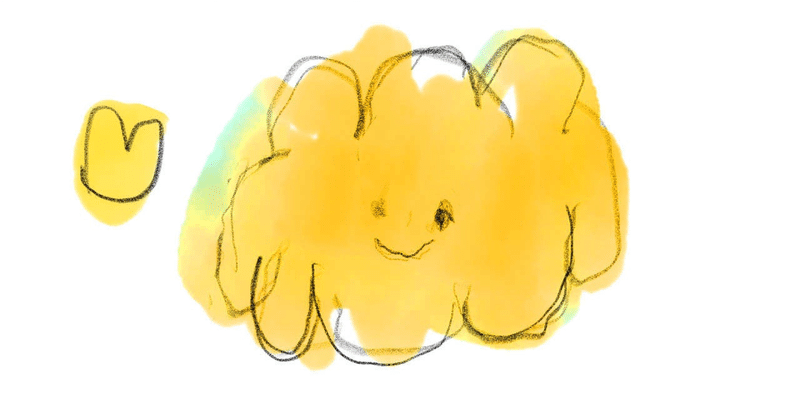
「主体的」とは何か、を突っ込んで考える
「他者」という概念が哲学にはある。これは、「他者」の一般的な語法である「他人」以上の意味を持つ。それは「理解を絶した事柄」である。他者における「他」を、より強調しているのだ。
<他者>の人とも呼ばれるユダヤ人哲学者であるエマニュエル・レヴィナスは、「他者」の「他」性を極めた人だと言われている。レヴィナスの議論では、もはや「私」という主体は、「他者」からの呼びかけによって存在しているとまで述べる、という。これは一回聞いただけではどういうことかわからない。
生まれたばかりの赤ちゃんを想像して欲しい。彼女にはまだ「私」が存在していない。つまり、赤ちゃんにとっては「私」という感覚がない、と思われる(聞いたわけではないが)。では、赤ちゃんはいつから「私」を獲得するのだろうか。それは、私を呼ぶ「他者」の声を聞き続ける中で獲得されていく。周りの養育者がかけてくる声が私に届く。繰り返し届く。そして、それは「私」に向けられていると感じる。確かにそう感じる。このメッセージが「私」に向けられていると感じる時、そこに始めて「私」が生まれる。
この説明を受けると、確かに「私」より以前に「他者」が存在していることが前提になる。普通の感覚だと「まず私」がいて、その周りに「他者」がいる、という思考を辿る。しかし、これをレヴィナスは否定したのだ。そうではない。私というのはあくまで「他者」によって生かされているような「受動的」な存在である、と。
このように「私」を捉えてみると、今、学校現場で言われている「主体的」とか「主体性」という言葉のイメージも変わってくるだろう。
例えば、国立政策研究所が出している『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』にある「主体的に学習に取り組む態度」の評価の説明は以下のように書いてある。
「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては、単に継続的な行動や積極的な発言を行うなど,性格や行動面の傾向を評価するということではなく,(中略)自らの学習状況を把握し,学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら,学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが重要である。
なお、この後の説明として、具体的な評価方法については、以下の二つの側面を評価するように書かれている。
①粘り強い取組を行おうとしている側面
②自らの学習を調整しようとする側面
ここで語られている「主体的」のイメージには「確固たる私」が付きまとう。「自ら」で把握し「自ら」が調整し、そんな「自ら」学ぼうとしている子どもの「意思的な側面」を評価する。
ここには「自己決定することができる自律した主体」を育てていこうとする思いを感じることができる。日本の教育行政は、そういう人間を育てたいのだ。
しかし、これはレヴィナスの考える、「他者」によって基礎付けられる受身的な「主体」像とは根本的に異なる考え方である。そしてこれは、今から20年ほど前の教育哲学の分野で盛んに議論されてきたことでもある。
「他者への教育は可能だろうか」というテーマは、2000年のはじめに教育哲学の分野では盛んに議論されていた。他者論自体は今でももちろん議論されてはいるが、その議論をするならば、この2000年代初めの議論を踏まえて議論することが求められる。
そして、そこでの共通了解としては、
「よくわからない他者」への教育をすることは困難であるが、それを諦めてはいけない。教育者は他者である子供に対して倫理的な姿勢が求められる。
といったことになる(これは筆者の管見の及ぶ限りでの話なので、異論は大歓迎)。
しかし、残念ながら、教育行政にこの知見は生かされていない。教育行政は、もう教育諸学問からの知見を活かして教育行政の方針を決めるというよりは、経済界の意向を汲んで「人材(この言葉が嫌いである)」を供給することにしか関心がないようである。
「確固たる自己」というのはあるのだろうか。
それを評価することはできるのだろうか。
この二つの問いについて考えてみれば、後者については容易に答えが出るし、それは現場の賢明な先生方の認識と一致するであろう。つまり「意思的な側面を評価なんて、できるわけがない」である。この議論については過去に何度もしているので、端的に言えば「学校が語る主体性は、教師への忖度」という一言に尽きる。
では、前者の問いはどうであろうか。
これも新自由主義的な教育政策の理念が結集したものであると捉えればわかりやすい。つまり、社会として人を育てていくコストを払うのは嫌だ、早く自律して、労働者になって、「消費する主体」へとなってくれ。
「経済を回す」。この新自由主義の単純なイデオロギーによって、ここ数十年踊り続けた結果、さまざまな大切なものが失われたのではあるが、教育行政は、いまだにそのダンスを踊り続けているようだ。
教育というのは「私」対「私」による、知識技能の伝授「だけ」の場ではない。そういう側面も教育には当然あるが、それはごく限られた話だ。学習が「個人の習熟」に焦点を当てるのに対して、教育は「関係性」に焦点を当てる。
子どもたちからすれば、教師や教材や世界という「他者」と出会うことによって、自分自身と「出会い直す」。
教師からすれば、子供という「他者」と出会うことによって、自分の教育観が常に見直され、より良い教育のあり方について葛藤し続ける謙虚で節度ある倫理的な姿勢が生まれる。
いずれも「出会い」という「関係性」が、教師や子どもを「成熟」へと導く。そこには文科省が掲げる「確固たる主体的な自己」は必要ない。むしろ、そんなものは望まなくてもいい。
教育行政の賢明なる動きを待つ必要はない。
現場の教師一人一人が成熟を目指して、教育的関係における「他者性」に気づいたとき、教育は今よりも、もっと素敵な姿になっているだろう。
