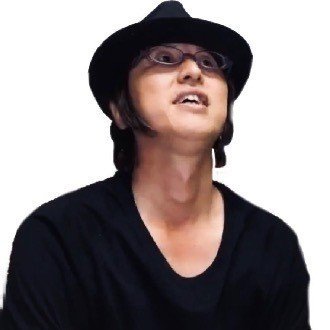【1ヶ月100時間のZOOMオンライン授業をするカリスマ講師"master honda"が教える】先生のためのZoomオンライン授業ノウハウ集! vol.000 『はじめに』(無料で全部読めます)
当記事は、(noteの使用上)この記事を含む「有料マガジン」の購読を判断してもらえるよう、有料ですが、全て無料部分として無料公開しています。(当記事をご購入いただく必要はありません)。当記事を「vol.000」としています。
シリーズを読まれたいと思われましたら、是非、マガジンをご購入ください。マガジンは未完成で随時、更新していきます。
なお、有料マガジンは、1マガジンあたり、記事数を2から4程度に考えています。記事が増えていくたびに、別マガジンとしてリリースします。(マガジンは「第1巻」からスタート)。

(↑実際の教室の写真です)
・ノウハウも正解もないオンライン授業の今
オンライン授業の普及が一気に進む気配を見せています。
コロナ危機を迎えた2020年は大きな節目の年となるはずです。
ところが、いざオンライン授業をしようとした時、何から手をつけていいのか、どうやればいいのかと、途方にくれる方がほとんどなのではないでしょうか。
ほとんど未知の世界、未開の領域ですから、正解も、基本の型のようなものもありません。
特に、一方通行の、いわゆる映像授業ではない、双方向型のオンライン授業に関しては、取り組んできた事例がとても少ないはずです。
個人の範囲で、家庭教師的に、というものがわずかばかりあったはずですが、個人のノウハウはなかなか共有されていません。また、こうした個人授業は、あくまでも、リアルのものをそのまま置き換えたもの、になりがちです。
当シリーズ記事では、ノウハウがほぼ存在していない双方向型のオンライン授業についてのノウハウをお伝えしていきます。
そして、既存のリアルの置き換えではない、新しいオンライン授業をあなたと共有し、構築していければと考えています。
・使用するのはZOOM。のべ400時間使用してみて分かること。
筆者は、学校が休校措置となる前後から、ZOOMのオンライン授業(主に小・中学生)を行なっています。現在も平日は、毎日5時間は必ずZOOMを使っています。
1ヶ月で100時間ほどは行っていることになりますので、のべ400時間を経過しました(2020年8月現在)。
ここではそうした実践をもとに、具体的なノウハウをお伝えしていければと思っています。
実際に授業をしていて気付くのは、「やってみないとわからないことが多い」ということです。
○○という機能があったとして、実際に授業で活用してみないと気づかないことが多くあります。
僕もここに至るまで、たくさんの修正を加えてきました。まだまだ今後変わって行くかもしれません。というか、変わっていくはずです。
用いるものがデジタルのツールであることは、大変な強みの一つです。これまでできないことができる可能性があるのです。
一方、やってみないとわからないことが多いという面もありますから、いわゆる修正主義、試しながら修正していく、という姿勢はとても大事だと感じています。その点は是非、理解していただきたい点です。
・リアル授業の置き換えではない新しい授業の構築を
映像授業はすでに存在しています。
ところが、これは双方向ではないですし、既存の方法論で事足ります。
新しい双方向型のオンライン授業は、リアルを単に置き換えようとするものではありません。実際に授業をしているとわかりますが、ただのリアル授業の置き換えと考えるのは非常に勿体ない。オンラインであることのよさ、デジタルツールを使うことの良さ、をもっと生かす授業を構築しませんか?
・欠かせない子どもたちの新しい特性
そしてもう一つ大事なことがあります。
それは、子どもたちの変化です。近年、子どもたちはその特性を大きく変化させてきました。価値観が大人のそれとは全く別物だと言って良いでしょう。
学びにおいても同じです。
これまでの一斉授業で学べていたことを学び取れなくなっています。
子どもたちの特性が違うわけですから当然です。
わかりやすく言えば、まなびにおける得手、不得手が従来の子たちとは大きく異なっているということです。
ご存知の通り、リアルでのコミュニケーションの力は年々低下しています。
だからこそ、今、子どもたちの特性にあった新しいオンライン授業が必要なのです。
(子どもたちの新しい特性については、「教え方2.0」というシリーズで詳しく述べています。ここでは紹介に留めます)
・ここまでのまとめ
まずは、ここまでをまとめます。
1・オンライン授業の重要性が増したが、ノウハウがない
2・これまでのリアル授業の置き換えでない、オンラインならではの新しい授業の構築が必要である
3・子どもたちの新しい特性も考慮すると、よりオンライン授業の重要度は増す
4・正解がない新しい授業、それをあなたと一緒に構築したい
見て分かる通り、まとめの4はここで付け加えました。
何が正解かわからない、だからこそ、ぜひ、これを読み実践したあなたからも、こういうやり方がある、こうするのはどう?というアイディアがあれば、どんどん共有させていただきたいと思っています。
授業や講義といっても、それぞれの環境や状況は異なるはずです。
ここでお伝えするのは、あくまでも私の環境下、状況下からの一つの提案であるということは頭に入れておかれてください。
・当シリーズの対象として想定している方はこんな方
当シリーズ記事(有料)で対象としているのはこんな方になろうかと思います。
1・オンライン授業をしたい学校の先生方(小中高)
2・ZOOMの使い方や機材はネットで無料で集められるのだけれど、実際の授業を想定したノウハウを知りたい
3・リアルの置き換えでない新しい授業を構築したい先生
4・学校以外で、オンラインで先生業をしている方
5・教育学部で勉強中など、これから先生を目指される方
1について。
実際に筆者が授業対象とするのは、小学生高学年と中学生全学年です。
高校生などでも有効に使えるスキルも含まれていると思われますので、ご了承の上、ご活用ください。
2について。
ZOOM自体の基礎的使用法は、インターネットで無料で見られるものが多いと思われます。ここでは、超基本的な使用法についてはお伝えしません。
ただし、授業向けのセッティングや機材については言及しますし、質問があれば、もちろん初歩的な問いにもお答えするつもりです。
・オンライン授業のための無料動画も更新中
参考までに、すでにzoomを利用したオンライン授業、特に実際の授業を録画したものを、Youtubeにて公開中です。
実際にはどんな風に行われているのか、どんな画面で、どんな操作をしているのか、ただ興味があるだけも構いません。みるだけでもその様子がわかるのではないかと思います。
また、指示命令強制ではない、「問いかけ」「コミュニケーションの仕方」も随所に見られるかと思います。
現代の子どもたちは、先生の上から目線に強烈に反応します。まさに「先生は偉い」そのままに、指示命令、強制の形での指導を実践してしまっている方だと、ほとんど生徒はついてきません。
先の「教え方2.0」動画の中でも述べていますが、信頼関係が何よりも重要です。そのためには、命令口調、上から目線を徹底して排除することが欠かせません。
こう話すと、「子ども(生徒)と友達にでもなれというのか、けしからん」と殺気立つ方も出て来られます(残念ながらそのくらい既存の先生像は古いわけですが)。
ご安心ください。子どもたちと友達のような関係になれという主張ではありません。単なる友人関係ではない信頼関係というのはいくらでも存在します。実際に、筆者はそれを現場で実践し続けて来ました。指示命令、強制、上下関係を強く意識し守る、そんな手法でなくとも、しっかりリスペクトのある関係を築くことが可能です。
一見、zoomオンライン授業とは関係のない話に思えますが、新たな先生像とそこにある価値観は、全てに影響を及ぼします。コミュニケーション、授業進行、授業スタイル、さらには親御さんとのコミュニケーションに至るまで、全て、です。
zoomを中心としながら、その辺りの新たな先生像についても、お伝えしていければと考えています。
・最後に/タイトルについて
タイトルに「カリスマ」という言葉を入れました。これはマーケティング上、戦略として使用したにすぎません。多くの方にお届けするには、どうしてもインパクトがあり、ある程度認知されている単語を使う必要があります。そのため、使用しましたので、どうぞその辺りはご了承ください。
あえて、お伝えしているのには訳があります。
求めていることは、「学習者が主体」「学び手である子どもたちが主役」であること。
だから、先生がスゲーとか、講師がカリスマ、とかは、どうでもいいのです。むしろ、そうでない方が良いとさえ思っています。
ちなみに僕は、子どもたちが自分のスクールに入ってくる際の面談で、「別に僕はいなくてもいいのだけれど・・・」という話をしています。
そのくらい、子どもたちが主体であることを大事に考えているのです。
カリスマという単語は、そんな僕が仕方なく用いた言葉です。
そのことを付け加えておきますね。
では皆さん、是非、このシリーズを読んでいただき、活用していただき、新たな授業の構築をなさってください。
(vol.000 終わり)
当記事は、(noteの使用上)、この記事を含む「有料マガジン」の購読を判断してもらえるよう、有料ですが、すべて無料部分として無料公開しています。
筆者プロフィール記事
(vol.000 終わり)
記事を気に入っていただけると幸いです。NPOまなびデザンラボの活動の支援に活用させていただきます。不登校および発達障害支援、学習支援など、教育を通じたまちづくりを行っています。